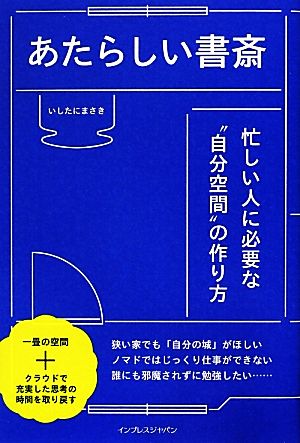あたらしい書斎 の商品レビュー
現代住宅事情、デジタルデバイス事情に基づいて、「いま必要な書斎」を考える一冊。 書斎に求められる要素は何か、実現に向けての困難は何かを紐解きながら、IKEAの家具をもとに実際に書斎を提案したり、クラウドサービスの活用法を提案。ハウツー本というよりは、読み物としても面白かった。引っ...
現代住宅事情、デジタルデバイス事情に基づいて、「いま必要な書斎」を考える一冊。 書斎に求められる要素は何か、実現に向けての困難は何かを紐解きながら、IKEAの家具をもとに実際に書斎を提案したり、クラウドサービスの活用法を提案。ハウツー本というよりは、読み物としても面白かった。引っ越しのときに参考にします。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
今正に書斎を作ろうとしていたので、購入してみる。 書斎というと、本が沢山並んで・・・。というようなイメージだが、(もちろんそういった綿も必要なのだが、筆者はこれを「こもる」場所と呼んでいる)それだけでなく、情報を発信することによって得られる「情報」にも言及する。著者はこれを「開かれた書斎」(ブログやSNS)と呼ぶ。 前者は、アナログが強く 後者は、デジタルでないと不可能である。 デジタルだけでもなく、アナログだけでもない。双方の得意な部分をミックスしようというのは、最近の流行りだろう。これは、完全なるデジタル化に対応できない人間が多いからなのではないかと思える。 本書の重要な点 1.家具は改造していい。 安価な家具であれば、ネジやビスそういったものを遠慮無く打ち付けることが出来る。使いやすいように加工するべき。 2.本棚は4つのエリアで分ける。 ①現在(読んでいる所) ②処分(本棚以外の場所に段ボールで保存いっぱいになったら業者に取りに来てもらう。) ③仮置きあとで読むことがありそうな本 ④保存ずっと保存しておく大切な本 3.情報を分類する フロー情報:これから編集が必要な情報→会話内容・メモなど ストック情報:編集された情報→辞書・雑誌の記事など フロー情報をなるべく早く、ストック情報に変えていく。情報は変質し、すぐに陳腐化してしまう。 となる。 未来の書斎等はまったく現実味が無い内容となるので、参考にできない。(書斎のために家を建てるといった内容) もうちょっと掘り下げて、ご自身の書斎を使っての感想などがあると、よかったなぁと思う。また、IKEAの完全バックアップの下作られた本であるので、IKEAのカタログですか?というくらいIKEA商品が出てきます。 私もIKEAは好きですが、店舗が近くに無く参考にならない点が痛い。 ページ数は、200以上になりますが思ったより内容が薄い。ゆえに★3つ。
Posted by
狭い家でも、一畳でも「自分の城」が作れるというタイトルに惹かれる。 集中するには場所と時間が大事。時間は、家族と個人を上手に別けるしかない。家族が寝ている夜や、早朝をうまく使いたい。
Posted by
ソーシャルメディアにおける情報の活用、スマホ・タブレットを始めとするモバイル機器の利用、ノマドを始めとするワーキングスタイル。これらをいかに駆使して、スキマ時間を有効活用するのか。今、多くのビジネスマンにとって、重要な課題となっているのではないかと思う。 そんなご時世の中、本書...
ソーシャルメディアにおける情報の活用、スマホ・タブレットを始めとするモバイル機器の利用、ノマドを始めとするワーキングスタイル。これらをいかに駆使して、スキマ時間を有効活用するのか。今、多くのビジネスマンにとって、重要な課題となっているのではないかと思う。 そんなご時世の中、本書はある意味で時代の逆を行く「書斎」をテーマとした一冊である。 古くから多くの「知の巨人たち」が日常から離れ、「こもる」ための空間として書斎を活用してきた。そんな書斎も、ネットやノマド全盛の時代において再定義される必要があるのではないか。著者は、そんな観点から「あたらしい書斎のあり方」を提案している。 重厚で荘厳な「書斎」を夢見る人は多いだろうが、現実的にスペースが…という人も多いのが実情。本書では、一畳のスペースから可能な、書斎の作り方が紹介されている。それを可能にしているのが、なんとIKEAの家具。デザインの良さ、価格の手ごろさ、カスタマイズ性の高さの三拍子が揃っているためであるという。 現代における書斎の基本的な要件として定義されているのが、「こもる」ための空間であるということ、そして集中の「スイッチを入れる」ための仕掛けが必要であるということ。そして実際に使われたのは、以下の様な家具たち。 L字型に配置した机をメインとサブの2つの机として利用し、イスを90 度回転させながら「モード」を切り替える。いわゆる日本的”ものづくり”の良さを凝縮したような空間作りである。目指したのは「書斎」という名の小宇宙。 これに加え、後半部分で掲載されている、学びや思索の「質を高める」ための本棚への言及も興味深い。実際に著者は、以下のような4つのエリアに分けて本を分類しているそうだ。 現在:今読んでいる本、これから読む本は机の周りに 処分:処分する本は段ボール箱に 仮置:あとで読み返す本 。「保存」に回る候補として本棚に 保存:ずっと保存しておく重要な本も、もちろん本棚に 印象に残ったのは、「本棚は自分や家族が許容できる最大限のものを最初に設置しておき、その中で運用するのがベストだ」という言葉だ。本棚のキャパを超える量の本は読めない ― そんなよく考えれば当たり前のことに、感心させられる。 ネット時代の情報発信というと、ついついガジェットなどのツール類に目が行きがちだが、自分自身のプラットフォームとなる後方基地をどのように整えるか。そんなところにまで踏み込んだ、まさに”使える一冊”だと思う。 次の本を買うのが先か、本棚を買うのが先か。じっくりこもって考えたい。
Posted by