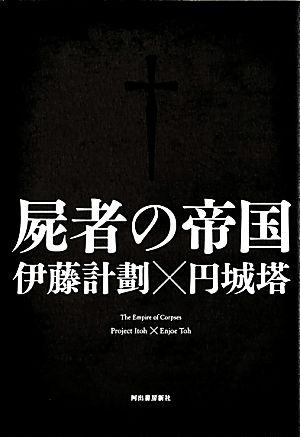屍者の帝国 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読書会レジュメより _/_/_/ 自分の伊藤計劃のイメージは、前作などから人間の「意識」を書く人というもの。このテーマについて円城塔はしっかり引き継いでいることを感じた。「意識」「魂」「自我」――普段自分が活動して考えている「自分」はなんなのだろうと考えさせてくるこのテーマはアイデンティティをぶち壊して人を不安にさせるけど、思索にふけるには楽しい題材です。 初期の何も考えることなく、プログラムのように振る舞う屍者による王国(全人類が屍者化した社会?)は、ハーモニーで描かれたユートピアと正反対かつ同じもの。前回も否定されたけど、自分はこういう結末を理想と考えます。進化の結果、人類は意識を持ったけれども、それは本当に進化なのか。と作品と正反対なことを考えたり。全般的に厨二… 巨大化したシステムのバグを人間の脳(というか複雑系全般)に当てはめるという考え方や、難解過ぎるがゆえに解かれず、その秘密性をもって安全を担保しているパンチカードなど、円城先生だからこそ書けたのではと思えることも。 ワトソン、バトラー、ハダリー、グラント、日本帝国、ザ・ワン……多くの意図が絡み合って展開を解きほぐすので忙しく、主人公サイドではそれぞれの意図を推測しつつ、分裂したり間違っていたりと二転三転して追っていくのが SFの読み方自体が久々の自分には重く感じました。 もちろん理解が及ばなかったところもあって、ワトソンの悪夢比喩や魂についてハダリーとの議論は、皆の解釈が聞きたかった。 ちなみに、今作最大の驚きは、円城塔が普通(という表現は適当でないけど)の小説をかけたこと。 円城先生は数学を超えた”哲学的何か”しかアウトプットできない訳じゃ無かったんや! 自分の中で、『円城先生 = 生物を超えた何か』説が有力視されていたので、自分と同じ俗世の存在らしいということが確認できて安心しました。
Posted by
伊藤計劃を悼む人はもちろん、"芥川賞作家"円城塔を愛する人も、多くいると思われる毛嫌いする人も、もうなんでもいいから是非に多くに読んで欲しい。 DarkKnightが、KickAssが、虐殺器官とハーモニーがそうだったように、飲み屋でなんとかどうにかしてこの本...
伊藤計劃を悼む人はもちろん、"芥川賞作家"円城塔を愛する人も、多くいると思われる毛嫌いする人も、もうなんでもいいから是非に多くに読んで欲しい。 DarkKnightが、KickAssが、虐殺器官とハーモニーがそうだったように、飲み屋でなんとかどうにかしてこの本の話をしたくなる、そんな本。 ことさら作家の物語を作品に読み込むのは、読書のスタイルとして正しくないとは思いつつ、しかし円城塔ほど確立された芸風をもつ作家が、3年(たぶん)をかけて伊藤計劃を悼んで、成りきって、語ったという物語性には抗えない。 イチSF読みとしては、このプロローグの続きは冲方丁あたりに引き継いで欲しかったのだけど、読み終えてみると確かにこの読後感は伊藤計劃のモノであり、円城塔のソレであるなぁと納得せざるを得ない。 この物語の全てを踏まえて、あぁ、死んじゃぁダメだと思う。続編はもちろん、この作家の次回作がないことはもうどうしようもない。あぁ。あぁ。
Posted by
早世の天才 伊藤計劃の遺稿を芥川賞作家の円城塔が引き継いで書き上げた大作。 ある種の壮大な思考実験のような感覚に引き込まれながら、過去の伊藤計劃作品のエッセンスがそこかしこに散りばめられている。実在・架空問わず著名人がわんさか出てきてニヤニヤしながら読んでしまいました(笑)文句...
早世の天才 伊藤計劃の遺稿を芥川賞作家の円城塔が引き継いで書き上げた大作。 ある種の壮大な思考実験のような感覚に引き込まれながら、過去の伊藤計劃作品のエッセンスがそこかしこに散りばめられている。実在・架空問わず著名人がわんさか出てきてニヤニヤしながら読んでしまいました(笑)文句なしに面白い!そして円城塔の才能にも脱帽!
Posted by
結果どこまで伊藤計劃なのかしら、と思っていたらテーマから何からきっちりそれらしくまとめてくれていました。口調というか、独特の文章スタイルもパクっていていい感じです。さすが円城塔! 屍者が生者の道具となり、共生する世界観も独特のもので、そこからお得意の意識と問題へと発展させる。ス...
結果どこまで伊藤計劃なのかしら、と思っていたらテーマから何からきっちりそれらしくまとめてくれていました。口調というか、独特の文章スタイルもパクっていていい感じです。さすが円城塔! 屍者が生者の道具となり、共生する世界観も独特のもので、そこからお得意の意識と問題へと発展させる。ストーリー展開もエンターテイメントさながらですが、この辺は舌を巻く展開であります。 実はあんまり期待していなかったのですが、ほっこり楽しめてお得な気分です。カラマーゾフ兄弟とか、そういうコネタも好きですな。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2012 9/8読了。頼んで買ってきてもらった。 伊藤計劃の遺稿(プロローグ)といくつか残したというアイディアをもとに円城塔が書き上げた、待望の小説。 開く前の期待感、そして何度読んでもワクワク感が異常に高まるプロローグ。微かな不安を覚えながら第1部を読み始めた時の安心感。 結末に至るまで、期待通りの本だった。 まずは既に公開されていた伊藤計劃のプロローグが、本当、何度読んでもワクワクする。 動物磁気説が正しかったとされていて、フランケンシュタインの怪物で実現された死者復活が、意思のない死体を労働力として駆動させる技術として一般化された19世紀の世界。 ロンドン大学医学部に通う若き日のワトソンは、同大を訪れたヴァン・ヘルシング教授と彼に連れられて行った先で出会った"M"に依頼され、アフガニスタン方面でスパイとして活動することになる・・・。 この時点で、 ・現実の史実では否定された学説(動物磁気説や骨相学)がこの世界では採用されている(場合がある) ・他のフィクション作品(フランケンシュタインの怪物、シャーロック・ホームズ、ドラキュラ、007)内での史実がこの世界でも取り入れられている場合がある ということがわかり、ていうかフランケンシュタイン化技術が普及している世界でワトソンが大英帝国のスパイマスターとしてアフガン潜入とかなにそれ超面白そう、っていう雰囲気がとんでもない。 この面白さの雰囲気を、円城塔は畳んでいく方向じゃなく、まずはどんどん広げていく。 『カラマーゾフの兄弟』や『風と共に去りぬ』からもキャラクターを取り入れる。 チャールズ・バベッジの解析機関が普及し、大規模計算が行われ、それらのネットワーク化も既に行われていることにする。 過去にすべての言語を包摂する大語族があったはずだとか、聖書に従えばいずれ死者はよみがえる⇒死者を実際によみがえらせることこそその証になるとか、原初の1人であるアダムを屍者化するとか。ぱっと聞けばトンデモとしか思えない説にしたがって行動する人々が現れる。 さらにもともと、伊藤計劃が世界中をわたる話にしたかった、それも日本にも赴く話にしたいと言っていた、ということを受けて、インド、アフガン、日本、アメリカ、そして再びイギリスへと至るグローバルな話にも仕立てる。 シャーロック・ホームズ、ヴァン・ヘルシング、カラマーゾフの兄弟、明治維新、米南北戦争と風と共に去りぬ、が、同時期の出来事であることは、世界史上でなんとなく知識としてわかっていても、物語の中でそれをこんなふうにつなげて提示される経験はあまりなく、やはり期待がどんどん高まることに。 明治天皇とグラント元大統領の会談中に屍者の軍団が攻めてきてさらにレット・バトラーが狙撃を!・・・って。・・・って!! (きっとまだ元ネタわかっていないキャラや設定もありそうなのでそれはこれから探したい) こういう言い方はなんだが、「熱い」要素を伊藤計劃はプロローグにもともといっぱい詰め込んでいて、その詰め込み方の方針にしたがって円城塔もめいっぱい詰め込み続けた感がある。 そりゃワクワクするに決まっているだろっていう。 もともと「言葉」に執着する2人だけあって伊藤計劃と円城塔の相性もいいのか、もちろん完全な円城文体なんだけどそれほどの違和感なく読み進めることもできた。 バーナビー大尉が適度にギャグ要員にもなってくれて、肩肘はってばかりにならず読めるのも嬉しい(というかバーナビーに対するワトソンの態度がギャグになっているんだが)。 これだけ色々突っ込んだ話で、なんでこの人物の名前が出てこない・・・と気になっていた人物についてもあっと驚く形で名前が出てきて納得できたし、屍者化とは結局なんなのか、その解釈の提示も幾度か変わり、最後に出された説は円城塔ならそういうよねっていう感じにもなっている。 ラストバトル、エピローグに至るまで、伊藤計劃×円城塔にかける期待を裏切らない満足度だった。 欲を言えば期待を超える何かがあるんじゃないかと思ってた、っていうところだけれど(それは期待と何が違うのか)・・・それについては自分が後半、急いで読みすぎた可能性もあるので、あるいは気づいていない要素がありそうな気もするので、引き続き考えたい。
Posted by
自分の「意識」は、真に自分が生み出した「意識」と 言えるのかどうか。 そして生命とは何で、死ぬことは何を意味するのか。 どこか押井守的世界の香りがして、 内容自体も押井守の「攻殻機動隊」を想起させるものの、 哲学を上手くエンタメの中に落とし込んでいて 非常に面白かった。 屍...
自分の「意識」は、真に自分が生み出した「意識」と 言えるのかどうか。 そして生命とは何で、死ぬことは何を意味するのか。 どこか押井守的世界の香りがして、 内容自体も押井守の「攻殻機動隊」を想起させるものの、 哲学を上手くエンタメの中に落とし込んでいて 非常に面白かった。 屍者=ノートパソコン&タブレット的な位置づけの アイデアが面白いし、登場人物のアイデアも秀逸で、 それだけでも楽しい。 ただしかし、伊藤計劃が書き上げていたら…という思いは どうしても拭えない…。
Posted by
伊藤計劃を意識してるなーっと思う箇所は多い。しかし文章が実にハードSFらしさに溢れていて、彼特有の読み易い小説には仕上がっていない。あと内容は難解。いろんな本を読んでないとこの小説から十分な面白さを受け取ることはできないのではないだろうか。
Posted by
円城塔って普通の文章も書けるんですねw 以前から気になっていた作家ではありますが、僕自身伊藤計劃の作品をひとつも読んだことが無いので雰囲気云々については何とも言えないですが、普通のSF小説としてもすごく面白いです。 プロローグ部分からよくこれだけ話を広げることができたなぁと思い...
円城塔って普通の文章も書けるんですねw 以前から気になっていた作家ではありますが、僕自身伊藤計劃の作品をひとつも読んだことが無いので雰囲気云々については何とも言えないですが、普通のSF小説としてもすごく面白いです。 プロローグ部分からよくこれだけ話を広げることができたなぁと思います。また、そのプロローグだけでも一気に引き込まれるような世界観がとてもいいですね。どこまでが伊藤計劃が考えていた道筋なのか。ちょくちょく歴史上の人物やフィクションものの有名な人物が出てきて、それらを屍者(死者に人工的に復活させたもの)が蠢く19世紀の世界にからめて物語を広げていくのは圧巻でした。 屍者はロボットのようなもので、自ら思考したり痛みを感じたりすることなく忠実に命令に従う存在として描かれていますが、それがよくSFで描かれれる人間とロボットの対比と似てるところもあり、異なるところもあり、面白かったです。
Posted by
早逝の天才伊藤計劃が書き残したプロローグを、彼の盟友であり芥川賞作家でもある円城塔が引き継ぎ、完成させた作品。奇しくものこの「屍者の帝国」は、「死んだ人間を化学の力によって蘇らせて、生者が都合良く使うようになった世界」を描いていて、この作品の成り立ち自体が作品世界をなぞっていると...
早逝の天才伊藤計劃が書き残したプロローグを、彼の盟友であり芥川賞作家でもある円城塔が引き継ぎ、完成させた作品。奇しくものこの「屍者の帝国」は、「死んだ人間を化学の力によって蘇らせて、生者が都合良く使うようになった世界」を描いていて、この作品の成り立ち自体が作品世界をなぞっているといっても過言ではない気が。 フランケンシュタイン、カラマーゾフなどフィクションの人物から大村益次郎、ダーウィンなど実在の人物まで多くの人物が登場し、話を盛り上げていきます。そのためある程度の歴史的知識、文学的知識が無いと楽しめないかも。そもそも主人公はホームズと出会う前のワトソンだし。 SFは私が苦手とする文学ジャンルの一つなのですが、伊藤計劃の作品は「もしかしたらこんな世界があるかもしれない」と思わせる説得力、リアリティがあり大好きです。本当にもっと生きて、この混沌とした世界を描いて欲しかった。 ところどころ理解しきれなかった部分もあるので、もう一度読みたいと思います。(が、なかなかの大作で読むのに時間がかかる・・・)
Posted by
伊藤計劃の遺したプロローグに、円城塔がその後を続けた作品。 それを意識してしまうと、企画ものとして読むのか、一つの作品として読むのか、どうしても雑念が湧いてしまう。 章が進むにつれ明らかに円城塔化してゆく文体、「ハーモニー」(第一章)、「虐殺器官」(第二章)、「メタルギアソリッド...
伊藤計劃の遺したプロローグに、円城塔がその後を続けた作品。 それを意識してしまうと、企画ものとして読むのか、一つの作品として読むのか、どうしても雑念が湧いてしまう。 章が進むにつれ明らかに円城塔化してゆく文体、「ハーモニー」(第一章)、「虐殺器官」(第二章)、「メタルギアソリッド」(第三章)との意識的と思える類似性。フィクションからの人物の借用は果たしてどちらの意図なのか? などなど、考え始めるときりがない。 ところが、第三章、事件の真相が明らかになり始めると、そんなことは全く気にならなくなる。なんという到達地点、なんという虚無。これは完全に伊藤計劃のものだ。「虐殺器官」「ハーモニー」のその先を見せてくれたと思う。 不完全さは数々あるけれど、これを出版にこぎつけたこの企画と、円城塔氏にはホントにお礼を言いたい。
Posted by