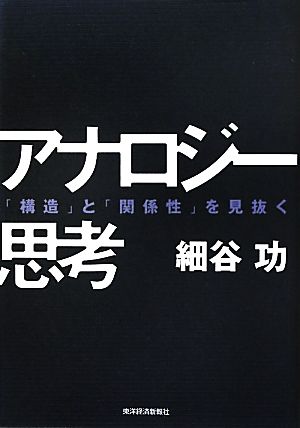アナロジー思考 の商品レビュー
構造を見抜き、他への応用、アイデアの発想⇒混沌とした時代に役立つ。 抽象化がポンと。 アンテナを張る。すべての事象が関心ごとになる。 ・自分から遠い本⇒アナロジー思考有効。
Posted by
アナロジー思考とは、構造レベルで類似するものを借りてきて組み合わせることで新たな発想を得るという思考法のこと。 遠ければ遠いほど、斬新な発想が得られるという。 類似性というと、普段は表面的なものばかりを考えてしまっていることに気付いた。もっと構造的な類似性に刮目する、そのために...
アナロジー思考とは、構造レベルで類似するものを借りてきて組み合わせることで新たな発想を得るという思考法のこと。 遠ければ遠いほど、斬新な発想が得られるという。 類似性というと、普段は表面的なものばかりを考えてしまっていることに気付いた。もっと構造的な類似性に刮目する、そのためには、普段からアンテナを立てておくことが必要とのこと。意識して日常生活を過ごして行きたいと思う。
Posted by
アナロジー思考とは「類推」 「借りてくる」発想 なるべく遠くから「借りてくる」 表面的類似ではなく「構造的類似」を見つけること 具体化よりも抽象化思考力が重要 「つなげる力」は大事 かなり難しく感じたのは、自分が「理数系」が弱いからだろう。とは言え著者が人によって100倍も開き...
アナロジー思考とは「類推」 「借りてくる」発想 なるべく遠くから「借りてくる」 表面的類似ではなく「構造的類似」を見つけること 具体化よりも抽象化思考力が重要 「つなげる力」は大事 かなり難しく感じたのは、自分が「理数系」が弱いからだろう。とは言え著者が人によって100倍も開きが出ると言うように、意識しなくては勿体無い事だ。
Posted by
■アナロジー思考 1.アナロジーとは全く関係ない世界から「借りてくる」発想のことである。 2.世の中のモノはフレームが決まってないから扱いにくい。逆にフレームを創ってしまえば見た目は驚くほどすっきりすする。(佐藤可士和) 3.アナロジー思考は、物事の表面的類似から形状の抽象化、カ...
■アナロジー思考 1.アナロジーとは全く関係ない世界から「借りてくる」発想のことである。 2.世の中のモノはフレームが決まってないから扱いにくい。逆にフレームを創ってしまえば見た目は驚くほどすっきりすする。(佐藤可士和) 3.アナロジー思考は、物事の表面的類似から形状の抽象化、カテゴリーの抽象化などをはかっていき、どこまで遠くを同じとみられるか鍵になる。 4.表面上の具体性だけ見ていると全てが違って見えるが、抽象度を上げてみればそれほど違いがない事が多い。つまり、「関係/構造レベルで同じもの」は同じとみてしまうのである。 5.抽象化思考には、常に具体的事象をさまざまなレベルのまとめ方で頭の中に整理し、階層的にしまっておく思考回路が求められるのである。
Posted by
アナロジーを理論的に知るには最適の本。 1の経験から10を学ぶためには必須の考え方。 未知のものにチャレンジする時の道しるべとしても使える思考法。 ただ、ちょっとくどい。
Posted by
【レビュー】 読者をけむにまくような内容が多いビジネス本の中で、これはよく書けている。ビジネス「書」といえる。おそらく、ジェームズ・ヤングの「アイデアの作り方」と本書の2冊でイノベーションは起こせるだろう。 【特記事項】 ●アイデアは既存のものの組み合わせ →ではどのように組...
【レビュー】 読者をけむにまくような内容が多いビジネス本の中で、これはよく書けている。ビジネス「書」といえる。おそらく、ジェームズ・ヤングの「アイデアの作り方」と本書の2冊でイノベーションは起こせるだろう。 【特記事項】 ●アイデアは既存のものの組み合わせ →ではどのように組み合わせるのか =アナロジー(類推。比喩)である。 ●既知の領域(ベース)から、未知の領域(ターゲット)へうまくマッピングすること=アナロジー思考 ・マッピング:ベースからより抽象化していけばいくほど、うまいアナロジーができる。 ・アナロジー思考はアブダクションである。 ●ターゲット課題の設定→ベース領域の選択→マッピング→評価 ●マッピングとは、類似性を探すこと →類似性:表面的類似性と構造的類似性。アナロジー思考では後者である。 (表面的類似性:ギャグなど) ・構造的類似を見抜くために、いくつかの関係・構造パターンを頭に入れておく。対称型(並立、対立、相互因果)、非対称(院が、順序、大小関係)、包含関係、一部包含、一部共通、非共通、循環型、統合・分解型など。 ●具体思考と抽象思考の双方が大切。具体思考が問題を創造し抽象思考が解決する。 ●アナロジー思考を鍛えるには、常に物事を観察し、それを退けるのではなく蓄えるようにしていく。違う、ではなく、何か応用できないか、という視点で。 ●アナロジーを強調しすぎないように。それは状況証拠レベルであって、物的証拠レベルには至らない。
Posted by
『地頭力』著者の新刊。関係のない2つの世界から「借りてくる」発想法=アナロジー思考をメインテーマとした本。 既知のことを利用し、未知のものを類推する思考法は、ビジネスだけでなく日常生活にも応用できると思います。 著者があとがきでも述べているように、アナロジーの演習問題があれば...
『地頭力』著者の新刊。関係のない2つの世界から「借りてくる」発想法=アナロジー思考をメインテーマとした本。 既知のことを利用し、未知のものを類推する思考法は、ビジネスだけでなく日常生活にも応用できると思います。 著者があとがきでも述べているように、アナロジーの演習問題があればもっと良かったと思うので☆4つ。
Posted by
一見何の関係もなさそうな出来事を、日ごろから意識して自分の仕事や研究に当てはめて考えてみる。頭では分かっているけれど、なかなか難しい。 本書ではアナロジー思考はどうすれば出来るようになるのか、身近な具体例に基づきながらその方法を解き明かしている。予算管理の新手法が、実は「がばん...
一見何の関係もなさそうな出来事を、日ごろから意識して自分の仕事や研究に当てはめて考えてみる。頭では分かっているけれど、なかなか難しい。 本書ではアナロジー思考はどうすれば出来るようになるのか、身近な具体例に基づきながらその方法を解き明かしている。予算管理の新手法が、実は「がばん」の中身からヒントを得て開発されたという例など、身の回りにはブレークスルーの種、イノベーションのヒントがごろごろ転がっている。結論は、常に思考を働かせてあらゆるモノや出来事を、表面レベルではなく構造レベルで共通点を探るようにすること、である。
Posted by
本の内容として、予想通りの論点トピックが多く、☆4つ。 ただ、アナロジーのための思考方法を一度体系的に言語化して学びたいという人にはお薦め。 巷にあるロジカルシンキングの本とはちょっと一味違って一読はしてみていいと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
書店で「地頭力」の筆者の新刊が出たことを知り、中身を読まず買ってしまた。思考することを思考するという類の本ではあるが、日々観察の視点にはとても役立つと思う。思いっきり抽象度が高いが、故に応用力が効きそうと思う。この本の目標部数いったら、ムック形式本が出てセットで販売するのでは…?
Posted by