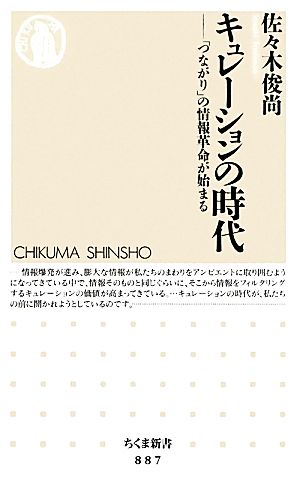キュレーションの時代 の商品レビュー
内田和成のブログでオススメされていて、読んだ一冊。 所感としては、当時は新しかったのかもしれないが、今となってはけっこう当たり前だし、外れた予測も多いなぁ、と。 ただ、自分が感じているインターネットの普及による情報革命を整理するためには、すごく役に立った。 あと、映画産業が音楽産...
内田和成のブログでオススメされていて、読んだ一冊。 所感としては、当時は新しかったのかもしれないが、今となってはけっこう当たり前だし、外れた予測も多いなぁ、と。 ただ、自分が感じているインターネットの普及による情報革命を整理するためには、すごく役に立った。 あと、映画産業が音楽産業が栄枯盛衰をどのように辿ったのか、についての解説は、一般論ではなく、非常に面白かったと思った。
Posted by
消費の仕方が、記号消費(セレブアピールしたくて、外車買うetc)➡つながり消費(一生懸命作った品物を、背景の物語に同意して買う) と変化してきた。 この変化は、ソーシャルメディアの存在により可能になった。 バーチャルとリアルが融合してきてる。面白い世界になっていくね。
Posted by
我々を取り巻く情報環境の変化を説いた本。 本書の題となっている、キュレーションとは、情報を収集し、選別し、そこに新たな意味づけを与えて、共有すること。 そして本書では、それを行なう人のことをキュレーターと定義しています。 1人の個人が社会の中で生きていくためには、社会から情報...
我々を取り巻く情報環境の変化を説いた本。 本書の題となっている、キュレーションとは、情報を収集し、選別し、そこに新たな意味づけを与えて、共有すること。 そして本書では、それを行なう人のことをキュレーターと定義しています。 1人の個人が社会の中で生きていくためには、社会から情報を取り入れることが必要です。 しかし、社会に存在してる全ての情報を取り込んでしまうと、情報のノイズに埋れて、どのような変化が社会で起きているのかを見通すことが出来なくなってしまう危険性がある。 そこで、我々は情報をフィルタリングする必要が出てくるのです。 ソーシャルメディアの世界では、キュレーターによって様々な情報がフィルタリングされ、絶え間なく組み替えられていきます。 また、収集される以前は膨大なノイズの海の中に漂う情報の断片でしかなかった存在が、キュレーターに拾い上げられることによって新たな意味を与えられ、別の価値をもって光り輝き始めるのです。 そして、キュレーターの周りに小さな情報の生態系のようなものがつくられる。 それが、本書で述べる新たな情報社会のカタチです。 本書で著者はこのように言います。 「このような世界にあっては、もう旧来の情報流通の常識は、一切通用しなくなるでしょう。マスメディアを経由して情報をコントロールする旧来の『広告』は消滅します。 (中略) マスメディアの記者に情報を提供する『広報』も意味をなくしていきます。」 マスメディア(テレビや新聞、雑誌など)の力を借りなくとも多くの情報を入手できる時代です。 著者の言うような変化を誰もが強く感じているのではないでしょうか。 しかし、例え誰もが感じる時代の変化でも、改めてその背景や理由などを理解しておくことは非常に重要なことだと思います。 本書を読んで、情報社会の変化を改めて整理することができました。 今後、このような変化は加速していくはずです。 このタイミングで、みなさんも今一度本書で、我々を取り巻く情報社会の変化を整理してみてはいかがでしょうか。 「今」を見つめ、「将来」に備える。 それが大事です。
Posted by
これからの時代は記号消費的な社会ではなく、つながりが重要になってくる! というのが本書のテーマ。 キュレーターと呼ばれるような「視座」を提供する人々。 それらにチェックインして情報を受け取るフォロワー。 そのような関係が新たな情報革命のかたちとして現れていくという。 Twit...
これからの時代は記号消費的な社会ではなく、つながりが重要になってくる! というのが本書のテーマ。 キュレーターと呼ばれるような「視座」を提供する人々。 それらにチェックインして情報を受け取るフォロワー。 そのような関係が新たな情報革命のかたちとして現れていくという。 TwitterやFacebookが普及した今だからこそ、 本書での指摘はわかりやすい。 これからの社会を生きていくために読んでおいて損はない一冊。
Posted by
従来のマス記号消費から最近のつながり消費への移り変わり、キュレーションを通じての情報収集についての大局的な流れがまとめられた本。とても読みやすい。バリエーションに飛んだネタからの本筋へのつながりがよかった。 消費の変遷や情報の流れについて、なんとなく感じていたことが言語化されて...
従来のマス記号消費から最近のつながり消費への移り変わり、キュレーションを通じての情報収集についての大局的な流れがまとめられた本。とても読みやすい。バリエーションに飛んだネタからの本筋へのつながりがよかった。 消費の変遷や情報の流れについて、なんとなく感じていたことが言語化されてスッと入ってきた感じ。 記号消費から機能消費へ、さらにはつながり消費というのは全く同意。これは最近はやりのストーリー消費にも通じていると思う。 これまでは自身の視座でしかインプット出来ていなかったが、キュレーションによって様々な視座を通じての情報が得られるようになった。 氾濫している情報ノイズの中から必要な情報を抜き出すのは難しい。そこでキュレーターを通じての情報収集することで効率的にインプットできる。タコツボ化しないためには、フィルタリングのボーダーを柔軟にすること。硬直化すると、変化に対応できず情報をスルーすることになってしまう。 ネットとセレンディピティの実現の話や、プライバシー問題とそれを解消したチェックインシステム、モンゴル帝国にみるプラットフォームなど興味深いネタもあり、面白く読めた。
Posted by
はしょりながら読みました。 これからの予見ではなく、いま起きていることを整理してくれています。 グローバル企業に勤めている場合はあまり役に立たないかもしれません。民族、主義、国をまたいで商売するということは、昔からこういうことをしていると思いますので。 著者が、自らの考察で...
はしょりながら読みました。 これからの予見ではなく、いま起きていることを整理してくれています。 グローバル企業に勤めている場合はあまり役に立たないかもしれません。民族、主義、国をまたいで商売するということは、昔からこういうことをしていると思いますので。 著者が、自らの考察で、本にするモチベーションができたのは硬直化したマスコミにいるからでしょう! なんにしても、現状整理、大変よくできました。引用が浅すぎますけどね。 ジャーナリストなら、未来を予見するぐらいじゃないとね!メイカーズ、フリーをお手本に!
Posted by
キュレーターとは誤解を恐れずに簡単に書くと美術用語で絵画に意味付けを与えてストーリーを作りだす役割。 佐々木氏は情報化社会では情報を司る存在で「収集し、選別し、そこに新たな意味付けを与えて共有する」役割を持つ。 ブランド志向の「記号消費」は消滅し、「機能消費」「つながり消費」の...
キュレーターとは誤解を恐れずに簡単に書くと美術用語で絵画に意味付けを与えてストーリーを作りだす役割。 佐々木氏は情報化社会では情報を司る存在で「収集し、選別し、そこに新たな意味付けを与えて共有する」役割を持つ。 ブランド志向の「記号消費」は消滅し、「機能消費」「つながり消費」の時代がやってくる。 「モノ」から「モノガタリ」へと。 キュレーターはコンテンツを紹介するだけではなく、コンテキスト、すなわち意味付けを与えてて市場に情報を与える。そしてそれがつながり、すなわりエンゲージメントを生み出す。 これこそがつながり社会。 もし情報化社会で勝つビジネスをするならば「プラッットフォーム」を目指すしかない。 1)圧倒的な市場支配力 2)使いやすいインターフェース 3)自由な活動の場 を提供するプラットファームだけが勝てる。 マーケティングメッセージが満載の本。ぜひ購入して欲しい。
Posted by
マスメディア・マスプロダクトはではもうダメだという話を、幾つかの事例を基に、ビオトープ、アンビエント、キュレーションといったキーワードを使いながら説いていく。 ちょっとどうかなという内容もあるが、概ねそうなんだとは思う内容。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いい意味で、雑多な本。人を視座とする情報流通について、多面的に見ている。つまるところ「こんな見方もあるんだよ」を提供するのがキュレーション。意味付けも伴いつつ。(((作品を選び、それらを何らかの方法で他者に見せる場を生み出す行為)))
Posted by
一座建立、ホストとゲストが共に作る素敵な空間。 主客一体の思想によるライブ感みたいなのって千利休の時代から存在してたのね。
Posted by