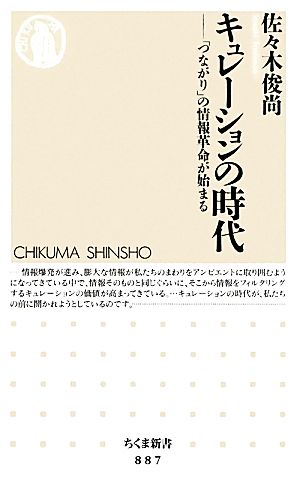キュレーションの時代 の商品レビュー
【総評】 具体例を交えつつ、ここ数年の消費・広告・情報収集の劇的な変化に着目しつつ、現在どのようなことが起きているのか、ということを、ビオトープ・コンテキスト・キュレーター・コンテンツなどの側面から読み解いている。小分けにされた項の文量がちょうど良く読み易い。 【各章まとめ】 ...
【総評】 具体例を交えつつ、ここ数年の消費・広告・情報収集の劇的な変化に着目しつつ、現在どのようなことが起きているのか、ということを、ビオトープ・コンテキスト・キュレーター・コンテンツなどの側面から読み解いている。小分けにされた項の文量がちょうど良く読み易い。 【各章まとめ】 1章 無数のビオトープが生まれている ブラジル出身のミュージシャン、ジスモンチの日本でのコンサート成功のために尽力した音楽プロモーターの田村直子さんのアプローチ方法等を具体例に出しながら、以前は情報の流量が少なく、それらがテレビ・新聞などを伝って人に伝わるという状態だったが、現在、指数関数的に日々増加していく情報の中では、そのようなメディアではなく、SNSやブログなどから、必要な情報だけを抜き取る必要があるし、そのような人々が増えている。この「情報を求めている人々が存在する場所」を「ビオトープ」と呼ぶ。これが、現在至るところに存在し、現代においては、これを見つけること、もしくは、闇雲に広告を打つのではなく、ビオトープに的確にアプローチすることが重要である。 2章 背伸び記号消費の終焉 記号消費とは、外車を乗り回してるひとは裕福だとか、フランクミュラーの時計をしてる人は裕福だとか、本来車や時計は、どんなブランドの物でも、機能に差は無いにも関わらず、それを持ってる自分的な感覚が先行する消費のことである。現代では、その記号消費が無くなりつつあり、変わって、車は移動の手段であってブランドや金額は関係ないというような、機能消費に移行している。必要な時に乗れれば良いという発想から、カーシェアリングが生まれたのもそのような潮流の産物である。しかし、完全に機能消費にはならず、消費とは、社会性という枠組みの中の重要な行為であり、社会と関わるために消費をする。よって、そこに人々はつながりを求める。秋葉原殺人事件の加藤被告が、掲示板で自分を偽ってまで住人とのつながりを求めたように、人は消費につながりを求める。それが、作り手が見える商品を購入する応援消費に繫がる。承認と接続のツールとしての消費。そこに存在する「共鳴出来る。共感出来る。」という土台こそが「コンテキスト」なのである。記号消費は消滅し、機能消費とつながり消費の、二分化がこれから進んで行く。
Posted by
刺激の多い良書でした。メッセージが多くて、まだ整理しきれてないが、、、 これからの情報技術は、人の意志をうまく取り込んで、人と情報、さらに情報の後ろにいる人とのつながり、共鳴を支援することが大事。例えばfoursquareはチェックインによって人の意志(共有したい伝えたい情報があ...
刺激の多い良書でした。メッセージが多くて、まだ整理しきれてないが、、、 これからの情報技術は、人の意志をうまく取り込んで、人と情報、さらに情報の後ろにいる人とのつながり、共鳴を支援することが大事。例えばfoursquareはチェックインによって人の意志(共有したい伝えたい情報がある)を捉えている。人の介在で画一化せず、流通する情報の多様性、偶発性も確保できる。
Posted by
情報ノイズの中から本当に欲しい情報を取捨選択するのは難しい。 いくら権威のある人の情報でも間違っている事があるので注意したい。
Posted by
一年半ほど前の本ですが、一度しっかりとキューレーションについて知っておこうと思い、読むことにしました。 もう少し、情報が膨大になる中での社会の変化、その中にあってキュレーターと呼ばれる人の必要性、重要性といった感じの情報社会という視点からの本だと勝手に想像していたわけですが、いい...
一年半ほど前の本ですが、一度しっかりとキューレーションについて知っておこうと思い、読むことにしました。 もう少し、情報が膨大になる中での社会の変化、その中にあってキュレーターと呼ばれる人の必要性、重要性といった感じの情報社会という視点からの本だと勝手に想像していたわけですが、いい意味で裏切られました。 少し前に読んだ『第四の消費』のように、消費のあり方の変化に合わせた人とのつながりの消費の重要性が述べられています。 ソーシャルメディアがマスコミを凌駕することで、情報の信頼性より人の信頼性が確実になるため、キュレーションの必要性はますます高くなると思います。 キュレーション 「無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること」 ビオトープ 「情報を求める人が存在している場所」 アンビエント化 「私たちが触れる動画や音楽、書籍などのコンテンツがすべてオープンに流動化し、いつでもどこでも手に入るようなかたちであたり一面に漂っている状態」 2010年代の消費の本質=商品の機能+人と人とのつながり ↓ 情報収集+人と人とのつながり ↓ 人が介在する必要性 「視点」だけでなく、世界をどう見るのか、どう評価するのかといった世界観や価値観という「視座」に進化。「視座=人」にチェックインすることで、その人のコンテキストという窓から世界を見る →視座を提供する人がキュレーター プラットフォームの定義 ①圧倒的な市場支配力を持っていること ②非常に使いやすいインタフェイスを実現していること ③プラットフォームの上でプレーヤーたちに自由に活動させる許容力があること <この本から得られた気づきとアクション> ・消費の方向性は、きっとここで指摘されているようになるだろう。その中でどんな情報が信頼でき、意味を持っているのか、これからは個人個人で判断して価値を見出していく姿勢が必要なんだろう。 <目次> プロローグ ジョゼフ・ヨアキムの物語 第一章 無数のビオトープが生まれている 第二章 背伸び記号消費の終焉 第三章 「視座にチェックインする」という新たなパラダイム 第四章 キュレーションの時代 第五章 私たちはグローバルな世界とつながっていく
Posted by
2010年代における情報流通のプラットフォームはどのようになっていくか。その中心 となる「キュレーション」とは何か。情報収集のあり方が目まぐるしく変化しつつあるなか、メディアの未来像はどのようであるべきか。 いとも簡単に人と人がつながり、個人単位での小さなメディアが急速に力を伸...
2010年代における情報流通のプラットフォームはどのようになっていくか。その中心 となる「キュレーション」とは何か。情報収集のあり方が目まぐるしく変化しつつあるなか、メディアの未来像はどのようであるべきか。 いとも簡単に人と人がつながり、個人単位での小さなメディアが急速に力を伸ばし、マスメディアが得意としてきた大きなビジネスが力を失いつつあります。 そんな中メディアに求められるのは、個々人のの視座に基づいた「自分自身の言葉」で語ることのできる人が、お互いにエンゲージメントによってつながっていくことである。 …って感じの内容です。 ともすれば単なる暇つぶしともとられかねない、日々のニュースや読書を通じた情報収集をどのようにビジネスモデルとして成立させていくか? ということを考えるためにも役立つ1冊です。 自分が普段行っている情報収集や読書をどのようにアウトプットしていくか、というのを模索していた自分にとって、大きなヒントを与えてくれる1冊でした。 音楽ライブのプロモーターのように、自分の目線に基づいて、ある特定の人々に強く訴えかけられる枠組みを提供するのが、いちばん現実的なアウトプット手段かな、と感じています。 おそらく、レコード会社やプロダクション、もしくはニュースサイトみたいな枠組みが現実的な類型なのかな…と感じています。その類型に基づき、自分なりの表現手段を見いだせたら、と。
Posted by
本書概要 キュレーションの時代 一言で言うと「つながり」の情報革命がはじまる ということです。 「キュレーションとは無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人々と共有すること」とある。 情報の流れの究極の課題を...
本書概要 キュレーションの時代 一言で言うと「つながり」の情報革命がはじまる ということです。 「キュレーションとは無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人々と共有すること」とある。 情報の流れの究極の課題を三つあげています。 ①ある情報を求める人が、いったいどの場所に存在しているのか。 ②そこにどうやって情報を放り込むのか。 ③そして、その情報にどうやって感銘を受けてもらうのか。 「この情報を求める人が存在している場所」を、本書ではビオトープと呼んでいる。 私たちはその巨大なグローバル化したブラットフォームの上で、無数のビオトープを形成し、そこに無数のキューレターを生み出し、いたるところに生息しているキューレターにわれわれはチェックインし、その視座によって情報を縦横に得ていく。 マスメディア時代からネット時代になり、「自分が求めている情報はどこに行けば得ることができるのか」ということが不明確になったと言っています。そして、この情報の洪水の中で法則が見出される、解き明かすことが、本書の最終ゴールとしています。 「大切なのは、将来出現してくるソーシャルメディアを軸とした情報の流路がどのような全体像になっていくのかというビジョン。」だと最後に語っています。 注釈 視座とはコンテキストを付与する人々によってもたらされる他者の価値観。 所見 では、我々はどのように行動して行くべきか? 私は下記の五点だと考えます。 ①企業であれ、個人であれ、誠実に正直に生き、信用、信頼されるように努める。 ②世界のビオトープを俯瞰して見る。 ③自分自身の考え方を明確に示して、世の中に伝える。 ④新しい価値観が生まれることを理解する。 ⑤様々な人々と交流を図り、より良い世の中のために新しい価値を共創していく。 以上です。
Posted by
読了したのは、かなり前だが、示唆に富んだ本だったという淡い記憶が。。。応援消費 博報堂 機能消費とつながり消費への二極化 アテンションエコノミー アンビエント化 エンゲージメント 主客一体 一座建立 (世阿弥「風姿花伝」) 暗黙Web(implicit web)とチェック...
読了したのは、かなり前だが、示唆に富んだ本だったという淡い記憶が。。。応援消費 博報堂 機能消費とつながり消費への二極化 アテンションエコノミー アンビエント化 エンゲージメント 主客一体 一座建立 (世阿弥「風姿花伝」) 暗黙Web(implicit web)とチェックイン タコツボ化とセレンディピティ 視点の固定化 マルコヴィッチの穴(スバイク・リー) Foursquare. ロケーションレイヤー 視座へのチェックイン アウトサイダーアート ジャン・デュブュッフェ アートブリュット(生の芸術)
Posted by
本書のタイトルにもなっている「キュレーション」。 これは、「無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること。」だそうです。 最近よくSNSが取り上げる中で、「気づき」を与えてくれる一冊であると感じます。...
本書のタイトルにもなっている「キュレーション」。 これは、「無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること。」だそうです。 最近よくSNSが取り上げる中で、「気づき」を与えてくれる一冊であると感じます。 事例の挙げられていた内容が興味深かったです。 生前は売れなかった画家や、コアなファンを持つアーティストが日本に来てチケットが即日ソールドアウトしてしまった例などが挙げられておりましたが、ある人がその情報が有意義である、価値があると思い、多くの人に共有し、またそれを受け取った人からも拡大していったという流れになっています。 逆に、悪意のある情報が、「有益」だと受け取られ、それを拡散してしまったというケースもあります。 ITサービスに対するリテラシーの重要性と言われる世の中ですが、 「情報」そのものに対しても、個々人のレベルで価値基準の判断が必要になっていくと感じます。 ちなみに、キュレーションとは、美術館のキュレーター(博物館・美術館等の展覧会の企画を担う専門職)に由来しているそうです。
Posted by
キュレーションとは。 無数の情報の海の中から、自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有すること。
Posted by
キュレーションっていまいち単語の意味がいまいちよく理解できていないので、そのために役立てばと思って読んでみた。
Posted by