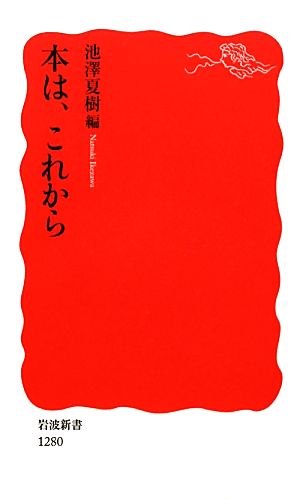本は、これから の商品レビュー
最近は、電子書籍についての考察が続くわけであるが、、 アマゾンクリックで購入した、こちらもリアル本。 著名人たちは、どのような思いで、 この電子書籍を眺めているのか気になってクリックした! 表題のは、"これから" というぐらいだから、 (『燃えよ剣』の土方...
最近は、電子書籍についての考察が続くわけであるが、、 アマゾンクリックで購入した、こちらもリアル本。 著名人たちは、どのような思いで、 この電子書籍を眺めているのか気になってクリックした! 表題のは、"これから" というぐらいだから、 (『燃えよ剣』の土方には怒られそうなのだが、、) 「どうなる、こうなる」ということを37人の著名人があれこれ述べる。 「リアル本は無くなるのか否か!」はたまた「両方残る!」だとか云々。 個人的には、 「どうなる、こうなる」と語り、んだから「俺は、こうする!」と簡潔に述べてくれた、宮下志朗さんが潔い。 読みながら結局のところ思ったのは、 「紙本」か「電子本」かは好みの問題、ということだな。 一長一短であり、「そんで、お前はどうする?」ということだ。 ただ、これからどうなろうとも、最終的に、 「言葉」は無くならないのだ。 読んだ(もしくは、見た)人の心の中に、残る。 果たして、大昔、手書きが印字になった時に、 『手書きが醸し出す"温もり"は、無くなったのだろうか?』 印字ゆえに、 『著者の意図したことは、伝わらなかったのだろうか?』 否、 「言葉」は今も昔もあり続けて、そのメッセージは読み手に伝わった。 誰かが書いた「言葉」を、 自分自身にどう活かすか? (あるいは、どう楽しむか?) ―言葉。 たぶん、そこに書かれた言葉と、 既に読み手の中にあった言葉の意味が一致した時に初めて、 読み手がそれに共感し、震える(奮える)のだろう。 それは、「小説を読んで泣いてしまうこと」であり、「自己啓発書を読んで何かやろうと思い立つこと」であるわけで。 個人的、第2冊目の作品は 鼓舞!@パブー(http://p.booklog.jp/book/18667) 「言葉」の力とは、これ如何に! ただいま、絶賛発売中!無料です! #という、宣伝オチwww
Posted by
2010年は電子書籍元年と言われ、盛んに議論が行われた。 本は、これからどうなるのか? その問いかけに識者たちが答えている。 ところが、さすがは電子書籍途上国、日本。 ほとんどの人がピントのずれた話ばかり。 特に電子書籍に触れたことのない人が想像だけで語るとは。 本が生き残る...
2010年は電子書籍元年と言われ、盛んに議論が行われた。 本は、これからどうなるのか? その問いかけに識者たちが答えている。 ところが、さすがは電子書籍途上国、日本。 ほとんどの人がピントのずれた話ばかり。 特に電子書籍に触れたことのない人が想像だけで語るとは。 本が生き残るか、電子書籍がそれを駆逐していくかというくだらない話が多い。 情報を読むための媒体が紙かデジタルかの違いだけで、それは読者が選ぶだけのこと。 それを論考してどうするのか? 電子書籍の本質はそこではないのではないか。 私もうまくは書けないが、知を体系的に捉える構造がより強固にできるということではないだろうか。 例えば学術書を読んでいて、古典が引用されていた。 そこでその文章からリンクで、その古典にとぶ。 さらにはその古典を批判する古典へとぶ。 もちろんこれは古典ではなく、新着のブログでもいい。 そして秀逸な論考があれば、それを本に印刷したり、端末にダウンロードする。 電子書籍によって出版界全体の質は高くなり、大切な紙の本を書棚にコレクションする人は増えるのではないだろうか。 本書のなかでも、さすがは「知の巨人」松岡正剛氏。 彼の論考だけは読んだほうがいい。
Posted by
個人的には、内田樹氏と出久根達郎氏の文章に共感。やっぱり、手にとって読む、ということが基礎になければ、電子書籍の存在意義も危ういのではないでしょうか。小さい子どもを相手に電子書籍で読み聞かせなんてできっこないし、そんなことをしていたら、子どもが読書を好きになるはずがない。読書が好...
個人的には、内田樹氏と出久根達郎氏の文章に共感。やっぱり、手にとって読む、ということが基礎になければ、電子書籍の存在意義も危ういのではないでしょうか。小さい子どもを相手に電子書籍で読み聞かせなんてできっこないし、そんなことをしていたら、子どもが読書を好きになるはずがない。読書が好きな人口が減少したら、電子書籍だって存在できないはず。って思いますけどねえ。
Posted by
本は、これから読了。 寄稿者は図書館員、書店員、大学教授、ブックコーディネーター、編集者、古書販売員、写真家、デザイナーなど多種多様。 紙の本至上主義・iPadやKindle嫌いっていう一辺倒な意見ばかりではなくて、とりあえず読んでいて安心した。 印象に残ったのは以下 上野千...
本は、これから読了。 寄稿者は図書館員、書店員、大学教授、ブックコーディネーター、編集者、古書販売員、写真家、デザイナーなど多種多様。 紙の本至上主義・iPadやKindle嫌いっていう一辺倒な意見ばかりではなくて、とりあえず読んでいて安心した。 印象に残ったのは以下 上野千鶴子「書物という伝統工芸品」 出久根太郎「追放本のてんまつ」 松岡正剛「読前・読中・読後」 岩楯幸雄「本屋をめざす若者へ」 上野千鶴子さんの書かれていた「伝統工芸品として残る紙の書物』と言う表現、いずれはそうなってしまうのかもしれないけれど、そういう形でしか紙の本が存在できなくなってしまってはなんだか一抹切ない。 電子書籍がこれからどんどん進んでいくことには賛成。賛成なのはきっと紙の本が無くなりはしないだろうと感じているから。 本のコンテンツによって、紙と電子メディアで向き不向きがあるのはもう語られてるし。 池上彰さんがkindleやiPadは道具であって、読書と言う行為は無くならないという言葉通り。 あ、でも自分は紙の本を買うことも辞めないと思うけれど。 代々木上原にある幸福書房の岩楯さん「健闘を祈ります」という言葉、とてもよかった。 教科書をまずはやく電子化しようって話がひとつも無かったのには、意外です。
Posted by
2011 1/15読了。研究室蔵書・・・いや、先生の個人蔵書? 本に関する37人の人々によるエッセイ集。1つ1つは短いのに、いくつかはとんでもなく濃い。正にエッセイ集で、研究テーマ柄色々と考えたくなることもあるのだがそれ以上に読み物として享受したいし、仕事の眼を外して読みたい本。...
2011 1/15読了。研究室蔵書・・・いや、先生の個人蔵書? 本に関する37人の人々によるエッセイ集。1つ1つは短いのに、いくつかはとんでもなく濃い。正にエッセイ集で、研究テーマ柄色々と考えたくなることもあるのだがそれ以上に読み物として享受したいし、仕事の眼を外して読みたい本。 製本講師の四釜裕子さんのエッセイがとても面白かった。 「紙の本がなくなることはないので心配はしていない。なぜなら私たちの手はそれを作ることができるので、失いたくない思いの深さだけ残すことができるからだ」。 昔、僕が書いた小説を幼馴染が製本していたのを思い出した。 失いたくなければ、僕たちはそれを作ることができる。
Posted by
タイトル通りのテーマで書かれたエッセイ集。それぞれがそれぞれの立場からいろんな切り口で、本とは、読書とは、電子書籍とは、と語る。 大いに同意するとこもあるし、ちょっと言い過ぎじゃないの?って思うところもあった。 自分としては、電子書籍とは流通革命、と捉えているが、全体を読み終えて...
タイトル通りのテーマで書かれたエッセイ集。それぞれがそれぞれの立場からいろんな切り口で、本とは、読書とは、電子書籍とは、と語る。 大いに同意するとこもあるし、ちょっと言い過ぎじゃないの?って思うところもあった。 自分としては、電子書籍とは流通革命、と捉えているが、全体を読み終えてその思いを新たにした。
Posted by
「本は、これから」池澤夏樹 編 岩波新書。 37人の各界文化人による、2010年昨今の電子書籍動向の中での、紙の本への思いを綴るエッセイ集。 かなりいろいろな立場の人々の視点で語られていて、なかなか読み応えがありました。 比較的紙の本への憧憬が勝る内容でしたが、電子書籍の登場...
「本は、これから」池澤夏樹 編 岩波新書。 37人の各界文化人による、2010年昨今の電子書籍動向の中での、紙の本への思いを綴るエッセイ集。 かなりいろいろな立場の人々の視点で語られていて、なかなか読み応えがありました。 比較的紙の本への憧憬が勝る内容でしたが、電子書籍の登場も肯定的に受け止めつつ、 結局のところそれらが内包する知的総体とどのような付き合い方をするのか、みたいな内容で、 最近の過度な端末機能ありき流通制度ありきの議論とは一線を画す。 その点だけでも手に取る価値ありですよ。 まあ敢えて批判をおそれず言うならば、著者の方々はかなり上の年代の方が多いので、 彼らのいうところの文化と僕達の感覚の文化は確実に変容している。 (それにしても普遍的によい作品に出会いたい欲求てのは一緒でしょうけれども!)(3)
Posted by
電子書籍と既存の本はどうなるのか、ということが論議の中心。本好きな人々がそれぞれの立場から考え方を述べる。古書店の人、図書館の人、本が好きな教授などなど、フィールドのちがう立場から述べられる意見は参考になる。が、これからどうなるのか?というのは、誰しもどうなるのかわからない、とい...
電子書籍と既存の本はどうなるのか、ということが論議の中心。本好きな人々がそれぞれの立場から考え方を述べる。古書店の人、図書館の人、本が好きな教授などなど、フィールドのちがう立場から述べられる意見は参考になる。が、これからどうなるのか?というのは、誰しもどうなるのかわからない、ということで結論を述べている本ではない。 出版まっただ中の人は、静観しているわけにもいかず、うーん。
Posted by
「本は、これから」という題目で37人の読書人が電子書籍に対する考え方を書いている。既存の「本」の立場の人が多いので、本は残る、残すべきと考え手いる人が多い。電子書籍礼賛派の人も読むべき一冊。 書き手もよくぞ、この人をという人が多く編者も見事。 さすが、「本」派だと思うのは、文章が...
「本は、これから」という題目で37人の読書人が電子書籍に対する考え方を書いている。既存の「本」の立場の人が多いので、本は残る、残すべきと考え手いる人が多い。電子書籍礼賛派の人も読むべき一冊。 書き手もよくぞ、この人をという人が多く編者も見事。 さすが、「本」派だと思うのは、文章が見事なこと。電子書籍礼賛派はえてして口語調になったりするが、この本では、どの人の文章も、大学入試に出題されるレベルまで、磨かれている。感嘆。
Posted by
40名弱によるオムニバス形式。昨今の電子書籍ブームに対するアンチテーゼ的著書、と表現してしまっても問題ないだろう。 タイトルのとおり「本」を愛する方々による著書なのだが、執筆者の面々は多種多様だ。批評家や教授をはじめ、写真家、デザイナー、国立図書館長、音楽家、書店勤務者…など。...
40名弱によるオムニバス形式。昨今の電子書籍ブームに対するアンチテーゼ的著書、と表現してしまっても問題ないだろう。 タイトルのとおり「本」を愛する方々による著書なのだが、執筆者の面々は多種多様だ。批評家や教授をはじめ、写真家、デザイナー、国立図書館長、音楽家、書店勤務者…など。 各々が異なる切り口で本への愛情を表現する。 中でも興味深いのは、各々の本にまつわる体験やストーリーだ。幼少期から現在に到るまで、本にまつわるエピドードが紹介されるのだが、それらが結果的に多彩な個性を紡ぎ出している。「40名弱…」と冒頭で記したが、まるで「40人40色」とも言うべき様相をなしているのは、それが起因しているに違いない。 一方で、あまりに本への執着が強く、短絡的な批評が散見される。どっぷり本に魅了されている方々なのである程度は承知していたけれど、フラットな視点から批評しようという努力はあまり感じられなかった(勿論全員というワケではなかった)。 ただ、こうした偏った批評は「本に対する愛情」の裏返しである、ということは理解すべきだ。 今後、電子書籍事情がどういった様相を呈すかは分からない。 しかし、彼らのような読書人が存在し、本を愛する者たちが多く存在するということは意識にとどめておかなければならない。
Posted by