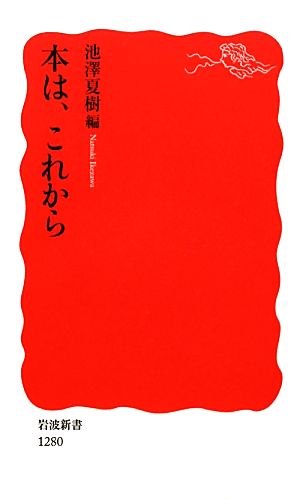本は、これから の商品レビュー
紙でも電子でもええとこ悪いとこがあるということ。 時間や場所、場合によって上手に使い分けられればええのかなと思います。 キンドルやら何やら欲しいなあ。
Posted by
2010/11発行 『電子書籍と本』について考える為に読んだ。 読み始めて最初は、いろんな立場の人が電子書籍に対して深い見識から述べる良本かと思ったけど 結局あとがきにもあるように、本がどうしようもなく好きな人たちが意見している。 一つ一つの意見にはっとさせられる部分はある物の...
2010/11発行 『電子書籍と本』について考える為に読んだ。 読み始めて最初は、いろんな立場の人が電子書籍に対して深い見識から述べる良本かと思ったけど 結局あとがきにもあるように、本がどうしようもなく好きな人たちが意見している。 一つ一つの意見にはっとさせられる部分はある物の、総じて元来の議論の枠から新鮮な意見と感じる部分はなかったような。 池澤夏樹ファンの人には、彼独自の空気感はみっちり感じるので良いかも。
Posted by
推薦理由: 電子書籍が登場し、情報のデジタルコンテンツ化が進む現代、「本は、これからどうなるのか」について色々な立場の人たちの考えが述べられている。これからの世の中で、情報メディアのひとつの形である「本」がどのように移り変わっていくのか、それを人々はどう受け止めようとしているのか...
推薦理由: 電子書籍が登場し、情報のデジタルコンテンツ化が進む現代、「本は、これからどうなるのか」について色々な立場の人たちの考えが述べられている。これからの世の中で、情報メディアのひとつの形である「本」がどのように移り変わっていくのか、それを人々はどう受け止めようとしているのか、本書を読んで考えてみて欲しい。 内容の紹介、感想など: 2010年は電子書籍元年と言われている。KindleやiPadなどの電子書籍端末が世の中に出回り始め、Googleが世界中の本をデジタルデータ化しようとしている現代の流れは、活版印刷技術を発明したグーテンベルグ以来の情報革命だという見方もある。本書は、そんな現代において「本は、これからどうなるか」というテーマで、作家、学者、ジャーナリスト、図書館長、書店員などの、本に深く関わってきた37人の人達が本に対する其々の思いを綴ったエッセイ集である。 「書店が多数あり、国民が読書にふける国はこれから発展する国である」と実感した池上彰は、どんな媒体であれ、読書そのものは永遠に不滅だと述べ、池内了は、辞書、事典、実用書、読み捨て本などは電子書籍で十分であり、絵本、教科書、古典、哲学書などは紙の本であり続けるという棲み分けがなされるだろうとし、内田樹は「紙の本はなくならない」と断じる理由として、電子書籍では、読書の全行程を鳥瞰する視野に立てない事と、宿命的な出会いが起こらない事を挙げている。日本図書館協会の理事である常世田良は、自己判断自己責任型の社会といわれる今日、国民の様々な課題解決と自立のために存在する公共図書館が、既刊、新刊の書籍をデータ化して様々な環境の利用者に提供する事は有意義であるとし、その一方で最後まで図書館には本が残るだろうと述べている。 本書からは、37人それぞれの思いが伝わってくるが、概ね電子書籍を全否定するものではなく、紙の本と電子書籍が用途により使い分けられ共存するだろうと予想したり、データ化された情報がいつでも手に入る電子書籍の利便性に期待したりという考えが多いようだ。しかし、どの文章からも感じられる事は、「本は、これからどうなるかはわからないが、それでも本は残るだろう、本は残したい」という、本に対する愛着である。
Posted by
約40人の学問や企業などで名を馳せている有名人の方々の、本にまつわるこれからの日本、または世界について書かれた作品がまとめられた豪華すぎる本です!
Posted by
私自身は、本=紙派なのだけれど、 この本を読んで考え方が少し変わった 電子書籍について、いろいろな立場の人が書いてあり面白い
Posted by
題名の意図は、「本はまだまだこれからだぜ!!」ではなく、「本はこれから、どうなっちゃうの・・・?」である。2010年は電子書籍元年と言われているらしい。けれども、今や読書の習慣をもつ人は希少なので、こういう問題意識をもつ人はあまりいないように思われる。大部分の人にとっては、本がど...
題名の意図は、「本はまだまだこれからだぜ!!」ではなく、「本はこれから、どうなっちゃうの・・・?」である。2010年は電子書籍元年と言われているらしい。けれども、今や読書の習慣をもつ人は希少なので、こういう問題意識をもつ人はあまりいないように思われる。大部分の人にとっては、本がどうなろうと、そんなことはどうでもいいのかもしれない。 書物が電子化されることに危機感を抱いているのは出版社や書店の経営者くらいのもので、私のような一ユーザーとしては、むしろ歓迎すべきことだと思っている。というのも、読書人口の減少に伴って、出版社は本を濫造しているからだ。紙だって貴重な資源である。一方で、ネット上にはジャンクな情報が氾濫している。書籍化するに足だけのコンテンツのみが書籍化されれば充分なのだ。また、町の本屋さんが消えていくことを嘆く人がいるけれども、そんなものは要らない。各地域の中核都市に、あらゆるジャンルの本を備えた超大型店が一つあれば済む話だ。 実際のところ、電子化されるべき領域では、すでに電子化されている。学術的な論文は、もはやほとんど冊子の形で出版されることはない。百科事典の類も不要だろう。新聞も、そのコストを考えれば、紙に印刷して配布するメリットはないと思う。つまるところ、自分の知りたい情報だけを得るのには、インターネットのほうが圧倒的に向いているのである。 けれども、紙の本を読むという作業は、それとは根本的に異なっている。読書の醍醐味は、読んでみないと、自分がどこに連れて行かれるかが分からないことである。読書は、身体性を伴う行為なのだ。紙の書物は、全体の位置を俯瞰的に知ることができ、読了したときには達成感が伴うのに対して、電子書籍なるものは、茫漠と広がる情報の海の中の1ピースに過ぎない。電子図書は、「読み終えた私」への小刻みな接近感を読者にもたらすことができない──この内田樹の指摘は、言い得て妙である。だから私は、決して電子書籍は読まないし、それが本の主流な形態になることもないだろうと思う。 中野三敏の文章が面白かった。書物は、これまでに二度の革命を経験している。一度目は写本から版本へ、二度目は版本から活版への移行である。驚くべきことに、明治以前の写本・木版本のうち、活字化されているのは1%ほどに過ぎないという。また、そのような書物は、楷書体の漢文著作以外はすべて、変体仮名と草書体漢字という「くずし字」で書かれている。現在、くずし字を読むことのできる「和本リテラシー」をもつ人は、日本に3千人ほどしかいない。これらの書物をすべてスキャンして電子化するプロジェクトが進行しているのかどうかは知らないが、活字化されていない書物に対しては、電子化は福音なのだ。
Posted by
珍しく文学的な書名である。電子ブックの登場で「本は、これから……どうなるのか?」いろんなタイプの書き手、読み手、書店、古書店、図書館、取り次ぎ、装丁、編集の位置からの短文を37そろえている。 以下、私が線を引いたところ(抄)である。 池澤夏樹 われわれは本を読みすぎるのだ...
珍しく文学的な書名である。電子ブックの登場で「本は、これから……どうなるのか?」いろんなタイプの書き手、読み手、書店、古書店、図書館、取り次ぎ、装丁、編集の位置からの短文を37そろえている。 以下、私が線を引いたところ(抄)である。 池澤夏樹 われわれは本を読みすぎるのだ。その大半は読み捨て、読み流し。かつて新井白石のような優れた知識人が生涯に読んだ本の何十倍もの量をわれわれはただ消費している。 紙という重さのある素材を失ったために文筆の営みはすっかり軽くなり、量産が可能になった分だけ製品はぺらぺらのものばかりになった。そもそも人類の智の総量が変わるはずないのだからインターネットによって生産を加速すれば中身は薄まる理屈だ。 →まさにその通り。私はおそらく、江戸の知識人よりも多く本を読んでいると思うが、その中味は到底彼らに追いつかない。それどころか、こんな文章を書いて、「中味を薄める」お手伝いをしているというわけだ。 しかし、世代は変わるのだ。新しいがジェットは若年層を突破口に社会に浸透する。今の子供たちはもう固定式の電話をほとんど使わない。韓国とシンガポールではあと二年もすれば教科書が電子端末に変わるという。 実を言えば、今の段階で電子ブックなどよりずっと恩恵をこうむっているのはこのインターネットによる古書のシステムだ。かつては欲しい本を探して神田の古書店の棚を尋ね歩いたものだが、今はたいていの本は即座に手に入る。古書というものの概念が変わってしまった。それはまた、手元の本を惜しげもなく放出できるということだ。必要ならばまた買えばいい。日本中の本全体が一種の共有財産と化してきた。 池内了 記録媒体としての電子書籍(やたら記憶が得意なシリコン頭にうってつけである)、自分のあたまを鍛えるための紙の本(考え想像するカーボン頭に最も相応しい)という棲み分けができそうである。 岩楯幸雄(幸福書房社長) でも、五年後にはどうなっているのでしょう。新宿・渋谷に超大型店が出店し、大型店通しの潰しあいが始まっています。それぞれが一人勝ちを狙っているのでしょうが、それは無理でしょう。電子書籍の影響を近い将来全部の店が公平に受けるのだとすれば、ダメージは大型店が一番大きいはずです。多くの借金や高い家賃を負担しているはずだからです。アメリカでは大型店の廃業が始まっているそうです。そう、5年後はどうなっているのか分からないのです。老人大国の日本で若い人が営む小さな本屋が、もしかしたら一番必要とされる時代がやってくるかもしれません。健闘を祈ります。 →私はおそらく、三年後には電子書籍を手にしていると思います。新し物好きですから。けれども、一方では老人が陽だまりの中、、20年積んだままにしている中江兆民全集や植木枝盛全集、マルエン全集などを読むことや、何度も読んだあの本やこの本を読むことを夢見ているというわけです。本屋の未来、この社長の言うとおり、これからは個性的な本屋さんの時代かもしれません。私ならば、こんな本を並べるのだけどなあ、というのはあるのだけど、誰か雇ってくれないかしら。
Posted by
豪華ラインナップ37人の本に関するエッセイ。サブタイトルをつけるなら「電子書籍はリアルの本を殺すか?」でしょう。 2010年本書が出たころといえば、キンドルと ipad の登場により 本に関する業界が大騒ぎしだした時。さすがに、多くの人が「本」はもうだめなのか?と思いはじめ、...
豪華ラインナップ37人の本に関するエッセイ。サブタイトルをつけるなら「電子書籍はリアルの本を殺すか?」でしょう。 2010年本書が出たころといえば、キンドルと ipad の登場により 本に関する業界が大騒ぎしだした時。さすがに、多くの人が「本」はもうだめなのか?と思いはじめ、では、本を偏愛する?知識人に語ってもらいましょう。と出された本です。 正直なところ電子書籍はつかえるようになって、まだ出始めの過渡期といえる。この段階で語られる内容は、ある程度予想がつく。 デジタルなのかリアルなのか。 リアルの本に親しんできたものとしては、ノスタルジーにも似た感傷に陥る。ほんの手触りや匂い、本を買いにいったときの気持ちや、そのとき見た風景など。これらがダウンロード購入などのデジタルでは味わえないという。 これは一面事実なのだが、本を情報を伝えるものと捉えるならば、本との接触の仕方が変わってきた、変わる、ということでしかないのでことさら問題ではない。 電子書籍はリアルの本を殺さない。むしろ多様な表現法が駆使されることで補強するものでさえありそうだ。 本に関係する37人がどのようなスタンスをとっているか比較してみると面白い。
Posted by
タイトルから、本はこれからどうなるのか、あるいは、本はまだまだこれからということなのか。 37人の著名人から無名の人まで、本とか読書に関するエッセイ集。 電子書籍で読書から「物質性」がなくなることについてモノ申してたり、本の流通などについて含蓄のある話をしていたり、様々な内容。...
タイトルから、本はこれからどうなるのか、あるいは、本はまだまだこれからということなのか。 37人の著名人から無名の人まで、本とか読書に関するエッセイ集。 電子書籍で読書から「物質性」がなくなることについてモノ申してたり、本の流通などについて含蓄のある話をしていたり、様々な内容。 岩波らしい一冊。
Posted by
私は電子書籍反対派というより、歓迎派なんだけど(まだ端末は持ってないけど) 本のこれからについて、本に纏わる様々な分野の人の意見に触れることができておもしろかった。 図書館でも、電子書籍のありかたというのはきちんと考えていかないなー。 一番おもしろかったのは、出版関係者でも図...
私は電子書籍反対派というより、歓迎派なんだけど(まだ端末は持ってないけど) 本のこれからについて、本に纏わる様々な分野の人の意見に触れることができておもしろかった。 図書館でも、電子書籍のありかたというのはきちんと考えていかないなー。 一番おもしろかったのは、出版関係者でも図書館関係者でもない、ジブリの鈴木敏夫さんの章でした。 もっともだ!と(笑)
Posted by