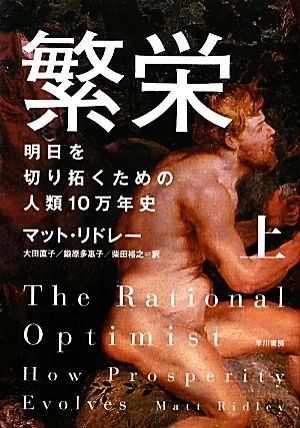繁栄(上) の商品レビュー
ものすごい端折ると、TPP 賛成の本。人間はその高度な協力・分業によって繁栄してきたし、これからも繁栄するという楽観主義。逆に言うと、今が辛いと人は昔を理想化しがちだけど、遡れば実は相当悲惨だったという現実主義。リスクやセキュリティを煽るほうがマネタイズしやすいという傾向に抗って...
ものすごい端折ると、TPP 賛成の本。人間はその高度な協力・分業によって繁栄してきたし、これからも繁栄するという楽観主義。逆に言うと、今が辛いと人は昔を理想化しがちだけど、遡れば実は相当悲惨だったという現実主義。リスクやセキュリティを煽るほうがマネタイズしやすいという傾向に抗って、この本ではさまざまな客観的なデータを通して楽観主義が示されるが、それは大枠、妥当で誠実なものだと思う。ただ、より大きくその二つの対立を捉え返すならば問題の所在は、なぜ今リスクやセキュリティがお金になるのか、そして、豊かになればなったがゆえに、クローズアップされうる不幸が生じるのはなぜかという、いわゆる相対的剥奪にあるのだろう。
Posted by
過去から現在までの人類の歩みを交換、分業、交易によりどうイノベーションを起こしてきたかよく分かった。自然淘汰による進化、タスマニア効果、クズネッツ曲線、緑の革命、生物多様性、遺伝子組み換え等著者の教養の幅広さがよく分かった。人類の歴史のことをよく考えてみたい。
Posted by
二枚の写真。ハンドアックスとコンピューターのマウス。どちらも人間の手の中にぴったり収まるようにデザインされている。マウスは、集団的知性による産物だ。ある時点で、人間の知性は、他のどんな動物にもない集団的・累積的になった。 良くできたプレゼンのスタートだ。その時代の文明の利器は、...
二枚の写真。ハンドアックスとコンピューターのマウス。どちらも人間の手の中にぴったり収まるようにデザインされている。マウスは、集団的知性による産物だ。ある時点で、人間の知性は、他のどんな動物にもない集団的・累積的になった。 良くできたプレゼンのスタートだ。その時代の文明の利器は、人間社会そのものを映し出す。模倣と交換。この二つの概念が飛躍的に人類を発展させた。本書は、この事について徹底的に考察し、解説する。 文化的進化にとっての交換は、生物学的進化にとっての生殖とまで述べる。生殖は複製であり模倣、遺伝子や欲求の交換でもある。リカードによる比較優位の概念では、交易や交換が各々の得意分野を伸ばすだけではなく、分業による存在価値を見出していく事を示す。 一方で上巻で気になったのは、タスマニア効果だ。隔絶された文明では、テクノロジーは進化せずに退歩する。企業でも度々そういう事がある。新たな取り組みが定着、管理されぬ限り、無能、無気力な担当者により失速し消えていく。文明において画期的な発明も、それを継承する能力や意欲がなければ滅びていくのだ。だからこそ、催事や教育が必要だという事だし、欲望交換と紐付けたシステムが重要だったのだろう。日常にタスマニア現象は頻繁している気がする。
Posted by
交換、分業、交易によりイノベーションが起きる。壮大な人類の歴史に自分が今、どこにいるのかわからなくなるほどである。
Posted by
交換・分業なくして繁栄なし。自給自足は貧困化し退歩する。 なんとなく自身と重ね合わせてしまって1人が楽な個人働きしてる身に染みる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
今日、昔のほうが暮らしやすかったと考えている人がいるが、このバラ色のノスタルジアを抱くのは概して富裕層に限られる。 繁栄とは交換と専門家による。 最後通牒ゲーム 市場を広く用いる社会は、協力と公平性と個人の尊重を旨とする文化を築く。集団的頭脳に浸っているほど、人は気前良くなる。 人類の反映の歴史は、双方が恩恵を得るノン・ゼロサム取引の再三の発見につきる。 交換は双方に二重の恩恵をもたらす。 世間はゼロサムの発想に支配されている。 マルクス主義は資本家が金持ちになるのは労働者が貧しくなるからだといったがこれは誤りだ。 思いやりは本能的なものかもしれないが、相乗効果はそうではないのだ。 交換は信頼を生み、信頼は交換を割かんにする。 2008年におきた金融危機 信頼が足りなければ、反映はしだいに失われるだろう。 豊かな国々が豊かなのは、国民の技能や、経済活動を支えている制度や慣習の質に負うところが大きい。 農業とは、分業と交換をほかの種まで広げることにほかならない 資本とは、いうなれば、必要に応じて別の機会に使うために蓄えられ保存されている一定量の労働 経済学者はすふに「市場の失敗」を口にする。 それはそれで正しいが、もっと大きな脅威を生むのは、「政府の失敗」だ。 政府が経営するのは独占事業なので、ほとんどが非効率と停滞に陥る。 中国明の衰退はこれに由来する。
Posted by
「今」ほど最高の時代はない。そして人類の生活レベルは地球規模でなお加速度的に向上している。。。どっちかというと「おれらこのままじゃやばいよね」的な主張を好んで読む自分からするとある意味新鮮だったりして面白い。「交換」が人類発展のパラダイムシフトである、ということは、内田樹さんも言...
「今」ほど最高の時代はない。そして人類の生活レベルは地球規模でなお加速度的に向上している。。。どっちかというと「おれらこのままじゃやばいよね」的な主張を好んで読む自分からするとある意味新鮮だったりして面白い。「交換」が人類発展のパラダイムシフトである、ということは、内田樹さんも言ってたなぁ。そのとおりかもしれん。
Posted by
でこぼこがあるにしろ、世界は繁栄の一途をたどっている、そしてその繁栄の一番の原因は物品やアイデアの「交流」と分業にあるという本。原題は「現実的楽観主義者」。上巻は、理論編。ここでも、大事なロジックは『残酷な〜』同様、比較優位説。下巻では、近代以降、悲観論者のいってきたことが、いか...
でこぼこがあるにしろ、世界は繁栄の一途をたどっている、そしてその繁栄の一番の原因は物品やアイデアの「交流」と分業にあるという本。原題は「現実的楽観主義者」。上巻は、理論編。ここでも、大事なロジックは『残酷な〜』同様、比較優位説。下巻では、近代以降、悲観論者のいってきたことが、いかにまちがっていたかを、笑っちゃうくらい、しつこく論破する。文明論好きな人は、読んで損無い!""
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年刊。「赤の女王」の著者の作で期待したが、今一歩か。本書の主張は、時代を問わず、物々交換と分業の進展が技術的・文化的進歩を招来し(リガードの比較優位論)、その情報を保有する者が一定数存在するがゆえに、技術的知見が退歩(著者の言う「タスマニア効果」)しない、ということ。ただ、これだけなら、それは尤もであるものの、新奇とは言えず、情報の流入・発信の阻害は回避すべしとの教訓くらいしかなさそう。しかも、提示するファクトが乏しく(やや良いとこ取り過ぎ)、人類史的に物々交換を創出・発展させた理由の説明は不足。 また、農業革命でも蒸気機関の発明でも、なぜ、その時期に、かかる知見が生まれ拡大して行ったのか、本書では十分な説明がなされたとは言いがたい。技術開発史とそれを生み出した生物学的要因とが混同され、説明が混乱している感。例えるなら①旧石器時代等の遺物の地域比較で物々交換がいつ始まったのか、ある程度は特定すること(三内丸山遺跡で他地域の黒曜石が発掘された例を想起)、②複数の技術的知見の伝播状況を世界史的視野で検討しないと説得力がないのでは…。そういう気がする。
Posted by
人類は今までも繁栄してきたしこれからも繁栄し続ける。人類史上、今ほど豊かで格差のない社会はなかった。そしてその豊かさは『交易』によって実現した。というお話。まさにこの本の要諦は『交易』の一言に尽きると思う。まず交易によって豊かになり、都市ができ、最後に王や政府や王朝などの権力によ...
人類は今までも繁栄してきたしこれからも繁栄し続ける。人類史上、今ほど豊かで格差のない社会はなかった。そしてその豊かさは『交易』によって実現した。というお話。まさにこの本の要諦は『交易』の一言に尽きると思う。まず交易によって豊かになり、都市ができ、最後に王や政府や王朝などの権力によって搾取され、衰退していく。それぞれが得意なものを作って交換したほうがみんな豊かになるというリカードの説がよく理解できる。前巻は10万年前〜5千年前までの話。
Posted by