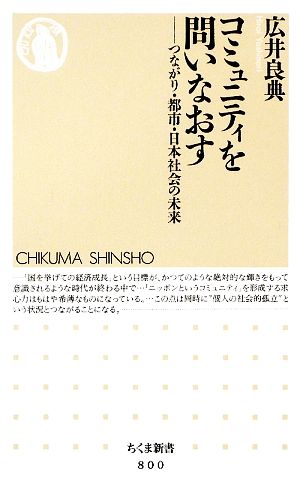コミュニティを問いなおす の商品レビュー
大学生のとき以来の広井先生。今も精力的に色々書いてる先生ですが、この本は先生の中心テーマというか関心の盛合わせ基本テキストという感じがしますね。農村型と都市型、都市論や地域に根付いた福祉のあり方など面白く読みました。日本のコミュニティの文脈を語るのに独我論まで持ち出したのはどうか...
大学生のとき以来の広井先生。今も精力的に色々書いてる先生ですが、この本は先生の中心テーマというか関心の盛合わせ基本テキストという感じがしますね。農村型と都市型、都市論や地域に根付いた福祉のあり方など面白く読みました。日本のコミュニティの文脈を語るのに独我論まで持ち出したのはどうかと思いましたが。地球の環境上の限界という制約こそが先生のいう普遍的な価値規範になるのか、あるいはよりローカルなレベルでの価値が成り立ちうるのか。そこが「定常型」という社会のあり方が可能かどうかの分水嶺なのでしょうか。
Posted by
科学、宗教、人類史から各国の政策、自治体アンケートまで幅広い内容で、時間~空間、ソフト~ハードと視点が切り替わりついていくのが大変だった。 日本の経済や社会に関する本は、同じようなことを違う切り口で述べていることに気づく。 高度経済成長期の功罪とか急激な都市化、そして歴史的に普遍...
科学、宗教、人類史から各国の政策、自治体アンケートまで幅広い内容で、時間~空間、ソフト~ハードと視点が切り替わりついていくのが大変だった。 日本の経済や社会に関する本は、同じようなことを違う切り口で述べていることに気づく。 高度経済成長期の功罪とか急激な都市化、そして歴史的に普遍的原理が不存在であること。経済や社会保障、生き方などに価値観の転換が求められていることなど、この本でより大きな視点から再確認できた。
Posted by
Kindle本。自分がコミュニティ政策に関心があることに気づくなぁ。 この前話していて思ったけど、最近、人が自然に動いてしまう仕掛け作り に関心がある
Posted by
第二部は”社会システム”という切り口からコミュニティを問い直していく章でした。主に都市計画や福祉政策の歴史的展開の振り返りや、社会システムの国際比較を通して、現在のコミュニティや公共を分析していくというテーマです。 具体的には、第一部の視座に加え、「公-共-私の役割分担/力点...
第二部は”社会システム”という切り口からコミュニティを問い直していく章でした。主に都市計画や福祉政策の歴史的展開の振り返りや、社会システムの国際比較を通して、現在のコミュニティや公共を分析していくというテーマです。 具体的には、第一部の視座に加え、「公-共-私の役割分担/力点の相違」「社会システムをインフォーマルな形で支えるもの」「土地の公共性の変化」「フロー/ストックからみた公平性」「住宅政策」「コミュニティの世代的継承性」などの様々な視点から分析をし、関連付けをしていました。 一番印象に残ったことは、ある地域のコミュニティを分析するためには、社会システムという様々な視点からも詳しく、詳しく分析する必要があるなぁということです。 そのためにも、他の地域の歴史や福祉/都市政策と比較するための知識・比較の軸を養っておかなければいけません,,,! まずは、各地方自治体の5カ年地域福祉計画などで、何が語られているか知るところからでしょうか。 今まであまり興味をもって読もうという気持ちにならなくなった行政の計画書や報告書が気になってきました。 現状の地域コミュニティを「地域コミュニティ再構築のチャンス!」と捉え未来を創っていくためにも、現在の地域コミュニティがどのように生まれているか、勉強していきたいと思います!
Posted by
広井良典『コミュニティを問いなおす』ちくま新書 読了。総じて雑多。帰納的な推測の正当性が気になる。だが、格差の源泉となるストックを公営住宅など福祉政策に活用する視点は斬新。生産性概念の転換を図れば、労働集約型が生産性に優れるとの考えも面白い。いずれにせよ政府の介入が前提となるが。...
広井良典『コミュニティを問いなおす』ちくま新書 読了。総じて雑多。帰納的な推測の正当性が気になる。だが、格差の源泉となるストックを公営住宅など福祉政策に活用する視点は斬新。生産性概念の転換を図れば、労働集約型が生産性に優れるとの考えも面白い。いずれにせよ政府の介入が前提となるが。 2012/03/04
Posted by
【由来】 ・天野祐吉の「成長から成熟へ」で「人口減少社会という希望」を検索したらMediaMarkerの関連本で出てきて、同じ著者で、しかも新書なら読みやすそうと思った。 【期待したもの】 ・ 【要約】 ・ 【ノート】 ・
Posted by
第9回大佛次郎論壇賞受賞作、と帯に書いてあった。恥ずかしながら、大佛次郎論壇賞を知らなかった。朝日新聞の賞らしい。ちなみに、本書の前の第8回は、湯浅誠『反貧困――「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書)だった。なかなか良書を選んでいる。 「戦後の日本社会で人々は、会社や家族とい...
第9回大佛次郎論壇賞受賞作、と帯に書いてあった。恥ずかしながら、大佛次郎論壇賞を知らなかった。朝日新聞の賞らしい。ちなみに、本書の前の第8回は、湯浅誠『反貧困――「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書)だった。なかなか良書を選んでいる。 「戦後の日本社会で人々は、会社や家族という『共同体』を築き、生活の基盤としてきた。だが、そうした『関係性』のあり方を可能にした経済成長の時代が終わるとともに、個人の社会的孤立は深刻化している。『個人』がしっかりと独立しつつ、いかにして新たなコミュニティを創造するか―この問いの探究こそが、わが国の未来そして地球社会の今後を展望するうえでの中心的課題となろう。」 「(a)物事の対応や解決が、主として『個々の場面での関係や調整』によってなされるような社会 (b)物事の対応や解決が、主として『普遍的なルールないし原理・原則』によってなされるような社会 …(a)や(b)といったあり方は、…特に『農村―都市』という対比を軸として、その社会の置かれた自然環境や生産構造、規模等に応じて、それに適応したバランスのあり方が存在すると考えるべきだろう。それがまさに『関係性の進化』ということの実質をなすことになる。」 関心をそそる問題提起とは裏腹に、正直中身はピンと来なかった。非常に残念。
Posted by
経済の成熟化により、富の源泉がフローからストックにシフトしている。ストックからの分配を行うこと。 人生前半の社会保障を行うことの2点が今後の社会保障のポイントである。 といった箇所が最も共感できた。 もう一度読み直したい。
Posted by
コミュニティの機能が失われた現代社会で、コミュニティの再生のために、コミュニティを問いなおす。しかし、それは、従来のコミュニティの再構築ではなく、新たな関係性、価値観にもとづいた、新たな機能を持ったものになるだろう。 本書の中で、著者はコミュニティの定義について、「人間が、それに...
コミュニティの機能が失われた現代社会で、コミュニティの再生のために、コミュニティを問いなおす。しかし、それは、従来のコミュニティの再構築ではなく、新たな関係性、価値観にもとづいた、新たな機能を持ったものになるだろう。 本書の中で、著者はコミュニティの定義について、「人間が、それに対して何らかの帰属意識を持ち、かつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶助(支え合い)の意識が働いているような集団」としている。その、「人間が」尊厳を取り戻し、社会が再び機能する場所として、「公」(政府)でもなく、「私」(市場)でもなく、「共」の場である「コミュニティ」に焦点を当てている。 著者が言うように、現代は、人々の価値観を含めて社会システムが大きく転換しないといけない時期に来ていると思う。そして、「共」の場で変化のリーダーシップをとっていける存在としては、事業体をもつ協同組合であったり、実績を積んだNPOなどであり、そのはたさなければならない責任は大きいと感じた。
Posted by
トマ・ピケティ「21世紀の資本」が売れに売れている2015年新春というタイミングでこの本を開きました。そのベストセラーにはまだ手をつけていませんが本書は「フローからストックへ」という社会の変化を先駆けて提示しているように思いました。もちろんエコノミーとコミュニティと目指すベクトル...
トマ・ピケティ「21世紀の資本」が売れに売れている2015年新春というタイミングでこの本を開きました。そのベストセラーにはまだ手をつけていませんが本書は「フローからストックへ」という社会の変化を先駆けて提示しているように思いました。もちろんエコノミーとコミュニティと目指すベクトルは違っているのですが…。基本にある「公‐共‐私」という社会の骨格に対するまなざしがとても「優しく」感じました。それは最終章で著者自身のライフテーマになっているくだりで裏打ちされました。はっきりしませんが自分のこれからのヒントを与えてくれる読書でした。
Posted by