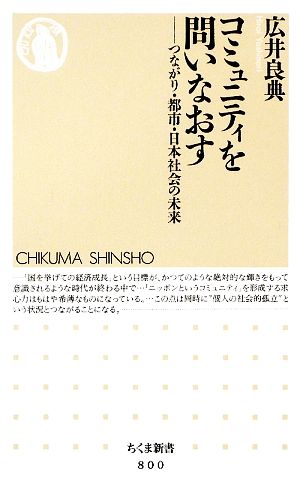コミュニティを問いなおす の商品レビュー
1年間放置して、やっと読み終わりました…(汗 (多分かなり詳細に・論理的に書かれたものだとは思いますが)結構錯綜していて大変でした。まぁ、素人が読むとそんなもんですね、きっと。 著者の「定常型社会において新たな形のコミュニティ構築が必要」という主な主張には大変同意します。 ただ...
1年間放置して、やっと読み終わりました…(汗 (多分かなり詳細に・論理的に書かれたものだとは思いますが)結構錯綜していて大変でした。まぁ、素人が読むとそんなもんですね、きっと。 著者の「定常型社会において新たな形のコミュニティ構築が必要」という主な主張には大変同意します。 ただし、以下の2点が気になります。 ①ローカルなコミュニティづくりって上手くいくのだろうか?? 著者によれば、地域ごとに教育・医療なりの分野と絡めながらコミュニティの拠点を設けていくべき、としているが、現状からみて、人々のそのような拠点へのコミットメント意欲は低い気がする。 ②「普遍的な原理」って登場しうるのか?? 本書の終わりの方で、かなり(コミュニティとコミュニティをつなぐ存在としての)「普遍的な原理」についての議論に舵を切っているが、これだけ情報があふれ価値観が多様化した時代にそのようなものが発生するかどうか。 私は、どちらかといえば、「極端に興味関心の分野がせまい(=「普遍的な原理」でつなぐのが難しい)コミュニティ」がたくさん登場するのでは??と思っているので、少々私と真逆かもしれません。 それでも、現状認識と今後の提案に関しては大変学べる話だったと思うので、また半年後なり一年後に読み返してみたいと思います。(つまり、もうちょっと勉強したら、ということですね。お恥ずかしい)
Posted by
2009年大佛次郎論壇賞受賞作。 高度成長期、我が国は経済成長をいわば価値原理にしてそれに向かい邁進してきた。しかし現代において経済拡大は飽和状態に達し、次の価値を模索する時代に突入している。 同様に、コミュニティという人間の集まりにおいても新しい局面が訪れている。高度成長期...
2009年大佛次郎論壇賞受賞作。 高度成長期、我が国は経済成長をいわば価値原理にしてそれに向かい邁進してきた。しかし現代において経済拡大は飽和状態に達し、次の価値を模索する時代に突入している。 同様に、コミュニティという人間の集まりにおいても新しい局面が訪れている。高度成長期には農村から都市への大移動がおこった。それまでコミュニティは主に「家庭」と「会社」という、閉鎖的性格を持つものが担っていた。しかし、高度成長が終わり新しい価値原理を模索しなければならない中で、ベクトルは新しいコミュニティ、つまり「農村型コミュニティ」から「都市型コミュニティ」へと向かっている(ここで「農村型コミュニティ」とは、「共同体的な一体意識」をもつ「情緒的(非言語的)」性格のもであるのに対し、「都市型コミュニティ」は「個人をベースとする公共意識」を持つ「規範的(言語的)」性格のものである)。 OECDによる2005年の報告書によれば、日本は先進国の中で最も社会的孤立度の高い―コミュニティの外との交流が少ない―国であったという。それは「農村型コミュニティ」の影響がいまだ根強く、「ウチ」と「ソト」との落差が大きい社会であるということを示している。広井氏は我が国の自殺率の高さを挙げた上で、このことが「生きづらさや閉鎖感の根本的な背景になっているのではないだろうか」と指摘している。 このような状況で、経済成長に代わる新しい価値原理は「有限性」と「多様性」を持つものになるべきではないかと広井氏は主張する。 ここで「有限性」というのは、有限な資源をどのように利用していくかという視点であり、「多様性」とは、お互いの違いを認識しそれを乗り越えていくための、ローカルからグローバルに発展する考え方である。 同時にコミュニティを巡る課題について、 1、量的拡大から質的深化(趣味や教養といった質的深化) 2、労働から非貨幣的価値感覚(社会保障やエコロジー) 3、日本社会における「独立した個人のつながり」の確立(都市型コミュニティの確立) という三点を提示して締めくくっている。 これらの提案に対しては明るい印象を受けた。ただ難しいのは、「質的深化」「社会保障」といったものが資本主義ないし貨幣的価値観と相反する性格を持つ中で、それらをどのように「ポスト資本主義」として融和させるかということだろう。本書ではその可能性という所までは言及しない。 ここでは新しい価値原理と、それに即したコミュニティのあり方ということについてのみ記載したが、本書はその他に「都市・市民」「社会計画・福祉国家」「スットク・フロー」「現代の病・ケア」「独我論」など多様な内容が展開される。 社会やコミュニティについて一歩深く考えることができる良書。
Posted by
日本におけるコミュニティのあり方、というのは2010年現在、ある意味でとてもホットな話題である。 ちょっと厚めの新書一冊によくこれだけ色々なものを詰め込んだと思える浩瀚な論であり、参考になる視点が様々にあった。 特に、筆者の言う『福祉地理学』は今後重要さを増す思考法であろう。...
日本におけるコミュニティのあり方、というのは2010年現在、ある意味でとてもホットな話題である。 ちょっと厚めの新書一冊によくこれだけ色々なものを詰め込んだと思える浩瀚な論であり、参考になる視点が様々にあった。 特に、筆者の言う『福祉地理学』は今後重要さを増す思考法であろう。どのような地域においても一律・普遍的な福祉を考えるのではなく、地域の実態に合わせた施策を。 その実現のために官・民のみならず「公共」の役割を拡大すること。(日本社会においては「公」の位置づけが曖昧であるとは、他の分野、他の論者も多く指摘するところではある) また、街づくりにおいてアメリカをモデルとしたために、自動車中心の都市が多くなったことについても指摘がある。人が歩き回れる程度の町、というのは高齢化を踏まえたうえで必要な視点であろう。
Posted by
コミュニティのあり方やその再生については多く議論されており、地方自治体では商店街や公民館、学校などを中心としてコミュニティを形成する試みがなされている。コミュニティが重要視されるのは、それが人が生活するうえでの基盤になるものと考えられているからであり、経済成長に頼らない豊かな生活...
コミュニティのあり方やその再生については多く議論されており、地方自治体では商店街や公民館、学校などを中心としてコミュニティを形成する試みがなされている。コミュニティが重要視されるのは、それが人が生活するうえでの基盤になるものと考えられているからであり、経済成長に頼らない豊かな生活を送る上での基盤になるものであると認識されているからである。 しかし、マンションの住人はマンションを単位としたコミュニティという意識は薄く、むしろコミュニティは排他性や同調圧力を生むためにコミュニティというしがらみからの開放が進歩であるとされてきたという歴史がある。文明の発展とは、コミュニティという集団によってではなく、個人がバラバラに生活できる社会が「進歩」であると考えられてきた。このような理由から、コミュニティという言葉に対して批判的な立場をとる人も存在する。 本書は、都市、グローバル化、社会保障、地域再生、ケアなどさまざまな観点から、人と人との新たなつながりの形を模索するものであるが、「コミュニティ(共同体)」をより具体的に分析し、感情的次元の「農村型コミュニティ」と規範的・理念的なルールによる「都市型コミュニティ」とに分類している。 人の移動が少なく、濃密な関係性が築かれるのが「農村型コミュニティ」であり、コミュニティという語についての一般的な認識がこれにあたると言える。そして、生産のために個々が集う場所が「都市型コミュミティ」であり、この外部に開かれている流動的な集団を、西欧では宗教が、日本では経済成長という理念が一つの集合として束ねていた。 明治以降、日本は欧米列強の進出に直面する中で、「文明の乗り換え」を行った、しかし価値原理(キリスト教)は受容せず、仏教・儒教の価値原理はほとんどを捨象した。この価値原理の喪失を経済成長という信奉が埋めたと言える。 そして経済成長が頭打ちになった現在、個々をまとめるコミュニティの意識が希薄になっていると言われているが、推論すると本書で言うところの「都市型コミュニティ」が薄れているのであり、重要ということになる。 しかし、ここで議論は転回し、社会保障の話に移る。制度としての保障だけにとどまらず、心のケアなども含めた保障で、ケアを施す場としてコミュニティが重要であるという内容であり、このコミュニティとは濃密な関係を受容する「農村型コミュニティ」、感情的次元による「つながり」の場についてである。 さらに、社会格差に対する保障にも触れているが、興味深いのは所得に関するフローの格差ではなく、ストック(資産)の格差が、日本の固定的な階層の中での世代交代により蓄積され、より拡大しているという議論である。このストックに対する保障という観点から都市政策による社会保障という考えが 導きだされている。これまでの都市政策は景気刺激策として行われてきた。そして福祉政策は担当省が異なるということもあり、制度やサービスが中心であった。 著者の提言は、NPOや地域コミュニティなどの「公」的な領域の発展と、所得の再配分や土地所有のあり方などの公的部門の強化が重要であるとし、大きく括れば社会保障のより一層の充実といえる。
Posted by
[ 内容 ] 戦後の日本社会で人々は、会社や家族という「共同体」を築き、生活の基盤としてきた。 だが、そうした「関係性」のあり方を可能にした経済成長の時代が終わるとともに、個人の社会的孤立は深刻化している。 「個人」がしっかりと独立しつつ、いかにして新たなコミュニティを創造するか...
[ 内容 ] 戦後の日本社会で人々は、会社や家族という「共同体」を築き、生活の基盤としてきた。 だが、そうした「関係性」のあり方を可能にした経済成長の時代が終わるとともに、個人の社会的孤立は深刻化している。 「個人」がしっかりと独立しつつ、いかにして新たなコミュニティを創造するか―この問いの探究こそが、わが国の未来そして地球社会の今後を展望するうえでの中心的課題となろう。 本書は、都市、グローバル化、社会保障、地域再生、ケア、科学、公共政策などの多様な観点から、新たな「つながり」の形を掘り下げる大胆な試みである。 [ 目次 ] コミュニティへの問い 第1部 視座(都市・城壁・市民―都市とコミュニティ;コミュニティの中心―空間とコミュニティ;ローカルからの出発―グローバル化とコミュニティ) 第2部 社会システム(都市計画と福祉国家―土地/公共性とコミュニティ;ストックをめぐる社会保障―資本主義/社会主義とコミュニティ) 第3部 原理(ケアとしての科学―科学とコミュニティ;独我論を超えて) 地球倫理の可能性―コミュニティと現代 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
人間にとってコミュニティとは何か。 人となった人類が歩んできたコミュニティとの関わりも分析されている。 他の生物と違って高度に発達した「脳」を持っている人類にとってのコミュニティ。 厚生労働省の官僚であったという経歴からくるコミュニティの分析。 とにかく今まで親しんできた...
人間にとってコミュニティとは何か。 人となった人類が歩んできたコミュニティとの関わりも分析されている。 他の生物と違って高度に発達した「脳」を持っている人類にとってのコミュニティ。 厚生労働省の官僚であったという経歴からくるコミュニティの分析。 とにかく今まで親しんできたコミュニティの本とは明らかに一線を画された著作である。
Posted by
2010.04 コミュニティーの話を発端に、日本の今後のあり方を考察している。とても参考になったが、争点がどこにあるのかが、今一歩わからなかった。
Posted by
コミュニティというものについて、1)都市論、2)社会制度、3)思想、の面から包括的に考察した本。都市論、社会制度の話は少し疑問は持ちつつも納得しながら読めた。思想については、付け焼き刃?というか急いで書いたって感じを受けた。 知らない人に挨拶もしない、レストランで隣に座った人...
コミュニティというものについて、1)都市論、2)社会制度、3)思想、の面から包括的に考察した本。都市論、社会制度の話は少し疑問は持ちつつも納得しながら読めた。思想については、付け焼き刃?というか急いで書いたって感じを受けた。 知らない人に挨拶もしない、レストランで隣に座った人と一言も会話しない、目があっても無視する。そんな日本の住みにくさを、コミュニティ論という耳慣れない分野が解こうと頑張っていることは分かった。しかしいわゆる「文系」の学問全てに言えることだけど、予測可能性のない、「理論」を目指さない「議論」って印象。 こういう議論をもとにした具体的な取り組みと、その効果を何らかの数値(住宅や貯蓄の統計値の変化とか、さ)で表した本があれば読みたいな。
Posted by
『コミュニティ』はアンテナ張っているキーワードだったから即購入。あたりでした。まとめると、日本はもっと共同体を超えた規範を共有することで、個人としてつながれる環境を整える必要がある、となる。コミュニティやソーシャルキャピタルなどに興味がある方は必読か。 コミュニティは暫定の定義...
『コミュニティ』はアンテナ張っているキーワードだったから即購入。あたりでした。まとめると、日本はもっと共同体を超えた規範を共有することで、個人としてつながれる環境を整える必要がある、となる。コミュニティやソーシャルキャピタルなどに興味がある方は必読か。 コミュニティは暫定の定義として『人間が、それに対して何らかの帰属意識を持ち、かつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶助の意識が働いているような集団』とされている。 コミュニティにはいくつも類型があるが、その重要な分類の一つとして、農村型・都市型というものがある。簡単にまとめるといかのようになる。 農村型(閉鎖的、うちわ、共同体としてつながる)⇔都市型(外交的、個人としてつながる) ここ数十年、日本の人口は農村から都市へ大きく移動したが、コミュニティベースで見ると、農村というコミュニティから、企業と核家族という都市にはあるが農村型なコミュニティに移動しただけであった。これは面白い。そして結局あまり都市型のコミュニティが発達しなかったという。 まぁ、結構僕の周りは都市的なコミュニティが多いんですけどね。やっぱり、見知らぬ人同志が自然に挨拶したり会話できたりできるような環境があった方がいいと思っています。僕自身はKYにもずかずかと話したりできるほうなんですがね。
Posted by
文中やたらと強調や補足が多くて読むのに難航。こちらの力量不足もあるかな。本書の全てに共感できる訳でないにしろ、今、自分が乗る船を選ぶとしたらここに手を挙げたい。他著にもあたってみたい。
Posted by