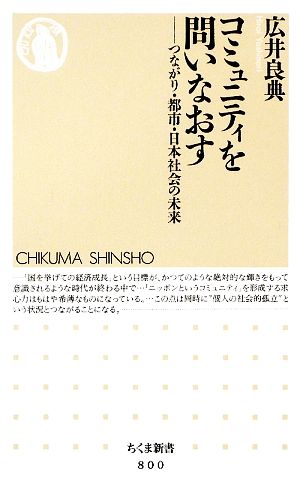コミュニティを問いなおす の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
テーマは『つながり』。 日本社会の各都市で起きている孤立問題から日本を覆う閉塞感、その打破のための普遍的原理追求を世界レベルの視点から模索しています。 もっさ抽象的ですが、今の日本には以前の高度成長期のような普遍原理(『追い付け追い越せ!』)が無くなり、カイシャという小さなコミュニティの中で個人は生きている。 排他的で余所者を受け入れない体質(ウチとソトの峻別)、しかし日本の都市計画ではそれが仇となり街の一体感や調和、コンセプトが見えない。乱雑した街並みになっている。 世界の都市(特に西欧)と比して目も当てられない凄惨な姿になっている。 西欧を倣って公有地を有効活用することが鍵と主張する。 特に住宅問題として、空き地の再開発(公営住宅)を通じて若年層の流出阻止及び流入を図り、ハード・ソフト共にコミュニティを再構築する機会と述べる。 普遍的原理については、紀元前5世紀に各地で隆盛した諸宗教がリージョナルレベルで浸透、いずれ来る諸原理の衝突にうまく折り合いを付け、価値観の多様性及び深化を遂げて現在に至る…。 とまぁ世界レベルから日本の地方都市レベルまで包括して『つながり』を主軸にして述べてますが、個人的に言えば同著『定常型社会』の衝撃の方が忘れられません。 次の時代は時間そのものを消費する社会になるという予言的文章には説得力があり、斬新な発想に驚愕しました。 またコミュニティについて、結局日本に無い普遍的原理の構築には社会心理学の最近の研究が目覚ましいほど発達していて、彼の問題提起を一歩踏み込んだ研究がなされています(社会心理学の山岸俊男教授や対人ネットワーク研究の増田直紀氏、また昨年亡くなった土居健郎著『「甘え」の構造』など)。 抽象レベルでは僕が今まで思っていたことを文章にしただけですが(過言です)、上記で紹介した本を併せて読むことで未来社会のビジョンが見えてくる気がします。 興味のある人は読んでみて下さい。 最後に…、この本は優れていると思います(実際、平成20年度大佛次郎論壇賞を受賞しています)が、もう一歩突っ込んだ内容にしてほしいと、期待をかけて星3つにします(笑)
Posted by
本書のみでの論旨の理解は難しいのかもしれない。理解不足ながら、まさに東京郊外に住み、現実発生している郊外コミュニティーの課題と合わせて読むとき、視点が整理されてくる。東京郊外における高齢化問題、コミュニティーとしての団地再生の課題、ロードサイドビジネスを中心とする街作りのあり方な...
本書のみでの論旨の理解は難しいのかもしれない。理解不足ながら、まさに東京郊外に住み、現実発生している郊外コミュニティーの課題と合わせて読むとき、視点が整理されてくる。東京郊外における高齢化問題、コミュニティーとしての団地再生の課題、ロードサイドビジネスを中心とする街作りのあり方など多くの問題の方向性を示してくれる。
Posted by
全体としてやや複雑で斜め読みでは理解するのが難しかったが、第5章「ストックをめぐる社会保障」において、経済が成熟し定常化した現在の社会では公有地を福祉政策、コミュニティ政策、都市政策の有効なツールとして積極的に活用していくことが重要であること、相続税、土地課税、環境税等によりスト...
全体としてやや複雑で斜め読みでは理解するのが難しかったが、第5章「ストックをめぐる社会保障」において、経済が成熟し定常化した現在の社会では公有地を福祉政策、コミュニティ政策、都市政策の有効なツールとして積極的に活用していくことが重要であること、相続税、土地課税、環境税等によりストックの再分配を図り人生前半の社会保障の財源として活用すること、などが提案されており興味深く読んだ。
Posted by
とても興味深い論文。 「コミュニティ」とはあちこちで唱えられているものの、どこか抽象的で、イメージで語られることが多く、自分自身も曖昧なことしか考えられていなかった。「時間から空間へ」「ストックからフローへ」「福祉政策と都市計画の連携」「コミュニティの二層性(内と外)」「普遍的価...
とても興味深い論文。 「コミュニティ」とはあちこちで唱えられているものの、どこか抽象的で、イメージで語られることが多く、自分自身も曖昧なことしか考えられていなかった。「時間から空間へ」「ストックからフローへ」「福祉政策と都市計画の連携」「コミュニティの二層性(内と外)」「普遍的価値基準の創造」等々、いままさに自分がおかれている状況に重ねながら、これからどうしたらいいか考えるヒントがたくさんある。 蓋し「日本の若者が外に出ていかない(海外に行かない)」のも、現代日本社会が定常型に移行したからと言えるのではないか。従って、その現象だけを取り上げて「積極性に欠ける」云々言うのは短絡的だと思う(若者の立場からもそう言いたい)。ただ、互いの多様性を認め合い関係を築いていく必要も高まっていて、それは外に出ていくベクトルがないと実現しにくいのは確かだと思う。 で、具体的にどう行動するかは私が考えないといけないわけだね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「私」の領域(市場)でも「公」の領域(政府)でもない、「共」の領域である「コミュニティ」からの新しい社会作りを提案した本。内容は社会、経済、福祉など多岐に渡り、この第三の領域を発展させることで諸問題を解決しようというものになっている。 この本でいうコミュニティとは、「メンバーの帰属意識やメンバー間の連帯、相互扶助を前提とする社会と個人の間に属する中間的集団」とのことである。 人間社会の消費形態は、物質の消費→エネルギーの消費→情報の消費、と変遷してきたが、現代は量的な情報の消費から、質的で内面的な充実を求める「時間の消費」の時代であるとされる。 その中で、人々は自然、公共性、スピリチュアリティなどを追求するようになり、NPOや社会起業家の活動が目立ち、神社などが見直されるようになった。 「時間の消費」の時代である現代では「地域」が見直されている。充実した時間を自分の所属する地域(コミュニティ)で過ごそうとする傾向である。 そこで著者はコミュニティの中心を福祉、医療施設、自然関係、大学などに置く「福祉地理学」が提唱している。以前なら日本のムラ社会のしがらみの代表例として扱われていた自治会・町内会の再評価もなされている。 これまで私も、人々が緩やかに所属できるコミュニティを作ることで、分断された個人の立ち直りや相互扶助、社会的ノウハウの共有が図れ、新たな発展に繋がるのではと朧気ながらも考えていたので、大いに参考になった一冊。
Posted by
内容の鮮度が高く、密度が濃くて、読後は新書にもかかわらず、「お腹いっぱい」の感がある。それぐらい、本書を「コミュニティ論」の入り口として、また新しい研究への出口として、活用できる良書である。 人は一人では生きられない。コミュニティには功罪があるが、しかし、そこを無視しては、何...
内容の鮮度が高く、密度が濃くて、読後は新書にもかかわらず、「お腹いっぱい」の感がある。それぐらい、本書を「コミュニティ論」の入り口として、また新しい研究への出口として、活用できる良書である。 人は一人では生きられない。コミュニティには功罪があるが、しかし、そこを無視しては、何事も解決の糸口はつかめない。 ・日本は先進諸国の中で、社会的な孤立度が一番高い国。 ・「市民」citizenshipはある種の資格。 ・コミュニティづくりに於ける都市部と小規模町村では課題が違う。→福祉地理学の必要性。 ・コミュニティは共同体であると同時に、外部に開かれた窓の側面もある。 ・公-共-私のバランスの中で、共の部分が肝になってくる。 ・経済成長による解決では立ちゆかない問題が増えており、一方、空間的な解決が求められる。 ・社会住宅の割合は日本は最低レベル。6.7%。 ・フローの格差(ジニ係数0.308)より、ストックの格差(貯蓄0.556,住宅0.573)の問題が深刻化している。→人生前半の社会保障の重要性(特に教育) ・人間の消費は、物質→エネルギー→情報→時間(スピリチュアリティを含む)と推移している。 ・15~44歳は精神疾患、アルコール依存、交通事故など、精神的・社会的な病気負担の割合が高い。→人生前半の医療の視点。 ・脳科学の分野でも、社会行動、コミュニケーションなど個体を超えたレベルでの研究は端緒についたばかり。 ・ソーシャルキャピタルと健康・医療の関わりには大きな相関がある。 ・社会的なつながりが人間にとって重要という当たり前のことが、科学で論証されている。
Posted by
興味があり、購入。 読み進めるには少ししんどい印象。 しかし、内容自体は最近自分の考えていた内容に大いに関係していると共に、これからの課題であると感じていたことであった。 コミュニティ形成に大切な要素が今の現状足りてないと感じた。
Posted by
領域、テーマは凄く興味大。なんだけど、文章が冗長的でしんどいね。エッセンスを抽出しながらの読み飛ばしができればいいんだけど。ということで、情けないけど、まだ奮闘中。
Posted by
「コミュニティ」を様々な視点から俯瞰しているが、切り口が都市・グローバル化・福祉政策など様々で興味深い。都市計画や環境が主な論点と思っていた分、福祉政策・ケアについての指摘は読んでいておもしろかった。なるほどしかし、所謂西洋的な独立した個人のいる社会と村社会的な社会が補完的とはよ...
「コミュニティ」を様々な視点から俯瞰しているが、切り口が都市・グローバル化・福祉政策など様々で興味深い。都市計画や環境が主な論点と思っていた分、福祉政策・ケアについての指摘は読んでいておもしろかった。なるほどしかし、所謂西洋的な独立した個人のいる社会と村社会的な社会が補完的とはよく考えれば成程と思わされてしまった。
Posted by
西洋・中国の都市と日本の都市、街並み・景観、公・共・私、…様々な角度から論じている。コミュニティをめぐる思索の旅に出た気分に。 結論の出せないテーマなので、最後がムニャムニャですが、終盤流し読みにしても十分満足な内容だと思います。
Posted by