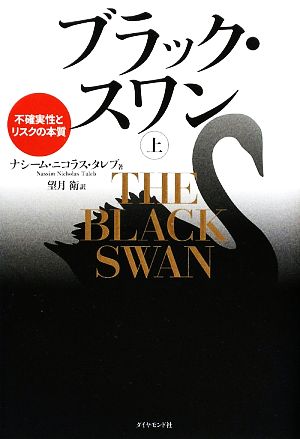ブラック・スワン(上) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
社会経済的に問題となっている格差の多くは、「果ての国」に属している。そこでは、法則に当てはまらない「黒い白鳥」が見て取れる。だから過去の情報から一般化して、将来を予測できるなんて思わないほうがよい。というのが本書の内容。社会科学における仮説は正しくそうなのかもしれない。新しく仮説を立てて因果を推論するたびに、我々の知識はプラトン化し、黒い白鳥に対応できなくなる。
Posted by
・予測可能な事象はごくごく限られている。 ・予測可能と思い込んでしまうのは、追認と後講釈によるところが大きい 言われてみればその通りだと思うが、このことを金融マーケットに身を置く人が主張するところが興味深い。
Posted by
皆こぞってものごとを予測しようと頑張るけど、世界の大きな出来事は予測から大きく外れているし、いつ起こるかもわからないよという話。 統計などに頼って物事を考える傾向がある私にとって、「ありえないことなんてこの世にない」という事実をつきつけてくる本書はとても新鮮、というより鈍器で頭を...
皆こぞってものごとを予測しようと頑張るけど、世界の大きな出来事は予測から大きく外れているし、いつ起こるかもわからないよという話。 統計などに頼って物事を考える傾向がある私にとって、「ありえないことなんてこの世にない」という事実をつきつけてくる本書はとても新鮮、というより鈍器で頭を殴られたような感じがしました。 何事も100パーセント否定せず柔軟にいきたい。 本書を面白いと感じた方は、ハンス・ロスリングのファクトフルネスもおすすめです!
Posted by
確率論。哲学。心理学。 とにかく難しい。前作『まぐれ』より難しいと感じた。 恐らく内容の1%も理解できてないと思うが、印象的な言い回しは多い。 下巻も頑張って読む。
Posted by
洋書に多い実験や検証の結果を長く書くものと違い、理論を事例やメタファーを混ぜて説明する(が、長い)、珍しい展開の書籍。 ブラックスワン(思ってもない予想外の出来事)ってのが存在するんだから、予測をするんじゃないと。 それよりも疑って実証していけと。 予想なんてできないし、複雑...
洋書に多い実験や検証の結果を長く書くものと違い、理論を事例やメタファーを混ぜて説明する(が、長い)、珍しい展開の書籍。 ブラックスワン(思ってもない予想外の出来事)ってのが存在するんだから、予測をするんじゃないと。 それよりも疑って実証していけと。 予想なんてできないし、複雑な物事をフレームワークに当てはめて単純化して理解する(プラトン的、と本書で言われている)のも間違っている。 自分は知らない、ということを知るべきだと。 うん。だとして、複雑な事象とか世の中をどう理解すればええんだ?というのが率直な感想。 冒頭から触れられている「懐疑的実証主義」ってのを実践せよって話の結論かなと「予測」してみる。
Posted by
上は心理について、 男性身長をランダムに100人調べると 平均身長170センチ に230センチが加わると 平均身長170.5センチ ➡️大きな衝撃ではない 【月並みの国】 拡張不可能 典型的なメンバーは凡庸 先祖の環境で見つかりやすい 勝ち馬は全体の一部を どんぐりの...
上は心理について、 男性身長をランダムに100人調べると 平均身長170センチ に230センチが加わると 平均身長170.5センチ ➡️大きな衝撃ではない 【月並みの国】 拡張不可能 典型的なメンバーは凡庸 先祖の環境で見つかりやすい 勝ち馬は全体の一部を どんぐりの背比べ 【果ての国】 巨人or小人 現代の環境で見つかりやすい 勝者総取りの世界 経済格差が大きい 現代 七面鳥は1000日までいままで美味しい食べ物をくれていたけど突然殺される。 Aがある証拠がない、というだけでないと決めつけてしまう。 法則がない、ストーリーっぽいのは想像してしまう宝くじ。 テロ保険。普通より高い金額で払う保険。 ストーリーが出来上がる事でありそうになる。 大成功した投資家 〜したから成功できた。 失敗した人の声は表に出る事はない。 結局は運。 生存者バイアス 因果関係を作りたがる。理由、説明をつけたがる。 強いランダム性や説明不可能な突然の事【ブラックスワン】に思考を巡らせることができなくなってしまう。
Posted by
タレブの経験と知識が詰め込まれた最高の本。 ブラックスワンという概念を始めて知る事ができた。金融トレーダーとして不確実性と常に戦っていた彼が綴る物語は面白いだけでなく、啓蒙的である。 ブラックスワンを予測するべきでもなく、後付けで考えるべきでもなく、分かった気になるべきでもない。...
タレブの経験と知識が詰め込まれた最高の本。 ブラックスワンという概念を始めて知る事ができた。金融トレーダーとして不確実性と常に戦っていた彼が綴る物語は面白いだけでなく、啓蒙的である。 ブラックスワンを予測するべきでもなく、後付けで考えるべきでもなく、分かった気になるべきでもない。 タレブの言説を本当に理解するにはまだまだ時間がかかりそうだなぁ。
Posted by
科学や歴史や政治家や世のビジネスマンに対する皮肉とユーモアの詰まった最高の哲学エッセイ集だった。たとえば土屋堅二さんの「われ笑うゆえにわれあり」を楽しめる人なら、夢中になって読めると思う。シリーズで出ればずっと買い続けるだろう。いつまでも読み続けたいけど、あまりハマると、かなりひ...
科学や歴史や政治家や世のビジネスマンに対する皮肉とユーモアの詰まった最高の哲学エッセイ集だった。たとえば土屋堅二さんの「われ笑うゆえにわれあり」を楽しめる人なら、夢中になって読めると思う。シリーズで出ればずっと買い続けるだろう。いつまでも読み続けたいけど、あまりハマると、かなりひねくれた、会社に合わない人間になりそうだ。図書館で上下巻まとめて借りて読んだが、上巻は多くの人に読まれた形跡が明らかにあるのに、下巻は新品のようにまっさらだった。なんだかもったいない。何か学術的に、理論に結びつけようとか、著者がトレーダー(本人の自己紹介は実証主義者にして非情なデリバティブトレーダーとなっている)だから間違っても経済学と何か結び付けようと頑張って読む人は(そういうレビュアーがいるみたい)、だんだん腹が立ってきて、途中で投げ出してしまうのではないだろうか。世の中、政治家も学者もビジネスマンも、申し合わせてバカになって、白鳥だけを見るように頑張っているからお給料が貰えるのだ。そういう中で頑張っている自分を慈しめているから、本書を読んで腹が立つのだ。非難されることではないと思う。この世界には大人の文脈があって、歴史も大人の文脈で描かれている。子供は違う、大人の知らないところで、黒い白鳥と日々対話して生きている。レバノンの内戦という非日常を日常として子供時代を過ごした著者は、より強烈に、黒い白鳥と向き合う子供時代を過ごしたのだろう。ここに強烈な切なさがある。911のビルに飛行機が突っ込むを見事に予言した人として著者は賞賛されるが、実際、子供は四六時中そんなことを考えている。ウクライナで砲火の下にいる子供たちと著者が重なった。私たちも明日、講和を見るか世界大戦への突入を見るのか分からない同じ世界にいるのだけど。
Posted by
シーム・タレブによる「リスクと予測」に関する著書。起こりそうにもないが実際に起こった時に破壊的な影響ももたらす事象が「ブラック・スワン」であり、著者曰く、これはまったく予測できるものではない。 歴史や社会の流れは必ずしも連続的なものではなく、大きな変化は寧ろ断層から断層への飛躍に...
シーム・タレブによる「リスクと予測」に関する著書。起こりそうにもないが実際に起こった時に破壊的な影響ももたらす事象が「ブラック・スワン」であり、著者曰く、これはまったく予測できるものではない。 歴史や社会の流れは必ずしも連続的なものではなく、大きな変化は寧ろ断層から断層への飛躍によって生ずる。人はこれを予測可能だとするし、ともすれば後付けでそれが起こった理由を探して「予測できたはずのもの」だと捉えるが、これは全くの誤謬である。ブラック・スワンは予測不可能であり、それを予測することを試みるよりもそれが起こった場合に備えることが重要だとする。 リスクへの「反脆弱性」がこの本のコアメッセージだといえる。これには納得感があるし示唆を与えてくれる。ただしエッセイ風なのもあり、とにかく冗長。さらっと読んで要約するぐらいが丁度良い。 パンチライン:「読み終わった本よりも読んでいない本のほうがよっぽど価値がある」
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「リスク」とはどのような意味でしょうか。 コロナで「第六波になるリスクがある」、「この金融商品は元本割れのリスクがある」など言いますね。 ネガティブな意味で使われるので、「危険性」という意味にとらえれることが多いです。 しかし、リスクの本来的な意味は「変化」です。 「この商品を投入すると損益が変わるリスクがある」というと、 損益が改善する可能性もあるし、悪化する可能性もある、という意味になります。 ブラックスワンは、簡潔に言うと「予想できない大きなリスク」を意味します。 なんとなく、ずっと働き続けられる、家族がいる、会社がある、と思っていませんか。 健康状態が悪化して働けなくなるかもしれません、自然災害や不慮の事故で家族を失うかも。 今時会社が倒産することも珍しくありません。 リスクを恐れて現状維持に努めるべきではありませんが、 自分が予見できているリスクが全部と盲信せずに、 ”見えているリスク”と”見えていないリスク”を区別しながら、 「取れるリスク」をしっかりとっていく、ということをこの本は言っていると思いました。 ただ、この本、洋書で元々表現が独特なのか、非常に読みづらいです笑
Posted by