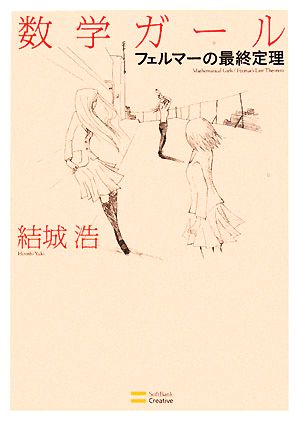数学ガール フェルマーの最終定理 の商品レビュー
2024.07.08〜2024.07.10 数学ガールの2巻目。 サイモン・シンさんが書いたフェルマーの最終定理は読んだことあったが、それよりもややライトに復習できて非常に面白かった。 前作同様、手を動かして数学をやりたくなる。 代数分野は大学時代苦手だったけど、いろいろ思い出す...
2024.07.08〜2024.07.10 数学ガールの2巻目。 サイモン・シンさんが書いたフェルマーの最終定理は読んだことあったが、それよりもややライトに復習できて非常に面白かった。 前作同様、手を動かして数学をやりたくなる。 代数分野は大学時代苦手だったけど、いろいろ思い出すとまたチャレンジしたいなと思えてきた。 やはり数式も多く出てくるので人を選ぶ本ではあるが、数学好きには引き続きお勧めしたい一冊。
Posted by
数学的な部分は噛み砕いて、発見的でほんとうに素晴らしい。 個人的には女の子の描き方が気になった。母も加えると女性全般か。ジェンダーの規範化が強く出てしまっている。
Posted by
いつもながら面白い。e^xのテイラー展開など、とても面白かった。谷山志村とかは表面のサラッとしたところだった。それでもとても難しかったが…。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第2巻は、フェルマーの最終定理。さすがに、これを説明するには、内容的にもボリューム的にも難しかったか?。雰囲気だけ理解できたような気になって終わってしまった。 しかし、あらためて数学の持つ面白さを体感させてくれる。 原始ピタゴラス数、互いに素、複素平面、余り、群、法、オイラーの公式、自然対数、指数法則。高校時代に漠然と聞いていた用語が、意味を持って繋がる気がする。かといって、人生に役立つわけではないが…。それがいいのかもしれない。 最先端の数学が、時代がくれば学校の教科書に載る、と語る。「負の数」や「複素数」のように。私たちは、まだまだ、新しい数学の世界を傍観するだけだけど。
Posted by
第6章6.2.2まで読了。 第2作『数学ガール フェルマーの最終定理』 プロローグ 整数は神が作った。それ以外は人が作った。 ークロネッカー 整数は神が作った、とクロネッカーは言った。整数と直角三角形とを結びつけたピタゴラスにディオファントス。さらに一ひねりしたフェルマー。そ...
第6章6.2.2まで読了。 第2作『数学ガール フェルマーの最終定理』 プロローグ 整数は神が作った。それ以外は人が作った。 ークロネッカー 整数は神が作った、とクロネッカーは言った。整数と直角三角形とを結びつけたピタゴラスにディオファントス。さらに一ひねりしたフェルマー。その茶目っ気が、三世紀以上も数学者を悩ませた。誰でもわかるのに誰にも解けない。史上最大のパズル。それを解くためには、すべて数学が投入されなければならなかった。単なるパズルとあなどるなかれ。 第1章 無限の宇宙を手に乗せて 第2章 ピタゴラスの定理 現実世界に存在する何よりもすぐれた道具、数学を持っている。 《整数の構造は、素因数が示す》 授業を聞くのは刺激になる。本を読むのもためになる。けれど、自分の頭と手を動かす時間をたっぷりとらなければ、授業も本もまったく無意味だ。 第3章 互いに素 第4章 背理法 「問題の意味って・・・読めばわかるんじゃないの?」 「問題を読む《深さ》が人によって違うんだ。」 「深さとか言われてもなー」 「問題を読むときにはね、定義を確かめるのが大事」 証明を丸暗記しても意味はない。自分でノートを広げて、シャープペンを持って、もういちど自力で証明しよう。 たいてい上手くいかないものだから、証明できなくてもがっくりこないようにね。どこかで行き詰まっちゃうんだ。自分でわかったつもりでいても、なかなか証明は完成できないものだよ。行き詰まったら、本や自分で書いた以前のノートを読んで勉強する。完成できるまで、何度も繰り返し練習する。・・・その繰り返しで、数学を学ぶ足腰が強くなる。丸暗記とは違う。数学的な構造を理解し、論理の流れを追う力、数の性質をうまく使って問題と取り組む力を養うんだよ 第5章 砕ける素数 数学者の最も大切な仕事の一つは、研究した結果を《証明》という形で残すことだ。歴史的に、無数の数学者が無数の仕事をしてきた。現代の数学者は、《証明》によってその歴史に自分の一歩を加えることになる。 第6章 アーベル群の涙 なにがしあわせかわからないです。 ほんとうにどんなつらいことでも、 それがただしいみちを進む中でのできごとなら、 峠の上り下りもみんなほんとうの幸福に近づく 一あしずつですから。 -宮沢賢治「銀河鉄道の夜」
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読んでいる わかった気持ちになってしまう それで十分気分が良い 自分で手を動かしたわけでもないし、 注意深く考えたわけでもないから 完全にこの世界に入り込めてはいないのだけど、 登場人物たちが この世界で 数学を楽しんでいることを感じて 最初の方の話が 最後の方で繋がってきて 数式で貼られた伏線というか ミステリィを読んで楽しいという気持ちに近いのかもしれない 知らなかったことが 少しだけわかるようになる楽しさ 論理を積み重ねていくことの心地よさ 今学んでいることは 大昔の最先端で 今の最先端は 未来の今学んでいることで そうして積み重なっていく
Posted by
一巻に続き読了。面白い。 しかし、やはり少し難しい。この続きのシリーズはしばらくやめて、秘密ノートシリーズを読むことにしよう。 無限降下法おもしろい。
Posted by
実際にフェルマーの最終定理が出てくるのは終盤なのだけど、 そこまでに扱われているネタも実はフェルマーの最終定理に絡むもの、ということが 分かればさらに楽しめるかな。 「最後ミルカさんがハイパー化する」という書評は読んでいて、それは確かに その通りなのだけど、一般人には理解不能なワ...
実際にフェルマーの最終定理が出てくるのは終盤なのだけど、 そこまでに扱われているネタも実はフェルマーの最終定理に絡むもの、ということが 分かればさらに楽しめるかな。 「最後ミルカさんがハイパー化する」という書評は読んでいて、それは確かに その通りなのだけど、一般人には理解不能なワイルズの証明のうち、雰囲気だけでも 感じてもらおう、という構成はさすがに良くできてると思った。 相変わらずストーリー展開の部分ではむかむかする所もあるのだけど、 前作よりは量的には減ってる気はするのでまだまし。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
だいぶ長い間積読になってたこの本、再開したいと思います。 自然数がいくつか並んでいたときにそれが偶数か奇数かを考えるのと同じように奇数を4で割ったときにどうなるか考える。余りが1か3に分類される。 ------------ 数学に触れたことがある人ならば誰でもその答えを知りたいと思うシンプルな定理それがフェルマーの最終定理かなと思う。本書ではフェルマーの最終定理が証明可能であることを解き明かしていくのだが、実際にその式が文中登場するのはP.222ページの中盤から後半にかけてである。それまでの間、導入部分では数字の仲間外れ、完全巡回をめぐって素数の不思議や互いに素であることの訓練を行っていく。またピタゴラスの定理という誰もが知っている直角三角形で使われる言葉から、原子ピタゴラス数は何かに触れそれが無数に存在することを証明する。 フェルマーの最終定理には背理法を使うため、前半クライマックス部分で「√2が有理数でないことを証明せよ」という問題を背理法で解決しその考え方に慣れる。 またその証明の仕方において偶奇(パリティ)を調べていくことの手段を知る。偶奇を調べる、辺々足す、辺々引く、式の部分を別の文字で置き換えるというプラクティスをずっと続け、やはり最後の証明に必要な基礎的な考え方を実践していく。 素数が複素数を含んだ積の形で表すことができるかどうかを考え、その結果砕ける素数は4で割った余りが3である素数であることを突き止める。 *4で割った余りが3であることで素数を分類のは一番最初の「数字の仲間外れ」で僕が用いた手法で従妹のユーリが「まるでこじつけみたい」とコメントしたように不自然な手法のようにも思われるが、やがて偶奇を調べることと同じくらい柔らかくなじんだ手法に感じられるようになっていく。 その後、数学の群を定義する。そして数学らしからぬ緩やかな定義に感じられる合同の考え方を学ぶ。 さてここまでを学んだ上でのフェルマーの最終定理である。その前に最も美しい数式といわれるオイラーの公式に触れるのであるが、これはフェルマーの最終定理を背理法で証明するにあたって、楕円関数と保型形式の世界をつなぐ谷山・志村の定理において指数関数をテイラー展開して得られた結果をあてはめると、素数=楕円関数の数例と保型形式の数列の間に和が成り立つという答えを得られるためであった。 このようにしてわかりやすいフェルマーの最終定理をその式の形とは全く異なる要素の背理法を使って証明し物語を終える。
Posted by
今回からユーリという新しい登場人物が参加です。 主人公と共に数学について考える3人の女性たちは各々考え方、得意分野、視点がバラバラです。 その特徴が面白く感じました。 数学というものは1人でコツコツ解いていくものという概念がなくなるほど、対話から生まれる新たな発見が魅力です。
Posted by