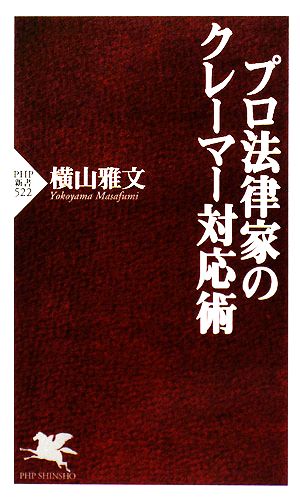プロ法律家のクレーマー対応術 の商品レビュー
近くの部署で著者に依頼することもあるらしいので読んでみた。 弁護士が書いた本だからという声もあるだろうが専門家に任せるという対応には賛同。 見えない金をケチる、担当部署間任せという企業は是非とも考えを改めていただきたい。
Posted by
マニュアル的なものではないが、実務的に使える内容。 何が「悪質」クレームか。悪質クレームは法的にはどう評価され、それにいかに対処するか。
Posted by
クレームの多かった元職場にいた時、元有名デパートお客様相談室長だった関根眞一氏の著書を読んだ。その延長として本書を読む。本書は弁護士の視点から、悪質クレーマーに対処するノウハウを教示してくれた。著者の主張は「悪質クレーマーは顧客として扱うべきでなく法的対応をすべき」ということ、「...
クレームの多かった元職場にいた時、元有名デパートお客様相談室長だった関根眞一氏の著書を読んだ。その延長として本書を読む。本書は弁護士の視点から、悪質クレーマーに対処するノウハウを教示してくれた。著者の主張は「悪質クレーマーは顧客として扱うべきでなく法的対応をすべき」ということ、「嫌がらせをしようとする人々は現におり、それによって苦しめられている人々がいる」という主張に、実感を伴って首肯できた。
Posted by
積ん読であったが、必要に迫られて読む。3時間程度で読み切ることができた。 クレーマーを5種類に別け、それぞれ性質と攻略方法が提示されているところが参考になった。 筆者も述べているように、終着点の見えない状況が担当者を疲弊させるので、一読しておくだけでも楽になるのかと思う。
Posted by
非常に役に立ちそうです。というより日々の対処に後ろ盾ができたという感じでしょうか。これまでのクレーム本とは一線を画す内容で、私は現実的な内容だと思いました。
Posted by
===引用ここから=== このように、悪質クレーマーは、いつ我々の前に出現するかわからず、運悪く取り憑かれれば、我々の人生を狂わすほどの脅威なのです。 ===引用ここまで=== 弁護士横山雅文氏の著書。顧問先企業の民事介入暴力、悪質クレーム対応の経験から、悪質クレーマーを分析し...
===引用ここから=== このように、悪質クレーマーは、いつ我々の前に出現するかわからず、運悪く取り憑かれれば、我々の人生を狂わすほどの脅威なのです。 ===引用ここまで=== 弁護士横山雅文氏の著書。顧問先企業の民事介入暴力、悪質クレーム対応の経験から、悪質クレーマーを分析したとのことで、クレーマーの分類・判別・対処方法まですっきりと整理されています。 良いことを教わったなというポイントをいくつか。 ・悪質クレーマー判断ポイント。①欠陥・瑕疵ないし過失の存否②損害の存否③欠陥・瑕疵ないし過失と損害の間の相当因果関係④損害と要求との関連性⑤クレーマーの行為態様 ・『欠陥』製品が通常有すべき安全性を欠いていること。『瑕疵』製品が通常有すべき機能を欠いていること。『過失』損害の発生について注意義務違反があること ・悪質クレーマーは4つのタイプに分ける。①性格的問題クレーマー②精神的問題クレーマー。③常習的悪質クレーマー④反社会的悪質クレーマー ・交渉窓口を弁護士に移管することも効果あり。 ・反社会的勢力は人の弱みにつけこむ。決して「秘密を共有しない」。 ・反社会的勢力の行動には経済的合理性がある。企業からお金が出ないことを悟らせるため、弁護士に早急に相談し、法的手段(仮処分、刑事告訴)をとることも検討。 ・念書、確認書など種類の如何を問わず、示談書のように会社の決済を経て最終的に正式に作成される文書以外、絶対に、交渉の場で文書を作成することに同意しない。裁判において強力な証拠能力をもってしまう。 行政窓口や企業のお客様相談室などでお仕事をされている方は、日々こういった悪質クレームに対応されていて、さぞかし大変かと存じます。長引くクレーム対応で力尽き、うつ状態になってしまう方も多いとのこと。長期的には、社員が健康で長く仕事できる環境を作ることに経済合理性がありますので、一時的な費用をケチらず速やかに弁護士を活用すること、また、悪質クレームに対して確固たる社内制度設計をするよう、経営層の方々にもご認識いただきたいと思いました。 実例に基づいているからか、どのケースもよくあるなあと思いながら読みました。担当者だけでなく、経営層や、クレーム担当者以外の方にも興味深く読める一冊です。
Posted by
実践的でよい本だと思う。紹介されているケースもリアルでとても生々しいし。 弁護士が書いた本なので、弁護士としても参考になる。法的な手段、どれを選択したらよいのか、ということが明らかになるのはとてもありがたい。手続きの進め方は勉強すればわかるけど、そもそもこのケースでどんな手段が適...
実践的でよい本だと思う。紹介されているケースもリアルでとても生々しいし。 弁護士が書いた本なので、弁護士としても参考になる。法的な手段、どれを選択したらよいのか、ということが明らかになるのはとてもありがたい。手続きの進め方は勉強すればわかるけど、そもそもこのケースでどんな手段が適切なのか、ということは経験がないとわからないことなので。 他方で、どんな人をクレーマーと認定すればよいかなど、現場の人の指針にもなる。一番役に立つのは現場の人にとってだろう。弁護士に仕事をつなぐ際の見通しも立つことになるので。 下手な現場レベルの技術論だけの本よりも格段にオススメ。
Posted by
●悪質クレーマーは、本質的に合理的な説明、常識的な対応では納得しない人々。そのため、悪質クレーマーとの交渉は必ず堂々巡りとなり、悪質クレーマーの不当な要求を吞まない限り、交渉を続けても平行線なのだ。 ●顧客と悪質クレーマーとは峻別して対応すべき。悪質クレーマーは顧客として対応すべ...
●悪質クレーマーは、本質的に合理的な説明、常識的な対応では納得しない人々。そのため、悪質クレーマーとの交渉は必ず堂々巡りとなり、悪質クレーマーの不当な要求を吞まない限り、交渉を続けても平行線なのだ。 ●顧客と悪質クレーマーとは峻別して対応すべき。悪質クレーマーは顧客として対応すべきではない。悪質クレーマーに対しては、顧客対応ではなく法的対応をとるべき。彼らの行為に対して、法的観点から客観的に対応するということ。例えば彼らの賠償要求が法的観点から認められないのであれば、文書でその要求を拒絶し、これが最終回答であると通知する。悪質クレーマーを対立する相手方として捉えて法的に対応することで、顧客対応から離脱するということが重要。 ●本来的にその部署の行為によって顧客に損害を与えたのであれば、その損害が会社の命令や方針・姿勢に基づくものであるか、あるいは、顧客の生命・身体に損害や危険を発生させたりした場合でなければ、会社の代表者が直接謝罪する必要はない。個々の行政窓口の不始末を、行政の長である内閣総理大臣や知事が直接謝罪する必要がないのと同じ。その担当部署の責任者が謝罪すべきであり、かつ、それで足りる。「本件は、会社の基本方針に基づいてかけたご迷惑ではなく、○○係のミスですので、担当部署の責任者が謝罪させていただきます」と丁寧に説明すればよい。 ●事実確認が済むまで(調べを尽くしても事実かどうかの判断がつかない場合も含む)、次のステップ、たとえば、損害の査定や賠償額の提示に進んではならない。 ●人間の思考というのは、常に安易な方向に習慣がつきやすいもの。一度安易な考えで処理すれば、必ず、習慣化する。そして、そのような処理はその人1人で済まない。同僚もそのような処理の「ゆるい雰囲気」の影響を受ける。さらには、後任者はそのまま、そのような処理を踏襲していく。悪質クレーム対応の巧拙は、従業員の志気、ひいてはその企業の文化に影響を与えてしまう。 ●担当者がクレーマーに迫力負けして混乱し、言質をとられないコツは、「自分には決裁権はないが、事実調査については自分が責任者である」ということを常に念頭において、事実関係の確認に集中することに尽きる。 ●悪質クレーム対応の7つの鉄則 ①まずお詫びから ②事実の確認を先行させる 事実確認とは、企業側に法的責任があるか否かを判断するための諸要素、すなわち、企業の過失、製品の欠陥、顧客の損害、過失や欠陥と損害の相当因果関係に関係する諸事実を確認すること。 ③感情的な対応は厳禁 ④堂々巡りになったときが最初のポイント 悪質クレーマーか否かの見極めは、クレームに対して、こちらが合理的な説明を繰り返しても、相手方がこれに納得せず、交渉が平行線になっとときにつく。 ⑤文書による最終回答・交渉窓口を弁護士に移管する通知を送る 「社内で検討し、文書でご回答します」と言って交渉を打ち切り、文書で「本件に関しましては、弊社と致しましては、重ねて申し上げましたとおりの対応しか致しかねますので、これをもって最終的なご回答とさせていただきます」と通知する。 ⑥加害行為には素早い仮処分と刑事告訴で対応 ⑦悪質クレーム事例を記録して対応の指針とする
Posted by
昔のレビューのコピペですが。 最近、権利意識の高まりとともに、理不尽な要求、不遜な態度、そんな客が増えてきている。 顧客と違って、“クレーマー”に対しては法的に事務的に対応が必要である。クレーマーの見分け方、分類、法律的対応策、例文集まで。実に簡潔に、わかりやすく書かれている...
昔のレビューのコピペですが。 最近、権利意識の高まりとともに、理不尽な要求、不遜な態度、そんな客が増えてきている。 顧客と違って、“クレーマー”に対しては法的に事務的に対応が必要である。クレーマーの見分け方、分類、法律的対応策、例文集まで。実に簡潔に、わかりやすく書かれている。 おれは患者相手だが、やっぱり問題のある人は多いし(地域によって差が激しい)、今の日本はサービス業がほとんどであり、どんな人でも一度は読んでおいて、いつこんな人と対峙することがあってもやり過ごせなきゃいけないと思う。 面白いし、役に立つ。お勧めの一冊。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
どんなお客様でも、対応が悪ければ悪質なお客様になってしまう。①まずお詫び。苦情が、お客様の誤解である場合も少なくないが、商品やサービスを利用し、お困りごとが発生したことには間違いない。先ずお詫びして事実確認を行う準備を整える。②最も大切なのは事実の確認。どんなお申し出ででも、お客様は何らかの損害を被っており、それを回復したいと思っているため、お客様自身に落ち度があったことを自覚していても、正確に話してくれない場合がある。③お客様の本当のお困りごと、本当に保証して欲しいことは何か?」ということを突き止める。
Posted by