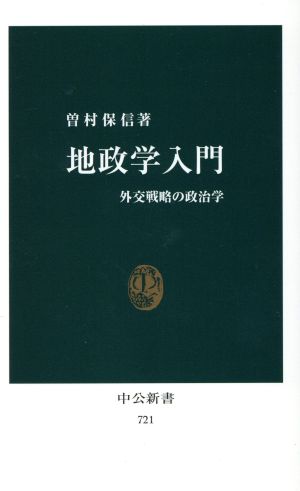地政学入門 の商品レビュー
入門とタイトルにあるが、そもそも地政学自体が地理は当然歴史、軍事等広大な範囲の知識を必要とするため、本書のみで地政学に入門を果たすことは難しいように思う。
Posted by
マッキンダー、ハウスホーファー、マハン等の地政学の理論家を、用語の解説含めて丁寧に説明。新書サイズで地政学に触れられる本は貴重なので、入門に最適です。日本では陰に追いやられてますが、地球を一つの単位として巨視する事の重要性は増しているので、地政学は現代こそ学習する意義があると思い...
マッキンダー、ハウスホーファー、マハン等の地政学の理論家を、用語の解説含めて丁寧に説明。新書サイズで地政学に触れられる本は貴重なので、入門に最適です。日本では陰に追いやられてますが、地球を一つの単位として巨視する事の重要性は増しているので、地政学は現代こそ学習する意義があると思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ダメ本。地政学の内容を俯瞰する本はほとんどないが、アマゾンでそれらしきものを検索するとでるが、地政学の成り立ちを述べているだけで、何の役にも立たない。
Posted by
この領域、政治地理学というべきか、マクロにみた世界史像というべきか。 本書では、地政学の成立史とその学問形成の背景を対談風に述べる。 イギリスの生んだマッキンガーが、「シーパワー」と「ランドパワー」の見方をしめす。海洋国と大陸国、情報収集で広範にして進歩的な海洋国、...
この領域、政治地理学というべきか、マクロにみた世界史像というべきか。 本書では、地政学の成立史とその学問形成の背景を対談風に述べる。 イギリスの生んだマッキンガーが、「シーパワー」と「ランドパワー」の見方をしめす。海洋国と大陸国、情報収集で広範にして進歩的な海洋国、ドイツ・ロシアなど海上交通で国際的なひろがりよりも伝統的・権威的な大陸派の対比をこころみる。 ドイツのうんだハウスフォーヘン。第一次大戦前後の時期に、東アジア、とりわけ日本の国勢に着目。「理想化」しすぎたとの地域観ながら、のちに枢軸国の一員となる伏流水を読み解く感がある。 ロシアの地政学と言うのもある。現代、地政学は地域振興のキーワードの感があるが、ここで論じられているのは第二次大戦に至る連合国、枢軸国体制の枠組みせつめいということ、か。 このように読んできたとき、世界の火薬庫というか、世界のオイルマネーがあつまるとして注目をあつめる中近東への視座がないのは、少し残念ということにもなる、が。しかし、それはあまりに直近の地政学を求めすぎるということになるのであろうか。
Posted by
地政学の教科書というより、マッキンダー・ハウスホーファーの紹介本。 【メモ】 ①マッキンダー・ハウスホーファー→西欧視点(英・独) マッキンダー:理論に一定の客観性を維持しているが、 ハウスホーファーなんて思いっきりドイツの話。 ②極東アジアにフォーカスした地政学研...
地政学の教科書というより、マッキンダー・ハウスホーファーの紹介本。 【メモ】 ①マッキンダー・ハウスホーファー→西欧視点(英・独) マッキンダー:理論に一定の客観性を維持しているが、 ハウスホーファーなんて思いっきりドイツの話。 ②極東アジアにフォーカスした地政学研究あるか? (シナ・メコン・朝鮮・日本)→継続リサーチ ③戦争の根源がつまりは人口・土地(資源)の問題であるならば、 アジア大陸(中東以東)に於ける大国(中国・インド)の 人口動態の変化は?又、人口減少に入っている国は? ④人口・土地に、無国籍資本の要素をどう反映?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] [ 目次 ] [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
新聞でよく「地政学的リスク」という言葉が登場する。 普段は読み飛ばしてみてしまうが、休み中に曽村保信著の表題の本を読んでみた。 ただ引きこもっているだけではよろしくないので、 家族でJRの首都圏大回り乗車(八高線・湘南新宿ライン中心)をしながら電車の中で読む。 中高で勉強する世界...
新聞でよく「地政学的リスク」という言葉が登場する。 普段は読み飛ばしてみてしまうが、休み中に曽村保信著の表題の本を読んでみた。 ただ引きこもっているだけではよろしくないので、 家族でJRの首都圏大回り乗車(八高線・湘南新宿ライン中心)をしながら電車の中で読む。 中高で勉強する世界史や世界地理は、地政学を理解する上で 基礎中の基礎と思う。そのときはわからないんだな。 地政学=シオポリティックスgeopoliticsで、地理と政治学との関係が強い。 地政学の流れには大きく分けてあるという。 ドイツのカール・ハウスホーファーが、 「国家は国力に相応の資源を得るための生存圏を必要とする」というもの。 この生存圏構想はヒトラーにより活用・実践されて消滅した。 海上貿易国家構想の基礎となるイギリスのマッキンダーによる、 大陸勢力(ランドパワー)と 海洋勢力(シーパワー:軍事力・港湾や海上交通を維持できる外交能力)が 世界の覇権をめぐって争っているというものだ。 大陸勢力は、ユーラシア大陸とアフリカ大陸の「世界島(ワールド・アイランド)」からなり、 そのハートランド(心臓部/内陸部)は、中央アジアとシベリア中部を指す。 東欧を制するものはハートランドを制し、 ハートランドを制するものは世界島を制し、世界島を制するものは世界を制す。 という考えの上で、各国の利害が絡み、先の大戦が起きた。 151頁のいわゆる「ヤンキー・インペリアリズム」という揶揄的な言葉があることも初めて知った。 なるほどモンロー主義の適用は、 米国による軍事介入の連続だったことからも明らかとのこと(154~157頁)。 今日でも、各国首脳陣は地政学を率先して活用し、外交政策を実施している。 日本では戦後この学問研究は禁止された。 ところで、昨今の沖縄基地の件は大丈夫かな。先行研究した上で施策を打たないと。 台湾と沖縄から米軍が撤退すると現状のパワーバランスが崩れると、 先日三菱UFJ証券の水野さんも言っていたし。 おまけ 直接的に関係があるわけではないけど、著書より引用。 「日本人には、何か新しい考え方が流行すると、それに集団で溺れるという傾向がある。」 「自由貿易も行きつくところは、結局他者の犠牲による独占体制の維持に落ちつかざるを得ない。」
Posted by
地政学には前々から興味があったので、思わず手に取った一冊。 なるほどBalance of Powersを重視する一般的な国際政治学とは一線を画す面白い視点である。 19世紀以来の対外政策を各の国家がおかれた地理的な条件を重視しながら、文化論・民族論を交えて論じるのが「地政...
地政学には前々から興味があったので、思わず手に取った一冊。 なるほどBalance of Powersを重視する一般的な国際政治学とは一線を画す面白い視点である。 19世紀以来の対外政策を各の国家がおかれた地理的な条件を重視しながら、文化論・民族論を交えて論じるのが「地政学的」アプローチと言えるだろう。 本書はイギリス、ドイツ、アメリカの地政学研究のおおまかな潮流を解説しながら、地政学全体の概説を行おうとしている。 ただ、普段歴史的(政治力学的)なアプローチに慣れている人間からすると論証がやや表面的になってしまっている(実証性に欠ける)と感じてしまう部分があり、その点では筆者が言う地政学の誤解されがちなイメージを完全に払拭するには至らなかった。
Posted by
地政学を初めて学ぶ上では良書だったが、少し古い。これが書かれた当時はまだ米ソ冷戦中であり、終章の「核宇宙時代の地政学」でも冷戦中のソ連にフォーカスを当てて書かれている。
Posted by
マッキンダーの考えを紹介することでイギリスを中心としたヨーロッパのシーパワーの地政学的考え方を、ハウスホーファーの考えを紹介することでドイツを中心としたヨーロッパのハートランドの地政学的考え方を、アメリカのモンロー主義の考えを紹介することでアメリカを中心としたシーパワーとハートラ...
マッキンダーの考えを紹介することでイギリスを中心としたヨーロッパのシーパワーの地政学的考え方を、ハウスホーファーの考えを紹介することでドイツを中心としたヨーロッパのハートランドの地政学的考え方を、アメリカのモンロー主義の考えを紹介することでアメリカを中心としたシーパワーとハートランドの融合という地政学的な考え方を紹介し、最後に旧ソ連の地政学的考え方を紹介している。 あくまで、学問的なこれまでの実績を紹介する入門書であって、新しい視点や独自の視点、さらには肝心の日本の地政学の視点が著しく欠如している。 地政学という「学問」はどういう学問なのか・・・を知るために、これまでの学問の歴史を知るには良い一冊。 地政学の本質には一切ふれていないため、評価は分かれるところ。新書という分野の欠点がそのまま出ている一冊。 まぁ、読んで損はない、といったところでしょうか。
Posted by