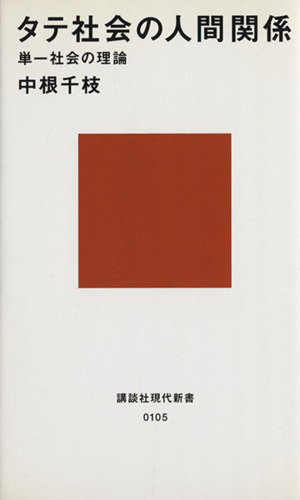タテ社会の人間関係 単一社会の理論 の商品レビュー
これは素晴らしい傑作…
これは素晴らしい傑作です。日本の場社会を批判したもの。なるほどの連続です
文庫OFF
多少古くなってしまっ…
多少古くなってしまったが、日本社会の人間関係を考える上では、欠くことのできない考え方である、『タテ社会』の理論が書かれている。時代の変化を踏まえた上で読めたら面白い。
文庫OFF
本書は1967年に初版が出されたものではあるが、現代社会の会社の中に、そして政治を動かす政党、官僚組織にも概ね当てはまる内容である。少なくとも私が所属する会社も一般的には社員規模数万人の大企業と言われ、本社組織だけでも1000人以上が働く会社であり、本書の言うタテの構造が全く当て...
本書は1967年に初版が出されたものではあるが、現代社会の会社の中に、そして政治を動かす政党、官僚組織にも概ね当てはまる内容である。少なくとも私が所属する会社も一般的には社員規模数万人の大企業と言われ、本社組織だけでも1000人以上が働く会社であり、本書の言うタテの構造が全く当てはまっている。今日も誰かが書いた稟議書を眺めながら、誰かが提出してくる企画書を忙しく眺めながら、「そこだけ担当してる立場ではないから、こんなに専門的に(さも知ってるかの様に)書かれても解らないよ」との考えを頭の隅に追いやって、まるで無意識でもある様に書類を決裁者に回す。時折、自分の存在に自信を失うほど、決まりきったタテの構造の一部に陥った自分の姿を客観的に眺めて、果たしてこれで良いのかと疑問に苛まれる。但しこうした構造があるからこそ、更に上の上司が世に言う盲印でもそれ程大きな問題になる事もない。決裁もその分早いのかもしれない。一方、他の部署との調整ごとはいつも難を極める。高く、分厚い壁を設けてくる部門間折衝ほど自分の力を発揮できそうで楽しいのだが、無駄な時間に感じられる事が多い。今日数名の部下と面談したが、正に本書でいうタテ構造の中で評価を勝ち得るか。その難しさに話が集中したりする。本来は組織の枠を超えて十分話し合い、役割分担を明確にしてから、スピード感ある施策を施さなければならないのに、どうも本書記載の通り、互いのチームに如何に仕事を持ち帰らないかの闘いの様相を呈して来る。知り合いのデジタル庁職員から話を聞く限り、各省庁間の横の連携も、概ね同じ様な形で仕事が進められているようだ。果たしてこの構造がいつまで続くだろうか。一つヒントになるのは従来の日本型雇用である、新卒一括採用と年功序列から役やり・能力をベースに組織化する形から、欧米のジョブ型雇用に変わりつつある点である。「うちの会社」も早くから実験的にジョブ型雇用を取り入れてはいるもの圧倒的な指示方=トップダウン式の仕事から脱却に至っていない。その辺りが日本的雇用体系、タテ組織の我が国にあっていないのか、中々当社で本格的に進めるのはハードルが高い。 少子化だからこそ、ジョブ型雇用の形を取りたいのだが、何となく上からの抵抗に毎回頓挫する事態だ。 これじゃあいつまで経っても大会社で組織の存在意義を100%意味のあるものにして、有機的に動かすなんて無理なのでは。その様な疑問を抱きながら、自社の組織に置き換えて、時にはメンバーや他の管理職の皆さんの顔が思い浮かびながら、ニヤニヤ読んでいる自分がいた。部門長の皆さんの机の上に配布でもしようかしら。
Posted by
日本という社会を明快に分析していると思う。場を基礎とする集団意識、縦を基礎とした樹状構造とそのヒエラルキー、これらは現在でも通じるものがあるだろう。初版初刷りの発行が 1967 年、底本の発表は昭和 39 年 (1964 年) というのが信じられないくらい。入社 2 〜 3 年で...
日本という社会を明快に分析していると思う。場を基礎とする集団意識、縦を基礎とした樹状構造とそのヒエラルキー、これらは現在でも通じるものがあるだろう。初版初刷りの発行が 1967 年、底本の発表は昭和 39 年 (1964 年) というのが信じられないくらい。入社 2 〜 3 年で転職してしまう若者が当時すでに増えていた (p.56) とはさらに驚いた。
Posted by
経営側ではなく、従業員の同期という発想が能力主義を阻み、年功序列を加速させる 日本では、良きディクテーターシップは起こり得ない。だから、リーダーは無能である方が良い。なぜなら、自身で思考できないが故に、全体の意見を吸収させるため。 カースト制度などインドは「資格」が重要だが、日本...
経営側ではなく、従業員の同期という発想が能力主義を阻み、年功序列を加速させる 日本では、良きディクテーターシップは起こり得ない。だから、リーダーは無能である方が良い。なぜなら、自身で思考できないが故に、全体の意見を吸収させるため。 カースト制度などインドは「資格」が重要だが、日本ではどのような「場」に所属しているかが問われる。そのため嫁にいった娘という本当の血縁関係よりも、婿養子の方が重要視される。
Posted by
なぜ日本では傑出したリーダーが生まれないのか、なぜ日本の労働力の流動性が低いのか、年功序列はどのように機能しているのか、、、そういった疑問について1つの枠組みを得ることができた。 60年前の本とは思えないほど、現代でも当てはまることが多くあった。社会が変わるということが、それほど...
なぜ日本では傑出したリーダーが生まれないのか、なぜ日本の労働力の流動性が低いのか、年功序列はどのように機能しているのか、、、そういった疑問について1つの枠組みを得ることができた。 60年前の本とは思えないほど、現代でも当てはまることが多くあった。社会が変わるということが、それほど難しいということなのかもしれない。 本書の内容が記憶に新しいうちに『タテ社会の力学』も読むと、筆者の主張がより理解できました。
Posted by
感想 時代は変わる。しかし社会のタテ構造はなかなか弛緩しない。気候が人種が、建物の構造が影響を与えているから。長所も短所もある。
Posted by
50年前に刊行されていまだに読み継がれているという日本社会を論じた代表的な書籍になります。いままで読む機会がなくようやく読みましたが、納得する点も多々ありました。原則ではなく人間関係がモノを言う、「ウチ」と「ソト」の意識、などの概念は今でも十分通用すると思います。ただ学術書ではな...
50年前に刊行されていまだに読み継がれているという日本社会を論じた代表的な書籍になります。いままで読む機会がなくようやく読みましたが、納得する点も多々ありました。原則ではなく人間関係がモノを言う、「ウチ」と「ソト」の意識、などの概念は今でも十分通用すると思います。ただ学術書ではなく一般書を意識してあえてそうしたのかもしれませんが、データの裏付けや検証部分については省かれていて、うがった見方をすれば「それは著者の周囲の偏った社会の中だけではないのか?」ということも言えるわけです。また海外との比較もたまに書かれていますが、英国、インドとこちらもかなり限られたサンプルとの比較であることは否めません。 5節では集団の構造分析ということでタテ、ヨコ、外周というような形で構造分析がなされていますが、私は本書のフレームよりも、エマニュエル・トッドが示した家族構造のモデルの方がピンときています(詳細は例えば『世界の多様性』などをご覧ください)。ただトッドも日本社会の分析となるとあまり切れ味が鋭くないことから(日本人の実感に合わない分析も多々ある)、そこは日本人の中根さんに軍配が上がる、ということで、日本社会の分析については本書が役立つと思いましたが、構造の一般化についてはさほど感銘を受けませんでした。
Posted by
メモ→ https://twitter.com/nobushiromasaki/status/1629094524361515008?s=46&t=iIkfXhkLTElgSN9R4n4cAQ
Posted by
タテ社会とは、タテの上下関係でできあがっている社会。動員は早く、一気に末端まで指示を浸透できる。リーダーとの人間関係という感情的な要素が強く、結束が強い。ただし、ヨコの連絡調整はタテの構造を弱くさせるということにもなる ヨコ社会とは、ヒエラルキーによって作られないので、個々の意見...
タテ社会とは、タテの上下関係でできあがっている社会。動員は早く、一気に末端まで指示を浸透できる。リーダーとの人間関係という感情的な要素が強く、結束が強い。ただし、ヨコの連絡調整はタテの構造を弱くさせるということにもなる ヨコ社会とは、ヒエラルキーによって作られないので、個々の意見が同様に扱われるので、意思決定をして進むには論理プロセスなどが必要になる。また、新規参加にあたっては、同列にすぐ参加できるが、何らかの資格が必要で、排他的になる。ただし、リーダーに依存していないため、個人がいなくなっても、集団組織は存続しえる。 タテ ヨコ 動員力強い 意思決定に工夫が要る 開放的・新規参加容易 排他的・新規参加に資格が必要 横の関係が機能しにくい 孤立などが起きにくい アジャイルの文脈でSAFeというのがあるが、 これはタテを重視してスピードと伝達能力を活かすやりかたになっている。 でも、Amazonなどの組織の作り方や、もとのスクラムというのは、このタテの重視では無かった気がする。タテを使ってスケール指せる要素はあるとおもうが、ヨコを重視する側面がある気がする。 整理がおいつかない。 (追記) タテ・ヨコという構造のほか、契約による構造という提示があった。 なるほど。 タテの社会というのは非常に優しい世界で、個々人を尊重するスタンスがあくまで求められる。 ヨコは、組織を動かすには向かないので、どうもそれだけでは成立しない。 契約の社会というのは、優しさがなくて、厳しさのなかで、組織が一定の契約で結びつく。 これだと、今の日本のメンバは、どこにも守られない中で、耐えられないかもしれない。 ただ、テレワークという中で、タテの結びつきを作る場がなくなりつつあり、さらに組織構造も薄くなった。 この中で、タテを求めて、優しさを求めてしまうと、キビシイ世の中になってしまう気がする。 もう少し整理しよう。
Posted by