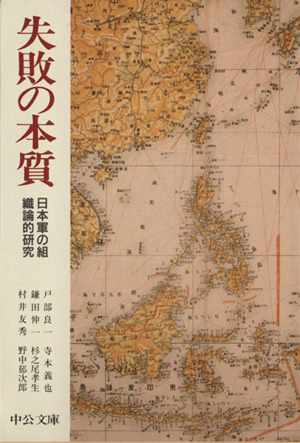失敗の本質 の商品レビュー
日本の組織がどのような欠点を持っているかが簡潔にまとまってる。戦争から60年たった今も、如何に日本社会が変わっていないかを改めて認識させられる一冊。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この書は、ミッドウェー戦やガダルカナル戦など大戦中の6つのケーススタディーを通して、日本軍の組織的な敗北に迫るものであるが、本書を通して、読者は奇妙な既視感に陥るだろう。「そうだ、あの頃と何も変わってはいないではないか」と。 読み進める毎に、吸い込まれつつも、極めて悲観的になってしまった。読後感として、全体に通じる日本軍の問題は今日の日本全体を覆う問題に直結する。日本軍の情緒的でまたプロセスを重視し、年功序列型の昇級から来る問題は、今日の日本企業の問題へ、戦闘において自立性を極度に制限させられた現場と集権的中央の関係は、今日の地方と中央の関係へ、また日本軍部エリート創出の教育過程における問題性は現在の日本教育の問題に通じている。組織的には結局、何ら変わらずにここまで来たのかと疑いたくなる…。 例えば、当時日本陸軍の戦略文化としてあった「短期決戦」による「必勝の信念」を疑わない姿勢は、それが万一失敗した場合のコンティンジェンシープランの作成を拒んだ。それを作るように進言する声に対して、それは「必勝の信念」を疑う事であり、消極的で士気を低下させる行為だと言う。ここにあるのは「神話」の絶対性で、それを疑う事を許さない文化だ。この事は、現在でも形を変えて生じているのだ。最近の問題として、原発行政に同様の問題があった。 本書で最も核心部は「大東亜戦争中一貫して日本軍は学習を怠った組織であった。」(p327)という「革新的組織」になるべく学習のあり方に関するものだろう。逆説的だが、日本軍は日清、日露戦争への適応を進めそれに特化してしまった結果、組織内に多様性を生み出す「緊張」や「変更」を望まない、極めて安定志向の組織のまま不確実性の高い戦争へ突入して行った事だ。 結果的に、現場からの声や作戦の失敗に対し得られた知識をフィードバッグし、既存の知識を否定し自己革新が出来ないシステムになり、同じ失敗を何度も繰り返して行った。この極度の特化から生じる問題は日本型の資本主義の欠点にもなるかもしれない… 20年以上前にかかれたが、全く古さを感じられないという事は、まさに『失敗の本質』という通り、日本の閉塞に普遍的に横たわる本質的な「何か」に焦点を当てているからだろう。近代戦について、本書は言う、「…概念を外国から取り入れること自体に問題があるわけではない。問題は、そうした概念を十分に咀嚼し、自らのものとするように努めなかったことであり、さらにそのなかから新しい概念の創造へ向かう方向性が欠けている点にある。」これは近代戦だけでなく、日本が「輸入」した近代国家を支える民主主義と資本主義の概念にも通じ、冷戦後の日本の長期停滞を招いている原因だと思う。 大震災以後緊急に、42刷として出版された本書の一読を勧める。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
"日本軍には本来の合理的組織となじまない特性があり、それが組織的欠陥となって、大東亜戦争での失敗を導いたと見ることができる。" ”日本軍の組織的特性は、その欠陥も含めて、戦後の日本の組織一般のなかにおおむね無批判のまま継承された。ということができるかもしれない”
Posted by
失敗の本質=硬直した体質。いまの政府。 20年前から読みたいと手を出していなかった。やっと読み終わった。
Posted by
副題が「日本軍の組織論的研究」となっていますが、本書は日本軍の失敗を通して日本型組織が抱える問題点を浮き彫りする試みだと理解しました。 歴史書として組織論の教科書としてはもちろん、企業文化論として等様々な読み方ができる名著だと思います。
Posted by
組織学の歴史的大作。大東亜戦争での6つの作戦の失敗を事例に、組織学的に分析しそこから現代の組織への学びとしようとするコンセプトが興味深い。前半は6つの作戦の失敗を事実を中心に淡々と説明し、後半は6つの失敗から旧日本軍の組織を総合的に分析する。前半は用語も難解で読むのを挫折しそうに...
組織学の歴史的大作。大東亜戦争での6つの作戦の失敗を事例に、組織学的に分析しそこから現代の組織への学びとしようとするコンセプトが興味深い。前半は6つの作戦の失敗を事実を中心に淡々と説明し、後半は6つの失敗から旧日本軍の組織を総合的に分析する。前半は用語も難解で読むのを挫折しそうになるが、後半の分析の納得感を高めるためには必要か。分析では米軍と比較していくが、「変化への適応」が個人的にはポイントだと解釈する。旧日本軍は組織的に完成されていたが、そこから自己革新することができなかったのだと。変化に適応できなかったのは、危機感の低さ、日本古来からの命の軽視、組織として統一されすぎた思想、あたりが原因か。古い本だが今読んでも十分に学びがあった(アウトプット勉強会の6月課題本)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
(日本軍の失敗の)コンセプト 日露戦争←⇒自己革新能力 本書の395頁に失敗の本質について直接的に述べている箇所がある。 「日本軍最大の失敗の本質は、特定の戦略原型に徹底的に適応しすぎて学習棄却ができず自己革新能力を失ってしまった、ということであった」(395頁)。 自己革新能力の喪失を引き起こす要因として本書では「空気」や士官学校での教育制度、人事システム、兵器体系などがあげられている。 「特定の戦略原型」とは陸軍の「白兵銃剣主義」、海軍の「艦隊決戦主義」のことである。そして、これらの戦略はどちらも日露戦争における勝利をモデルとして策定されたものである。 すなわち、「日露戦争の戦略を革新できなかったことが大東亜戦争における日本軍の失敗の本質」と言える。 戦略がどんなものであれ、自己革新能力がなければ環境に対応できずにいつかは負ける、という点で自己革新能力(の喪失)は失敗のパワーである。一方で、大東亜戦争での失敗は戦略を日露戦争モデル(白兵銃剣主義と艦隊決戦主義)に定めたことでより深刻なものとなったと考えられる。例えば白兵銃剣主義・艦隊決戦主義はどちらも短期決戦が前提になっているのに対して、アメリカ軍は長期決戦を前提とした戦略モデルを採用しており(338頁)、これが戦争が長期化するに従ってアメリカ軍に有利に働いた。もし、日本軍の戦略モデルが長期決戦を前提としたものであれば、戦果はまた違ったものになっていただろう。よって、その戦略モデルを採用する原因となった日露戦争をコントロールであると考えた。 本来なら、日本軍の失敗を一般化して現代社会の組織にあてはめることが必要だけど、時間がないので今日はここまで。余裕があれば追記する。
Posted by
歴史背景をある程度知らないと、読むのは結構ベビーかもしれない。 既に廃刊で新刊は売っておらずAmazonのマケプレで定価で売っていたが、ブックオフの半額コーナーに3軒回れば見つかるくらいなので、時間がある人はブックオフのはしごで手に入れると良いかも。
Posted by
図書館で借りました。 読み応えありすぎ 第二章だけでも良いかも。 現代の日本に通じることが一杯あると感じる。
Posted by
【目次】 はしがき 序章 日本軍の失敗からなにを学ぶか 本書のねらい 本書のアプローチと構成 一章 失敗の事例研究 1. ノモンハン事件──失敗の序曲 プロローグ 第一次ノモンハン事件 第二次ノモンハン事件 タムスク爆撃 ハルハ河渡河作戦 ...
【目次】 はしがき 序章 日本軍の失敗からなにを学ぶか 本書のねらい 本書のアプローチと構成 一章 失敗の事例研究 1. ノモンハン事件──失敗の序曲 プロローグ 第一次ノモンハン事件 第二次ノモンハン事件 タムスク爆撃 ハルハ河渡河作戦 砲兵戦 「事件処理要綱」 持久防禦 ソ連軍の八月攻勢 アナリシス 2. ミッドウェー作戦──海戦のターニング・ポイント プロローグ 作戦の目的とシナリオ 日本海軍の戦略思想 ミッドウェー作戦の目的とシナリオ 米海軍のシナリオ 海戦の経過 序幕──索敵の開始 第一機動部隊VS.ミッドウェー空港基地 南雲指令朝刊の意思決定 フレッチャーとスプルーアンスの意思決定 加賀、赤城、蒼竜の被弾 山口司令官の意思決定 閉幕──全空母喪失と作戦の中止 アナリシス 後知恵と錯誤 連合軍隊司令部の錯誤 第一機動部隊の錯誤 日本海軍の戦略・用兵思想 3. ガダルカナル作戦──陸戦のターニング・ポイント プロローグ 作戦の経過 一木支隊急行 第一回総攻撃 第二回総攻撃 撤退 アナリシス 戦略的グランド・デザインの欠如 攻勢終末点の逸脱 統合作戦の欠如 第一線部隊の自律性抑圧と情報フィードバックの欠如 4. インパール作戦──賭の失敗 プロローグ 作戦構想 東部インド進攻作戦構想 ビルマ情勢の変化 牟田口ののインド進攻構想 作戦計画決定の経緯 作戦目的および計画をめぐる対立 大本営の許可 作戦の準備と実施 鵯越戦法 作戦の準備 作戦の発動 作戦の実施と中止 アナリシス 5. レイテ海戦──自己認識の失敗 プロローグ 捷一号作戦計画の策定経過 サイパン島没落後 連合艦隊の捷号作戦要綱 マニラでの作戦打合わせ 捷号作戦計画策定後の状況推移 バダオ誤報事件とその余波 沖縄空襲 台湾沖航空戦 捷一号作戦の展開──レイテ海戦 捷一号作戦発動 レイテ湾突入計画 ブルネイ出撃 栗田軍隊「反転」 アナリシス 作戦目的・任務の錯誤 戦略的不適応 情報・通信システムの不備 高度の平凡性の欠如 6. 沖縄戦──終局段階での失敗 プロローグ 沖縄作戦の準備段階 第三二軍の創設 台北会議 第九師団の抽出と配備変更 第八四師団派遣の内示と中止 作戦の実施 沖縄作戦発動の航空作戦 米軍上陸 北・中飛行場喪失に対する反響 第三二軍事司令部の内部論争 アナリシス 二章 失敗の本質──戦略・組織における日本軍の失敗の分析 六つの作戦に共通する性格 戦略上の失敗の要因分析 あいまいな戦略目的 短期決戦の戦略志向 主観的で「帰納的」な戦略策定──空気の支配 狭くて進化のない戦略オプション アンバランスな選抜技術体系 組織上の失敗要因分析 人的ネットワーク偏重の組織構造 属人的な組織の統合 学習を軽視した組織 プロセスや動機を重視した評価 要約 三章 失敗の教訓──日本軍の失敗の本質と今日的課題 軍事組織の環境適応 日本軍の環境適応 戦略・戦術 資源 組織特性 組織学習 組織文化 自己革新組織の原則と日本軍の失敗 不均衡の創造 自律性の確保 創造的破壊による突出 異端・偶然との共存 知識の淘汰と蓄積 統合的価値の共有 日本軍の失敗の本質とその連続性 戦略について 組織について 参考文献 文語版あとがき 大東亜戦争関係図 *****
Posted by