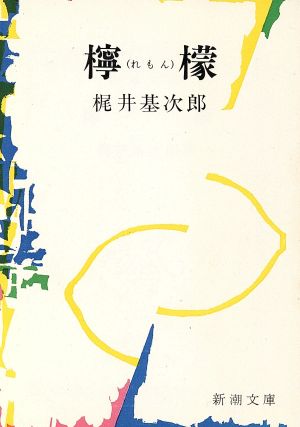檸檬 の商品レビュー
「檸檬」をはじめとする作品20編を収録した短編集。比較的読みやすく、印象に残るようなフレーズもあり、良かった。表題作である「檸檬」はストーリーとしては希薄だが、想像力に富んでいて、表現が面白かった。「檸檬」と「桜の樹の下には」「のんきな患者」が印象強く、桜の樹の下には屍体が埋まっ...
「檸檬」をはじめとする作品20編を収録した短編集。比較的読みやすく、印象に残るようなフレーズもあり、良かった。表題作である「檸檬」はストーリーとしては希薄だが、想像力に富んでいて、表現が面白かった。「檸檬」と「桜の樹の下には」「のんきな患者」が印象強く、桜の樹の下には屍体が埋まっている!というフレーズが面白く、またのんきな患者は作者自身と重ねたのかなと考えると趣きを感じた。
Posted by
短編集だったからサクサク読み終わるかと思っていたけどなかなか進まなかった 理由はわかっています ん?どういうこと? と思うことが多かったから 何回同じところを読んだことか そういう人達ばかりではないのは知っているけれど、どうしてこう昔の文豪たちは苦労人が多いのだろう
Posted by
表題作の「檸檬」は馴染み深いけれど、個人的には「桜の樹の下には」がぶっ飛んでいて好きかもしれない。他にも、「冬の蝿」「愛撫」などの描写が想像がしやすくて楽しめた。梶井基次郎短編集を読むのは2度目だけれど、まだ理解しきれない自分なので表現をじっくり味わえるように年を重ねていきたい。
Posted by
自分には読みづらく読み終わるのに時間がかかった。ただ何気ない日常を文学的に、何でもないものをここまで言語化して描写する表現力は素晴らしいと思った。 個人的に好きなのはKの昇天とある崖上の感情。どちらも自分的には読みやすく、登場人物の感情もストンと理解できた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
檸檬しか読んでないが、いつでもどこでも読める分量と、いつものインパクトを与えてくれる。個人の深いところに焦点が当てられ、だれしも一度は考えたことのある、個人的な思惑を代表するようなワンシーンだった。
Posted by
短編集。20編収録。 とても細やかな心理描写、特に「不安」に関する表現が素晴らしく、ここまで自分が感じる不安をうまく表現した作品はこれまでに読んだことがないと思った。 何気ない毎日の中で頭の中に閃く思念を一つ一つ丁寧に掬い上げたような作品だった。
Posted by
梶井基次郎の短編集。 著者の肺病や実生活によるものだろうか、陰鬱で退廃的な話が多かった。夜や闇に対する恐れ、肉体と影の分離、などいくつかのモチーフは複数の話で登場しており、著者の抱える悩みが伝わってくる。 表題作の檸檬は、主人公の行動だけ改めて振り返ると意味がわからないが、心情描...
梶井基次郎の短編集。 著者の肺病や実生活によるものだろうか、陰鬱で退廃的な話が多かった。夜や闇に対する恐れ、肉体と影の分離、などいくつかのモチーフは複数の話で登場しており、著者の抱える悩みが伝わってくる。 表題作の檸檬は、主人公の行動だけ改めて振り返ると意味がわからないが、心情描写を踏まえると何故か納得してしまった。古い時代の作品のため文章表現は難解な部分は多いがそれを超える説得力がある。
Posted by
ミステリアスな雰囲気、鮮やかさ、繊細な美しさを持つ魅力的な一冊。読みながら日本の原風景が連想され穏やかな気持ちになった。
Posted by
二回読む。梶井の作品は二回以上読むべきなのだろう。 初回の感想は「難しい」。 決して、日本語としては難しくない。 何が難しいのか、考えてみた。 日本人は英語で聞き取れない音域が多くあるという。これは言葉を耳から学ばないから。(子供、例えば帰国子女は耳から言葉を覚えるので、この音...
二回読む。梶井の作品は二回以上読むべきなのだろう。 初回の感想は「難しい」。 決して、日本語としては難しくない。 何が難しいのか、考えてみた。 日本人は英語で聞き取れない音域が多くあるという。これは言葉を耳から学ばないから。(子供、例えば帰国子女は耳から言葉を覚えるので、この音域を聞き取ることができる) そして聞き取れないと発音ができない、ということらしい。これが日本人が英語を話すことが苦手な理由の一つ。 このことを思い出した。 つまり、我々が身近に感じることを、梶井は、その想像を超える言葉で表現しているのだ。 だから難しい。 初めて読んだ時に梶井の表現する風景が頭に浮かべることができない。 詰まり、これが「難しい」理由なのだが、2回目には、梶井らしさに慣れ、そしてその文体、表現力に惹きこまれていく。 言い換えれば、梶井は、できごと、風景を極めてユニークな形で言葉に落とす能力に傑出している、ということだと思う。 それは、自ら体調を崩し、常に死と向き合ってる状況の中で、内面を鋭く見つめているということ、そして、それを表現し、伝えようとする強烈な意思、意欲がそうさせるのだと思う。 どの作品でも、自分を蔑むことなく、悲しみに暮れることでもなく、宗教のように何かにすがることでもない。 私小説なのだろうが、どこか自分を客観的に、冷静に見つめているところがある。 そのような姿勢が文章を研ぎ澄ませることにつながるのだろうか。
Posted by
最初は詩的な表現に「苦手かも…?」と思いましたが、読むうちに印象は変わってきました。ここまで心情をありありと、こんなふうに表現できるとは。暗い、辛い、やるせないを美化するのではなく、直視しながら生への渇望を見出せるところは、他の退廃的小説と一線を画す作品として読めました。
Posted by