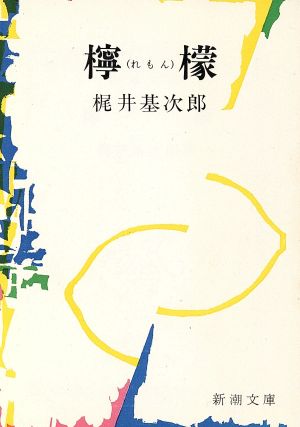檸檬 の商品レビュー
僕にはまだ早かったか、面白くないというより文章が頭に入ってこなかった。どこがそこまで評価されているのかいまいちわからない。 時間を置いてまた挑戦してみようかな
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1925年発売、梶井基次郎の短編小説。『檸檬』は梶井の代表的作品で本書に集録されている14篇のうちの1つの作品。 『檸檬』 主人公は得体の知れない不吉な塊に心をおさえつけられている。彼はお金がないが、美しいものが好きだ。時間はたっぷりあるので街をぶらぶら散歩しながら美しいものを見てまわる。花火、おはじき、香水壜、煙管、小刀等々。 いつもと変わらない八百屋で珍しく檸檬が並んでいた。檸檬の味ではなくその存在が好きな彼は1つ買っていく。握りながら歩いているといつも心をおさえつけている不吉なものがいくらか緩んだ気がした。「檸檬1つで不思議なもんだ」と彼は思った。檸檬を何度も鼻に持っていっては嗅いでみるとカリフォルニアが思い浮かんだ。そして深々と胸いっぱいに空気を吸い込むとなんだか身体の内側から元気が出てきた。彼は昔の詩人の事など考えながら一種誇らかな気持ちを感じながら歩けた。幸福だった。 どこをどう歩いたのだろう、最後に立ったのは彼の好きな丸善だった。「今日はひとつ入ってみてやろう」とずかずか入ると、だんだんと幸福な感情が逃げていった。好きな壜も煙管を見ても憂鬱が立て込めてくる。彼は画集の棚の前に行き、重たい本を抜き出し開いてみるのだが、さらにめくっていく気にならない。そして棚に戻し違う画集をパラパラとやっていくのだ。しまいには大好きなアングルの橙色の重い本も持てなくなり、憂鬱になってしまった。 「あっ、そうだ」と彼は檸檬を握った。するとまた軽やかな興奮が帰ってきた。彼は手当たり次第に画集を積み上げ、ときおり檸檬を握り、また積み上げた。赤や青の奇怪な幻想的な城ができ、躍り上がる心を制しながらその城の頂に檸檬を据えつけた。その檸檬の色彩はガチャガチャした色の階調を吸収しカーンと冴えかえっていた。檸檬の周囲だけ変に緊張しているような気がした。彼はしばらくそれを眺め、それをそのままにして何食わぬ顔をして外に出た。丸善の棚へ黄金に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けた悪漢となり、あの美術の棚を大爆発させたらどんなに面白いだろうと想像しながら京極の街を下って行った。 ———————— ちょうど100年前、京極に丸善デパートがあったということや、今とは違う当時おしゃれだったものが知れて面白かったです。そして100年前も今も人の心は変わらないのだと思いました。 抑圧された心や、純粋さとその裏側の見栄、“画集を一度パラパラとめくらなければいけない”という彼の呪い、画集の上に檸檬を載せて帰るという奇怪な行動。主人公の繊細さや心のあやういバランス。私にはそのような呪いはなく変な行動もしませんが、なぜ彼がそのようなことをするのかはよくわかります。 ————————
Posted by
写生文好きな私としてはめちゃくちゃ好きな本です。 他愛ない日常の風景の中に作者ならではの発見や見方、作者(登場人物)の心情が細やかな描写で表されているので心に程よく染み込んできます。 読んでいて作者の孤独感が猛烈に伝わってきますが共感でき、それは誰しもが経験できる孤独なのかなと感...
写生文好きな私としてはめちゃくちゃ好きな本です。 他愛ない日常の風景の中に作者ならではの発見や見方、作者(登場人物)の心情が細やかな描写で表されているので心に程よく染み込んできます。 読んでいて作者の孤独感が猛烈に伝わってきますが共感でき、それは誰しもが経験できる孤独なのかなと感じました。 てかなんでこんなにも共感できる感覚を言葉で表現できるのか!!!!本当に驚愕です。すごすぎます。 じっくり何度でも読み返しさらに味わい深く、また新たな楽しみを得られる宝物のような本です。 特に「路上」「器楽的幻覚」「冬の日」「冬の蝿」が好きです。
Posted by
新潮文庫の100冊 2024を読もうと入手した。 (2024.12.18) ※2024.12.8古本をネットオフに注文、12.13到着 新潮文庫の100冊 2024:7冊目 2024.12.27読書開始
Posted by
※主に『檸檬』『冬の蠅』についての感想です 物語を追うというより、その美しい言語表現を目で追って、好きなフレーズはあるかなぁと探しながら読みました。 意外にも共感出来ることが多くあり、今まで好きだったものがある日を境に距離を置きたくなるものになったり、粗末でどこにでもあるような...
※主に『檸檬』『冬の蠅』についての感想です 物語を追うというより、その美しい言語表現を目で追って、好きなフレーズはあるかなぁと探しながら読みました。 意外にも共感出来ることが多くあり、今まで好きだったものがある日を境に距離を置きたくなるものになったり、粗末でどこにでもあるようなものに惹かれるようになったり、幸せな時間が来たとき、その後に訪れるであろう苦痛の時間を想像して憂鬱になったり、「分かるなぁ」という気持ちになった場面が多くありました。 あと、作品全体を貫くどこかひょうきんで明るい雰囲気が好きでした(病気は辛かったと思うけど) 檸檬、冬の蠅は読書初心者でも読みやすいかも?(なにを隠そう私がそうだったので…)
Posted by
あれ?小説なのに内容が頭に入ってこないしページも進まない... たまらず途中で他のレビューを読んだら、やはりみなさん「難しい」「読みづらい」の感想が。 情景の描写がこれでもかと言うほど細かい。いつもみたいにぱーっと読んでいると追えなくなって、気づいたら他のこと考えてた...の繰...
あれ?小説なのに内容が頭に入ってこないしページも進まない... たまらず途中で他のレビューを読んだら、やはりみなさん「難しい」「読みづらい」の感想が。 情景の描写がこれでもかと言うほど細かい。いつもみたいにぱーっと読んでいると追えなくなって、気づいたら他のこと考えてた...の繰り返し。 がんばって集中すると、情景がふんわり浮かび上がってくる感覚はある。 最近本を読むのもスピード重視になっていたのを反省した読書体験でした。
Posted by
梶井の文は難しいようで、生々しく共感しやすいところが面白いと思います。 私は檸檬、桜の樹の下には、ある崖上の感情が特に好きだったのですが、愛撫の出だしを読んだ瞬間なんて奴なんだと1度本を閉じました。梶井の頭の中は色んな意味で凄いのだと再実感。 とても楽しく読ませていただきました。
Posted by
好きな話は冬の蝿(闇の絵巻)、冬の日、Kの昇天、泥濘 収録の中で異彩を放っていたのは、 城のある町にて(巻末の解説にあるとおり、単純で、平明で、健康な世界) ある崖上の感情(不安定さは感じない。感情の発露?) 愛撫(変態的だけど猫への愛情を感じる) 病のせいか、常に死を身近に感...
好きな話は冬の蝿(闇の絵巻)、冬の日、Kの昇天、泥濘 収録の中で異彩を放っていたのは、 城のある町にて(巻末の解説にあるとおり、単純で、平明で、健康な世界) ある崖上の感情(不安定さは感じない。感情の発露?) 愛撫(変態的だけど猫への愛情を感じる) 病のせいか、常に死を身近に感じているように読めました。 常に精神不調で絶望しているけど、世の中の一般的な幸せや娯楽、喜びを分かっている。分かっているからこそ対になっている絶望が深い。 人並みの幸せを求めつつも、幸せを意識すると途端に苦しみが増す矛盾に苦しんでいる様子と、その状況を楽しんでいるようにも思えました。 のんきな患者で、梶井の本音が書かれているように思います。 自分の体のために他人に何か頼むことへの遠慮。 孤独な夜の時間への恐怖・不安。 いたたまれなさ。 寂しさを纏いながらも、自然や生き物を表現する時に使われる言葉の美しさには、作者の非凡を感じずにいられませんでした。
Posted by
一つ一つの情景や事柄に対しての説明が綺麗で細かい。 だからこそ自分の語彙力の無さ、感受性の無さが原因なんだろうけど、非常に難しい。 一回では全てを理解できないので、いつか再読する時が来たらもう少し作品に近づく事ができるんだろうか。
Posted by
苦労を重ね(原因が身体にあるにしても)参ってしまった人間の、暗いモヤモヤした日常を正確に描いている。 不思議と負の感情は少なく、小さなことに幸福や安心を見出したり、また暗闇に落ち着いたりする。 精神的に病んだ経験がある人ほど共感を得やすいかもしれない。 多くの人が漠然と持ってい...
苦労を重ね(原因が身体にあるにしても)参ってしまった人間の、暗いモヤモヤした日常を正確に描いている。 不思議と負の感情は少なく、小さなことに幸福や安心を見出したり、また暗闇に落ち着いたりする。 精神的に病んだ経験がある人ほど共感を得やすいかもしれない。 多くの人が漠然と持っていたりする、あまりに抽象的な感覚が日本語でハッキリと表現されていてハッとする。 このような精神状態を文学として言葉にして表現された例はあるのかないのか知らないが、ここまでリアルな感覚は他にないのだろう。 非常に独特の読後感。 梶井基次郎の世界観に飲まれて脱力する。 現代の忙しさから逆行する感覚がある。 唯一無二であることが素晴らしいのであるならば、梶井基次郎の短編集は日本文学の頂点のうちのひとつ言えるかもしれない。 個人的には非常に好みの作品で、作者の心情を汲み取りながら、限りなくゆっくり読むほうが楽しめると思う。
Posted by