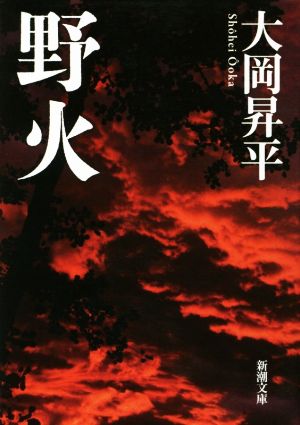野火 の商品レビュー
私は道徳的に生きてきたと思っていた。しかし、それは、たまたま道徳に反する必要がなかっただけだ。人生の分かれ道はたくさんある。その選択の数だけ人生はある。それが必然なのか偶然なのかわからない。ただ、この小説を読むと、私の人生や価値観は偶然でしかないように思われる。
Posted by
モラルとか良心とか、普通の暮らしを成り立たせている観念は実はとっても脆いものなんだなとしみじみ思った。死が身近な環境だと、共同体や他者との関係なんてないようなもの。
Posted by
19歳くらいの時に読んだ時は、カニバリズムに興味津々で人肉を食うなんて一体どんな話!?という感じでストーリーは頭に入ってこなかった。 しかし10年が経ち、再び読むと、この本はそれを伝えたいのではないのだと分かった。 単に人肉を食うその衝撃さを伝えるというよりも、飢えに苦しんだ末...
19歳くらいの時に読んだ時は、カニバリズムに興味津々で人肉を食うなんて一体どんな話!?という感じでストーリーは頭に入ってこなかった。 しかし10年が経ち、再び読むと、この本はそれを伝えたいのではないのだと分かった。 単に人肉を食うその衝撃さを伝えるというよりも、飢えに苦しんだ末に人肉に手を出すか否かという人間の極限状態にスポットを当てた作品である、といまは考察している。 キリスト教の影響を受けた考え方なのか分からないが、1度は食べようとした味方兵の死んだ肉体。彼は死ぬ前、俺が死んだら食べてもいいよと右足を指していた。 主人公は、山蛭が彼に吸い付き吸い込んだ血を、 山蛭を介して吸い込む。人間の血であるが、直接でなければ問題ないと考えたのだ。 そして、結局主人公は飢餓の極限状態に陥ったとき、味方兵から与えられた干し肉 を食らう。 猿と言われていたそれは、実は滅んだ兵士の肉だった。 葛藤があれと、この主人公は自らは決して人肉を食べようとしなかったが、他人から与えられたものは素直に口にしてしまうんだなと。飢えとはそういうもの、正常な考えを麻痺させてしまう危険なものなのだと、感じた。
Posted by
戦争風景の叙述と、哲学的死生観が混ざるが、死生観は難しい。悟りか諦めか暁光か。 繰り返しの日常と、死へ向かう前進が対になるということはわかった。 戦争が原因であり運命であった殺人と、人肉を食べないという主体的選択の差。そう思わないとやってられない窮地のロジックと言うのはあまりに外...
戦争風景の叙述と、哲学的死生観が混ざるが、死生観は難しい。悟りか諦めか暁光か。 繰り返しの日常と、死へ向かう前進が対になるということはわかった。 戦争が原因であり運命であった殺人と、人肉を食べないという主体的選択の差。そう思わないとやってられない窮地のロジックと言うのはあまりに外側から見ているからか。解説が難しすぎて… 戦争を論ずるときに、為政者や市民を話題にすることは多いが、敗残の一兵卒を見ることも感じ入ることは多いと思う。 死ぬまでの時間を思うままに過ごすことができるという無意味な自由だけが私の所有であった
Posted by
娘の学校で推薦図書の一冊になっていた本であるが、あまりに重い。戦争は本当に過酷だ。極度の飢えに襲われた時に、自分や周りの人間がどういうことになるか、あまりに恐ろしい。戦争文学とはどういうものかがわかる一冊である。
Posted by
「生命感というのは、いま行うことを無限に繰り返す予感」というフレーズが非常に印象に残った。 自分が間もなく死にゆく身だと悟ったとき、日常の光景や世界はどう見えるのだろうか。
Posted by
太平洋戦争末期、敗戦色濃いフィリピン戦線。主人公田村は、結核を患い、所属している部隊から追われて、野戦病院へ向かう。そこでも、食糧・医療品不足から拒絶され、わずかな食糧と共にフィリピンの原野を彷徨う。 極度の飢え、野火の広がる原野。怪我や病気で、死んでいく同胞。その極限の中、感じ...
太平洋戦争末期、敗戦色濃いフィリピン戦線。主人公田村は、結核を患い、所属している部隊から追われて、野戦病院へ向かう。そこでも、食糧・医療品不足から拒絶され、わずかな食糧と共にフィリピンの原野を彷徨う。 極度の飢え、野火の広がる原野。怪我や病気で、死んでいく同胞。その極限の中、感じる神の存在。 彼らは、既に、何と戦っているかなど考えられない。空腹を満たすため、最後の一線、人肉を口にするか否かという、人としての存在と戦う。 なかなか全てを理解できない。再読して、思いの外、フィリピンの原野の表現が鮮明で戦地での逃亡であるけれど、何処か行人の様だった。この作品は、反戦の言葉や本格的な戦闘場面があるのではなく、一人の普通の兵士の異常な戦地体験を俯瞰的に描き戦争の愚かさを静かに語る。 私の手元に、皇紀2603年 昭和18年の日記がある。大日本青少年團編。戦死した母親の兄の遺品。 私が生まれる前に亡くなった叔父。フィリピン上陸直後、戦死したらしい。母親もまだ小さく記憶が曖昧な所があった。 18歳くらいの、招集令状が来た年の日記で、癖字で筆記用具が悪く、まだ全部は読み切れていない。 これから、少しずつです。
Posted by
大岡昇平氏(1909-1988)のフィッリピン・レイテ島での戦争体験をもとに、死を直前にした敗残兵(田村一等兵)の死の彷徨をとおして、人間の極致の心情を描いた戦争文学。 野火の燃えひろがる原野を、極度の飢えに襲われながら友軍の死体に目を向ける〝私は道端に見出す死体の一つの特徴に注...
大岡昇平氏(1909-1988)のフィッリピン・レイテ島での戦争体験をもとに、死を直前にした敗残兵(田村一等兵)の死の彷徨をとおして、人間の極致の心情を描いた戦争文学。 野火の燃えひろがる原野を、極度の飢えに襲われながら友軍の死体に目を向ける〝私は道端に見出す死体の一つの特徴に注意していた。海岸の村で見た死体のように、臀肉を失っていることである。誰が死体の肉を取ったのであろう・・・あまり硬直の進んでいない死体を見て、その肉を食べたいと思った〟・・・武田泰淳氏の『ひかりごけ』を連想させる気魄に満ちた小説。
Posted by
「大岡昇平」が自らの戦争体験を基にした戦争小説『野火(のび)』を読みました。 この季節になると太平洋戦争に関する作品を読みたくなります… 忘れてはいけない歴史ですもんね。 -----story------------- 敗北が決定的となったフィリッピン戦線で結核に冒され、わず...
「大岡昇平」が自らの戦争体験を基にした戦争小説『野火(のび)』を読みました。 この季節になると太平洋戦争に関する作品を読みたくなります… 忘れてはいけない歴史ですもんね。 -----story------------- 敗北が決定的となったフィリッピン戦線で結核に冒され、わずか数本の芋を渡されて本隊を追放された「田村一等兵」。 野火の燃えひろがる原野を彷徨う「田村」は、極度の飢えに襲われ、自分の血を吸った蛭まで食べたあげく、友軍の屍体に目を向ける……。 平凡な一人の中年男の異常な戦争体験をもとにして、彼がなぜ人肉嗜食に踏み切れなかったかをたどる戦争文学の代表的名作である。 ----------------------- 太平洋戦争末期の日本の劣勢が固まりつつある中のフィリピン戦線… 陸軍一等兵の「田村」は肺病のために部隊を追われ、野戦病院からは食糧不足のために入院を拒否される、、、 現地のフィリピン人は既に日本軍を抗戦相手と見なすという状況下、米軍の砲撃によって陣地は崩壊し、全ての他者から排せられた「田村」は熱帯の山野へと飢えの迷走を始める… 律しがたい生への執着と絶対的な孤独の中で、「田村」にはかつて棄てた神への関心が再び芽生える。 しかし彼の目の当たりにする、自己の孤独、殺人、人肉食への欲求、そして同胞を狩って生き延びようとするかつての戦友達という現実は、ことごとく彼の望みを絶ち切る… ついに「この世は神の怒りの跡にすぎない」と断じることに追い込まれた「田村」は「狂人」と化していく。 著者のフィリピンでの戦争体験に基づいており、死を目の前に感じた人間の極限状態やカニバリズムを描いた作品… ひと言、ひと言が重くて、心にずしずしと響いてくる内容でしたね、、、 自分が「田村」の立場だったら、どんな判断をして、どんな行動をしたんだろうか… 考えてみるんだけど、答えが出てこない… 平和な日本で暮らしているとリアルに想像できない究極の情況ですが、考えることや想像することを諦めたくなくて、いつも以上に頭を使いながら読んだ作品でした。
Posted by
第二次世界大戦、フィリピンのレイテ島で敗走する日本兵をモデルにした大岡昇平の小説。 地元民を不用意に殺したことよりも、人肉食の方に忌避を感じているが、それが正当なことであるのかが自分にとってこの小説のテーマになっている。すでに亡くなった人の肉体をいまだ生命があり生き延びる可能性...
第二次世界大戦、フィリピンのレイテ島で敗走する日本兵をモデルにした大岡昇平の小説。 地元民を不用意に殺したことよりも、人肉食の方に忌避を感じているが、それが正当なことであるのかが自分にとってこの小説のテーマになっている。すでに亡くなった人の肉体をいまだ生命があり生き延びる可能性がある人間が食するのはそれほど忌避すべきことなのかとも思う。一方で、過酷で今すぐにでも命を落とす戦地において生命よりもあるのかもしれない人間としての尊厳の方を大事にするということはリアリティがあることなのかもしれない。 教会の描写など、ところどころにキリスト教の影が入る。死後に自分の肉を食してよいと言った将校の肉を削ろうとする右手を左手が制するところは見所だが、そのことをどう解釈すべきだろうか。何がそれを押しとどめたと考えることをこの小説は求めているように感じる。「良心」という言葉で済ますものではないだろう。そうまでして生き延びたいと思っていいのか、という躊躇いでもあったのかもしれない。
Posted by