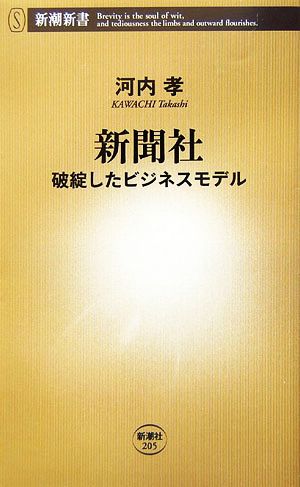新聞社 の商品レビュー
個別配送ができることが最大の強みというのは確かにと 思うが、テレビですら広告価値を認めにくくなっている 世の中で、どのように事業拡大の道筋を作っていくのだろう。 活字離れと言われて久しいが、別にそのために新聞を 読まなくなっているわけではなく、ネットでは無料でニュースを 読める...
個別配送ができることが最大の強みというのは確かにと 思うが、テレビですら広告価値を認めにくくなっている 世の中で、どのように事業拡大の道筋を作っていくのだろう。 活字離れと言われて久しいが、別にそのために新聞を 読まなくなっているわけではなく、ネットでは無料でニュースを 読めるし、テレビでは元々無料で垂れ流している状況。 如何に買ってもらえる新聞を作るか?読み手の視点に 立って考え直す必要がある。 iPadブームにより、新聞のあり方はもう一度大きく変革すると 思われるが、個別配送を強みとするのであれば、本当に その価値を活かす企画を考え出す必要があるでしょう。 夕刊はもちろん不要だけど、欲しい情報をタイムリーに 届けてくれるのであれば、ニーズはあるはず。 コストセービングしたいという気持ちが強まっている 世の中で、価格コンシャスな人の気持ちを動かす サービスを提供されることを期待します。 今のままでは新聞社は絶対に生き残れないでしょう。
Posted by
副題にある通り、新聞社のビジネスモデルが破綻していることが明らかにされている。 新聞社の現状は、販売店に多量の部数を押しつけ、その無駄な部分を新聞社自身が払っているマッチポンプ的状態。 無駄が無駄を呼び、それが新聞自体の質の低下につながっている。 毎日新聞の経営陣として在...
副題にある通り、新聞社のビジネスモデルが破綻していることが明らかにされている。 新聞社の現状は、販売店に多量の部数を押しつけ、その無駄な部分を新聞社自身が払っているマッチポンプ的状態。 無駄が無駄を呼び、それが新聞自体の質の低下につながっている。 毎日新聞の経営陣として在職した著者は、新聞業界への不安を期待を込めてこの著書を出版したのだということがよくわかる。 ダークなマスコミ業界の一端がうかがえる。
Posted by
日本にとって産業での一番の危機は人口減少。 食べる人の数も減る。 新聞販売の拡張団という暴力団紛いのような組織があるそうだ。恐ろしい。 携帯電話の普及に伴って、毎月の費用を新聞から携帯に替えてしまうらしい。 新聞なんて恐ろしく読まない。まして毎日新聞なんて一番読まないよ。 毎日新...
日本にとって産業での一番の危機は人口減少。 食べる人の数も減る。 新聞販売の拡張団という暴力団紛いのような組織があるそうだ。恐ろしい。 携帯電話の普及に伴って、毎月の費用を新聞から携帯に替えてしまうらしい。 新聞なんて恐ろしく読まない。まして毎日新聞なんて一番読まないよ。 毎日新聞はポータル戦争でもヤフーに負けている。 日本の新聞が高いのは毎日家まで配達してくれるから。
Posted by
内容のよーやく 日本の新聞業界は衰退に向かっている。理由としては大きく二つある。一つ目に、新聞社は産業的な危機に陥っていることである。専売配達網・個別配達の維持のために新聞は総売上に対する販売経費率は45%を超えるなど異常な販売コストを抱えており、相当な高コスト体質となっている...
内容のよーやく 日本の新聞業界は衰退に向かっている。理由としては大きく二つある。一つ目に、新聞社は産業的な危機に陥っていることである。専売配達網・個別配達の維持のために新聞は総売上に対する販売経費率は45%を超えるなど異常な販売コストを抱えており、相当な高コスト体質となっている。現代は人口減、読まない層の増加、閲読時間の減少、インターネットの出現による広告費の減少などによりこの高コスト体質は維持できなくなってしまった。しかし新聞社の経営陣は環境の変化に対応できず、昔ながらの経営方法を取っており、抜本的な解決策を打ち出せないでいる。さらに近いうちに、実行されるだろう消費税率引き上げ、公正取引委員会による新聞の再販制度とそれに伴う特殊指定の見直しが新聞産業の危機に追い打ちをかけている。 二つ目に、読者から新聞が離れていこうとしていることである。新聞社はこれまで定価の根拠となる制作原価、人件費、流通経費などの経営情報を読者に開示してこなかった。また部数至上主義のため、悪質な拡張などの乱売が行われた。さらには、国民の知らないところで言論の寡占化が進む。具体的には、テレビがNHKと民放5系列化し、大新聞と民放キー局が一体化した。これでは民主主義的で多様な議論はできず、相互批判監視しメディアの質を高めていく機能は失われてしまった。つまり新聞が読者から離れたのである。 そしてこのような新聞業界を再生させるための著者の意見はこうである。まず、二大紙に対抗できる第三極を作る。次に生産、流通の全工程にある非効率・非合理性をなくす。その後、業界の正常化にある程度成功した後に産業体質の根本的な改革を行うというものだ。 これらを述べた後にIT社会との付き合い方を述べている。 かーんそう 多くの新聞産業に関する議論はこの本を元にしている。本書の社会的な影響は大きい。 政策提言は新聞業界全体の再生ではなく、結局は大新聞社のみの生き残りである気がする。言論の多様性を強調しているのだから大新聞社以外も生き残る道を模索すべきなのではないか。様々なデータから新聞という産業を捉えており、主張の一つ一つに説得力があった。説得力があるからこそ、新聞の生き残りはかなりきついもののように思えた。新聞社は経営から紙面内容から抜本的な改変を迫られていることには間違いない。経営陣は早く現実から目をそらさずに現実と向き合い、保守的な考えを捨てなければ、新聞に未来なんてない。新聞論に関するグラスルーツ的な本。
Posted by
2年くらい前にマスコミを目指していた頃に買った本。 今ではマスコミ志望じゃないけど・・・とても良い本でした・・・
Posted by
20071205 毎日新聞の元常務の書いた、新聞社のビジネスモデルに警鐘を鳴らす本。 販売店と押し紙の話は書いてある。 まあ、広告代理店絡みの黒い話はかかれてませんが。 ジャーナリズム批判やネットの話はあまり触れられていません。 記者上がりはヤバイとは書かれていますが。
Posted by
社会の実態を報道し批評する立場にあるはずの新聞社の経営体質の古さ、 そのことによって生じている様々な問題について書かれた本。 発行部数と実売部数の差(残紙による水増し) テレビ局の系列化による報道機関の寡占化 業界にとって都合の悪い事実は一切報道しない体質 等々 4章は毎日新...
社会の実態を報道し批評する立場にあるはずの新聞社の経営体質の古さ、 そのことによって生じている様々な問題について書かれた本。 発行部数と実売部数の差(残紙による水増し) テレビ局の系列化による報道機関の寡占化 業界にとって都合の悪い事実は一切報道しない体質 等々 4章は毎日新聞の問題にフォーカスしすぎており、あまり必要ないかも ここからはあくまでも私見であるが、 これらの問題の根底にあるのは、 記者クラブや再販制度といった既存新聞社の権益を守る制度であり、 政治の側も新聞業界の問題にはメスを入れてこれなかった現状が垣間見える。 (再販制度に関しては以前問題になったことがあるが、 各社が一斉に反発してお蔵入りになっているようである) 政治家にしてもこの問題を取り上げて、 ほぼ全ての新聞で一斉に批判されたらたまったもんではないから、 新聞業界の既得権益が維持されてきたのもある意味では当然であるとも言えるのだが。 でも、毎日新聞の取締役をやってる人が、こんな本を書くという現状を見ると、 かなり追い込まれた状況であるようなので、 今後大きな動きが起こってくるかもしれない。
Posted by
新聞ビジネスとテレビメディアの関係はよく分かった。 ただ後半の4章以降における業界再編案(毎日、産経、中日合併案)を披露する辺りは興ざめ。 そのような案は青写真として個人の頭の中に収めている分にはいいが、このように関係者の意向も無視して勝手に披露されると、かなりの反感を買うのでは...
新聞ビジネスとテレビメディアの関係はよく分かった。 ただ後半の4章以降における業界再編案(毎日、産経、中日合併案)を披露する辺りは興ざめ。 そのような案は青写真として個人の頭の中に収めている分にはいいが、このように関係者の意向も無視して勝手に披露されると、かなりの反感を買うのではないか。まるで独裁者のような皮算用である。 だから毎日新聞社内の改革もうまくいかなかったのではないか。 ちょっと興ざめ。
Posted by
元毎日新聞常務。説得力あり。ニュースの需要はあるわけだから、プラットフォームをどう再構築するか、、、。
Posted by
新聞社はもう終わってるのだな、もう破綻してるのだな、ということがよくわかる。それは新聞社だけじゃない。出版社だって同じ…。印刷・紙媒体はいったいこれからどうなる、どうする。この業界に飛び込んだばかりで、これからも生きていこうと思っているわたしも一体どうする。
Posted by