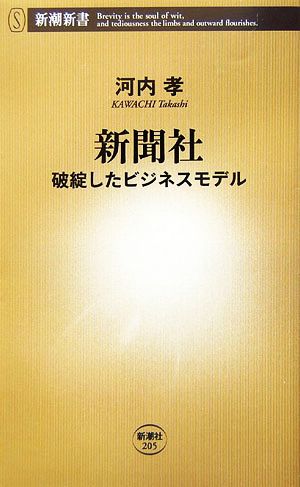新聞社 の商品レビュー
著者は元毎日新聞の常務である。本書を読むと新聞社も綺麗事をいっても所詮ビジネスという事がわかる。決して公正ではないし欠点も多いのだが、民主主義のためにはなくてはならない。読者としては割り切って活用する事が求められるであろう。もちろん単なる内幕ものとしても十分に楽しめる本である。
Posted by
何のかんのとまとまった時間が取れず読むのに結構時間がかかってしまいました。読み終わりました。 新聞、と言う情報媒体の現状と生き残り策の提示が具体的に説かれています。自分は父の仕事が新聞社と言う事もあり、同年代の人よりは新聞に関心があるほうだと思うのですが知らない事だらけでびっ...
何のかんのとまとまった時間が取れず読むのに結構時間がかかってしまいました。読み終わりました。 新聞、と言う情報媒体の現状と生き残り策の提示が具体的に説かれています。自分は父の仕事が新聞社と言う事もあり、同年代の人よりは新聞に関心があるほうだと思うのですが知らない事だらけでびっくりです。ただ確かに今の時代欲しい情報はネットですぐに検索でき、テレビをつければ最新ニュースは報道されている中で新聞が果たす役割とはなんだろうな、と思ったことはあります。 大学時代、アメリカの教授が講義の中で新聞を取る人は既にニュースはテレビ・ラジオでそのニュース概要を把握している。それでも新聞を読むのは活字として認識することによってそのニュースが事実であることを再確認するのだ、と言うようなことを言っていました。その時はああ、そうだな、テレビのニュースはまだ100%の信頼度を得ていないのかな、と納得したのですが。それから10年。時代は変わりました。今の時代、活字で読むニュースもテレビもネットも信頼度はさほど変わらないと思うのです。実際問題、自分の友人も新聞取っている人ってどれくらいいるのかな?正直自分も一人暮らしで新聞を取るか?と言われたら考えてしまいますし。(実際新聞を読む時間が無い。電車通勤なら違うのかもしれませんが車通勤だとちょっと無理。新聞読むために早起きするのは…)それでもやっぱり自分は新聞を取るとは思うのですが。(個人的にはやっぱりきちんと読まなくては、と思ってはいます。)自分で読みたい記事だけ選んで読むネットでのニュースだとどうしても偏りが出てしまうので。とは言えあまり世間の動向を知らないですごしていることばかりなのですが… 色々と企業間の関連など知らない事が多くてへえ、と感心したり、そうなんだ、と驚いたり。面白かったです。
Posted by
「社会の公器」も利益が出なきゃ元も子もない。経営面からの分析もいいが、やはり新聞は紙面の内容があってこそ…ではないのだろうか。
Posted by
2009年末の冬季休みは、新聞社の経営についての新書を読み漁った。 新聞社出身の著者の指摘は説得力を感じた。
Posted by
[ 内容 ] 新聞という産業は今、様々な危機に直面している。 止まらない読者の減少、低下し続ける広告収入、ITの包囲網、消費税アップ、特殊指定の見直し-そして何より、金科玉条としてきた「部数至上主義」すなわち泥沼の販売競争は、すでに限界を超えている。 いったい新聞は大丈夫なのか。...
[ 内容 ] 新聞という産業は今、様々な危機に直面している。 止まらない読者の減少、低下し続ける広告収入、ITの包囲網、消費税アップ、特殊指定の見直し-そして何より、金科玉条としてきた「部数至上主義」すなわち泥沼の販売競争は、すでに限界を超えている。 いったい新聞は大丈夫なのか。 生き残る方策はあるのか。 元大手紙幹部が徹底的に解き明かす、新聞が書かない新聞ビジネスの病理と、再生への処方箋。 [ 目次 ] 第1章 新聞の危機、その諸相(朝日と読売の「共闘宣言」 異常な販売コスト ほか) 第2章 部数至上主義の虚妄(新聞は「あちら側」 言論と企業活動のギャップ ほか) 第3章 新聞と放送、メディアの独占(相次いだメディアの「不祥事」 空文化した「放送政策の憲法」 ほか) 第4章 新聞の再生はあるのか(産経新聞の実験-夕刊廃止と低価格 携帯電話と読者の高齢・無職化 ほか) 第5章 IT社会と新聞の未来図(新聞版のロングテール ポータルサイト争いで完敗 ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
天下を誇るビジネスモデルが壊れようとしている。確かに考えてみればおかしい部分はたくさんある。 新聞社が今危機的状況にあるのは間違いない。読者への信頼を誇る分、経営も健全であってほしいものだ。
Posted by
「新聞再生」に続いて、学環報道班のためのお勉強として。 「新聞再生」とは違い、業界全体の抱える問題について書かれている。 3年前の本なので、取り巻く状況については少々古い感はあるが、 業界の内部構造についてはとても勉強になる。 (特に冒頭の産業構造図は分かりやすく、全体の話を理解...
「新聞再生」に続いて、学環報道班のためのお勉強として。 「新聞再生」とは違い、業界全体の抱える問題について書かれている。 3年前の本なので、取り巻く状況については少々古い感はあるが、 業界の内部構造についてはとても勉強になる。 (特に冒頭の産業構造図は分かりやすく、全体の話を理解するうえで必須。) 部数至上主義という考えを支えるための、再販制度や特殊指定、世界に類を見ない強力な戸別配送網などが抱える問題点について。放送支配の流れや影響について。 一番受けた強く印象は、「ほとんど非上場だから、数字に信憑性がないんだなあ」ということ。信頼のおけるデータが全然ないんだなあ、と感じた。
Posted by
ジャーナリズム論ではなく、ビジネスとしての新聞社論。著者は06年まで毎日新聞社常務取締役(営業・総合メディア担当)を務めた河内孝氏。上場企業ではない新聞社の経営はブラックボックスになっており、経営側の人間からの著書というのは珍しい。 新聞産業は転換期を迎えている。部数減、広告収...
ジャーナリズム論ではなく、ビジネスとしての新聞社論。著者は06年まで毎日新聞社常務取締役(営業・総合メディア担当)を務めた河内孝氏。上場企業ではない新聞社の経営はブラックボックスになっており、経営側の人間からの著書というのは珍しい。 新聞産業は転換期を迎えている。部数減、広告収入の落ち込み、消費税、特殊指定の見直し。同書ではテレビと新聞社の関係、最近、裁判にもなっている「押し紙」(新聞社が販売店に必要以上の新聞を押し売りすること)など、新聞社の暗部に言及。これらは新聞では語られない部分である。 河内氏は諸悪の根源は今や常軌を逸した「発行部数至上主義」と断じる。過当競争、編集工程を含めた生産や流通面の非合理性を改善することが「生き残り」の最低条件で、再生策としては読売・朝日に対抗する第三極を作って、過当競争を正常化し、設備、人員の合理化を図るべきだ、と主張する。 同書が発行されたのは07年2月。その後、読売、朝日、それに日経の3社は同年10月、1)インターネット事業、2)販売網、3)災害時の協力体制を約束した「ANY連合」を発表。さらに、今秋には読売と朝日はさらに相互印刷、共同輸送などで基本合意した。著者は「勝ち組」3社の連合を想定して、提言を急いだのかもしれない。 昨今、新聞を購読する人は減った。たいていのニュースはインターネット、携帯電話で知ることができるからだ。しかし、新聞がなくなったら、当然、ネットや携帯で見ることはできないことも忘れてはいけない。 新聞社の経営には問題があるのは確かだ。しかし、新聞はなくなっていいものではない。表現の自由、多様な言論を守るためには、多くのメディアが切磋琢磨することが望ましい。新聞の危機は実はひとつの業界の危機ではなく、国民全体の危機である。もちろん、何よりも急がれるのは新聞社の経営改善である。
Posted by
新聞社が抱える問題を網羅的に解説した本です。この業界をざっと把握するのに役立ちました。人口減を前に新聞(を印刷して配達する)業界はどう考えても縮小産業状態。あと数年で、新聞記者が原稿を書いて、読者はネットで読む時代がくるでしょう その意味では新聞記者業界(執筆業界)はなくならな...
新聞社が抱える問題を網羅的に解説した本です。この業界をざっと把握するのに役立ちました。人口減を前に新聞(を印刷して配達する)業界はどう考えても縮小産業状態。あと数年で、新聞記者が原稿を書いて、読者はネットで読む時代がくるでしょう その意味では新聞記者業界(執筆業界)はなくならないわけで、中間コストが減った分、広告費減少でもやっていけるような気がします。でもその場合、新聞記者の性格、位置付けも変わってるでしょう。 夕刊はもういらないな。
Posted by
参考になるところもあったが、ちょっと違うだろ、というところもあった。 今となっては当たり前のことばかり(2010.6)
Posted by