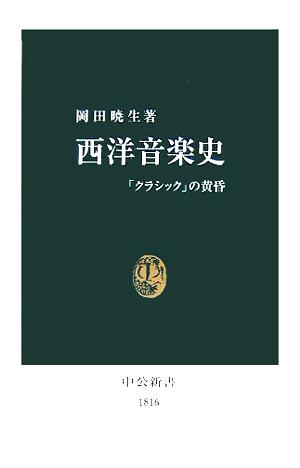西洋音楽史 の商品レビュー
文章は学術的な感じが強いので、少し難しいところもありますが、クラシック音楽の歴史の流れをこれだけわかりやすく解説した本は、なかなかないと思います。 もともとクラシックについて、それほど知っていたわけではないですが、知らなかった話が多く書かれていて、興味深く読むことができました。
Posted by
分かりやすいだけでなく、文章が巧い。内容もよくまとまっており、地に足の着いた議論が展開されている。ありきたりの解説にもシニカルに歪んだ奇説にもなることなく、中道的ながらフレッシュな論理展開がなされていて好感。軽く要約もして、大いに勉強させて頂いた。再読の価値あり。
Posted by
作曲された当時と今とでは、聴き手の対象や聴く環境が異なることを、時代背景とともに知ることができました。 また、現在の音楽史を把握できない理由として、音楽史の主役が作曲家でなく、いわゆる名演と言われる巨匠たちに移っている点に納得させられました。 取り上げられた音楽を実際に聴きな...
作曲された当時と今とでは、聴き手の対象や聴く環境が異なることを、時代背景とともに知ることができました。 また、現在の音楽史を把握できない理由として、音楽史の主役が作曲家でなく、いわゆる名演と言われる巨匠たちに移っている点に納得させられました。 取り上げられた音楽を実際に聴きながら、再度読み返したいと思いました。 2021,3/18-3/19
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ヨーロッパ音楽史の概要書を求めていたので読んだ。大まかな歴史は理解できた。 気になった点:ストラヴィンスキーやシェーンベルクが音楽には新しい方法や技術がもう無いという認識、つまり「音楽の終焉」を予感した上で活動していたという指摘。また、哲学者のテオドール・アドルノはポピュラー音楽を「常に新しく見えるが常に同じもの」という意味で常緑樹、エヴァーグリーンと呼んだという。我々現代人が日常的に聞いている音楽は19世紀ロマン主義音楽を継承している。そこには新しいものなど無い。音楽学、音楽理論上はそうなのだろう。ただそういった指摘があるからso what?としか聴衆は思わないだろうし、自分もなにか問題でも?と思ってしまう。
Posted by
西洋音楽史を学ぶと同時に、西洋の歴史も学べる。学生時代、単に中世期、ルネサンス期、バロック期、古典期、ロマン主義期などを時系列だけで学んできたが、背景にある歴史、文化、宗教、神への信仰心、革命や戦争と音楽は深く交わっていることが、楽しく理解できた。
Posted by
率直な感想として、音楽史を俯瞰できる立場にある現代人は本当に幸せだと思う。 中世の時代にバッハを聴くことは出来ないし、バロック時代にモーツァルトを聴くことも出来ない。そんな中、我々は好きな時代の好きな曲が聴き放題という贅沢な時代に生きている。これを享受しない人生とは勿体ないと思...
率直な感想として、音楽史を俯瞰できる立場にある現代人は本当に幸せだと思う。 中世の時代にバッハを聴くことは出来ないし、バロック時代にモーツァルトを聴くことも出来ない。そんな中、我々は好きな時代の好きな曲が聴き放題という贅沢な時代に生きている。これを享受しない人生とは勿体ないと思う。 以前にパウル・ベッカーの『西洋音楽史』を読んだが、全然理解できなかった反面、こちらは非常に分かりやすい解説。 パウル・ベッカー並びに文学含め、ドイツ人は気難しいなぁと個人的に思っていたが、まさしく本書でもその気質について言及されている。 今″クラシック″が指す音楽はドイツで生まれたもので、コンサートホールで目を閉じて聴き入るという姿勢が定着したのもドイツ人の気質に由来するのだそう。 交響曲もピアノ・ソナタもその気質ありきのものだったというのは驚いた。 ドイツのロマン派が音楽に具象を超えるものを求めたが、その後に音楽は音楽でしかないと反論されたという話は笑ってしまった。 初学者の僕にとっても理解し易い内容と構成になっているので、少しでも音楽に興味があれば是非読んでみるといいかも!
Posted by
名曲ガイドや巨匠紹介のような類の本ではなく、時代背景に即して西洋音楽史を概観していくような内容。非常に流れがはっきりとしているので、一気に読み進められた。ただ、芸術史や文化史を読む上では当然ながら、頭に西洋史の知識や作曲家の名前が入っていないとさすがに読んでいくのに若干厳しいもの...
名曲ガイドや巨匠紹介のような類の本ではなく、時代背景に即して西洋音楽史を概観していくような内容。非常に流れがはっきりとしているので、一気に読み進められた。ただ、芸術史や文化史を読む上では当然ながら、頭に西洋史の知識や作曲家の名前が入っていないとさすがに読んでいくのに若干厳しいものがある。
Posted by
西洋音楽入門にはピッタリじゃないでしょうか。論旨の切れがいいですね。出てすぐに高校生に「案内」しましたが、読む子はなかなかいませんでしたね。「のだめ」が流行っていたころなので、「ひょっとして」と思いましたが。 その「案内」をブログに載せました。 https://plaza.ra...
西洋音楽入門にはピッタリじゃないでしょうか。論旨の切れがいいですね。出てすぐに高校生に「案内」しましたが、読む子はなかなかいませんでしたね。「のだめ」が流行っていたころなので、「ひょっとして」と思いましたが。 その「案内」をブログに載せました。 https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/202002110000/
Posted by
邦楽とクラシックは伝統という一点においては通じ合えるし、音楽、という本質も一緒なんだけれど、感覚と理論というか、言葉のまま、東洋と西洋の思考形態の違いが見事に反映されているのだと腑に落ちる。
Posted by
クラシック名盤ガイドを探している時に名著として出てきて読んでみました。確かに名著だ。一気に読ませる熱量がある。文章は華麗でいて平明、歴史の中で鳴っていた音、現代人には聴き取れない音があったのだと遥かな想いになる。グレゴリオ聖歌から態度を正して改めて聴きたくなる。これが新書ですよ、...
クラシック名盤ガイドを探している時に名著として出てきて読んでみました。確かに名著だ。一気に読ませる熱量がある。文章は華麗でいて平明、歴史の中で鳴っていた音、現代人には聴き取れない音があったのだと遥かな想いになる。グレゴリオ聖歌から態度を正して改めて聴きたくなる。これが新書ですよ、一冊でわかった気にさせてくれる、もちろん幻想と知りつつ、巻末にはブックガイド。扉を開いてくれたら大成功、が新書の使命(2020-01-09)
Posted by