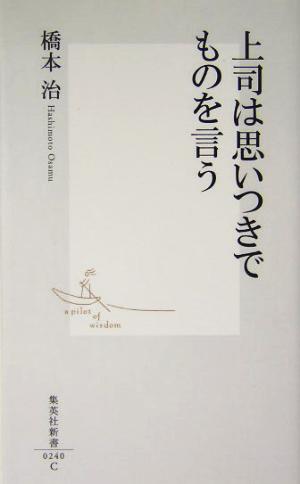上司は思いつきでものを言う の商品レビュー
この本を読んで「上…
この本を読んで「上司は思いつきでものを言う」生き物だと再確認(あきらめ?)し、自分を慰めてください。
文庫OFF
思いつきでものを言う…
思いつきでものを言う上司への対応法を説く本ではありません(笑)。ただ、その原因を文化的に説明してくれます。また、この本自体が確信犯的に思いつきなものになっています。
文庫OFF
上司とはどういうもの…
上司とはどういうものか、また部下はどうしなければならないかなど心得的なことが書かれている。それにしても全国の企業でこうなのかと思わせられる。
文庫OFF
確かにこれは現状かも…
確かにこれは現状かもしれませんが・・・それは当たり前だと思いました。
文庫OFF
上司は多くの気付きが…
上司は多くの気付きが重要かと。そんな中での発言は時に多くの経験に裏打ちされた思いつきだったりもする。この本の示すところはやや表面的か。
文庫OFF
論理的には、正しいこ…
論理的には、正しいことを言っているかもしれませんが、世のサラリーマン上司はそんなもんじゃないよな~と思いました。本書のタイトルは、むしろ「この本は思いつきでものを書いている」にした方が適切だと思います。あまりタメにはなりません。
文庫OFF
読み応え十分
ビジネス人向けの自己啓発や「困った上司対応法」のような本ではありません。日本人の根底に流れるもの、思考パターンについて儒教の影響を交えて論が展開されます。癖のある文章ですが、読み応え十分。
midori
現場から離れた上司が所詮、中間管理職であること。 中間管理職であるがゆえに、自分も管理されていること。 現場からの根本的な提案に、素直にyesを言えないこと。 上記の理由で、思いつきものをいう、(ように見える)
Posted by
著者、橋本治さんの作品、ブクログ登録は2冊目になります。 橋本治さん、どのような方か、ウィキペディアで再確認しておきます。 ---引用開始 橋本 治(はしもと おさむ、男性、1948年(昭和23年)3月25日 - 2019年(平成31年)1月29日)は、日本の小説家、評論家...
著者、橋本治さんの作品、ブクログ登録は2冊目になります。 橋本治さん、どのような方か、ウィキペディアで再確認しておきます。 ---引用開始 橋本 治(はしもと おさむ、男性、1948年(昭和23年)3月25日 - 2019年(平成31年)1月29日)は、日本の小説家、評論家、随筆家。 ---引用終了 で、70歳にて亡くなっています。 本作の内容は、次のとおり。 ---引用開始 この本はサラリーマン社会の閉塞を嘆じるものではありません。「上司は思いつきでものを言う」ということが、なぜ起こってきたのかを、儒教の伝来まで遡り、とてもスリリングに解剖していく本です。日本の男たちが、なぜ戦国時代と幕末維新の時代ものが好きなのか。こんな「なぜ」も見えてきます。そして、では日本はどうするのか-「現場」の声を聞く能力の復活に向けて、上司のみなさんにも、上司でないみなさんにも、懇切丁寧な今後の道中案内の書であります。 ---引用終了 本作は、著者が56歳位の時に書かれた作品になります。 タイトルに惹かれて手にした作品ですが、よくわからない内容でした。
Posted by
橋本治(1948~2019年)氏は、東大文学部国文科卒、イラストレーターを経て、小説家・評論家・随筆家となる。小林秀雄賞、柴田錬三郎賞、毎日出版文化賞、野間文芸賞等を受賞。 私は新書を含むノンフィクションを好んで読み、興味のある新刊はその時点で入手するようにしているが、今般、過去...
橋本治(1948~2019年)氏は、東大文学部国文科卒、イラストレーターを経て、小説家・評論家・随筆家となる。小林秀雄賞、柴田錬三郎賞、毎日出版文化賞、野間文芸賞等を受賞。 私は新書を含むノンフィクションを好んで読み、興味のある新刊はその時点で入手するようにしているが、今般、過去に評判になった新書で未読のものを、新・古書店でまとめて入手して読んでおり、本書はその中の一冊である。(本書は2004年出版) 本書は何と言っても「上司は思いつきでものを言う」というタイトルが目を引くが、私は常々「上司は、部下の話(提案)に対して何かコメントしないと、存在意義を否定されると考えるので、何でもいいから思いついたことを言う」と考えており(自戒の念も含めて)、著者の論理展開を興味を持って読み進めたが、シンプルにまとめると以下のようなものである。 ◆問題がある会社・組織において、部下が建設的な提案を行うと、上司(達)はそれまで自分(達)がやって来たことに問題があったと言われたと感じるため、素直に受け入れることができない。そして、上司(達)は(それほどバカではないので)、問題があることは薄々認識しつつも、その責任を問われるような建設的な解決案には賛成せず、(問題の所在・責任を明確にする必要のない)ムチャクチャなアイデアを口にする。 ◆上司とは、「現場」から乖離した立場なので、そもそも、現場の部下から上がってきた建設的な提案に対して、有効なコメントなどはできなくなっているものなのだが、自分は偉いと思っている上司は、優位性を保つために、部下を困らせるようなテキトーなことを言い、また、部下思いで未だに部下と一緒に仕事をしたいと思っている上司は、(悪気はなくとも)ピントのズレたアドバイスをして部下を困らせることになる。 ◆上司から思いつきでものを言われたときの対応策は、論争などをすることではなく、ただ「あきれて」何を言い返されても聞き流すことである。「本当にあきれられて、それで己の愚に気づかない人間はいない」と思うべし。 後段では、そのほか、日本の会社・組織の問題点を、歴史を遡っていろいろと分析している(著者は当初、「サラリーマン(社会)の欠点」というタイトルで書くことつもりだったという)が、本書において肝腎なことは「上司は思いつきでものを言う」ということなのだそうである。 よく言われるように、著者の文章は独特で、くねくねして、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして、少々読み難いのだが、「上司は思いつきでものを言う」というテーマは、こうした思考回路の著者だからこそ面白く書けたとも言えるのかも知れない。(理路整然と書かれても、「ちょっとなぁ」と言ったところか。。。) 前半だけでも一読して面白い一冊と思う。 (2022年7月了)
Posted by