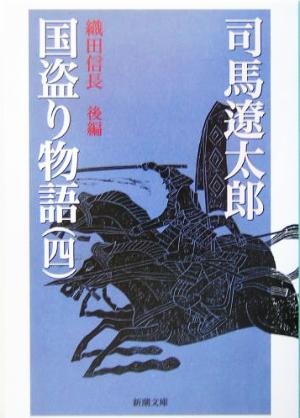国盗り物語(四) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
光秀はずっと信長をライバル視し、心の中では上から目線で批評してばかりだったのだが、自身が担ぎ上げた将軍足利義昭の器の小ささに(わかっていたことだが、改めて)失望すると同時に、運だけでは説明の付かない信長の実力を目の当たりにし、はっきりとその能力を認めるようになる。 二人の主に同時に仕えるという微妙な立場で、時に板挟みになりながら、細川藤孝という代え難い友との絆も深め、自身の功名のために粉骨砕身、信長に仕えていく。 道三の失脚で故郷を追われて以来、ただ志と自負だけで何も持たなかった光秀の人生においては、もっとも充実した日々だったのではないだろうか。 しかし主従関係となった二人の間には相変わらず「気にくわない奴」という人間としての肌合いの絶望的な違いが根底に流れている。時間が流れても、ともに大きな仕事を達成しても、その乖離は少しも埋まらないままで過ぎていく。 それでも、そのずば抜けた能力の高さだけは、互いに認め合っていて、主である信長は光秀を抜擢し続ける。著者の言い方では道具として使い倒していく。光秀は光秀で、京都の社交の場で、そちこちの山野の戦場で、だれよりも駆け回り、働き続ける。その懸命の働きが老いとととも光秀の精神をすり減らしていく様は、読んでいてなんとも痛々しい。 また信長にしても、古くからの武将を無慈悲に使い捨てていく終盤の描写を見ると、滅びるべくして滅びた独裁者のように見えてしまう(もちろん結末を知っているからなのだけど) 主人公ではないから登場は少ないが、秀吉も光秀と並ぶ逸材として常にきらりと輝いているし、同盟者としての家康もなんとも魅力的に描かれている。 そうした次の時代の覇者たちを、さりげなく星のようにちりばめながら、光秀の、行く末の明らかな(親友さえ味方しない)、暗く救いようのない謀反は決行されてしまう。 この本能寺の辺、そして光秀の死によって、道三の二人の後継者は息絶え、国盗り物語は幕を閉じた。 この歴史の道筋の暗さの中に、信長と光秀とはまるで違う秀吉の明るさが、次の道を照らす灯りとしてきちんと用意されているようで、暗い結末を読んでいながらも、心底絶望的な気持ちにはならない。 さっさと「新史太閤記」を読んで気持ちを切り替えねば。
Posted by
光秀はやっぱり天下を取る器ではなかったのかな、と思った。 多芸で、伝統を重んじる礼儀正しい人だからこそ、他人に自分の本心を見せたり、わがままに甘えたりすることが出来なかったから、周りにも引かれてしまったみたいだった。 裏切ったり裏切られたりの戦国時代も、知ってみるとおもしろいと...
光秀はやっぱり天下を取る器ではなかったのかな、と思った。 多芸で、伝統を重んじる礼儀正しい人だからこそ、他人に自分の本心を見せたり、わがままに甘えたりすることが出来なかったから、周りにも引かれてしまったみたいだった。 裏切ったり裏切られたりの戦国時代も、知ってみるとおもしろいと思った。
Posted by
ついに完結。 天下統一に向けて様々な革新的なことを進めながら包囲網に立ち向かう織田信長と、 その信長を支える明智光秀の微妙な距離感。 それが徐々に開いていく様の描き方が素晴らしい。 結末がさっぱりしてるのもまた味がある。
Posted by
前半は斎藤道三、後半は織田信長、明智光秀が主人公の話。歴史の流れがイメージできて楽しいのは勿論、ネガティブなイメージであった光秀にも共感し、印象が変わったのは著者の力か。 殆ど平民の出から、大商人になり、時には主人さえ蹴落とし一国を持つようになる。また、「道三の真の敵は、美濃国...
前半は斎藤道三、後半は織田信長、明智光秀が主人公の話。歴史の流れがイメージできて楽しいのは勿論、ネガティブなイメージであった光秀にも共感し、印象が変わったのは著者の力か。 殆ど平民の出から、大商人になり、時には主人さえ蹴落とし一国を持つようになる。また、「道三の真の敵は、美濃国内の反対派地侍ではなく、中世的権力であった」と言われるほど、経済的な改革を進める。道三が楽市、楽座の先駆け。 その後は、信長、明智光秀の話に移る。「道三の娘婿が信長、道三の妻の甥が明智光秀。本能寺の変は道三の相弟子同士の戦い」と言うことを知る。 歴史上の大きな不思議と言われている、本能寺の変に答えていると言える一作。 【心に残る言葉】 人間としての値打ちは、志を持っているかいないかにかかっている(光秀)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
織田信長の日本統一に向ける足跡とその最後の時代を描いた最終巻。 今回の主人公は信長ではなく、不世出の天才明智光秀。 京の幕臣でありながら信長の配下であるという板挟みに苦しめられ、信長の天下になってからは信長の非人道ぷりとパワハラについに心身を消耗し、討ち入りという暴挙に出てしまう。 三巻までのような派手さはないけど、非常に優秀だが教科書的な生真面目な性格故に苦しむ辛さがよく描かれた痛ましい話でした。
Posted by
織田信長と、明智光秀を中心に描く。信長の天才性と狂気のような側面、何でもそつなくこなすが故に信長に便利な道具のように酷使される光秀の苦悩など、本能寺に至るまでの過程が自然に思えてきた。
Posted by
ついに明智光秀と織田信長は本能寺で相まみえることとなる。四巻にきた急に明智光秀が普通の人間になってしまった気がする。本能寺に至るまでの経緯が、怨恨を中心に展開しているのもどうかと思う。明智光秀には天下を狙う意志があったとも言うが、「国盗り物語」ではそのあたりにはあまり踏み込んでい...
ついに明智光秀と織田信長は本能寺で相まみえることとなる。四巻にきた急に明智光秀が普通の人間になってしまった気がする。本能寺に至るまでの経緯が、怨恨を中心に展開しているのもどうかと思う。明智光秀には天下を狙う意志があったとも言うが、「国盗り物語」ではそのあたりにはあまり踏み込んでいない。
Posted by
最後の数十ページは読むのがつらかった。 天下を取るには秀才ではだめなのだ。 人心掌握術というか、知識やそういったものではなく、 人の良さでもなく。 天性のものと、育っていく過程で学び身についていくもの。 光秀が優秀なだけに、最後を読むのは辛かった。けど、現実ってこういうもんだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
悪とは何か。正義とは何か。それを知りたかったら戦国時代を学べ。 美濃一国からはじまり、日本一国を獲ろうという男たちの物語完結。 斉藤道三は「悪い人」だった。頭の回転が速く、人心掌握の術に長け、巧みに嘘をつける。 織田信長は「悪ガキ」だった。頭は良いが、人間関係を理解できない、策よりゴリ押し事態を乗り切る。 明智光秀は…「…」悪い人だった。悪になれたけれど、その師である道三とは決定的に違かった。境遇が?いや、少し清潔すぎたのかもしれない。頭がいいから時代を読んで朝倉、足利、織田と仕える主をコロコロ変えられたし、その外交能力を見れば人の心を読む力も十分だし、策略家である。道三の力をよりよく引き継いだのは信長よりも光秀であるにもかかわらず、頭でっかちの金柑頭では天下は取れなかったんだというのが、斉藤道三への皮肉である。結局、道三では天下は取れなかった。のかもしれない。。 それにしても正義というのは難しいものである。正義がなければ政治はできないものらしい。 道三も正義を利用して土岐氏を追放した。けれど、竜興によって自身が討たれたのも親の敵という正義のためだった。 信長も馬鹿ではなく、正義がなければ天下が取れないということは分かっていたらしい。義昭を立てなくてはならず、我慢を重ねたところは偉いと思った。 光秀は信長の不正義に自分の不正義をぶつけてしまった。もし、光秀が正義をうまく扱えていたら…。 人が作るものである以上、社会・政治・経済その他なんでも正義が尊重されてしまうのだな。正義という美しい響きに、疑う心を忘れて聞き惚れてしまうことの危険性も同時に理解せねばいけない。 ___ ● 過去の成功に囚われない 信長は過去の成功に囚われず、常に目の前のことに注力していた点が非凡なところだった。当時の武将は過去の功績を自慢できてなんぼのもんだったろうが、信長はそういうものをくだらないものとして軽蔑したんだろう。桶狭間での大勝利があるにも関わらず、それに囚われず、一戦一戦常に先頭に立って戦い抜いた。意図せず信長は仏教的な悟りを持っていたんだな。 ● 無駄観のなさ 信長の父:信秀は無駄を大切にした。無駄ができない者は天下は取れないとまで言っているが、息子にはその心意気はあまり受け継がれなかったようだ。合理主義的な信長は無駄を惜しむところがあった。この物語に出てくるところでいえば、今日の御所を建てなかったところであろう。まぁ、その偏った性格だから他人から見れば無駄なこともしていたんだろうが、言葉少ない話し方とかを見れば無駄はNGだったと予想できる。しかし、無駄ができない者は天下をとれないとは、信秀も先見の明があったのだな。まさか自分のうつけ息子に当てはまるとは思いもしなかっただろうが。 p610 狡兎死シテ、走狗烹ラル 狩場で獲物の兎がいなくなれば、猟犬は不要になりその肉を煮て食われてしまう。信長の人の使い方もそのことわざ通りで、佐久間信盛が追放されたのがよい例である。それを恐れて荒木村重は謀反に走り、光秀も将来を危ぶみ「時は今…」と思ってしまったのだ。 時は今 天の下しる 皐月かな (明智光秀)
Posted by
面白かった。しかし、後半の信長編は、実質明智光秀やな〜。司馬遼太郎の作品で、ど真ん中に信長を扱った作品はなかったっけ?。
Posted by