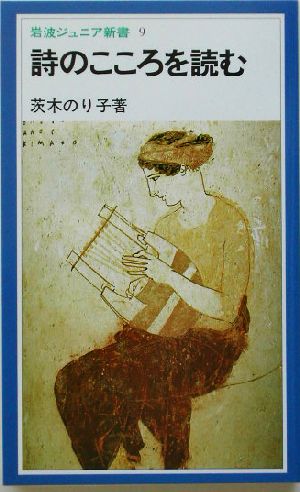詩のこころを読む の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1979年、著者が53歳くらいの頃に書かれた本書は、一切古さを感じさせない文章で「詩を読む楽しさ」を教えてくれる。 著者がそれまで出会ったお気に入りの詩を選りすぐり、ユーモアを交えながら卓越した考察力で読み解いていく。 「誕生」から「死」までの5段階で流れるように並べられているので、小説のように一気に読み進めてしまうところも魅力だ。 『はじめに』の冒頭3行で、全てが語られている。 「いい詩には、ひとの心を解き放ってくれる力があります。いい詩はまた、生きとし生けるものへの、いとおしみの感情を優しく誘いだしてもくれます。どこの国でも詩は、その国のことばの花々です。」 自分の気持ちを代弁してくれる詩に出会い、心にスーッと入って感じるカタルシスは最高の慰めになる。そして何より優しい気持ちになれるのだ。 あまり詩というものに触れてこなかった自分にとっては目から鱗であった。 自分が53歳になる頃にはお気に入りの詩を並べてみたいと思う。
Posted by
性格的に、詩よりも散文、評論、随想のほうが好きなのですが、一度くらいちゃんと触れてみようと思い、読んでみた一冊。詩人でもある茨木のり子さんが、自分の好きな詩を集め、その詩とともに解説を書いている本(この前読んだ国語の教科書『新編 国語総合』に「詩集ではないが、最良の詩の入門書」と...
性格的に、詩よりも散文、評論、随想のほうが好きなのですが、一度くらいちゃんと触れてみようと思い、読んでみた一冊。詩人でもある茨木のり子さんが、自分の好きな詩を集め、その詩とともに解説を書いている本(この前読んだ国語の教科書『新編 国語総合』に「詩集ではないが、最良の詩の入門書」と書いてあったので購入)。 詩は理屈ではないので、あいかわらず「分からんなぁ」というものも多いのですが、中にはピンと来るもの、好きなものもあって、次はその人たちの詩集を買ってみようと思う(川崎洋、阪田寛夫、黒田三郎など)。 そういう意味では、「最良の詩の入門書」という触れ込みもダテではない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「茨木のり子」という著者の名前も、教科書で目にした記憶しかない。それくらい不勉強な私でも、一編一編、著者の視点を通して詩の世界にぐっと近付けてもらった。 自分の気持ちに合う詩、を探すことは、自分自身にとって新しい読書体験になるかも。 印象に残った言葉 ・言葉が着陸の瞬間を持っていないものは、詩とはいえない。 重装備でじりじり地を這い、登山するのが散文 地を蹴り宙を飛行するのが詩 ・詩人が人々に供給すべきは、感動である。 それは必ずしも深い思想や、明確な世界観や 鋭い社会分析を必要としない。 気になった詩 ・I was born 吉野弘 →どこかで読んだことがある気がするが、 いつも最後にドキリとしてしまう ・練習問題 阪田寛夫 →思春期をお洒落に表現している ・くるあさごとに 岸田衿子 →くるくる、、 忙しい毎日、駆けまわる毎日を思ってしまう ・海で 川崎洋 →粋な若者たちの冗談に、心が爽やかになる ・風 石川逸子 →戦争に基づく詩のようだが、 今のSNS社会を風刺しているように感じる ・新しい刃 安西均 →また1つ成長する息子を眩しく見つめる視線に 親近感を覚える ・その夜 石垣りん →働き続ける女性に病が迫る日があったとしても 「私ひとりの祝祭日」と受け止める強さを持ちたい ・悲しめる友よ 永瀬清子 →古いジェンダー観と切り捨てることもできるが もし苦しむ友がいれば、この詩をそっと教えてあげたい
Posted by
琉球大学附属図書館OPAC http://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN03640864
Posted by
永瀬清子さんの「悲しめる友よ」に出会えてよかった。茨木のり子さんの解説はご自身の詩人として人としての感性が率直に綴られていて素敵だった。
Posted by
紹介されている全ての詩が大好きになるような解説。 詩人による解説は贅沢で、読んでいる時間も至福でした。 何度ドキッとさせられたことか。 詩って、難しいと思っていたのですが 素直に読んで、感じて、分からなければ分からないでそっと閉じていいのかな、と あるいは、優しい詩を好...
紹介されている全ての詩が大好きになるような解説。 詩人による解説は贅沢で、読んでいる時間も至福でした。 何度ドキッとさせられたことか。 詩って、難しいと思っていたのですが 素直に読んで、感じて、分からなければ分からないでそっと閉じていいのかな、と あるいは、優しい詩を好んで読んでも それは素敵なことなのかな、と思えました。 ここで知った詩人の詩集も買ってみようと思いました。
Posted by
詩は、感情や感性のもの。 散文は論理を積み重ねていきますが、 そうやって分析することができないものを、 詩人は、詩として表現する。 だから、 読んでみて浮かぶ感想ははっきりした言葉にならず、 大かたは、 「ああっ」 だとか 「はああっ」 だとか、 「そうなんだよ!」 だとかの感...
詩は、感情や感性のもの。 散文は論理を積み重ねていきますが、 そうやって分析することができないものを、 詩人は、詩として表現する。 だから、 読んでみて浮かぶ感想ははっきりした言葉にならず、 大かたは、 「ああっ」 だとか 「はああっ」 だとか、 「そうなんだよ!」 だとかの感嘆や納得の気持ちが多い。 あるいは、詩は自分の内部に埋もれている感覚や感情や記憶を 呼び起こすトリガーになったりもするでしょう。 詩でこそ開いていける、というところがある。 社会に対してだってそうだし、 人間理解だってそうだし、 世の中そのものだって、過去や未来や宇宙にだってそうなんだなと 今回、本書を読んでそう思いました。 繊細だけれど力強くもあり、 まあるくなってそうで、とがってもいる。 体内を流れる血であり、流れ出た血でもある。 何を書いているかはっきりはからないから苦手、という人は多くいそうです。 僕だって、ずっとそうでした。 言葉の遊戯、言葉のパズル、言葉のコラージュなんだろう、 と決めつけたこともあります。 そういった面は、技術としてあるのでしょうが、 詩が発現してくる源に目を凝らしてみると、 また考えが改まります。 本書は、著者・茨木のり子さんの解きほぐし方が、 丁寧だし、いろいろと察してもいるし、 大事に詩を扱っているし、 言葉がわかりやすいしで、 詩にひたる経験がしたい! という人にはうってつけの本でした。
Posted by
15年前に読んだ本 いまだに一番好きな本 たくさんの気づき はっとすることがある 読むたびに心に響く詩がかわる これからさきも また人生の時がすすむた 読み返したい一冊
Posted by
詩人の茨木のり子さんによる詩の解説書。 詩のテーマになることが多い 生まれて、恋唄、生きるじたばた、峠、別れ の5つのカテゴリーごとに、有名な詩をピックアップして解説する。 詩の技法や鑑賞にあたって着目すべき点について解説があればと思って手にとったので、自分の用途には合わなかった...
詩人の茨木のり子さんによる詩の解説書。 詩のテーマになることが多い 生まれて、恋唄、生きるじたばた、峠、別れ の5つのカテゴリーごとに、有名な詩をピックアップして解説する。 詩の技法や鑑賞にあたって着目すべき点について解説があればと思って手にとったので、自分の用途には合わなかった。また、ところどころエモーショナルな言葉を使うのも個人的には苦手。 ただ、詩人石垣りんの生い立ちと、彼女の「くらし」という詩を知ることが出来たのは本書のおかげなので読んでよかったと思う。
Posted by
仮名遣いが優しく、言葉選びにそつがない 短く凝縮された、時に難解な詩を自分なりにでも読み解くことができる教養や感性を身に付けたいものだと思う
Posted by