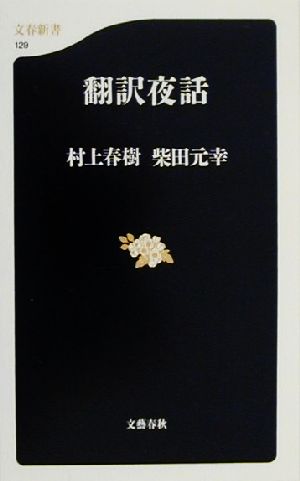翻訳夜話 の商品レビュー
翻訳にそれほど興味はないが、翻訳者の柴田元幸さんには以前から興味があった。相手が村上春樹さんとあれば、なおさらだ。 翻訳の裏話がたくさん出てくる。 個人的に好きな部分は挙げきれないので、ここでは割愛。 1つだけ挙げるなら、村上さんの、翻訳者に必要なのは、偏見のある愛情という話。 ...
翻訳にそれほど興味はないが、翻訳者の柴田元幸さんには以前から興味があった。相手が村上春樹さんとあれば、なおさらだ。 翻訳の裏話がたくさん出てくる。 個人的に好きな部分は挙げきれないので、ここでは割愛。 1つだけ挙げるなら、村上さんの、翻訳者に必要なのは、偏見のある愛情という話。 内容に直接関係はないけれど、カーヴァーやフィッツジェラルドを読みたくなった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
海外文学を読み始めてまだ日が浅いけれど、このお二人がとてつもない量の仕事をしていることは嫌でもわかる(各々5人くらいいるんではないかと疑ってる)。それほどまでに英米文学の棚には彼らの名が連なっている。柴田氏の訳文は海外文学初心者の私でもスーッと脳に染み込むようで心地よく、みんなにオススメしたい。 しかし、100%自由に書ける小説と違い、翻訳というのは原作の上に成り立つ。そこにストレスはないのだろうか?翻訳者でもあり、世界中さまざまな言語に翻訳される著書を多数持つ村上春樹氏の翻訳に対する見解は意外なものだったー“多少誤訳があっても、多少事実関係が違ってても、べつにいいじゃない、とまでは言わないけど、もっと大事なものはありますよね。僕は細かい表現レベルのことよりは、もっと大きな物語レベルのものさえ伝わってくれればそれでいいやっていう部分はあります。作品自体に力があれば、多少の誤差は乗り越えていける。それよりは訳されたほうが嬉しいんです。”ー 人称をどう訳すか、he said she said〜みたいなくどい文章をどのように訳すか、過去形と現在形を織り交ぜてリズムを作り出す、などなど、訳文はあらゆる小さなこだわりの積み重ね。あらゆる翻訳は誤訳である、何らかのノイズは忍び込む。そのノイズをいかに取り除き、原文の文学的価値を損なわないようにする、繊細すぎるにもほどがある仕事だということがわかった。 今からでも翻訳家になりたいなー。そりゃ、ダジャレなんかも理解できないといけないくらい、英語そのものだけでなく現地の文化などへの理解も求められる大変なものだとは思うけど。柴田さんの、芸術方面に興味があるけど事務処理が得意っていうの、すごいわかる(わかるなんて言ったらおこがましいけど)。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
パラパラと。 文章は天から降りてくる。そして、辞書は小説を書いている時は使わない。 これを文才というべきものか否かは悩むが、二人の、特に本書で語られる村上春樹氏の天禀には言葉もない。
Posted by
村上春樹さんが、「趣味で訳す」という趣旨の話をしていて、柴田元幸さんが「読み手がいないならしない」と言われてたけど、私はまちがいなく前者。読む人が自分以外にいなくても、訳したい。好きなお話や、歌や、詩を、思う存分訳したい。読んでくれる人がいれば尚いいし、いつか小説の訳をしてそれが...
村上春樹さんが、「趣味で訳す」という趣旨の話をしていて、柴田元幸さんが「読み手がいないならしない」と言われてたけど、私はまちがいなく前者。読む人が自分以外にいなくても、訳したい。好きなお話や、歌や、詩を、思う存分訳したい。読んでくれる人がいれば尚いいし、いつか小説の訳をしてそれが本になったりしたら、さぞ素敵だろうとも思うけど。
Posted by
しぐさの英語表現辞典 研究社 出てすぐに読めば良かった!高校生にすごくオススメ。最後の文を自分で訳してから2人のを読んだりしたらさらに面白いかと。
Posted by
またか、と思われるかも知れませんが、村上春樹だから買って読んだ本です。そういう読者が多くて、本書もやっぱりベストセラーになっています。だからわざわざ僕が紹介するまでもないのですが。村上春樹ファンとしては著者がどんなことを考えて執筆しているのかをちょっと知ってみたいもので、そういう...
またか、と思われるかも知れませんが、村上春樹だから買って読んだ本です。そういう読者が多くて、本書もやっぱりベストセラーになっています。だからわざわざ僕が紹介するまでもないのですが。村上春樹ファンとしては著者がどんなことを考えて執筆しているのかをちょっと知ってみたいもので、そういう意味で本書は裏話がいくつか聞けて楽しめました。聞けてと書きましたが本書の構成は2人の翻訳家(?)を中心に学生や翻訳のプロたちが行ったフォーラムが中心になっています。まあ、翻訳のテクニカルなことについてはそんなに興味はないわけだけど、2人の訳し比べなんかもあって結構楽しめました。さて、村上春樹ファンとしては一応、村上訳の本は文庫になっているものならすべてそろえています(たぶん)。だいたい、書店でも村上氏自身の著書といっしょに翻訳書も並んでいるので、見つけやすい、というか買わされてしまうのです。で、それらをすべてきっちり読んでいるかというと、それがそういうわけでもない。本棚にあるものをざっと数えてみると、17冊あるうち6冊くらいは途中までしか読んでいない。村上著の本は一気に読んでしまうことが多いから、これだけ残してしまうというのはちょっとおかしい。何が違うんだろう。本書の中で村上さん自身も語っていますが、やはりご自身の著書と翻訳書では書き方からして違う。同じ人が書く日本語だから、雰囲気、よく使われる言葉とかは一緒なんだけど、翻訳はもとの著者がいるわけで、そこで書かれている話が僕にとって読みにくいということが多いのかもしれない。アーヴィングの「熊を放つ」なんかは何が書いてあるのかもう一つ理解できなかったという印象しかない。上下巻のうち上巻の途中で止まっていると思う。ただ、村上さんの文章スタイルが現代アメリカ作家から得たものが多い、そしてたくさん吸収したいものがあるから翻訳しているんだということを知ると、しっかり読んでおきたいとも思ってしまう。それとは別に村上さんはこんなようなことも言う。長編、短編、翻訳、いろいろ書くことで精神のバランスを保っている。なるほどなあと思ってしまう。日本の作家でこんなに翻訳している人はいないんじゃないかとも。さて、しっかり読んだ翻訳書というと、以前にも紹介しているけど、ギルモア著「心臓を貫かれて」とオブライエン著「ニュークリアエイジ」。どちらもすごい長編なんだけど、何だか一気に読み進むことができた。(もっとも僕の一気は3ヶ月だったりするのだけど。)それぞれの感想は、それぞれの紹介文を読んでもらうとして、本書の最後の方でふれられていること。他人の文章を読むとそれに影響されることがある。だからやはりいい文章を読んだ方がいいのかも知れない。雑誌やテレビは見ない方がいい。僕も村上さんの本を読んだあとは、頭の中が村上モードになってしまう。最後に、僕に対するほめ言葉、「村上春樹みたいな文章だね。」こういわれると、すごーく鼻が高くなってしまう。
Posted by
特に翻訳に興味があるわけではない、と言うか、むしろ翻訳の文章は頭に入ってこないので苦手な世界だが、その舞台裏はとても面白い。興味がないけどそのマニアックぶりが面白いという点では「小澤征爾さんと、音楽について話をする」を連想する。やはり村上春樹が面白いのだ。 翻訳のあれこれを語ると...
特に翻訳に興味があるわけではない、と言うか、むしろ翻訳の文章は頭に入ってこないので苦手な世界だが、その舞台裏はとても面白い。興味がないけどそのマニアックぶりが面白いという点では「小澤征爾さんと、音楽について話をする」を連想する。やはり村上春樹が面白いのだ。 翻訳のあれこれを語ると読者や作家活動にも関係してきてその広がりも面白いところ。 ここでは2つの短編を二人が翻訳して掲載し、比べるという面白い試みもしている。例えば登場人物の職業について書かれていない場合、翻訳者が肉体労働者と思うか知的労働者と思うかで訳文がかわってくる。淡々としたものにするか熱いものにするか、主人公は「僕」なのか「私」なのか、過去形か現代形か、受け身にするかどうか、段落をかえるのは原文と同じにするかしないか(日本の小説は外国の小説よりは段落を替えるケースが多いので、原文どおりにすると日本人は読みにくく感じる。)などいろんな選択があるんですね。 それに翻訳者の物語への思入れもあって、タッチがかわってくる。海外ドラマの吹き替えで、声の調子でキャラクターが出てしまうのに似てますね。 アンダーラインを引きたくなるところが満載すぎて例示に困るので30ページごとに開いてみる。 『リズムがない文章というのは読めないんです。~だから翻訳するときには、何はともあれ原文のリズムをうまく日本語に移し換えるということを意識します。』 筆者が文章スタイルを意図的にぶち壊そうとしている『日本語にするともう収集不可能になってしまう。だから適当に止めちゃったんですよ。』『作者の意図がどうであれ、日本語にしたら読む人は違和感を感じると思ったら、翻訳者は自分の判断で変えていいんじゃないかと、僕は考えています。』 『とにかくもう何でもいいから、寝食を忘れて一生懸命いろんなものを翻訳して、何度も何度も読み直して、何度も何度も書き直して、人に読んでもらってまた書き直すということを続けていれば、スタイルというのは自然に出てきます。』 『「僕」のほうが「私」より色がありますよね。で、なるべく色なし、人間性なしでいきたかったので、本当は、だから何も書かないのがいちばんいいのだけど、さすがにそうもいかないので仕方なく「私」にした』 『僕は絶対言葉に出さない。というのは、音声的なリアリティーと文章的な、活字的なリアリティーってまったく違うものだから、音はあまり意味ないんですよね。』
Posted by
二人の翻訳愛が溢れ出ている。村上春樹が翻訳の愛情を迸らせ、柴田元幸がそれよりも少し冷静に見えるのが面白い。様々な質問を巡り、議論が交わされるが、結局、答えの向かう先は翻訳に対する愛なのだ。
Posted by
一部は東大の学生の前で、二部は翻訳の専門学校生の前で、そして三部は中堅の翻訳家・研究者の前で二人が翻訳に着いて語ったことが収録されている。 言葉を訳す。文章を訳す。雰囲気、世界観を訳す。 どう訳すかの選択から翻訳がはじまるのだと思った。 村上春樹と柴田元幸がそれぞれに、カーヴ...
一部は東大の学生の前で、二部は翻訳の専門学校生の前で、そして三部は中堅の翻訳家・研究者の前で二人が翻訳に着いて語ったことが収録されている。 言葉を訳す。文章を訳す。雰囲気、世界観を訳す。 どう訳すかの選択から翻訳がはじまるのだと思った。 村上春樹と柴田元幸がそれぞれに、カーヴァーとオースターの短編小説を訳し、そのちがいを読み比べる第三部が面白かった。 本来村上春樹が訳しているはずのカーヴァーの作品でさえ、私には柴田訳の方が読みやすかった。 もともと村上春樹は英文で書かれた小説を読んで自分の文体を作ってきたのだそうだ。 だから彼の小説は、脳内では英文で構成されているものを、書くことによって日本語として自然なものに翻訳されているようなものなのだろう。 思考の枠組みが英語的で、文章が極めて日本的。 これが村上春樹の文章なのだということが、ここにきて理解できた。 計算して計算して、頭で書かれた文章なのである。 対して柴田元幸は、この時主人公はどのように思ったのか?など、登場人物や作者に思いを寄せることによって、心の中から湧いて出てくる文体らしいのだ。 もしかして、北島マヤ? じゃあ、村上春樹が亜弓さん? 村上春樹は文体とはリズムだと言っているが、そのリズムとは音ではなく、文章を読んだときの、目のリズムなのだそうで、訳した文章のリズムを確認するために音読することはないらしい。 柴田元幸は、口を動かし手を動かしながら、文章のリズムを作っていくというのだから、翻訳の仕方などは人それぞれなのだ。 正しい翻訳の仕方なんてない。誤訳はあるが。 いくら美しい日本語だといっても、普段使っていない身についていない日本語なら使わない方がいいと二人は言う。 確かに読んでいても、言葉が浮いているな~と思うことがある。 そういうことだったのか。 翻訳の賞味期限について。 同時代性を表現するのに流行りの言葉を使うと、すぐに言葉が色あせていくことになる。 逆に当時は一般的ではなかったので敢えて訳語を使用したところ、今では直訳の方が伝わることもある。 フランス旅行団→ツール・ド・フランス 新しいバランスのスニーカー→ニューバランスのスニーカー 読む方はあっさりと読み流してしまうようなことを、実にいろいろ考えながら訳してくれていることがわかり、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも、よい作品をたくさん日本語に訳してください。
Posted by
翻訳物を多く読む訳でなく、著者に思い入れがある訳でもなく、なのに何故か気になり手にとり気になり読み始めてみると面白い。グイグイ引き込まれながら読みました。 翻訳とはどういうことかを、まずは大学のワークショップの学生の前で、次に翻訳家を目指す若者の前で、そして同じ短編小説をそれぞれ...
翻訳物を多く読む訳でなく、著者に思い入れがある訳でもなく、なのに何故か気になり手にとり気になり読み始めてみると面白い。グイグイ引き込まれながら読みました。 翻訳とはどういうことかを、まずは大学のワークショップの学生の前で、次に翻訳家を目指す若者の前で、そして同じ短編小説をそれぞれが翻訳した作品を挟んで若き翻訳家の前で質問に答える形で示していく。 それぞれの立場も違えば取り組み方も変わる。しかし翻訳という行為そのものを楽しんでいる様子はふたりから溢れています。そこに強く大きく引き込まれたのでしょう。
Posted by