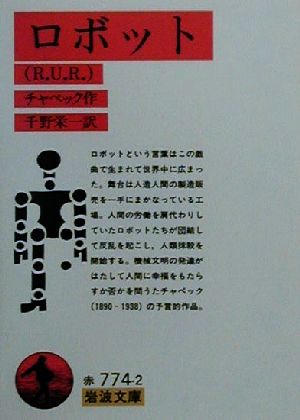ロボット の商品レビュー
全編を通じて生命とは何かを繰り返し問うている。すごく真面目なストーリー。 これが世界初のロボットかー、感動。カレル・チャペックいい仕事してます。 最初からロボットによる終末論が描いた慧眼に畏れ入る。 この作品なら、人類のロボットもののお初はこの作品です、と宇宙人に対して自信を持っ...
全編を通じて生命とは何かを繰り返し問うている。すごく真面目なストーリー。 これが世界初のロボットかー、感動。カレル・チャペックいい仕事してます。 最初からロボットによる終末論が描いた慧眼に畏れ入る。 この作品なら、人類のロボットもののお初はこの作品です、と宇宙人に対して自信を持って紹介できる(意味不明?)。 人類の至宝と言って過言ではないでしょう。 戯曲としては、戦艦や、ロボット軍団の侵攻などは表現が難しそう。それに科白の表現が地味。あまり戯曲向きではないような。 ストーリーも重いので、本で読みたいところ 挿入されている写真がマジで怖い。ますますわざわざ演じなくても、と思える。 SFとしては、フランケンシュタイン、モロー博士の島と同レベル。ぐにゃぐにゃこねまわして生体組織を作ります。 ただし、ストーリー上、どうしてこうなった?という疑問は多く、作品の完成度は決して高くない。 活動には痛覚が必要、などの洞察と示唆に富んでいるので、細かいところでも楽しめる。
Posted by
知ってはいても、読んだことが無い。 そういう本はたくさんある。 この本は、そうした本の1冊。 「ロボット」という言葉を広めた本でもある。 でも、この本のロボットは機械的なそれではなく、もっとバイオ的なものとなっている。 大量のロボットが生産され、人間は働かなくて済むようになる。...
知ってはいても、読んだことが無い。 そういう本はたくさんある。 この本は、そうした本の1冊。 「ロボット」という言葉を広めた本でもある。 でも、この本のロボットは機械的なそれではなく、もっとバイオ的なものとなっている。 大量のロボットが生産され、人間は働かなくて済むようになる。しかし、それと引き換えに出生率が低下し、子どもがまったく生まれない社会になってしまう。 そして、ついにロボットが反乱を起こし、人間は一人を残し死に絶える。しかし、ロボットはロボットを生産する術を持っていなかった… 1920年に書かれたとは思えない進んだ内容。古典として残るには理由があるのだなと感じた。戯曲形式であり、舞台で上演されていたとのこと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
機械仕掛けではなく、血と肉で形作られた人造人間が本作におけるロボットである。人間との姿の差異は非常に少なく、ロボットの人道的解放を説きに来たヒロイン/ヘレンも見分けることが全く出来なかった。人間との違いは魂を持たないこと。そして子供を生んだり、同朋を生産することが出来ないこと等だが、それらは大きな違いに感じられた。しかし研究が進むことで魂さえ宿ったロボットが誕生しだす。人間に大きく近づいたロボットたちはもうひとつの問題の解決に乗り出す。つまりロボットを製造する工場の制圧に動き出したのだ。 私がおもしろいと思ったのは、ロボットが人間に、人間がロボットに近づいていく過程。 意志を持たないロボットには望みなどなかった。人権団体や聖職者などが何を言っても意に介さず、主の指示する労働にだけ意欲を示す。理想的な労働力としてのロボット。けれど自己保存のために痛みを感じる機能が付けられると、自分たちの行動に疑問を持ち始める。自分たちはどうありたいのか? ヒロインのヘレンを自分のモノとしようとせず、仲間たちで囲んで日々を安穏と暮らす研究者たちの姿には生物としての生存本能を全く感じない。同じように世界の人々も生きる努力を必要としなくなり、ゆっくりと種の破滅が近づいてくる。出生率は低下し、ロボット同様に自身の種を増やすことができなくなる。暮らしは優雅でも、向上心の生まれない中では自分たちはどうありたいのか見えてこなくなる。 人とロボットの立場が逆転するのは必然だった。 時に曖昧に、時に明確に描かれる人間とロボットの差異は私たちの日々の生活にも当てはまる。著者チャッペクが描いた未来の姿は現代の本質をついていて考えるべきことが多い。これが100年以上前に書かれたものだとすると、人間の本質は全く進歩しておらず、悪く悪く堕ちていっているのではないかと思わされる。 原点にして頂点の傑作。
Posted by
言うまでもなくSF文学で最も有名な戯曲作品の一つです。10年以上前に,高校の現代文で筒井康隆を読んだときに先生が紹介していたのが本書でした。そのことを思い出し,少し懐かしい気持ちで表紙を開きました。 題名になっている「ロボット」と名づけられた存在は,現代の多くの人々が想像するであ...
言うまでもなくSF文学で最も有名な戯曲作品の一つです。10年以上前に,高校の現代文で筒井康隆を読んだときに先生が紹介していたのが本書でした。そのことを思い出し,少し懐かしい気持ちで表紙を開きました。 題名になっている「ロボット」と名づけられた存在は,現代の多くの人々が想像するであろう「からくり」や「マシン」ではなく,皮膚や血管,臓器,脳までを化学的に合成し組み立てた「人口生命」のような存在です。「ロボット=機械」という意識があったためか,序章で語られる開発過程の描写には,そのあまりのギャップにかなり衝撃を受けました。その記述は,一歩間違えば「グロテスク」と取られかねないような内容を語る科白であり,危うい印象を感じさせます。 私の印象では本書は,科学技術の行きすぎを批判する文脈で引き合いに出されているような気がしますが,本書のテーマは果たして本当にそんなところにあったでしょうか。本書には「科学」という語はほとんど登場しません。その代わり「生産」「速さ」「時間に正確」「労働」…そんな単語がしばしば登場します。そしてR.U.R.社の社員たちが頻繁に口にする「進歩」。人間を労働から解放することと生産を究極的に効率化することとを,同時に実現する試みとして造ったロボットによって人間が滅ぼされてしまうという2幕までの物語が伝えたかったのは,資本主義と共産主義の両方に対する強烈な皮肉と風刺だったのではないかと,そんなことを考えてしまいました。 どこかでちらりと聞いた話では,英語圏ではこの2幕までしか紹介されなかったため,ロボットに「人間に敵対する恐ろしい存在」というイメージがついてしまったのだとか。しかし3幕を読むと,その印象はがらりと変わります。本書は,人間の最後の一人となった人物が「愛」に「希望」を見出し「信仰」を告白するというなんともキリスト教的な終わり方をしますが,これをどう感じるかは判断の分かれるところだと思います。が,私としては素直に「人間『性』への賛歌」として受け取っておきたいと思いました。千野栄一訳。 (2010年8月入手・2011年9月読了)
Posted by
ロボットの反乱をキリスト教的な視点から描いている。 おもしろいけど、戯曲だからどうしても小説だと表現の限度があると思う・・・。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
11.04.02読了。ロボット開発をし後に地球がロボットに支配されてしまうって話。1920年代、しかも舞台はチェコなのでロボットとは労働代理人として考えて読んだほうがよい。倫理的要素も含む考えられる本。ただ描写が微妙。くどい。
Posted by
チェコの有名な作家、カレル・チャペックの代表作なのに読んだことがなかったので読んでみました。 ロボットの語源となったお話なのですが、一般的にロボットという言葉からイメージする機械的なものではなく、人造人間のようなものなのに驚きました。 内容もおもしろく、あっという間に読了しました...
チェコの有名な作家、カレル・チャペックの代表作なのに読んだことがなかったので読んでみました。 ロボットの語源となったお話なのですが、一般的にロボットという言葉からイメージする機械的なものではなく、人造人間のようなものなのに驚きました。 内容もおもしろく、あっという間に読了しました。機械に対してもそうですが、これから遺伝子などの研究が進んでいくと生命倫理という意味でも本当にこの戯曲のような状況が起こってしまうのではないかな、とちょっと怖くなりました。地球に対する「神」のような人間の振る舞いへの大きな警告のような気がします。 ラストは心温まる展開で、とても優しい気持ちになれました。
Posted by
ロボット。 現在では日常的なものになりつつあるこの言葉は、チェコ語で「賦役」を意味するrobotaから生み出された(とのことである。) つまり、ロボットの存在意義とは労働することなのだ。 ロボットと言われて思いつくのは主に電子制御で動く機械だが、この戯曲ではロボットとは人間と同...
ロボット。 現在では日常的なものになりつつあるこの言葉は、チェコ語で「賦役」を意味するrobotaから生み出された(とのことである。) つまり、ロボットの存在意義とは労働することなのだ。 ロボットと言われて思いつくのは主に電子制御で動く機械だが、この戯曲ではロボットとは人間と同じ材質で作られた人造生命のことである。 ロボットは繁殖手段を持たない。 新たなロボットを生みだす神秘は人間が握っている。 ロボットは死や苦痛を恐れず、ゆえに他者を思いやるということがない。 ただ命令通り人間に尽くし、ありとあらゆる労役を肩代わりする。 だが問題があった。 人間は労働から解放された。 しかし、同時に新たな人間が生まれなくなったのである。 これが自らの手による生産を必要としなくなった種の末路なのだろうか? 人間は減り続け、ロボットは増え続ける。 心を持たず人間に服従するようロボットがプログラムされていたことによって保たれていた平和は、人間の優しさによって破られる。 この本は、労働観等キリスト教的な要素を含みつつも、人造人間を人に反抗する禁忌として恐れる、所謂フランケンシュタインシンドロームとは異質である。 むしろそこには、ロボットを人間を追い込むものとして排斥するのではなく、ロボットを通して人間の存在意義を問い直そうという姿勢が見て取れる。 労働から疎外された人間はなぜ繁殖しなくなったのか? 愛を持たないロボットはなぜロボットを再生産できないのか? ありとあらゆる人工生命が人間と同じレベルの知能を獲得した暁に抱えるであろう問題とその未来は、チャペックによってロボットと言う言葉が生みだされた瞬間からすでに予見されていた。 SFは常に現実の先を行く。 その先見は恐るべきものがある。
Posted by
サイボーグに近い。アイ・ロボットとは違ったロボット感。 1921年のこの時代にロボットという言葉を作り出し、 人間との関係を描いたこの作品は、歴史的にも興味深い。
Posted by
数十年ぶりの再読だけど「こんなに面白かったっけ」というのが印象。 チャペックのナンセンス童話(『長い長いお医者さんの話』)を再読したのをきっかけに購入。中学時代に読んでいたんだけど、とうに本は紛失し、今回改めて買ったもの。 「ロボット」の語が生まれたので有名な作品で、「予言的...
数十年ぶりの再読だけど「こんなに面白かったっけ」というのが印象。 チャペックのナンセンス童話(『長い長いお医者さんの話』)を再読したのをきっかけに購入。中学時代に読んでいたんだけど、とうに本は紛失し、今回改めて買ったもの。 「ロボット」の語が生まれたので有名な作品で、「予言的作品」だとか「歴史的作品」なんてことが言われる。だけどそうした「評判」がなくても十分楽しめる作品。 戯曲形式のもので(ぼくはこの形式が苦手)、筋としてはありきたりのもの(今にして思えば)。ただそれぞれの登場人物がうまく書き分けられていて、ストーリー以外の部分も十分に楽しい。 前述の童話の際のような「関節外し的ナンセンスギャグ」はないけれど、ユーモアはあちこちにある。最初の方の「人間を十年もかけて作るなんてナンセンス」というのを見ただけで嬉しくもなってしまった。
Posted by