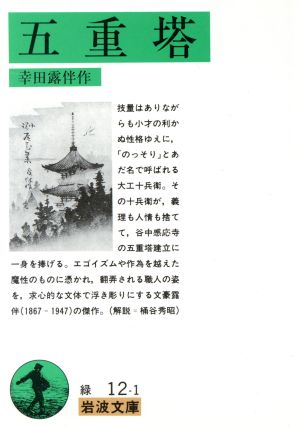五重塔 の商品レビュー
建築家の安藤忠雄さんが何かの本で触れていたのだが、最近の若い所員は全く本を読まないので、あえて事務所で働く人のために読書の時間を強制的に設けている。必読のテキストは幸田露伴の五重塔とのこと。 なるほど、現代の建築に携わる人にとって仕事に取り組む際の揺るぎない指針にふれるようなも...
建築家の安藤忠雄さんが何かの本で触れていたのだが、最近の若い所員は全く本を読まないので、あえて事務所で働く人のために読書の時間を強制的に設けている。必読のテキストは幸田露伴の五重塔とのこと。 なるほど、現代の建築に携わる人にとって仕事に取り組む際の揺るぎない指針にふれるようなものが書かれているかと思いきや、まあとにかく冒頭から読みづらい。 もはや辞書なしでは読めない旧漢字に古い言い回し、目にすることすら少なくなった踊り字のオンパレードで、おまけに読点でダラダラと繋ぐ口上のような文体はゴツゴツしていて肝心の話が全く頭に入ってこない。 ただ単に古い本を読める教養がないだけかもしれませんが、作者の職人(大工)に対する過剰な理想と幻想も手伝ってか自分の文章に酔っている印象もあり、何度も放り投げてはけっきょく義務感だけで読み終えたけれど、小説としてはどうなんだろう。 この時代の文化資料として読むのであれば、ありではないでしょうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読みにくいったらありゃしない 内容は面白い!面白いんだけど、、、本当に文語体苦手すぎて(舞姫とかも読めない笑) 主人公のエゴは何かに取り憑かれた感じがあり、狂気を感じた。
Posted by
坪内逍遥や二葉亭四迷を日本近代文学の嚆矢とするならば、次に来るのは明治20年代、紅露時代とも称された尾崎紅葉及び幸田露伴の名前が挙がる。私も近代文学に漠然とした興味があり、坪内逍遥やら二葉亭四迷の小説を読んではいたが、尾崎紅葉も幸田露伴も読んでいなかった。明治時代の小説は読み辛...
坪内逍遥や二葉亭四迷を日本近代文学の嚆矢とするならば、次に来るのは明治20年代、紅露時代とも称された尾崎紅葉及び幸田露伴の名前が挙がる。私も近代文学に漠然とした興味があり、坪内逍遥やら二葉亭四迷の小説を読んではいたが、尾崎紅葉も幸田露伴も読んでいなかった。明治時代の小説は読み辛いからだ。大正時代というと谷崎潤一郎や武者小路実篤など、比較的読みやすいイメージがあるのだが、まだまだ文語の抜けきらない明治期の文体は、近代文学の奥深く、容易に立ち入らせてはくれない魔窟の様相を呈する。まして『金色夜叉』『五重塔』という表題からは、四角四面な印象を受け、難しいだろうと避けていた。 それでも何とか読むぞと謎の意気込みで、とりあえず薄いし読めるだろうと買ったのが、この『五重塔』。 読み始めるとストーリーも明快だし登場人物も分かりやすく、文章はもちろん読み辛いが勢いもあり、結構楽しめた。 技術には長けているけど愚鈍に見える大工の十兵衛が、既に能力実績人望アリの完璧人間である源太が建立することが決まっていた五重塔を、自分に造らせてほしいと懇願する。ドラえもんの、のび太と出木杉みたいな感じ。源太(出木杉)は十兵衛(のび太)の熱意もあり、一緒に造ろうというのだが、十兵衛はこれに否という。それならお譲りしますと。十兵衛を主担当とするといっても、それも否。源太は大人の対応で十兵衛一人で造ることを容認し、今まで集めた図面やら何やらを提供してやるという親切心を見せるが、十兵衛はそれすら拒んでしまう。 譲ってもらったくせにその後の善意まで蔑ろにするさまは、私が源太の立場だったら(そもそも自分に十兵衛に譲るだけの心の広さがあるか疑問だが)確実にブチギレだろうと思う。それくらい、まるで何かに取り憑かれているかのような、五重塔に対する十兵衛の執念。職人気質ともちょっと違う。まるで人智を超越した何かに操られるかのようだ。 何をも顧みず一つのものに打ち込む様は、サン=テグジュペリ『夜間飛行』やジブリ映画『風立ちぬ』などで触れた。格好いいと思う気持ち、非情な様に対する複雑な気持ち、自分がそもそもそういった葛藤を抱くことがないという安心あるいは空虚な気持ちを味わった。 だが、この小説を読んで感じたのは、激しい熱意の根源が、自分の外側にあるのではという違和感。何だか霊的なものがどうといったオカルトな話をしたいわけではないのだが。職人として生まれた自分の、世界に対する責務とでも言ったらいいだろうか?
Posted by
訳が古く読みづらい。 にも関わらず、引き込まれる文体。 魂の職人。 東洋版スティーヴ・ジョブス。 何よりも良いものを、後世に遺るものをつくる。 その常軌を逸した姿勢にあっぱれ。
Posted by
五重塔 (和書)2011年10月19日 19:34 2001 岩波書店 幸田 露伴 シーゲルこと飯島先生がお勧めしていた本です。多分全集で読んだらちんぷんかんぷんだっただろう。この岩波文庫版は全てにふりがなが振ってある。吃驚したが、手間が省けて良かった。 建築に関しては必読...
五重塔 (和書)2011年10月19日 19:34 2001 岩波書店 幸田 露伴 シーゲルこと飯島先生がお勧めしていた本です。多分全集で読んだらちんぷんかんぷんだっただろう。この岩波文庫版は全てにふりがなが振ってある。吃驚したが、手間が省けて良かった。 建築に関しては必読書だというので読んでみました。 建築関係の小説だったら坂口安吾の「夜長姫と耳男」がかなりお気に入りだよ。
Posted by
教科書に出てくる幸田露伴『五重塔』 内容は十分知っている、はず 『五重塔』、教科書の場面は 嵐の中、作りかけの五重塔で 大工十兵衛がすっくと立って、夜叉のように守り通す が強く残っている いやいやそれはわたしの理解不完全 読み不足、ポイントはそこにない 技術はあるのに...
教科書に出てくる幸田露伴『五重塔』 内容は十分知っている、はず 『五重塔』、教科書の場面は 嵐の中、作りかけの五重塔で 大工十兵衛がすっくと立って、夜叉のように守り通す が強く残っている いやいやそれはわたしの理解不完全 読み不足、ポイントはそこにない 技術はあるのに小才のきかないのっそり大工十兵衛が 力量世慣れすぐれている親方・師匠の源太を押しのけて なんとしても五重塔の塔を棟梁になって作る権利を得たかった 義理も人情もへったくれもない、エゴイズムの そのすさまじい、ごり押しの場面はサディスティックでもあり 願いかなって塔を作り出していく場面はマゾヒスティックでもあるのである 文豪幸田露伴さんの文学性に不謹慎かもしれないけども
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
安藤忠雄さんの本で薦められたので読んでみた。 十兵衛の執念が嵐に乗り移った描写は圧巻。ただ、自分にはこの昔の文体は読みにくさが半端なく、全て理解できないのがかなしい。。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
教科書にも載っている文豪による代表作。文語体で記されているが、文庫本で100ページあまりしかないので読みやすい。一読してまず感じたのは、まるで紙芝居のような作品であるということ。起承転結がハッキリした展開といい、個性的なセリフの掛け合いといい、「読む」というよりは「語る」といったほうがしっくりくる文章だし、名高い暴風雨のシーンも、まるで情景が眼に浮かぶようである。内容は、「のつそり」こと大工・十兵衞が、谷中・感應寺に五重塔が建立されると聞き、師・源太と激論の末にその仕事を勝ち取り、その後紆余曲折ありつつも、一心不乱につくりつづけて完成させるという話である。十兵衞の愚直に仕事に取り組む姿勢が、ただただ美しい。いろいろと衝突してしまうのも、すべては仕事に真剣すぎるゆえ。「のつそり」と呼ばれているほどなので、十兵衞はけっして立派な技術をもった職人でもないし、どちらかといえば醜い存在として書かれている。それでもやはり美しい。「美しい」という言葉がもつ真の意味を、十兵衛はただひたすら大工仕事だけをもって示しているのである。
Posted by
幸田露伴の本は初めて読んだ。 明治に書かれた小説なので、始めは読むのにやや苦労したが、すぐに引き込まれた。 なんて美しい文体なんだろう。これがわずか24歳で書かれたものとは驚愕だ。 ストーリーはwikiればすぐに出てくるので割愛する。 私には、これが主人公のエゴイズムによる執念と...
幸田露伴の本は初めて読んだ。 明治に書かれた小説なので、始めは読むのにやや苦労したが、すぐに引き込まれた。 なんて美しい文体なんだろう。これがわずか24歳で書かれたものとは驚愕だ。 ストーリーはwikiればすぐに出てくるので割愛する。 私には、これが主人公のエゴイズムによる執念とは思えない、一種の魔性だ。
Posted by
日本文学史に燦然と輝く名作。 反面、文語文が難しすぎるとの前評判からやや身構えてましたが、鴎外の「舞姫」や「うたかたの記」などで慣れていたためかさほど難しさは感じず。 ただただ露伴の凄み圧倒されるばかりでした。
Posted by