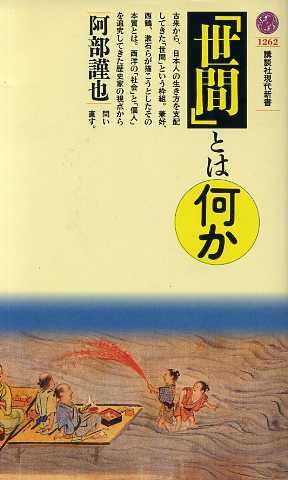「世間」とは何か の商品レビュー
古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 目次情報 第1章 「世間」はどのように捉えられてきたのか 第2章 隠者兼好の「世間...
古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 目次情報 第1章 「世間」はどのように捉えられてきたのか 第2章 隠者兼好の「世間」 第3章 真宗教団における「世間」―親鸞とその弟子達 第4章 「色」と「金」の世の中―西鶴への視座 第5章 なぜ漱石は読み継がれてきたのか―明治以降の「世間」 と「個人」 第6章 荷風と光晴のヨーロッパ
Posted by
日本人特有の「世間」を考察した本。 歌、仏教、漱石、藤村などから様々な時代の「世間」を捉えている文章は面白い。 色々あって大学のゼミで読んだ本だったけれど、文芸思潮や社会学をかじるのには良いかも。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
昔からあるようでなかった、日本特有の人間関係「世間」について考察した本。 近代西洋の自由で平等な「個人」を前提とする「社会」が普遍的で抽象的なのに対し、日本独特の「世間」は具体的、その外にいる者に対し排他的、長幼の序・互酬の原理が根付いている、情理や感性と関係が深い、無情、世知辛い、ままならないものと捉えられていた、といった特徴を持っている。 そんな「世間」の共通項は万葉の時代から続いているとされる。そして、第一章以降で、日本の奈良~平安時代、鎌倉時代、江戸時代、明治時代において、「世間」がどう捉えられていたかが述べられている。 良い意味で情緒的、悪い意味で閉鎖的な「ムラ的」であるとされる日本だが、人々が世知辛さを感じながらも、そんなムラ的な「世間」が続いたのは、彼らが「世間」に生活の指針を与えていたからなのだと思った。 我々は世間をなくすのではなく、世間とどう向き合っていくかを考えていく必要があるのだろう。なかなか面白く読めた。
Posted by
日本人特有の人付き合い、世間について、兼好、親鸞、西鶴、漱石、荷風らの著作から、その時代においての世間という言葉の概念の変遷を考察している。
Posted by
阿部謹也連読。 最近ソーシャルメディアが騒がれているので、ソーシャルとは何かを自分なりに考える為に再読した。 世間とsocietyの違いが「実名」と「匿名」の違いに繋がるのではないかという、自分なりの気づきがあった。 だが、何よりも読んでて感じたのは、著者の「孤独」。別に著者の気...
阿部謹也連読。 最近ソーシャルメディアが騒がれているので、ソーシャルとは何かを自分なりに考える為に再読した。 世間とsocietyの違いが「実名」と「匿名」の違いに繋がるのではないかという、自分なりの気づきがあった。 だが、何よりも読んでて感じたのは、著者の「孤独」。別に著者の気持ちが書かれているわけではないが、金子光晴の引用は、著者の気持ちを代弁しているようで、響いてきた。考えすぎかもしれないけど。
Posted by
[ 内容 ] 古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。 兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。 西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 [ 目次 ] 第1章 「世間」はどのように捉えられてきたのか 第2章 隠者兼好の「世間」 ...
[ 内容 ] 古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。 兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。 西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 [ 目次 ] 第1章 「世間」はどのように捉えられてきたのか 第2章 隠者兼好の「世間」 第3章 真宗教団における「世間」―親鸞とその弟子達 第4章 「色」と「金」の世の中―西鶴への視座 第5章 なぜ漱石は読み継がれてきたのか―明治以降の「世間」と「個人」 第6章 荷風と光晴のヨーロッパ [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
「世間」を学術的な検討の俎上に挙げたという意味で名著。まえがきは読み応えがあるが、本論はやや羅列的で退屈ではある。
Posted by
日本の歴史から、「世間」の存在を見出していく本。 ・日本人は長い間、世間を基準としていた。 ・日本人は他の人間との関係に基準を置いている。 ・自分の意見を述べるために「世の人」を引き出す。 ・吉田兼好について知りたくなった。 ・漱石は、日本人が個性を大切にせず、常に集団の中...
日本の歴史から、「世間」の存在を見出していく本。 ・日本人は長い間、世間を基準としていた。 ・日本人は他の人間との関係に基準を置いている。 ・自分の意見を述べるために「世の人」を引き出す。 ・吉田兼好について知りたくなった。 ・漱石は、日本人が個性を大切にせず、常に集団の中で行動している点を不満に思っていたと考えられるが、だからと言って欧米の賛美者になっていたわけではない。 ・世間や世の中のさまざまな掟に縛られている個々の人間としては、自分なりの生き方をしたいと思っても容易にできない。 ・よき人 深く立ち入らないさまをしている人 知っていることでも物知り顔に語らない人 よく知っていることでも口重く、聞かれない限り話さない人
Posted by
<本の紹介> 古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 「世間」とか「社会」とかって言葉の違いをあんまり意識したことはなかった。 でも、話し言葉では「...
<本の紹介> 古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。兼好、西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。西洋の「社会」と「個人」を追究してきた歴史家の視点から問い直す。 「世間」とか「社会」とかって言葉の違いをあんまり意識したことはなかった。 でも、話し言葉では「渡る世間に」とか「世間は狭いね」とか、「世間」を使うことが多いように感じる。 逆に、「社会」って言葉は文字として見ることが多い気が。教科書とか、新聞とか。 おもしろいなーと思いました。 自分を日本人の代表だとは思わないけど、日本に生まれてずっと日本に住んできて、やっぱ見える範囲は大きい社会じゃない。もっと狭い、自分と関わりのある人たちの範囲を自分の社会として見てるんだろうなって思いました。 多分、それぞれの人たちのその範囲を「世間」って言って大きくずれてないと思うし、自分が今までに大事にしてきた人たちも、これから大事にしていきたい人たちも、この「世間」の中に入る人たちだったりする。 本の中では、同じ電車に乗ってる人でも自分と関わりのない人に迷惑がかかってもそこまで気が回らない人も、自分と一緒に乗ってる人に同じことされると気分を害したりして、そこに境界線があるんじゃないかって書き方をしてて、「たしかに」とか思っちゃいました。 その「自分の世間」の範囲を広げていければって思ってもいるし、年々広がっていってるような気もするけど、だからと言って世界中の人たちとつながろうとまでは思ってない。そこまで大きな社会で生きているわけじゃない。 ただ、世界の人たちは「6次の隔たり」でつながっているわけだから、自分が自分の周りにいる人たちと楽しく笑って過ごしていくことを続けていければ、それを受け取った誰かがまた他の誰かにつなげていければ、いつか世界の裏側の人にも届くんだ。だから、自分の世間を大事にしていこう、と改めて思いました。 あと、日本特有の文化として、こんなこともあるんだそうです。 ・世間を騒がせたことをお詫びしたい、という言葉は 英語やドイツ語に翻訳することができない。 ・宝くじにあたると日本では世間をはばかって隠したりするが、 アメリカでは新聞に堂々と顔写真がでる。 個人的には、そんな日本の文化の方が好きです。 周りにいる人たちのおかげで、自分も活きる。 自分がいることで、周りにいる人たちが活きていく。 自分が今いるのは、両親はもちろんたくさんの人たちのお世話になってきたからだ。 だから、その人たちに自分にできるだけのことを返せる人になりたいです。 そして、もらった分は自分たちだけのものにせず、自分の同世代や後輩たちに確かにつないでいけるといいなと思います。 この本が明らかにしたかったことは全然違うのかもしれないけど、周りの人たちの存在とか、その人たちとの付き合い方について考えるいいきっかけになった本でした。
Posted by
「世間」に関して分析的に考えるというよりも、世間に囲まれて生きている中でなんとか世間を対象化しようと試みた人たちの文学作品を通して、世間を捉えてみようという試み。 なので、最初に出てくる世間の定義(個人個人の関係の環)や世間の掟(長幼の序と贈与/互酬の原理)がその作品の分析から引...
「世間」に関して分析的に考えるというよりも、世間に囲まれて生きている中でなんとか世間を対象化しようと試みた人たちの文学作品を通して、世間を捉えてみようという試み。 なので、最初に出てくる世間の定義(個人個人の関係の環)や世間の掟(長幼の序と贈与/互酬の原理)がその作品の分析から引き出されてくる訳ではない。 作品の解説は、万葉集から始まり、徒然草、親鸞の思想、西鶴の諸作品、夏目漱石、永井荷風、金子光晴に至る。
Posted by