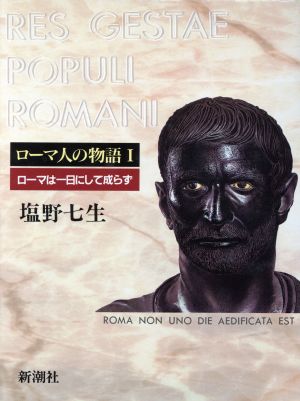ローマ人の物語(1) の商品レビュー
おもしろくて読みやすい。 要約しても仕方ないので、印象に残ったことを書く。 ローマ人と比べて、現代日本人の政治に対する意識は低いな、と思った。ローマ人にとっては、政治が直接、市民の利害にかかっていたのだろう。また、市民の属性もさまざまで、平民出身、貴族出身、商業重視、農業重視...
おもしろくて読みやすい。 要約しても仕方ないので、印象に残ったことを書く。 ローマ人と比べて、現代日本人の政治に対する意識は低いな、と思った。ローマ人にとっては、政治が直接、市民の利害にかかっていたのだろう。また、市民の属性もさまざまで、平民出身、貴族出身、商業重視、農業重視、などいろいろな路線が考えられた。だから、自分の属性、考え方をもとに、どのリーダーを選べばもっとも自分の考えを政治に反映できるか、という「利己主義」を利用して政治が成り立っていた。一方、いまの日本は、自分の考えを政治に反映させようという意識はない。つまり、みんな同じ考え方(のはず)だから、誰にとってもいい政治をする人をリーダーにしよう、そして最良のリーダーを選ぶのは自分である必要はない、他人に任せよう、というような。考え方が違う人がものを決めるからこそ必要な民主制なのだ。ローマの例をみていて、そのような考え方は違うのかもしれない、と思った(民主制、の生まれからして)。だいぶ本の内容からは逸脱したが、このようなことを考えた。
Posted by
知力では、ギリシア人に劣り、 体力では、ゲルトやゲルマンの人々に劣り、 技術力では、エトルリア人に劣り、 経済力ではカルタゴ人に劣るのが、自分たちローマ人であると、・・・ローマ人自らが認めた板。 それなのに、なぜローマ人だけが、あれほどの大をなすことができたのか。一大文明圏を築き...
知力では、ギリシア人に劣り、 体力では、ゲルトやゲルマンの人々に劣り、 技術力では、エトルリア人に劣り、 経済力ではカルタゴ人に劣るのが、自分たちローマ人であると、・・・ローマ人自らが認めた板。 それなのに、なぜローマ人だけが、あれほどの大をなすことができたのか。一大文明圏を築き上げ、それを長期に渡って維持することができたのか。 民衆側の権利獲得へのスタートは、法の成分かを求めることからはじまる場合が多い。
Posted by
いよいよこの超大作に手を出すことにした。歴史の教科書程は固くないにしても説明文のみなので果たして最後まで読みきれるか。 でも紀元前のローマやギリシアの話で、人名も地名も横文字で分かりづらいのに読んでると夢中になる瞬間もあったわけで、これはこの著者のすごい所だと思う。 今回は...
いよいよこの超大作に手を出すことにした。歴史の教科書程は固くないにしても説明文のみなので果たして最後まで読みきれるか。 でも紀元前のローマやギリシアの話で、人名も地名も横文字で分かりづらいのに読んでると夢中になる瞬間もあったわけで、これはこの著者のすごい所だと思う。 今回は紀元前700年~紀元前200年くらいが中心となっているが日本で言えば縄文~弥生の頃だが、よくもこれほど情報が残っているものだと思う。
Posted by
他民族が地続きで接していると、必ず領土問題に直面し、それが戦争に結びつく。 結果だけ見ると、戦争が政治のシステムを改変して成熟させたり、文化の交流の役割りを果たしていたのかもしれない。 今の世界で行われている戦争を、後世から見たらどうなるんだろう?
Posted by
第1巻では、紀元前753年と言われているロムルス(ローマの語源)によるローマの建国から紀元前270年のルビコン川以南のイタリア半島統一までの約500年の期間を扱っています。著者をして「後にローマが大をなす要因のほとんどは、この五百年の間に芽生えはぐくまれたのである」と言わしめてい...
第1巻では、紀元前753年と言われているロムルス(ローマの語源)によるローマの建国から紀元前270年のルビコン川以南のイタリア半島統一までの約500年の期間を扱っています。著者をして「後にローマが大をなす要因のほとんどは、この五百年の間に芽生えはぐくまれたのである」と言わしめているように、後にローマ帝国として君臨する国家の基礎がつくられたのが、この500年に相当すると言えます。体力においても、知力においても決して優れていたとは言えない民族が、どのように国を作り出し発展させていったのか?また衰退していった原因などは、およそ2000年後に生きる僕たちにも大きな示唆を与えてくれました。
Posted by
HBOのDVD、ローマを買ったので 見る前に読むか、と手に取る なるほど評判になったのが分かる 軍事以外、何者も生み出さなかったスパルタ ペルシャ軍との戦い「300」は映画になった。p125 ローマもケルト族に征服されてボコボコ 身代金を払って立ち退いてもらう 山岳民族のサム...
HBOのDVD、ローマを買ったので 見る前に読むか、と手に取る なるほど評判になったのが分かる 軍事以外、何者も生み出さなかったスパルタ ペルシャ軍との戦い「300」は映画になった。p125 ローマもケルト族に征服されてボコボコ 身代金を払って立ち退いてもらう 山岳民族のサムニウム兵にもやられる。 敗軍の将は罰されない。任務失敗の恥が罰、名誉を失うこと 負けて新戦術の導入、投げ槍取り込む ローマ連合の拡大と確立 政治体制の話と軍制の話。硬派だ。 以下は単行本のページ 20 ギリシア人、都市=港、エルトリア人=小高い岡の上に城壁、フィレンツェとか 28 ギリシア人、気軽に畝に帆をはる民族。独立心も旺盛 35 ロムルス、雷雨中に失踪。暗殺? 37 2代目ヌマ。晴耕雨読型。 44 夫婦喧嘩や寝取られ男にも神 45 巫女(ヴェスタ)。吉凶、凶も目を閉じれば効力ナシ 47 宗教=ユダヤ、哲学=ギリシャ、法=ローマ、人間の行動原理の正しさ 74 ブルータス、アホの意味 77 ブルータスの2人の子 93 ドーリア人、ギリシャ破壊。400年間、「ギリシャの中世」 102 ソロン、自作農たちを借金地獄から救済 112 スパルタ、支配と被支配がくっきり分離 115 軍務至上 116 女性も健康一番。甘味、酒、美食だめ。ダイエット。訓練も競技会も男同様に裸で行う 117 鉄貨のみ、泥棒のいないスパルタ。発言も簡潔第一 119 ギリシア史、内ゲバに特徴 136 ギリシア文化、ペリクレスの30年を中心にした200年 143 ローマ人、保守的。変化も必要なときにのみゆっくりと 176 ローマ人、模倣の民?他民族から学ぶ 188 カッサンドラ、説得すれば聞き入れられると思う人たち 208 ローマ連合、政治建築の傑作、トインビー 215 ローマ、敗者を隷属させず共同経営者にした 218 道を直線・平坦、拡幅、舗装。高速道路化した。ギリシャ人=神殿に力。ローマ人は公共施設 221 直接税は軍役で払う。「血の税」 262 前267年に自前の通貨。それまでは南伊のギリシア都市のものを使う 270 ローマ人の開放性。宗教、政治システム、他民族同化
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【後編3 歴史的同時性の時代】 同時性における復帰摂理延長時代の「ローマ帝国迫害時代」。メシヤ降臨準備時代部分にも関わる。キリスト教史をローマ帝国抜きで語ることは出来ない。はじめはキリスト教徒に対する迫害者として、のちは保護者として。コルプスクリスティアヌムという言葉は覚えておくべき。ヨーロッパ共同体の根っこにある3つの精神のことである。ギリシャの哲学、ユダヤの宗教、ローマの法。この三つの現実的精神的要素が共同体の中に根付き、世界史の中心ヨーロッパが築き上げられていく。 ローマ帝国の歴史を学ぶにはいろいろとあるが、ここでは現代的に著名な「ローマ人の物語」を取り上げたい。塩野七生の著である。小説家が書いたローマ史なので、歴史家からすればいろいろと言いたい事があるようだが、そういったことを差し引いても、ローマ史を学ぼうとするときにはこの読みやすさがアドバンテージになる。難易度を★5としたのは、その長さ(大型本で15巻、文庫本では43巻)故であって、内容は読みやすい。簡単に書いてあるということよりも、ドラマチックで非常に読ませる。 同時性のみではなく、メシヤ論、イエス路程などを学ぶ際のバックグラウンドとしても重要。著者の情熱も伝わりグッドである。 ローマ人の物語(大型本:15巻、文庫本:43巻)
Posted by
勉強にはなるんだけど、人物名が頭に入ってこない。。 そして、読みにくい。。 読み物ではなく、歴史の教科書、という感じ。 でも、一通りの歴史は頭にいれたいなぁ!
Posted by
日本では縄文時代・・・。すでに政治の仕組みを整えていた。異文化を受け入れて発展していく。そうでないものは衰退。今に通じる。
Posted by
ローマ人の考え方には、集団を如何に統率するか、企業が他社を買収したのちに如何に統合していくかは現代の経営でも学ぶことがあると思いました。 高校で学んだ世界史でのローマ史は退屈でしたが、深く知るとこんなに面白く役に立つんだ!と感じました。学校での歴史は暗記中心でしたが改める必要があ...
ローマ人の考え方には、集団を如何に統率するか、企業が他社を買収したのちに如何に統合していくかは現代の経営でも学ぶことがあると思いました。 高校で学んだ世界史でのローマ史は退屈でしたが、深く知るとこんなに面白く役に立つんだ!と感じました。学校での歴史は暗記中心でしたが改める必要がありますね。歴史のつまらない教科書読むより、この本読んだ方がいい気がします
Posted by