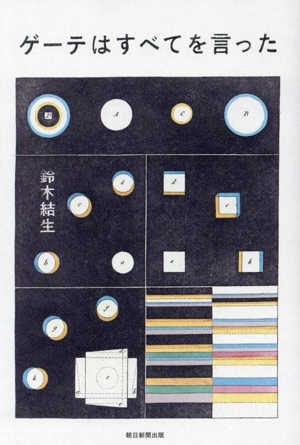- 書籍
- 書籍
ゲーテはすべてを言った
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ゲーテはすべてを言った
¥1,760
在庫あり
商品レビュー
3.4
51件のお客様レビュー
物語の起点と結末がわかりやすくて、非常に読みやすかった 読み終わった頃には点と点が繋がった感じがしてスッキリした 以下、感想 ・引用の誤用に厳しい社会への皮肉があるのかなと思った。間違った使い方をしたらすぐに指摘される。でも何もかも裏をとるのは疲れる。意図が伝われればそれでい...
物語の起点と結末がわかりやすくて、非常に読みやすかった 読み終わった頃には点と点が繋がった感じがしてスッキリした 以下、感想 ・引用の誤用に厳しい社会への皮肉があるのかなと思った。間違った使い方をしたらすぐに指摘される。でも何もかも裏をとるのは疲れる。意図が伝われればそれでいいのでは?というのを言いたいのかなと ・そして言葉の引用はただの記憶力でしかないのに無駄に権威を持ってるよねということも言いたいのかなと思った。それだけで教養人に見えるという力がある。でも、個人的には何か物事を主張するときの技術としてあっても良いのかなと思ってます ・ゲーテはあらゆることを知ろうとした人間だけど、全てを知ることは良くないこと的なニュアンスをファウストを通じて言っている認識。そして統一もゲーテに詳しくてもなお全てを知ろうとして苦悩してるのは滑稽だなと思った ・家族は初めの方はまとまってるように見えてまとまっておらず、後半で本音を曝け出すことでまとまり、愛し合おうとした。結果うまく行くようになった。まさに「愛はすべてを混淆せず、渾然となす」という感じだった。この結末は痛快だった
Posted by 
2024年下半期「芥川賞」受賞作品。 つい先日読み終えたばかりのデートピアと比較すると、全く異なる作風につき、たしかにこれは二作同時受賞もわかる気がした。 感想としては、なるほどよくできていると思いつつ、個人的にはやっぱりデートピアの良くも悪くも灰汁のようなものに毒されたあとに読...
2024年下半期「芥川賞」受賞作品。 つい先日読み終えたばかりのデートピアと比較すると、全く異なる作風につき、たしかにこれは二作同時受賞もわかる気がした。 感想としては、なるほどよくできていると思いつつ、個人的にはやっぱりデートピアの良くも悪くも灰汁のようなものに毒されたあとに読んだからか、作者への興味の部分での差を強く感じてしまった。次作は果たして手に取るかどうか。 でも、どちらも読んでいない方がいたら勧めるのは、おそらくこっち。多くの方に愛される作品ゆえの判断として。 ★3.0
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
こりゃ、やられた! と思った。とても、かなわんな、とシャッポを脱ぐというか、しっぽを巻いてと言うべきか。 近年、芥川賞でさえも、素人クサイというか、なんなら自分でも書けるんじゃないか? と思わんでもない作品が受賞することがある。でも、こいつは、ちょっと違うな、と。 でも、ストーリー展開が面白いかというと、そうではなく、きっとこれは本屋大賞は獲れないな、とかも思ったりもする。 タイトルにあるように、テーマは大文豪ゲーテだ。しかも、主人公は大学の教授で、ゲーテの研究者、そしてその一家や同僚の学者たちが登場人物。表現や会話が、やたらアカデミックとなり、著者の持つ知識のひけらかしのような文章が、かなり濃密なまでに展開され、それらを追うだけで、ずいぶん疲弊してしまう(実際、いつもより読了まで日時を要した)。図書館で借り出した本なら、早々に、テイストが合わないと放り出していたかもしれない。 それでも読み通せたのは、真面目で鼻持ちならないペダントリーの応酬にもかかわらず、どこかしら諧謔に満ち、可笑しさが滲み出ているようで、半分、これは冗談でやってるのか? 敢えてのブッキッシュな設えか? と思えるのだった。 ゲーテの作品『ファウスト』について、手塚治虫が出てくるのは分かる。たしか、未完の絶筆が『ファウスト』だったか。でも、そのクダリで『マカロニほうれん荘』が出てきたり、「白は二百色あるみたいよ」という芸能人がいるという話は、これ、バラエティ番組でのアンミカのセリフだったなと、これ、おふざけで書いてるの? と思ったり。映画の引用もあったり、卑近な例も散見されるところが面白い。 『ファウスト』そのものを、「非常に真面目な冗談」と文中、登場人物に語らせるように、本作自体が、まさに「真面目な冗談」のようだった。 教授の家族の物語で、途中で、ゲーテと邂逅する夢の世界も出てきたり、筒井康隆原作の『敵』が、今年(2025)、映画化されたが、そんなテイストも纏う。 でも、この家族、一族の関係性は、心温まるな。悪い人間関係は描かれていない。 ストーリー展開は、じつにまどろしく、動きのない場面ばかりで退屈だ(たぶん、映像化するなら、よほど工夫しないと脚本がまとまらないだろう)。 構成上の工夫は、登場人物が書いた小説であるという入れ子構造になっている点だが、最後の「後記」の登場で、あれ? なんで? と違和感と共に、そうだった! と、それを思い出し、改めて冒頭部分を読んで、あ、そうか、そういうことか!? と「果たして、娘が連れてきたのは、紙屋綴喜であった」の一文に、あらためて驚くのだった。 そうしたところに意識が及ばなくなるほど、怒涛の知識、学識、引用やメタファで押しまくる力技の凄みも感じた。 いつものように『文藝春秋』の掲載号にて。詮衡書評と合わせて読んだ。 上記の、ペダントリーやブッキッシュという語彙は、自分は普段使わない。詮衡子も、本作には使わざるを得なかったのだろう。「ペダントリー」は複数人が使用、そこから借用した。その他、似たような表現で、同様に本作を評していたことも印象的。 ちょっと、近年にない、異色の作品だったと思う。 好きか嫌いか、と問われたら、嫌いとまではいかないが、テイストではない。 でも、次回作、テーマによっては手に取るかもしれない作家さんだ。
Posted by