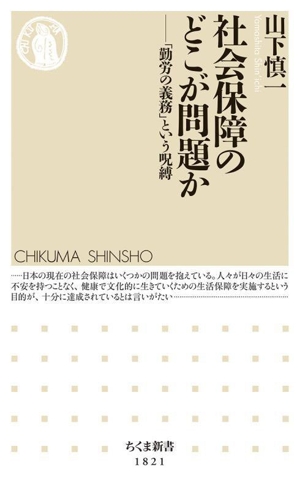- 書籍
- 新書
社会保障のどこが問題か
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
社会保障のどこが問題か
¥1,012
在庫あり
商品レビュー
3.8
5件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本の社会保障は制度が複雑。 意識がブレーキになる可能性がある=憲法27乗の勤労の義務既定が邪魔をする。 社会保険では、傷病手当金と出産手当金が国保と違う点。 雇用保険は自営業者にはない。求職者支援制度がある。 労災時は、治療費はゼロ、自営業者は健康保険だから3割負担。 労働者と自営業者の差異は大きい。 もともとは1941年の労働者年金制度が始まり。1959年に自営業者の国民年金ができた。 自営業者は、就業の形、所得の形が違うという理由で傷病手当金がない。 家族経営の農業が多く、失業を想定していない。非自発的な失業を想定しているので、雇用保険はない。 労働者中心の社会保障が確立した。 社会保障は申請しないと受けられない。時効で消滅することがある。行政に情報提供義務がない。 生活保護は、働く意思があって、働く場がない場合または足りない場合、に支給される。 職業選択の自由との兼ね合いはどうか。友禅の仕事をしたいが仕事が減ってきている場合、どう解釈するのか。 勤労の義務を果たさないと生存権や社会保障は受けられないか。職業選択の自由は問題にならない、とも考えられる。 不正受給にもそれなりの事情がある。娘の修学旅行のためのアルバイト収入をどう考えるか。 勤労の義務に対する規範意識が生活保護を批判する風潮につながっているのでは。 多くの人が好きでもない仕事をしている、という前提がある。 勤労の義務とともに権利も規定されているが、具体化されているのは労働者に向けた規定だけ。 労働者は、労働力しかもっていない。自営業者は生産手段を持っている。したがって保護すべきは労働者だけ、という前提になっている。これが今の社会実態に合っているか。 憲法は国家を名宛人にしている以上、憲法の義務規定を法的義務と解釈することは必然ではない。 戦前は、兵役に行くと教育になってしっかりした人間ができるという通念があった。それがなくなったので、勤労を義務としたほうがいい、という考え方があった。生活権を保証する以上、勤労を義務にすべき、という考え方。 近年は、労働者でありながら厚生年金に入れないため国民年金に入っている人が増えている。フリーランス、ギグワーカー、クラウドワーカー、など。 勤労の義務を道徳的義務と考えれば、働くことが社会保障の前提にならない。働き方も関係なくなる。 ドイツでは芸術家に関する社会保険制度があって、国と芸術家の生産物を利用する業界が、保険料の半分を負担している。 マイナンバーを活用すれば、生活保護に関しても給付を自動化できる。不正受給にも対応できる。
Posted by 
法制定当時と今だと自営業の生活様式がかなり変わっている。確かに。勤労の義務と生存権、この国では前者が優先されがち、ってのも言われてみれば目から鱗。 複雑な制度と人の業によって福祉から遠ざけられてしまう人が、マイナンバーとかAIとかで減るとよいよね…
Posted by 
社会保障の制度は分かりづらいなと前から思っていましたが、改めてそう思いました。 必要な人が利用できるように少しずつでいいから利用しやすくなるといいなと思います。 そのためにも、話し合いは大事だと思います。
Posted by