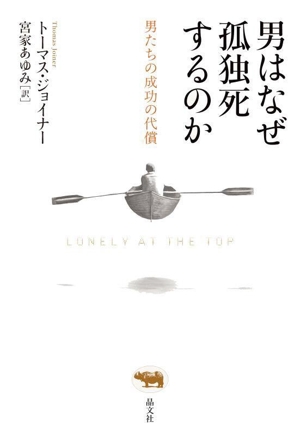

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 晶文社 |
| 発売年月日 | 2024/05/24 |
| JAN | 9784794974198 |
- 書籍
- 書籍
男はなぜ孤独死するのか
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
男はなぜ孤独死するのか
¥2,420
在庫あり
商品レビュー
3.3
22件のお客様レビュー
男性の孤独と自殺について。 規則正しい睡眠と自然に触れること。 ・人間関係の道具性 ・よそよそしく、独立性が高く、秘密主義で、甘やかされている
Posted by 
書名の強さに惹かれて図書館で手にした本ですが、逆に強さに引いてしまい、何回か1ページも読まずに返却を何回か繰り返した本です。このお正月、時間があるところで苦い薬を飲むつもりで一気読みました。案の定、今の自分の合わせ鏡になる本で胸苦しくなりました。多少、薬(?)が口から吹き出してい...
書名の強さに惹かれて図書館で手にした本ですが、逆に強さに引いてしまい、何回か1ページも読まずに返却を何回か繰り返した本です。このお正月、時間があるところで苦い薬を飲むつもりで一気読みました。案の定、今の自分の合わせ鏡になる本で胸苦しくなりました。多少、薬(?)が口から吹き出しているかもしれません。著者自身が父親の自死という過酷な体験を持っていることが本書の執筆のドライバーになっているとのことですが、そこまで過酷な体験がない「男たち」にとっても身につまされる内容なのではないでしょうか?なぜ自殺による死者というカテゴリーで男性が女性を圧倒的に上回っているのか、という疑問から始まっている本ですが、分析だけでなく対処法も超具体的に述べられています。先ず原因の分析については『甘やかされること』『「俺の邪魔をするな」という態度』『地位や金銭への過度の執着』『「頂上の孤独」の経験による助長』この4つが挙げられます。そして解決策としては「毎日、誰かに電話をかけること」「同窓会をすること」「睡眠を規則的にとること」「自然とつながること」…なるほど、同窓会すると最近ソロキャンプを始めたという友人がその話を嬉々とするパターンが多いことに合点がいきました。この本の副題は「男たちの成功の代償」ですが、同時に最近気になっている「弱者男性」という時代のキーワードも思い出しました。時代の中で蓄積されている「自尊感情」が自分の中にもあることがわかってしまうことが、この本が苦い理由です。全然違う話だけど映画『ロボット・ドリームズ』が大ヒットするのもここら辺が理由かも。あのロボットは孤独死防止ロボットだったのかも…
Posted by 
LONELY AT THE TOP: The High Cost of Men's Success https://www.shobunsha.co.jp/?p=8239
Posted by 

