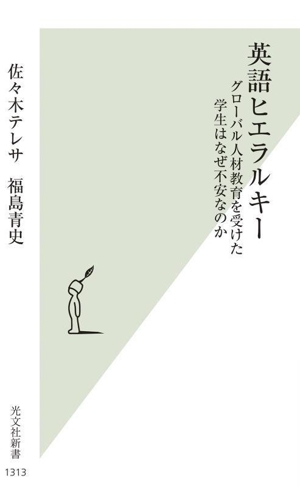

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 光文社 |
| 発売年月日 | 2024/05/15 |
| JAN | 9784334103255 |
- 書籍
- 新書
英語ヒエラルキー
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
英語ヒエラルキー
¥990
在庫あり
商品レビュー
3
5件のお客様レビュー
「~なぜ不安なのか」というタイトルに「おっ」と見覚えのようなものを感じたので読んでみた。 大学4年間がほぼ完全に英語開講で過ごすことの(どちらかと言えば)難しさ・辛い部分が卒業生の対談の中で語られている。高校で比較的英語ができる人と帰国子女とが一緒に学ぶ環境で、明確な能力差を感じ...
「~なぜ不安なのか」というタイトルに「おっ」と見覚えのようなものを感じたので読んでみた。 大学4年間がほぼ完全に英語開講で過ごすことの(どちらかと言えば)難しさ・辛い部分が卒業生の対談の中で語られている。高校で比較的英語ができる人と帰国子女とが一緒に学ぶ環境で、明確な能力差を感じてしまって英語ができないと感じる人の劣等感が強まる気持ちはけっこう分かる。 教養学部という明確に専門を定めずに入学してから学べる環境というのは、選択肢が幅広く選べるメリットがある一方で、うまく活用できないと広く浅く学ぶだけで4年間が経過してしまうことにもなる。きっかけを掴める人にはよい仕組みだけれど、掴めない人にとってはなかなか酷な面もあるのだなとは自分自身の学部時代からうっすら感じていたことかもしれない。なので、「授業をきっかけとして自分で考え、学びを深める癖をつけていった」とある卒業生が話していたことはよい試みだったと思う。 「たまに人前で英語を使って、「英語話せるんだね」と言われたあとに続く、「そんなことないです」は、決して謙遜ではない。自分は全く英語が不得意だと真剣に思っている」(p.212) これは感覚として非常によくわかる。できる人のことを知ってしまっているがための感覚だ。最低限話せれば・伝わればOKという経験を経ることがなければ、自分もその感覚に陥り続けていたかもしれない。 一方で、企業に入社してから「日本語がなんか変」となる話はどうなのかなと思ってしまう。自分の場合はすべての授業が英語ではなかったということもあって、日本語を使う機会もたくさんあったからだろうか。また、良くも悪くも同調圧力的な雰囲気が薄い会社にいるので、その意味での苦労も少なく済んでいる気がする。 あと、「グローバル人材」という言葉を無自覚・無批判に使うことへの注意はしておいた方がいいなと改めて思った。
Posted by 
「学生の生徒化」を地で行くEMI学部。「学校の授業」以外の場や学習・経験に全く言及がないのも不思議。大学の教室を一歩出ればまごうことなき日本語・日本文化の環境。大学の教室で学ぶことがすべてなのか?時間的・経験的にも異言語・異文化にさらされるのは体験のごく一部にしか過ぎないのに、こ...
「学生の生徒化」を地で行くEMI学部。「学校の授業」以外の場や学習・経験に全く言及がないのも不思議。大学の教室を一歩出ればまごうことなき日本語・日本文化の環境。大学の教室で学ぶことがすべてなのか?時間的・経験的にも異言語・異文化にさらされるのは体験のごく一部にしか過ぎないのに、このあたりの分析がまったくない。学校という制度以外で「勉強」 したり、様々な「体験」しないのか??大学の休みは長いのに??まるでこのEMI学部での体験を4年間の生活全部(留学期の1年を除く)と同一視している記述にかなり違和感を覚えた。 限定的とはいえ異言語オンリーのEMI学部で「英語」コンプレックスをこじらせたり、日本語を体系的に振り返り、強度を増した経験を積まなければ日本語に不安をもたらすことになる。これは、これまでの異文化研究・第二言語習得研究の蓄積から見れば、自明のことで特に新規性はない。 日本の会社に入って言語面を含めた「会社文化」に適応しにくいのは、この学部に限った話ではないのでは? 異言語に否応なくさらされる異文化環境ではないのに英語も日本語ができない「感想」をこじらせるのは、筆者の言うようにやはりEMIの制度の不備があることになるのかもしれない。このあたりのフォローをする機関があってしかるべきだが、「当該学部」にはないのか?「当該学部」になくても大学全体ではあるはずだ。 「当該学部」に言語教育や異文化接触、教育学の専門家があまり見当たらないのも気にかかる。取り急ぎ、アメリカの「リベラルアーツ」制度を直輸入したのだろう。直輸入するのなら、チューター制度を取り入れ、美術、音楽や運動文化の専門家も必要なはずだ。 ましてや、日本で異言語である「英語」でリベラルアーツ教育するならさらなる手厚い指導や、綿密な「高大連携」が必要だ。学習範囲がある適度決まっている高校までの英語や履修の関係で「教養」を深められてはいない「生徒」が、いきなりリベラルアーツ教育をを母語ではない異言語で施されれば、ほとんど何もわからないのは当たり前で、そういった意味では「当該学部」の「学生」は高い学費を負担しているにも関わらず、強い不満・不安を抱くのは当然だろう。 いまの日本の大学ではEMIの教育は制度的にも、人員的にも財政的にもかなり無理があるのだろう。 本書はEMI学部の問題点を江湖に問うた点では評価できるが、このボリュームの新書にする意味があったのかというと疑問符がつく。個人的には繰り返しの記述が続き読むのに苦痛を覚えた。参与観察の分析も、サンプル数をもう少し多く、かつ同質性の強い知人・友人以外にも広げられなかったのかと気になった。 「当該学部」がある大学は最近まで充実した多言語の「言語研究所」があったのに閉鎖されてしまった。英語帝国主義の軍門に下ったからだな。在野精神はどこへいったのやら。
Posted by 
自分自身が英語ができないという現実に向き合うことが、単なる語学力の優劣の域を超えてアイデンティティ崩壊や自信喪失にまで陥るという構図。それを冷笑的に「なるほど、若者の苦悩だ」ととらえると肝心なことを見失う。私見ではここまでその英語力にウェイトを置きすぎ、「グローバル人材」という概...
自分自身が英語ができないという現実に向き合うことが、単なる語学力の優劣の域を超えてアイデンティティ崩壊や自信喪失にまで陥るという構図。それを冷笑的に「なるほど、若者の苦悩だ」ととらえると肝心なことを見失う。私見ではここまでその英語力にウェイトを置きすぎ、「グローバル人材」という概念に期待をかけ過ぎている日本社会の歪みをこそ実に当事者たちの言葉を引いて生々しくあぶり出した着眼点をこそ評価したい。そして、そうした英語偏重に釘を差しぼくたちのアイデンティティと言葉の関係性にまで肉薄した本として実に侮りがたく思う
Posted by 

