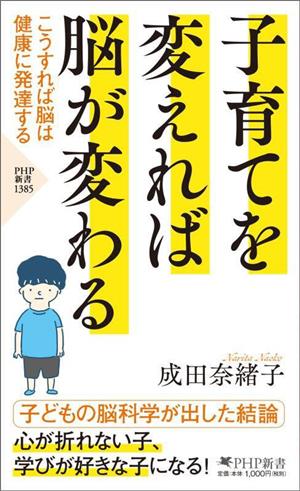- 書籍
- 新書
子育てを変えれば脳が変わる
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
子育てを変えれば脳が変わる
¥1,100
在庫あり
商品レビュー
4.4
10件のお客様レビュー
現在妻が妊娠中であり、子育てについてまずは色々な本を読んでみようと重い、書店で手に取った。 短い本でさっくり読めるが、非常にわかりやすく実践にも繋げやすい内容だった。 からだの脳、おりこうさんの脳、こころの脳と脳の発達段階別に考え方や接し方を合わせていくことが健やかな成長に必...
現在妻が妊娠中であり、子育てについてまずは色々な本を読んでみようと重い、書店で手に取った。 短い本でさっくり読めるが、非常にわかりやすく実践にも繋げやすい内容だった。 からだの脳、おりこうさんの脳、こころの脳と脳の発達段階別に考え方や接し方を合わせていくことが健やかな成長に必要だと著者は述べている。 この本で1番参考になったのは、 最初の五年間で早寝早起きができるかが勝負 ということ。 この幼少期に自分で寝起きできる力を身につけることだけできるように親が頑張ることが最重要だそうである。
Posted by 
本書は、「子育ては、脳が育つ順番に沿えばうまくいく」という著者の科学的研究結果を基に、脳育て及びその順番について解説されたものである。脳育てを、①からだの脳、②おりこうさんの脳、③こころの脳という3段階のフェーズに分け、それぞれ説明されている。土台となるからだの脳から、それ以降...
本書は、「子育ては、脳が育つ順番に沿えばうまくいく」という著者の科学的研究結果を基に、脳育て及びその順番について解説されたものである。脳育てを、①からだの脳、②おりこうさんの脳、③こころの脳という3段階のフェーズに分け、それぞれ説明されている。土台となるからだの脳から、それ以降のおりこうさんの脳、こころの脳に至る脳育ての重要性を認識することができ、非常に勉強になった。我が子の状況に置いてみると、からだの脳の次の段階であるおりこうさんの脳が育つ時期にあることを意識し、実践していきたいと思う。 ※何冊か著者の書物を読んでみて、個人的には本書が最も理解しやすいと感じた。 【メモ】 ○はじめに ●子育ては、脳が育つ順番に沿えばうまくいく。 ●最初の5年間で「早寝早起き」習慣をつけることさえ頑張れば、あとは楽 ○序章 ●脳が育つ順番 ①からだの脳(0~5歳で育つ。身体機能) ②おりこうさんの脳(6~14歳で育つ。知能・言語機能) ③こころの脳(10~18歳で育つ。論理的思考や問題解決能力) ●家に例えると… ・1階がからだの脳、2階がおりこうさんの脳、階段がこころの脳 ●脳を育てるとは、神経細胞をつなげること ○からだの脳 ●最初の5年間は「夜8時に寝る」生活を徹底 ・我が家ではほぼ夜9時就寝であったが、仕方なしと考えよう。 ●5歳までは、11時間以上の睡眠が必要 ・我が家は平日夜9時~6時半(9時間半)。休日は夜早め。 ●早く寝かせるためには、早く起こす ・朝6時台を目標に。休日は朝遅めになることもあるので気をつけよう。だいたいは勝手に6時半頃に起きるのでよい傾向か。 ○おりこうさんの脳 ●本人が「勝手に勉強しだす」ような脳をつくる ・経験を積ませる。自分をとりまく世界を見る・知る・機会を与える。 ・最も重要なのが「家庭生活」。家庭は最も小さな単位の「社会」。他者との共同生活を学ぶ。家庭という社会の一員として自らを位置付けることが、広い世界を知るための最初の一歩。 ●子どもの役割をつくり、自己肯定感を上げる ・すべてが人任せだと「自分は~できる」という実感を得られない。 ・役割を与える。役割を果たして感謝されることの喜び、慣れるに従って段取りや作業がうまくなっていく達成感を味わえる。小さな社会の一員として役立っていることへの誇りも得られる。 ●頼み事は、フルセンテンス&敬語で話させる ・「~が必要で、〇〇円するのですが、を出してもらっていいですか?」(著者のお家のルール) ・社会でも申請が必要。親は基準をあいまいにしないで判断する。 ●おりこうさんの脳時代は、こころの脳の準備期間 ・この時代に「思いやりの持ち方」をインプットする。→親がやってみせる。 ・電車に高齢者や体の不自由な人が乗ってきたら?→席を譲る。 ・レストランで子どもがグラスをひっくり返してしまったら?→親が「申し訳ありません!」と相手に謝罪する。 ○こころの脳(中核期は10~14歳) ●幸福にいきるための脳が、こころの脳 ・情動のコントロール。論理的思考力。想像力や思いやり。心折れずに前を向けるレジリエンスの力など。 ●幼いころから前頭葉を鍛える働きかけ3点(事前の仕込み) ①安心をインプットする(前頭葉の中で大丈夫という結論を導き出す)。 ②子どもの言葉を引き出すコミュニケーションをする。 ③ルールを設定する。 ●レジリエンス(辛いことや苦しいことがあっても、その事象を柔軟に捉えて希望を見出し、乗り越えていく力) ①自己肯定感 ②社会性→周囲の人々との関係をつくる力 ③ソーシャルサポート→自分は周りの人に助けられていると感じる力 ○脳育て(何歳からでもやり直せる) ●子どものストレス対応力をつめるなら、まず大人から ・親のストレスは子どもに強い影響を及ぼす(親自身が自分のストレスに気づく)。 ・ストレスコーピング(対処法)を多く持つ。→子どもに伝える。 ・子どものストレスサインに気づく。 ●「褒める」より「認める」 ・認めるとは、子どもの存在を丸ごと承認すること。 【目次】 序 章 なぜ「子育て=脳育て」と言えるのか? 第1章 「からだの脳」の育て方 第2章 「おりこうさんの脳」の育て方 第3章 「こころの脳」の育て方 第4章 脳育ては何歳からでも挽回できる!
Posted by 
小児科医・医学博士・公認心理師が書いたPHP新書。 「からだの脳」 5歳までに鍛える 早寝早起きしっかり食べる 「おりこうさんの脳」 1歳から18歳。ピークは6‐14歳、小中学生 勝手に勉強しだすよう経験を積ませる 「こころの脳」 10歳から。安心、言葉、ルール。...
小児科医・医学博士・公認心理師が書いたPHP新書。 「からだの脳」 5歳までに鍛える 早寝早起きしっかり食べる 「おりこうさんの脳」 1歳から18歳。ピークは6‐14歳、小中学生 勝手に勉強しだすよう経験を積ませる 「こころの脳」 10歳から。安心、言葉、ルール。 1階がからだ、2階がおりこうさん それをつなぐ階段がこころ なかなか説得力がある。 この順番を間違えて、早くから英才教育と称してがつがつ勉強させても無駄、むしろ害。 なにより親が子供にいろいろやりすぎて不健康で接するのがよくないと。そう思う。 意外だったのは、夫婦喧嘩は見せていいと。子供のことでの言い合いは見せてはいけないが、 それ以外はむしろ刺激になると。 仮に離婚になってしまったとしても、隠さず伝えるのがいいと。。。 我が家は離婚まではいかずに済んだが、長女の前ではかなり激しくケンカしていて、 それが娘の脳に悪影響を及ぼしたのではないかと心配していたが、ちょっと安心した。 大人が読むべき本。 脳の世界は奥深い。 序章 なぜ「子育て=脳育て」と言えるのか?(世の「育児本」が分かりづらい理由;脳には3つの種類がある―「からだの脳」「おりこうさんの脳」「こころの脳」 ほか) 第1章 「からだの脳」の育て方(からだの脳とは、生きるための脳;5歳までは、11時間以上の睡眠が必要 ほか) 第2章 「おりこうさんの脳」の育て方(おりこうさんの脳は、勉強させても育たない;子供の役割をつくり、自己肯定感を上げる ほか) 第3章 「こころの脳」の育て方(こころの脳は、幸福に生きるための脳;幼いころから、前頭葉を鍛える働きかけを ほか) 第4章 脳育ては何歳からでも挽回できる!(「脳育て」は何歳からでもやり直せる;反抗期は「先輩モード」で対応する ほか)
Posted by