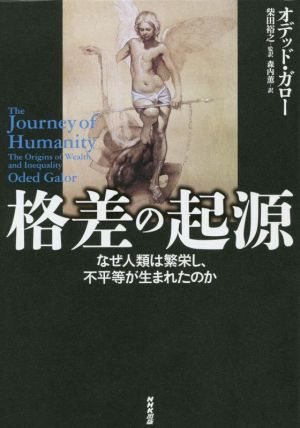

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | NHK出版 |
| 発売年月日 | 2022/09/27 |
| JAN | 9784140819111 |
- 書籍
- 書籍
格差の起源
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
格差の起源
¥2,530
在庫あり
商品レビュー
3.7
24件のお客様レビュー
本書は、「多様性」推奨の根拠として薦められていたので、読んでみた。 うん、そうなのかな? 正直、なるほどと理屈が通っているような、いややっぱりムリヤリ辻褄合わせてしているように思えるところもあるような、、、(苦笑) 第一部 何が「成長」をもたらしたのか マルサスの「貧困の罠」...
本書は、「多様性」推奨の根拠として薦められていたので、読んでみた。 うん、そうなのかな? 正直、なるほどと理屈が通っているような、いややっぱりムリヤリ辻褄合わせてしているように思えるところもあるような、、、(苦笑) 第一部 何が「成長」をもたらしたのか マルサスの「貧困の罠」から抜け出せた理由 第二部 なぜ「格差」が生じたのか 一部地域(欧州)が特別に成長の恩恵を受けたのは、人類発祥の地アフリカから近く「多様性」があったため。 (成長の基準が「所得」というのも、個人的にはピンとこないのだけど、それ以外に基準にできるものがないので、そこは目をつぶります。)
Posted by 
この手の本はサラッと読むとエセ科学が潜んでいることがある。しっかり疑って読む。わかったつもりになってはいけない。自分なりにエビデンスを調べて確信を持たないといけない。この本では、ちょくちょく使われる比喩が怪しい。 第一部は156ページ書かれているが、そのまとめとして最後に6ペ...
この手の本はサラッと読むとエセ科学が潜んでいることがある。しっかり疑って読む。わかったつもりになってはいけない。自分なりにエビデンスを調べて確信を持たないといけない。この本では、ちょくちょく使われる比喩が怪しい。 第一部は156ページ書かれているが、そのまとめとして最後に6ページ割かれている。そこには、150ページのまとめとともに、特に目新しくないことが書いてある。150ページはなんだったのか? 第二章こそが、この本の本質であり、タイトルに合致する。 ただし、内容的には、高校世界史レベルに幾つかの事例を継ぎ足した感じか。それほど目新しくはない。帯で称賛している人の著書を読むのも、ちょっとためらう。
Posted by 
そもそもの経済成長がどのように行われてきたかの話が始まり、そこから歴史を現代から過去にさかのぼりながら格差がなぜ起きたかを解明しようと話が進む。 様々な要因があるのではないかと疑問を投げかけつつ、その要因を深彫りしていって、最終的に多様性というところに着地している。そしてアフリカ...
そもそもの経済成長がどのように行われてきたかの話が始まり、そこから歴史を現代から過去にさかのぼりながら格差がなぜ起きたかを解明しようと話が進む。 様々な要因があるのではないかと疑問を投げかけつつ、その要因を深彫りしていって、最終的に多様性というところに着地している。そしてアフリカからの距離と多様性の相関について話しており、その点に面白さを感じた。 完全に納得してはいないものの、私の思いつかない色々な観点での洞察があり、非常に感心した。
Posted by 



