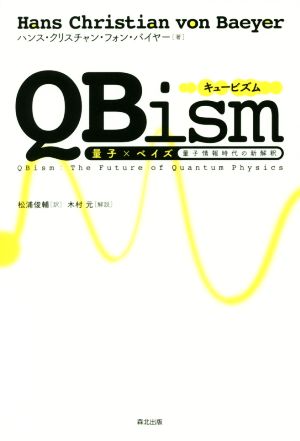- 書籍
- 書籍
QBism
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
QBism
¥3,080
在庫あり
商品レビュー
3.6
5件のお客様レビュー
頻度主義的確率からベイズ確率へというアイデアは非常に興味深かった。まだ理解しきれていない部分も多いので、何度も読み直していこう。文献のいくつかにも目を通してみたい。
Posted by 
量子力学の専門家が、新たな考え方「QBism」について書いた本。かなり簡単に説明していると思うが、素人の私には十分理解できなかった。量子力学は難解だと認識しているが、やはり難解であることを理解した。 「(波動関数に従い進む)電子がスクリーンに当たるとき、奇跡が起きる。波動関数が...
量子力学の専門家が、新たな考え方「QBism」について書いた本。かなり簡単に説明していると思うが、素人の私には十分理解できなかった。量子力学は難解だと認識しているが、やはり難解であることを理解した。 「(波動関数に従い進む)電子がスクリーンに当たるとき、奇跡が起きる。波動関数が突如、説明のつかない形で画面の一点に収縮するのだ。当たる直前までは波動関数の値は空間に広がっていた。衝突すると、波動関数の値は電子が当たったことを記す小さな光点以外では、無視できるほど小さくなる」p39 「電子が届いた印となる光点は、そのパターンの範囲内でランダムな位置にできる。ランダムとは、理由がない-予測できない-ということで、法則がない。このささやかなランダムという言葉が通常の古典力学と量子力学の違いの要を記述している」p39 「(「ギャンブラーの誤謬」)ある硬貨が続けて100回表を見せた後は、101回表が続くのはとんでもなくありえないから、裏が出る可能性は50%をはるかに超えた値になるにちがいないと信じてしまう間違いのこと」p81 「私が数字0.999...という数は、「...」が同じ数字の繰り返しを表すとして、1という数に限りなく近いというと、学生は同意する。しかし私がさらに「それは1よりごくわずかでも小さいと思うか。つまり、0.999...<1と書くことは数学的に正しいか」と尋ねると、その答えはおおむね「正しい」となる。そこでそうではないのだと私は反論する。「ごくわずか」とは、数学的に受け入れられる言葉ではない。先ほどの問題に対する正解は「正しくない」で、0.999...=1となる(納得するには、1÷3を計算すれば、1/3=0.333...で、両辺を3倍してみればよい)」p143 「量子力学は、現代物理学の支柱であり、現代科学技術の欠かせない基盤でもある。あらゆる素粒子現象、原子の安定的構造、化学現象や磁石の仕組みといった身近な性質から、半導体、レーザー、超流動や超伝導といった不思議な物性までを見事に説明する。近年では、量子暗号や量子コンピュータといった量子情報科学の発展が目覚ましく、量子力学は、近未来の情報通信技術の基盤ともなると期待されている。今や人類は、世界の不思議な現象をうまく説明できる「便利で万能な道具」を手に入れたと言っても過言ではない。それにもかかわらず、量子力学を勉強すればするほど、そして、量子力学の専門家であればあるほど「量子力学を理解した気になれない」と白状したことになる」p194 「語りえぬものについては、人は沈黙しなければならない(ヴィトゲンシュタイン)」p199 「「QBイズム」とは「量子(クオンタム)・ベイズ確率主義(ベイジアニズム)」の略で、量子力学の確立解釈をベイズ確率にするという方針を示します」p221 「(モンティ・ホール問題)一種のくじで、途中で選択変更の機会を与えられたとき、選択を変えた方が「当たり」の確率は上がると考えることが正解の問題で、直観的には変えても変えなくても同じなのですが、変えた方が確率は上がるので、変えたほうが良いということになります。ただし「確率は上がる」というのは数学的な頻度説に基づく計算で、このゲームを何度も行う、たとえば主催者側からすると確かにそうなるだろうと思われる事態です。この1回に賭けなければならない場合は、いくら数学的には選択を変えるほうが正解だと言われても、選択を変えたら確率1で当たるというのならともかく、やはり外れる可能性もあるのなら、すんなり変える方がいいとは思えません。ベイズ確率はそういう結果が出る前の場面で、それでもその都度の1回の選択にとって参考になるよう考えられた確率だと思います」p221 「本書が述べられる、いわば物理学と心理学という、従来全く別物とされたものを組み合わせた世界像を立てようという、その機が熟してきたのかもしれない」p222
Posted by 
量子力学の理論というのは、文系人間にとってはとってもSF的に見えて中二病心をくすぐるものですが、非常に真面目に量子確率の新解釈を示してくれているであろうこの本は、ますますその感を深くするものでした。 量子状態の「確率」というのは、観測者が利用できる全情報に基づいて、合理的にそれが...
量子力学の理論というのは、文系人間にとってはとってもSF的に見えて中二病心をくすぐるものですが、非常に真面目に量子確率の新解釈を示してくれているであろうこの本は、ますますその感を深くするものでした。 量子状態の「確率」というのは、観測者が利用できる全情報に基づいて、合理的にそれが起きると予想する「信念の度合い」に過ぎず、したがって観測者ごとに異なったとしてもそれが本来の姿である。ただし、共通する十分な情報を持った、同じ場所にいる観測者同士なら、その「予想」は通常一致し、その一致するものを科学的な「理論」とか「法則」と呼んでいるに過ぎないというのが、僕の理解したこの本の趣旨といったところでしょうか。グレッグ・イーガンのSFや、ゲーム「カオス・ヘッド」の「共同幻想」を思い起こされましたが、実は、これらのフィクションは、理論的にも結構いい線行っていたのかもしれませんね。 ところどころ難しい部分もありますが、全体として言っていることはよくわかりましたし、一種目からうろこ的なところもあって、非常に面白く読めました。巻末の「解説」では、これに対する批判も掲載されており、合わせて読むとさらに納得度が高かったです。
Posted by