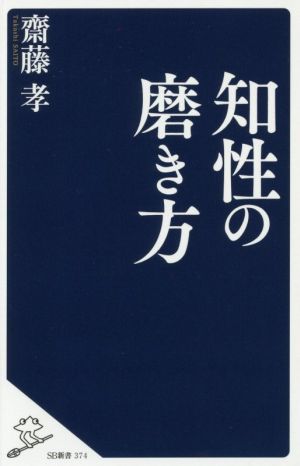
- 新品
- 書籍
- 新書
- 1226-18-15
知性の磨き方 SB新書374
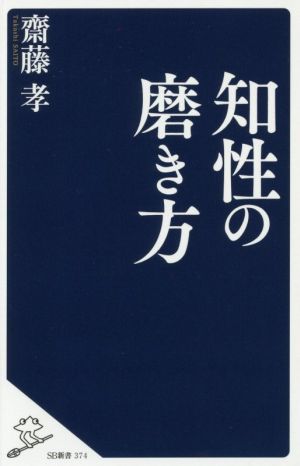
880円
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | SBクリエイティブ |
| 発売年月日 | 2017/01/01 |
| JAN | 9784797388787 |
- 書籍
- 新書
知性の磨き方
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
知性の磨き方
¥880
在庫なし
商品レビュー
3.9
20件のお客様レビュー
『#知性の磨き方』 ほぼ日書評 Day848 高校時代の友人の読書記を見て。 相変わらずこの人は構成が上手いな。 漱石、諭吉という大御所の "知られざるエピソード" からロジカルに入って、最後は折口信夫、太宰治の "憑依型の理解" ...
『#知性の磨き方』 ほぼ日書評 Day848 高校時代の友人の読書記を見て。 相変わらずこの人は構成が上手いな。 漱石、諭吉という大御所の "知られざるエピソード" からロジカルに入って、最後は折口信夫、太宰治の "憑依型の理解" 等と、いわばスピリチュアルに締めて余韻を残す。これで、次は何を読もうか…という気にさせるのだ。 人それぞれ(若い人なら全般的に)気になる・タメになる内容が散りばめられているが、評者があらためてなるほど…と感じたのは次の一節。 貧乏書生だった頃の、福沢諭吉の話。オランダ語に精通したつもりでいたが、開港したばかりの横浜などへ行ってみると、言葉が通じない。蘭学など現実世界では無意味なことに気付かされる。 しかし、である。英文を蘭文に訳すところから始めてみると、両言語の文法に大差ないことに気づく。 "福沢の時代には、外国語の自主や文法書は数自体少なく、あったとしても、今のもののように内容がしっかりしているわけではありませんでしたから、外国語の文章を読もうとするなら、まずはテキストそのものに没入し、自分の前頭前野をフル稼働しながら読み解く作業が必要でした。こういう読み方では最初に読んでみた段階では、何が書いてあるか皆目わかりません。しかし、これを書いた外国人は、絶対に何か意味のあることを言いたかったはずであり、書いたはずだ。そう信じて、わずかにわかる単語や限られた情報を手がかりに、何度も何度も読み返しているうちに、不意に「あ!意味が通った!」と言う瞬間が訪れる━━そのプロセスの繰り返しなのです。" 後の慶應義塾設立に際しても、この精読独学の精神を重視したという。 効率重視の現代ではなかなかに贅沢な時間の使い方だが、人生のどこかで、こういうものの学び方をするのも悪くない。 評者や同世代の方は、むしろこれからか?! https://amzn.to/4hnJ023
Posted by 
ネットですぐ調べられるようになった今、自分で深く調べて得られる満足感は減ってしまっているからこそ、ちょっと回り道した楽しみ方が重要だなと思った。本屋や図書館であえて自分が興味ないジャンルもぶらつくとか、できることを考えてみようと思った。 ここに出てきた福沢諭吉の子供時代の話(近...
ネットですぐ調べられるようになった今、自分で深く調べて得られる満足感は減ってしまっているからこそ、ちょっと回り道した楽しみ方が重要だなと思った。本屋や図書館であえて自分が興味ないジャンルもぶらつくとか、できることを考えてみようと思った。 ここに出てきた福沢諭吉の子供時代の話(近所の神社の御神体をその辺の石と取りかえる)をカラリとした精神としてたけど、だめだろと思った。一万円にふさわしい人物と書いてたけどこれ知ってむしろふさわしくないと思った。
Posted by 
知性の磨き方 著:齋藤 孝 SB新書 374 おもしろかった イメージ豊かに知性ある人生を愉しむためのアドバイスを与えるのが本書である 知とは目に見えないものなので、知をイメージするためには、さまざまなたとえ(比喩)をつかえば、より分かりやすくなる。 知というか、肚のくく...
知性の磨き方 著:齋藤 孝 SB新書 374 おもしろかった イメージ豊かに知性ある人生を愉しむためのアドバイスを与えるのが本書である 知とは目に見えないものなので、知をイメージするためには、さまざまなたとえ(比喩)をつかえば、より分かりやすくなる。 知というか、肚のくくり方というかが、語られてもいます。 気になったのは、以下です。 ・人は、正しく理解するからこそ正しく判断し、正しい行動ができるのであって、正しい理解に基づかない判断・行動をすると、誤った方向にしか進めない。理解に基づかない決めつけを、先入観という。 ・芭蕉「不易を知らざれば基たちがたく、流行を知らざれば風新たならず」 時流とは関係のない普遍性を知らなければ俳句を読むことができないが、新らしいものを知らなければ凡作しか作れない ・好き嫌いではなく、相手を理解することから始まる関係は、時間がかかるかもしれないが、容易に崩れることはない ・悩んだ末に自力で探しあてること ・常に考え抜く ・牛のように押せ、泥くさく悪戦苦闘せよ ・悩んでも混乱せず、問いから逃げない ・再出発をいとわない ・人が合理性に欠く行動をとるときは、たいていその背後に、嫉妬や、保身の感情がうごめているものです ・福翁自伝 まず獣身を成して後に人心を養う 丈夫な体を育ててから、人の心を育てる ・知性は物事を整理し、心の恐れをも減らす ・葉隠:生きるか死ぬか、2つのうち1つを選ばなければならない局面では、迷うことなく死ぬほうに進むほうがいい、別に難しいことではない、腹を据えて進むだけのことだ ・仏教の本来の目的は、死の恐怖を乗り越えることにあるが、武士道とは、死を恐れないことから出発するもの、最初から死の恐怖を克服してしまっている ・日本人の「肚」 肚のない人とは、落ち着いた判断のできない人である 肚のない人はすぐ驚き、神経質である 肚のない人は、直線的で、頭が固く、目標がない ・胆力とは、自分の利害にこだわらないことである ・一燈を提げて、暗夜を往く。暗夜を憂ふる勿れ、只だ一燈を頼め 八方ふさがりで希望が見えないような状況でも、ただ1つの明かりがあれば、恐れる必要はない ・論語:知仁勇 知性(判断力)、仁(やさしさ、誠実さ)、勇気(行動力) ・西郷隆盛 啓天愛人 人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽くして人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし ・自分自身でものを考えられる。それが真に知性のある人です ・全体という大きな存在と一体化する。そのときに人間は幸福感を味わう。漢語で、梵我一如、という ・清濁併せ呑む ・知性的であるとは、判断がまちがっていたときに、それを修正していけるということです ・頭はいいかもしれないけれど、情が伝わらない人だと、一緒にいて楽しいとはならない ・和歌の枕詞、奈良時代には、すでに意味が分からなくなっていた。神にかかることばであり、儀式的な意味があることを人々が知っていたからこそ、今日にまで伝わった ・理解には2つある。分析的な理解と、直感的理解である 目次 はじめに 第1章 悩みぬくことで鍛えられる知性 第2章 激変する時代を切り拓く知性 第3章 肚、身体に宿る知性 第4章 自我を解き放つ知性 第5章 探求を続ける者から生まれ出る知性 おわりに ISBN:9784797388787 出版社:SBクリエイティブ 判型:新書 ページ数:208ページ 定価:800円(本体) 2017年01月15日初版第1刷発行
Posted by 



