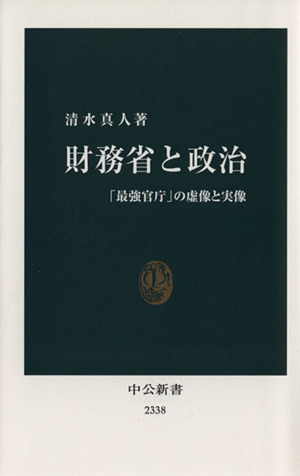
- 新品
- 書籍
- 新書
- 1226-15-01
財務省と政治 「最強官庁」の虚像と実像 中公新書 2338
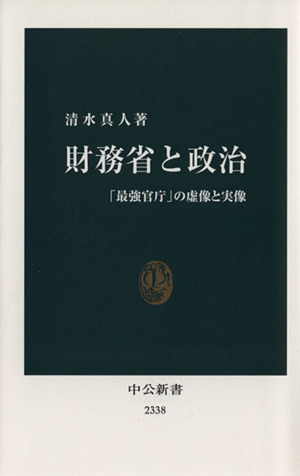
968円
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2015/09/23 |
| JAN | 9784121023384 |
- 書籍
- 新書
財務省と政治
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
財務省と政治
¥968
在庫なし
商品レビュー
3.9
14件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
政治と財務省の関係を時系列を追って記述し、その立ち位置と絡みの深さを事実として示した2015年の本。元日経記者というだけあって淡々とフラットに書かれている。 自民党長期政権と大蔵省の体制の序章から始まり、バブル崩壊後の新党さきがけへの政権交代、金融危機と大蔵省解体とどんどん進んでいく。 政治や経済に詳しくない自分にとって、「常識やぶりの驚天動地」として書かれていることも今ひとつ分かりづらく、数多く出てくる人名に馴染みもなく、読み進むのに苦労した。記者として中立の立場を維持して書きたいのはわかるが著者は財政規律派だろう。ある程度主張の入った解説を混じえてくれるほうがわかりやすいのにと思う。 しかし、小泉政権のあたりから、知らなかった政治の裏側が覗けたようで面白くなった。財務省と政治のかかわりを書いているのだが、それは政局の最も中心の動きと言えるのだろう。表向きの報道と実際の政治で起こっていることはまったく違うとわかって気が遠くなる。 財務省は、首相はじめ政治の中枢にいる政治家たちに頼られたり嫌われたり避けられたり恫喝されたりしながら提案したり誘導したり調整したりして最後はどうにかまとめて実行する組織である。 政治家は財務省と距離をとって自分の主張を通すため、独自に学者を起用しようとしても、結局は各方面との折衝・調整・実務に長けた財務省に頼らずには立ち行かない。 消費税引き上げの法制化は民主党時代の野田佳彦首相が政治生命を懸けて実現したという。あれ? 自民党じゃなかったのか……と、そら恐ろしくなった。自民党は消費税を上げても「だって民主党が法律で決めたんだから」と責任逃れの言い訳ができるわけだ。 どの政党が政権を取っても、変わらず財務省の思惑どおりだ。財務省最強。 内閣が強権な政治主導となってからは、財務省は内閣と与党の間に立って調整役となる。総括すると著者はそれが財務省の役割としているようだけど、それでいいのかとても疑問が残った。誰が首相になろうとも、財務省は財務省。事務次官になると名前が出てくるけれど、組織として「財務省は」という主体がある。そこで根拠となる経済理論はどうやって選択されているのだろう? 逆に財務省を洗脳しているのは誰なんだろう? たぶん、財政規律という強い信仰のもとに動いているのだろうけど、その信仰の強さで国民から搾り取ることばかり考えられてはたまらない。 いろいろな力関係や駆け引きがあって政府も与党も官僚も大変なんだな。ご苦労さまだと思うものの、そこに力のない国民のことを考える余地は全くなさそう。 経済活性化のために法人税を引き下げ、消費税は上げる。賃金引き上げを奨励するというけど、それで給料があがるのは大企業だけだし。たぶん、国民の生活は国の存続のため犠牲にすべしくらいに思っているんだろう。 置き去りにされる境遇の者としては、絶望感をおぼえる本であった。本書は足りない財源は消費税引き上げで賄うのが既定路線としている。軽減税率の話すらなく、あまりに能が無いように見えてしまう。
Posted by 
細川内閣から第二期安倍政権途中までの財務省と政治の関わりを描く。 財務省は、与党自民党の実力者と結託し予算編成スケジュールを見ながら族議員や各省と調整し落とし所を見つける。時には最強官庁としての虚像も活用しながら泥を被ることも厭わない。極めてパワフルで政治的な官庁だったが、橋本行...
細川内閣から第二期安倍政権途中までの財務省と政治の関わりを描く。 財務省は、与党自民党の実力者と結託し予算編成スケジュールを見ながら族議員や各省と調整し落とし所を見つける。時には最強官庁としての虚像も活用しながら泥を被ることも厭わない。極めてパワフルで政治的な官庁だったが、橋本行革、大蔵不祥事、小泉総理・竹中大臣のリーダーシップ、民主党政権、第二次安倍政権の慣行に囚われない政権・人事運営を経て、行政に対する政治の優越が進んでいく。本書の登場人物の変化にもそれが現れており、細川政権では大蔵次官といった官僚個人にスポットライトが当たるが、そうした場面が徐々に減っていき第二次安倍政権時はほとんど政治家に焦点が当たっていた。政治と財務省の力関係の変化を象徴しているように思えた。 興味深いエピソードもあったが、全体的に、時系列で起きた出来事や取材で得た情報を並べているだけ、という印象だったので評価は低めにした。筆者は日経新聞の記者らしいが、先日読んだ年金官僚の文体も似たような感じだった。記者は綺麗な文章は書けても、長い書籍としてそれを組み立てるのは得意でないのかもしれない。
Posted by 
55年体制の自民を序章に、非自民連立政権、橋本行革、小泉官邸、民主政権、安倍官邸など、それぞれの時代のおける政治と大蔵・財務省の関係が、ドキュメント的に描かれている。 登場者がどの視点からどのように財政や金融を動かそうとしたか、その流れの概略が掴める。財務省自体を細かく解説するも...
55年体制の自民を序章に、非自民連立政権、橋本行革、小泉官邸、民主政権、安倍官邸など、それぞれの時代のおける政治と大蔵・財務省の関係が、ドキュメント的に描かれている。 登場者がどの視点からどのように財政や金融を動かそうとしたか、その流れの概略が掴める。財務省自体を細かく解説するものではなく、政治との関係を焦点にしてその考え方や行動原理を浮かび上がらせたもの。意図してかどうか、戦後後期の政治史としても面白い。
Posted by 



