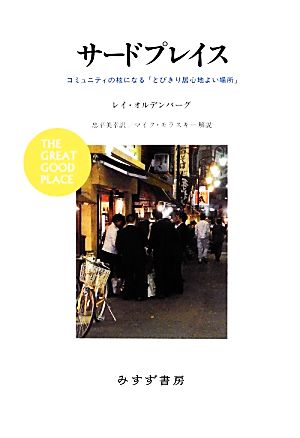- 書籍
- 書籍
サードプレイス
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
サードプレイス
¥4,620
在庫あり
商品レビュー
3.5
23件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
5. 関係のない人どうしが関わり合う「もう一つのわが家」 17. サードプレイスの一番大切な機能は、近隣住民を団結させる機能 18. サードプレイスはいわば「ミキサー」なのだ 25. 人がサードプレイスに何度でも戻ってきたくなる基本的な動機は楽しさである 27. アメリカ人はヨーロッパ人の三倍から四倍の時間を買い物に費やすが、その違いのほとんどではないにしても多くは、ほかに選択肢がないことと関係がある 30. サードプレイスはオフィスの代わりになりうる。ある種の取引は、当事者のどちらか一方の「ホームグラウンド」ではなく、どこかの中立的ない場でおこなうほうがいい。しかもなるべくなら居心地がよくて、堅苦しくない場所だ 42. 「人はある場所で働き、別の場所で眠り、ほかのどこかで買い物をし、楽しみや仲間たちの見つかるところで見つけ、これらのどの場所にも関心を払わない」 49. アメリカでは街なかで消費される飲み物全体のうち、ビールや蒸留酒が占める割合は、1940年代の約90%から現在は約30%まで落ち込んだ 51. 世論は「ストレスの原因は社会にあるが、その治療は個人で対処するもの」 54. コーヒーブレイクは単なる休憩時間にとどまらない。身体を休めるよりも、他人とのなごやかな触れ合いに利用されるのだ。このような「小休止(タイムアウト)」の範囲が拡大される 57. サードプレイスが、家庭や職場と同じく一つの独特な場所であることが重要 60. 産業化以前、ファーストプレイスとセカンドプレイスは一つだった。産業化は、居住地から仕事場を切り離し、家庭から生産性の高い仕事を奪い去り、それを距離的にも倫理的にも精神的にも家庭生活から遠ざけた 65. サードプレイスという、ストレスや孤独や疎外感に効く「庶民の治療薬」 67. 「人は、互いに相手から身を守る何らかの手段をもっているときにしか社交的になれない」 by社会学者リチャード・セネッソ 67. ジェイン・ジェイコブズ(米作家、都市計画評論家)は、おおかたの友情につきものの矛盾と、結果として生じるそのための場を提供する必要性について力説している。彼女によれば、意義のある有益で楽しいつきあいができる相手だけれども「自分の身辺には立ち入ってほしくないし、先方も自分に対してそう思っている」ような人が、都市にはごまんといるという。もし友だちづきあいなどの気楽な交際が、自分の私生活に入ってきてもかまわない人だけに限られたら、その都市は本来の役目を果たさなくなる。私たちに豊かで多様な交流を提供するには、人の集まってくる「中立な領域」がなければならない 71. 平等化は、日常の世界での地位が高い人にとっても低い人にとっても、喜びであり安らぎである 79. 人は大きな騒音にさらされると飲酒の量も速さも増す傾向にある 82. サードプレイスへの行きやすさの重要性が浮き彫りになる。サードプレイスが生き残って役目を果たすには、それらの利用が容易でなければならず、サードプレイスを訪れるのが容易かどうかは、時間と場所の両方の問題である 83. サードプレイスは、人がよそで義務をこなす前であれ、合間であれ、後であれ、社交や気晴らしをしたいときにいつでもその要求に応える用意ができていなければならない 83. 店の立場から見ると、客の来る時刻も帰る時刻もまちまちだし、そのときどきで顔ぶれが違う。そういうわけだから、サードプレイスの活動は、たいてい無計画で、予定外で、組織のまとまりがなく、型にはまらない。しかし、ここにこそ魅力がある。中級階級の組織志向からの脱却が、サードプレイスに大きな特徴と魅力を与え、家庭や職場のルーティンから完全な離脱を可能にする 92. 家(home)という言葉の1「家族の住み処」と2「同居している家族によって形成される社会単位」にも当たらない。しかし、3「快適な環境」は、平均的な住宅よりも、平均的なサードプレイスのほうが当てはまりそうだ
Posted by 
スターバックスコーヒーをはじめ、さまざまな場面で目にする「サードプレイス」という言葉だが、その原点とも言えるのが本書である。一般的にサードプレイスというと、自宅と職場に次ぐ第三の場所という程度の意味で用いられる事が多い(スタバが代表例)。 しかし本書を読むと、本書の言うサー...
スターバックスコーヒーをはじめ、さまざまな場面で目にする「サードプレイス」という言葉だが、その原点とも言えるのが本書である。一般的にサードプレイスというと、自宅と職場に次ぐ第三の場所という程度の意味で用いられる事が多い(スタバが代表例)。 しかし本書を読むと、本書の言うサードプレイスは、コミュニティの拠点となる場所のことであり、そこにはメンバーの多様性(社会階層を問わない)や定期性(その場きりではない)がある。ここが懐古主義と言われたりもする理由だと思うのだが、本書の問題意識はあくまでも失われゆくコミュニティを取り戻すことなのだ。こんにち一般に言われるサードプレイスは、著者が「見せかけのサードプレイス」と批判する「BYOD(Bring Your Own Friends : 友達を連れてきてね)のカフェ」のほうが近いだろう。 本書を読んだ感想、サードプレイス再興の道のりは遠いな……というのが第一感である。サードプレイスを謳う場所であっても、結局は内輪だけで多様性がなく閉鎖的だったり、定期性がないただのカフェになっていたり、という例の方が多いはずだ。けれども、もしかすると、本書が例示する場所がいずれもそうであるように、サードプレイスを名乗っていないどこかに、本当のサードプレイスが存在するのかもしれない。
Posted by 
ここで書かれるサードプレイスは探してる場所と少し違うけど、それほど親密でない自分の趣味嗜好と違う人の集まる場所だからこそ自分にないものを提示される意外性があるっておもしろいと思いました。
Posted by