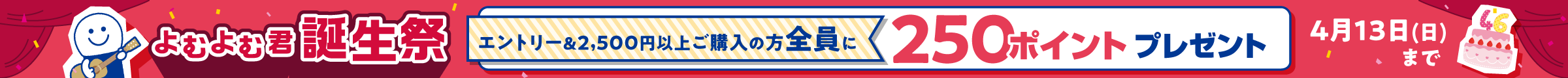- 書籍
- 書籍
世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業
¥1,540
在庫あり
商品レビュー
3.5
89件のお客様レビュー
『具体と抽象』を読んだ後に読んだこともあり、抽象化や前提の一致等通ずる部分が多くあったように感じた。本書は自分で考えることと、それを強めるために議論することに焦点を当てている。日本人における意見交換は弱点のように感じられるのは、非常に共感できる部分であり、身に着ける必要性を感じる...
『具体と抽象』を読んだ後に読んだこともあり、抽象化や前提の一致等通ずる部分が多くあったように感じた。本書は自分で考えることと、それを強めるために議論することに焦点を当てている。日本人における意見交換は弱点のように感じられるのは、非常に共感できる部分であり、身に着ける必要性を感じる。この本を読んでいて感じたのは、主にビジネスマンの場面として思い浮かんだ。しかし、抽象化してみると他の人にも当てはまることが多いと思うし、日常生活で行かせる部分がほとんどであるように思える。また、意見交換時にあるマナーや心構えはしっかりと学んでおく必要があると感じた。 意見→根拠(事実)→証拠 この構造が必要。また、根拠を述べる際にもそれは根拠になっているのか、根拠の根拠はあるのかと深堀していくことで、自分の意見に説得力を持たせる。逆にそれがないと意見として甘い。また、この際専門家が言っていたというのは根拠になるか怪しい。それはその専門家の意見なのか事実なのかを見分ける必要がある。事実が故の意見である可能性があるので、誤解してはいけない。さらに、○○先生がおっしゃっていたというのは、本当にその先生が言っていることが保障されるのか。つまり、意見と事実を分ける必要性がある。 考えの根拠以外にも予測も大事。 本文抜粋 『考える対象となっている案に「賛成」だと思っている場合(また、肯定的な考え方をしている場合)、特に注意して考えるべきは「上手くいかなかった場合のシナリオ」です。』 「欲望が複数重なったプロジェクトは成功しない」→目的は一つがいい。それに対する手段方法は何が適切か。 「この〈根拠〉が本当にこの〈結論〉を導き出すのか、と考えてみます。」 「人の頭の中で考え出すものである以上、1人1人の意見はそれぞれ違っていて当然です。」 「『間違っているかもしれないんですけど…』などと思わないでください。そして、そのようなことを言わないでください。」 『誰かが反論してきたとしても、その人が反対しているのは、あなたの「意見」であって、あなた自身ではないはずです。』 『根拠を言わずに結論だけを言う(たとえば、「うちの車では無理だよ、そんなの」とだけ言って、根拠を言わない)というのは、議論ではしてはいけないことです。』 「反対するなら代替案を」 「相手の意見に賛成する場合も、どこにどう賛成できるのか、具体的に言ってあげてください。」 「大人たるもの、責任が持てないような発言、つまり覚悟を持てないような発言は本来してはいけないのです。」
Posted by 
こういう内容が書かれているのかな、こういう内容が書かれていればいいな、ということが書いてあってよかった。自分の力で考えることができるようになるプロセスが書かれていた。こういうのは習慣化し、日常生活で繰り返されることで養われると思う。欧米の授業が例として挙げられていて欧米人がはっき...
こういう内容が書かれているのかな、こういう内容が書かれていればいいな、ということが書いてあってよかった。自分の力で考えることができるようになるプロセスが書かれていた。こういうのは習慣化し、日常生活で繰り返されることで養われると思う。欧米の授業が例として挙げられていて欧米人がはっきりとして意見を持つことの良さというものを実感。
Posted by 
日本人は話すことが自体が英米人に比べて苦手であることに気づき、意見を持ち、言ったり、考えたりするようにできるようになることを目指して書かれた自己啓発本。 クリティカルシンキングや 質問法や 視点の変え方や 予測の仕方や 批判や反論時のルールや 気持ちに気付く方法。
Posted by