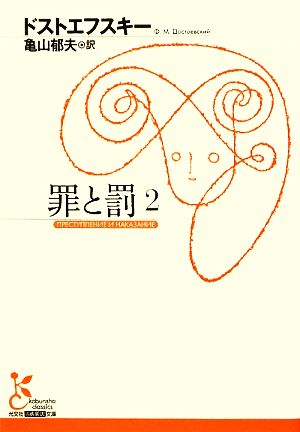

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 光文社 |
| 発売年月日 | 2009/02/09 |
| JAN | 9784334751739 |
- 書籍
- 文庫
罪と罰(2)
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
罪と罰(2)
¥902
在庫なし
商品レビュー
4
58件のお客様レビュー
第二巻(収められているのは第三部、第四部) 老女殺しは てっきり貧乏と、心気症と、老女の因業な金貸しが憎くて殺害かと思ってたけど、それだけではない様子 ラスコの考え方、思想も殺害に影響している ラスコを追い詰める予審判事ポルフィーリーがおもしろい 「選ばれた人間は思想や自...
第二巻(収められているのは第三部、第四部) 老女殺しは てっきり貧乏と、心気症と、老女の因業な金貸しが憎くて殺害かと思ってたけど、それだけではない様子 ラスコの考え方、思想も殺害に影響している ラスコを追い詰める予審判事ポルフィーリーがおもしろい 「選ばれた人間は思想や自分の信じる道を実現するにあたり、誰かを殺してもかまわない」というラスコの思想を指摘し、 曖昧模糊にラスコをあおって、じらして、頭に来させて、相手の内面を揺さぶり心理的に追い詰める 泳がせて、相手がボロをだす、カマをかけるみたいなやり方で 読みにくさはあるけど、おもしろさもあるので第三巻も読む
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
長大な物語を饒舌な会話の力で一気に押し切るという本作の技法は、現代のエンターテインメントにとっても参考になるだろう。読者にとっては、程よい長距離走のような読書体験であり、読後には大きな達成感が得られる。 ただし、「殺人」というテーマの是非については掘り下げがやや不十分かもしれない。ソーニャへの悔悟に関しても、まだその入口に立ったに過ぎない。
Posted by 
引き続きドストエフスキーの『罪と罰』にどハマりしながら、その世界の中に没入しております。 1巻目の時に書いた「ロシア名は覚えにくい」は撤回。その特殊性により逆に覚えやすく感じるようになりました。そしてその名を持つ者がどのような人物なのかがより鮮明に頭の中で結び付くようになってき...
引き続きドストエフスキーの『罪と罰』にどハマりしながら、その世界の中に没入しております。 1巻目の時に書いた「ロシア名は覚えにくい」は撤回。その特殊性により逆に覚えやすく感じるようになりました。そしてその名を持つ者がどのような人物なのかがより鮮明に頭の中で結び付くようになってきた。 第3部、第4部に進むにつれ読み取らなくてはならないことが多種多様になり、人の心の動き、表と裏、表象しているもの…複雑に絡まり合ってくるけれど、そこがとくに素晴らしい。 世界一の小説に敬服する。
Posted by 

