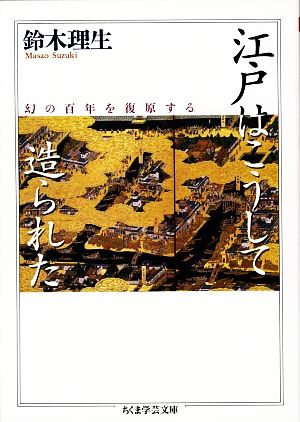
- 新品
- 書籍
- 文庫
- 1224-26-01
江戸はこうして造られた 幻の百年を復原する ちくま学芸文庫
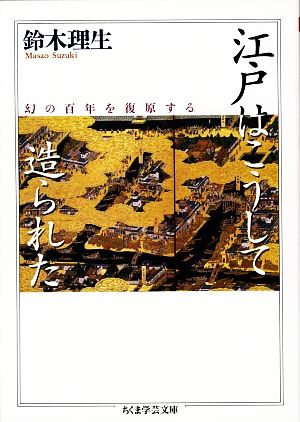
1,320円
獲得ポイント12P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房/筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2000/01/06 |
| JAN | 9784480085399 |
- 書籍
- 文庫
江戸はこうして造られた
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
江戸はこうして造られた
¥1,320
在庫なし
商品レビュー
3.8
6件のお客様レビュー
家康の江戸入り(1590年)から、天下普請完了(1690年)までの江戸形成100年を地誌の観点で描く。 天下普請の大号令と共に、舟運を重視した水の都が形成されていく姿がビビッドに描かれる。 江戸前史の江戸は縄文海進期の面影を残していた。 日比谷入江の存在は、江戸城が海に面して造...
家康の江戸入り(1590年)から、天下普請完了(1690年)までの江戸形成100年を地誌の観点で描く。 天下普請の大号令と共に、舟運を重視した水の都が形成されていく姿がビビッドに描かれる。 江戸前史の江戸は縄文海進期の面影を残していた。 日比谷入江の存在は、江戸城が海に面して造られていたことを示す。 丁度、現在の浜離宮から東京湾を見るような景色が見えたことだろう。 船で房総に逃避した源頼朝は、陸上を鎌倉に向かうのに長い時間を要した。 それは、千葉から神奈川に行くのに、入江と葦の江戸湾を越えるのに難儀したためだった。 家康が江戸を整備するまで、どんな場所だったのかを頼朝の行路は示している。 江戸は陸奥の最南端だった。 秀吉が家康を関東に配置したのは、陸奥の制圧による日本統一が目的だった、と見ることが出来る。 行徳は塩業の重要拠点だった。 行徳と江戸の水路の重要性が納得できる。 会社の近くに福徳神社があった。 日本橋室町にある福徳神社は平安時代からの由緒ある神社で、その際(きわ)には西堀留があった。 行徳から運ばれた塩はそこで捌かれていたのだ。 同時にそこは塩河岸と呼ばれていた。 通勤のコースが正に、江戸にタイムスリップ出来る場所だったのだ。 正に目から鱗が落ちまくる。 こうした優れた学者がいたのだ、と嬉しい。 この本は、そこいら辺の江戸の形成史とはレベルが違うぞ!
Posted by 
円覚寺領(荘園)江戸前島が家康によって横領され、その記録が幕府により隠蔽されたというショッキングな序文で始まる本書は、自分のそれまでの江戸に対する思いを改めることになった。江戸の痕跡を探しながら東京を歩くのは楽しいことだが、江戸前島の記憶を辿るのは無理筋というものだろう。運河の都...
円覚寺領(荘園)江戸前島が家康によって横領され、その記録が幕府により隠蔽されたというショッキングな序文で始まる本書は、自分のそれまでの江戸に対する思いを改めることになった。江戸の痕跡を探しながら東京を歩くのは楽しいことだが、江戸前島の記憶を辿るのは無理筋というものだろう。運河の都・江戸も、埋めては掘り、そしてまた埋めるという繰り返しの中で発展したという歴史と地層の重層の上に成り立っていったのだな〜。内川廻しの項で故郷・銚子湊が家康の物資回送の拠点だったと知り、ちょっと嬉しい。
Posted by 
本書で言う『幻の百年』とは、 徳川家康が江戸入りした天正18年(1590年)から、 幕府が諸大名に課した都市開発・整備事業である「天下普請」が完了する 元禄3年(1690年)までをいう。 この百年に大江戸八百八町の版図(はんと、地図)が作られた。 それは基礎構造に支えられた巨大...
本書で言う『幻の百年』とは、 徳川家康が江戸入りした天正18年(1590年)から、 幕府が諸大名に課した都市開発・整備事業である「天下普請」が完了する 元禄3年(1690年)までをいう。 この百年に大江戸八百八町の版図(はんと、地図)が作られた。 それは基礎構造に支えられた巨大都市の完成であった。 戦国時代の江戸湊がこの百年で「大江戸」と呼ばれる百万都市に変貌したのである。 本書で一番気になった箇所は、江戸の寺町という項目の話。 江戸の時代、お寺の数。 家康の江戸入り当時、現千代田区内には、65寺あったものが、増加につぐ増加で 現皇居周辺に32寺、神田地区には73寺、麹町には38寺、合計143寺もあった。 その約三分の一が、徳川の旧領国にあった寺が徳川家臣団と共に江戸に移転 してきたもの。 三分の一が、大名が徳川に対する忠誠のあかしとして寺と墓地を作り、江戸に骨を 埋める装置としての寺。 さらに三分の一が江戸の町人たちの死体処理場としての寺。 多くは京・近江・伊勢などの先進文化地域の寺の「出店」としての江戸寺だった。 江戸の整備の為に寺を移転するときに、すごいのが、位牌のみ持って行って その他の墓石、遺体等は残していくことだ。もちろん全ての寺がそうではないが。 その証拠に、昭和50年に都立一橋高校の新築工事現場から、おびただしい人骨が 出土して、当時話題になった。 本書は貴重な史料を元に江戸が出来るまでの流れを 分かりやすく説明している名著である。
Posted by 



