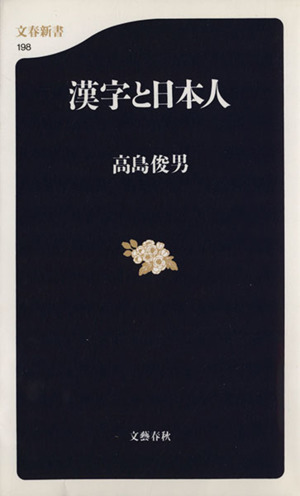
- 新品
- 書籍
- 新書
- 1226-33-01
漢字と日本人 文春新書
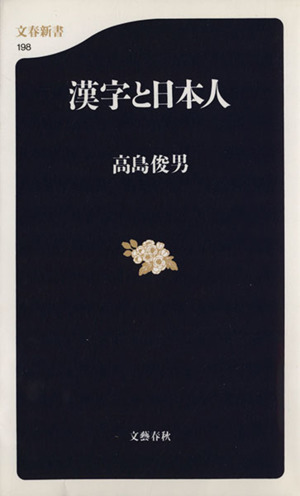
990円
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2001/10/20 |
| JAN | 9784166601981 |
- 書籍
- 新書
漢字と日本人
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
漢字と日本人
¥990
在庫なし
商品レビュー
4
57件のお客様レビュー
著者は、もともと日本…
著者は、もともと日本語を学ぶ外国人のために書いたそうです。しかしそれが図らずも、日本人が漢字との付き合い方を考え直すための根本文書です。「とる」を「取る」「撮る」「摂る」「盗る」「獲る」「執る」「採る」「捕る」などと書き分けることの無意味さを知らされ、さりとて漢字との決別はできな...
著者は、もともと日本語を学ぶ外国人のために書いたそうです。しかしそれが図らずも、日本人が漢字との付き合い方を考え直すための根本文書です。「とる」を「取る」「撮る」「摂る」「盗る」「獲る」「執る」「採る」「捕る」などと書き分けることの無意味さを知らされ、さりとて漢字との決別はできないことがわかります。
文庫OFF
日本語は特殊な言葉だ…
日本語は特殊な言葉だと聞くことが多いが、自分は「そういうのってアレでしょ、『個性的な自分』とかの延長で『個性的な日本』と思いたいだけでしょ(笑)」とバカにしていたのだが、どうもある意味において日本語は本当に特殊らしいのである。特殊どころか「奇形」であるようなのだ、自己を記述する文...
日本語は特殊な言葉だと聞くことが多いが、自分は「そういうのってアレでしょ、『個性的な自分』とかの延長で『個性的な日本』と思いたいだけでしょ(笑)」とバカにしていたのだが、どうもある意味において日本語は本当に特殊らしいのである。特殊どころか「奇形」であるようなのだ、自己を記述する文字との関係が。 そして、日本語はどう奇形なのか?我々はそれとどのようにつきあっていくべきなのか? それをこの本は示している。また、日本語の音標文字化(と、それに伴う漢字廃止運動)について詳しく説明が
文庫OFF
常用漢字などの歴史を知ることができた。過去の日本人がどのような考えで、漢字とひらがなをどうしていきたかったのか。文字から過去を知ることができた。文字と国の思想は一致する、というけどたしかにひらがなは柔らかく、日本の精神が宿っている。学校の先生はできるかぎり漢字を使いなさいと教えた...
常用漢字などの歴史を知ることができた。過去の日本人がどのような考えで、漢字とひらがなをどうしていきたかったのか。文字から過去を知ることができた。文字と国の思想は一致する、というけどたしかにひらがなは柔らかく、日本の精神が宿っている。学校の先生はできるかぎり漢字を使いなさいと教えたが、それは本来の漢字の使いかたではないと知った。日本語の音が少ないからこそ、意味を漢字にして伝えやすくする。漢字とひらがなの共存をしていかなければならない。
Posted by 



