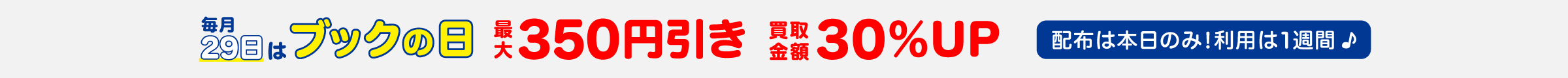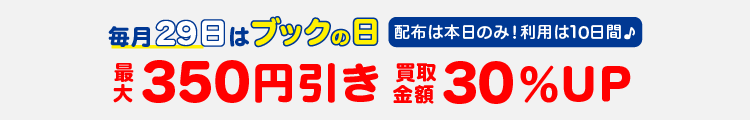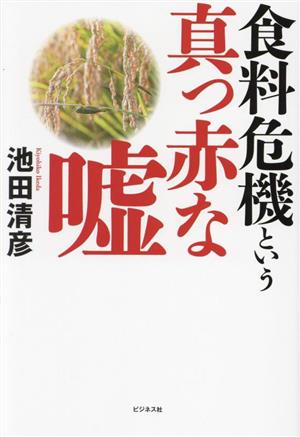
- 中古
- 書籍
- 書籍
食料危機という真っ赤な嘘
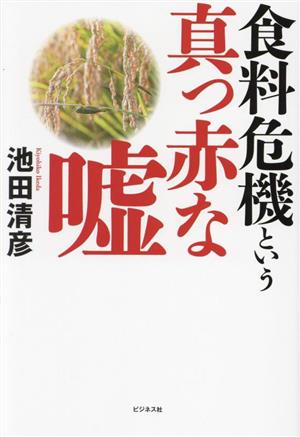
定価 ¥1,870
1,100円 定価より770円(41%)おトク
獲得ポイント10P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ビジネス社 |
| 発売年月日 | 2023/11/01 |
| JAN | 9784828425733 |
- 書籍
- 書籍
食料危機という真っ赤な嘘
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
食料危機という真っ赤な嘘
¥1,100
在庫あり
商品レビュー
3.3
3件のお客様レビュー
食に関する色んな角度での知識が得られて面白い本だと思う。しかし、何故、評価があまり高くないのだろうとページを捲る。なんとなく分かってくる。〝昆虫食推し“なのだ。それもやんわりお薦めするレベルではない。ゴリ押しだ。かつ、タイトルの食料危機の話なんて殆ど関係なくなっている。虫食え虫食...
食に関する色んな角度での知識が得られて面白い本だと思う。しかし、何故、評価があまり高くないのだろうとページを捲る。なんとなく分かってくる。〝昆虫食推し“なのだ。それもやんわりお薦めするレベルではない。ゴリ押しだ。かつ、タイトルの食料危機の話なんて殆ど関係なくなっている。虫食え虫食え。虫食いへの忌避感はあなたのイメージのせい。牛肉や豚肉だって、屠殺する所から見れば十分グロテスクでしょうと。 まあ、確かに。家畜を殺す時代は、カロリー生成において非効率なのでいつかはやめれば良いと思っている。その代わりに、昆虫食や人工肉に置き換える必要性はいずれ来るだろう。でも、感情的に受け入れられないのは、今、その選択肢を選ぶとすれば、「肉を食えるもの」と「虫を食わざるを得ないもの」という残酷な対立構図に見えてしまい、虫を食べる人間が餓鬼亡者の如く、弱者の選択に見えるからだ。やるなら、動物愛護的な観点で、全世界で禁止して欲しいが。 つまり昆虫食を薦める人たちは、そこで稼いだ金で国産牛を食べるわけだ。抵抗感の一つはそれである。もっと素直に、虫が苦手みたいな拒絶感もあるが。いずれにせよ、食べなくても良いものを食べる理由は、敗者の選択か、法改正か。勿論、無茶苦茶美味しいプレミアムな昆虫食が今後誕生する可能性については否定しない。 ー 食肉で問題となっているのは、「成長促進剤や抗生物質入りの肉」だ。牛や豚を太らせる、成長促進剤(ラクトパミン)はEUや台湾などでは禁止されているが、アメリカやオーストラリアでは規制されていない。これを使うと短時間で太るのでコストパフォーマンスがよく、安い肉を作ることができる。ただし、発がん性が疑われており、これを使って育てた牛や豚の肉は裕福な自国民はまず食べない。そこで、日本に輸出するわけだ。アメリカやオーストラリアの牛肉が安いのは理由がある。日本国内ではラクトパミンは使えないが、輸入肉に関してはフリーパスなのだ。 日本は食においても海外から押し付けられている。ひろゆきが食料自給率は低くくても、サプライチェーンを多様化する事でリスクヘッジする策を考えるべきと、食料自給率向上派に反論していた。池田清彦は、余剰食料は輸出し、いざという時は自国優先に供給する事を前提に、生産能力を維持せよという論説。私は池田氏が正しいと思う。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
減反が食料自給率を下げた。米を作りすぎたら補助金をつけてでも輸出するべきだった。いざとなれば自国民の食料になる。世界の食料問題にも貢献する。 トウモロコシの60%以上は飼料用。 肉(タンパク質)は不足する。昆虫食の勧め。 米、イモ、昆虫、時々養殖魚か鶏肉、いつかは培養肉。 カモシカは、鹿というより牛の仲間。うまい。 タヌキ汁のタヌキは、アナグマ。 動物は恐怖心を与えると肉がまずくなる。今のとさつ技術は、失神させて血を抜く。 1960年代くらいまでは長野県でカラスを食べていた。カラスは狩猟鳥。取っていい時期と場所が決められている。 遺伝子組み換え作物は怖くない。農薬のほうが怖い。宍道湖でネオニコチノイド系農薬のせいで、ミジンコなどがいなくなり、ウナギやワカサギがいなくなった。ヨーロッパでは禁止されている農薬。 成長促進目的の抗生物質を食べている牛や豚。EUや台湾は禁止。アメリカ、オーストラリアの牛肉が安い理由。 MRSAは抗生物質がきかない。抗生物質の耐性菌。 チリの養殖サーモンは抗生物質漬け。 政府の「みどりの食料システム戦略」は実現不可能。SDGSに似ている。やっているふり。 人類はもともと雑食。ただし腸の長さから見ると肉食に近い。 古代ギリシャではバッタは鶏肉として食べられていた。 日本でも、蜂の子、カミキリムシの幼虫、イナゴ、カイコのさなぎなどが食べられていた。カイコ以外は養殖に向かない。 日本の魚介類の半分は外国産。 養殖魚は薬漬け。ノルウェー産はまだ少ない。 無毒フグは厚労省が認めない。 シロナガスクジラを取りすぎたおかげでミンククジラが増えて、保護してもシロナガスクジラは増えない。エサのオキアミが共通だから。 培養肉の前に大豆ミート、微生物タンパク。 人口窒素肥料によって、富栄養化、赤潮の原因になった。
Posted by 
タイトルのみをネットで見て衝動買いしてしまった本です。食料自給率の低い日本でどのように近い将来に予想される食糧危機にどのように取り組むべきかについて書いてあるのだろうと期待を持って読みました。結論としては、私たちが慣れてしまった食生活を見直して、本来(明治維新以前)の食生活に立ち...
タイトルのみをネットで見て衝動買いしてしまった本です。食料自給率の低い日本でどのように近い将来に予想される食糧危機にどのように取り組むべきかについて書いてあるのだろうと期待を持って読みました。結論としては、私たちが慣れてしまった食生活を見直して、本来(明治維新以前)の食生活に立ち返ろう、というものです。 和食中心の食生活という言い方もできますが、筆者が強調しているのは昔の人は普通に食していた「昆虫食」の薦めでした。他にも、家畜を殺さないで培養した肉、合成肉等の紹介もありましたが、最も環境に優しくて日本が取り組むことができるのは「昆虫食」のようです。そういえば80歳を過ぎた母が子供の頃は、田んぼに発生する「いなご」をとって食べていたという話を思い出しました。 昆虫をその姿のまま食べるとなると抵抗がありますが、私たちが食べている肉や魚も、本来の姿をとどめているとはいえない形で毎日のように食べているので、この本で紹介されている「コウロギパウダー」あたりから始めることはできるかもしれないなと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・2022年度の一人1日の供給カロリー2260kcalで、国産供給カロリーは850なので自給率は37%、生産額ベースでは58%である、飢えに直面したときに問題になるのは摂取カロリーである(p13)戦争に負けた瞬間1946年の食料自給率は88%であったが、輸入食品が十分に入ってこないので国民の多くは腹をすかせていた(p17) ・日本の減反政策は1970年から2018年まで48年間続けられてきた、これが食料自給率が38%まで落ち込む元凶であった、減反政策後も水田の畑地化への支援制度は続いていて米の生産量は減少傾向にある(p19)一部の農家にとっては米の価格を高いままでキープ、そして米を作らないで税金がもらえた良い制度であった(p22) ・食料輸出の最大の利点は、いざとなればこれが自国民の食料になること(p25)ロシアが1年半を経過してもまだあの不毛な戦争を続けられるのは、エネルギー自給率が200%近くあり、それを海外に売って戦費を調達しているのと、食料自給率が高いから(p31) ・前回の南海トラフ巨大地震は1946年に起きた(昭和南海地震)、そのとき1m15センチ隆起して徐々に戻ってきた、それがちょうど元に戻るのが2038年である、それに誘発される形で富士山も噴火すると言われている、1707年の宝永南海トラフ地震では49日後に富士山が噴火活動を始めている(p33) ・牛の場合生体1キロ作るのに飼料は10キロ、豚は5キロ、鶏は2.5キロ、しかも卵を産んでくれる、養殖魚は3キロなので、タンパク質の自給自足には、養鶏と養殖に力を入れるべきである(p45)食料が輸入できなるとすると、1)養殖に頼らないタンパク源開発、2)飼料をあまり使わないコスパの良いタンパク源を養殖することになる、前者は「培養肉」後者は「コオロギ」である(p60)生体1キロにむくまれるタンパク質の割合は、牛8豚=鶏12、コオロギ16%である(p123) ・日本の未来を救う日本人の食生活は、米・芋・昆虫・時々養殖魚・養殖鶏肉、いつかは培養肉(p63)江戸時代くらいまで、多くの日本人はタンパク質の大部分を魚と虫から摂って食べていた(p64)675年に天武天皇が「牛・馬・犬・猿・鶏」の明確な肉食禁止令をはじめて発布した、これは仏教の考えに基づいているが、本当の狙いは「稲作」であった、牛や馬は米を作るのに欠かせない(p66) ・2018年に日本はIWC(国債捕鯨委員会)から脱退を発表、2019年に脱退し商業捕鯨を再開した(p77) ・タピオカの原料のキャッサバという作物には青酸が入っているので生でたくさん食べると死んでしまう恐れがあるが、タピオカが無毒なのは収穫したのちに毒を抜いて粉にしているから(p91) ・シロナガスクジラを増やすにはどうすれば良いか、ミンククジラを獲ればいい、ミンク鯨たちが食べていたオキアミが余るので、その分、今度はシロナガスクジラが繁殖できる余裕が生まれる(p198) ・光合成のための光源には電気エネルギーが必要で、それを生み出すには当然コストがかかる、このコストが自然農法よりも高いうちは野菜工場は普及しないだろう。そこで期待されるのが核融合発電である(p215) 2023年11月16日読了 2023年11月19日作成
Posted by