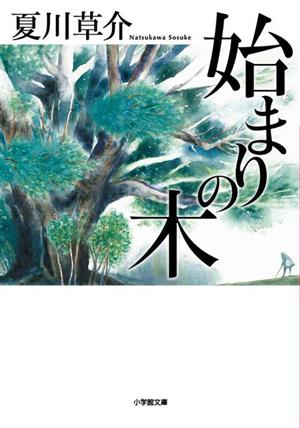
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
始まりの木 小学館文庫
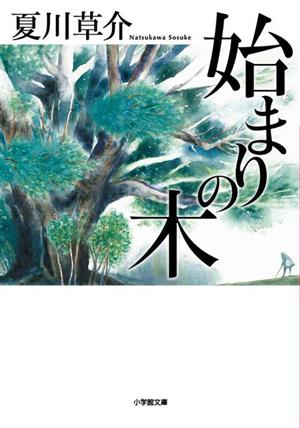
定価 ¥869
660円 定価より209円(24%)おトク
獲得ポイント6P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
7/4(木)~7/9(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 小学館 |
| 発売年月日 | 2023/08/04 |
| JAN | 9784094072839 |
- 書籍
- 文庫
始まりの木
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
始まりの木
¥660
在庫あり
商品レビュー
4.1
17件のお客様レビュー
民俗学の准教授古屋神寺郎と大学院生藤崎千佳の物語。民俗学とは何ぞや、と問いかけながら、日本人としての矜持を問いかける。 二人の五つの旅が五つの短編となる。 偏屈ものの古屋と、彼を尊敬しながら偏屈さに耐える千佳の会話が絶妙で面白い。 「観音様とは特別な仏ではない。心の中にある自然を...
民俗学の准教授古屋神寺郎と大学院生藤崎千佳の物語。民俗学とは何ぞや、と問いかけながら、日本人としての矜持を問いかける。 二人の五つの旅が五つの短編となる。 偏屈ものの古屋と、彼を尊敬しながら偏屈さに耐える千佳の会話が絶妙で面白い。 「観音様とは特別な仏ではない。心の中にある自然を慈しんだり、他人を尊敬する心の在り方を例えている言葉である」 仏も神も日本人としてのあり様であるという古屋の教えは、とても気持ちよく心に染み込んでくる。 自然を敬い、自然を畏れ、他者を大切にする。それが古来の日本人であり、その事を改めて学ぶのが民俗学である。 ネットで調べたり映像で見るのではなく、自分の足を運んで見たり感じたりすること。心がけなくてはいけない大切な事だと思う。
Posted by 
ここ最近で一番の本だった。 民俗学について研究する女学生と大学の先生の話で、何よりこの2人のやり取りがおもしろい。 民俗学って何なのか、まずそれが分からないと思うが、本を読んで思ったのは倫理に近いものだと感じた(正確には違う)。理屈ではない、神に対する信仰心とかそういった類のこと...
ここ最近で一番の本だった。 民俗学について研究する女学生と大学の先生の話で、何よりこの2人のやり取りがおもしろい。 民俗学って何なのか、まずそれが分からないと思うが、本を読んで思ったのは倫理に近いものだと感じた(正確には違う)。理屈ではない、神に対する信仰心とかそういった類のことである。 正直私は、神とかまったく信じていない。この本に出てくる例えば、樹齢何百年の木とかも新しく道路を作るために伐木するのに何も思わないし、どんどんしろとも思うタイプである。それが経済のためになるし。 ただそれに対してこの本では、そういう自らの幸福を求めている人だけの国は亡びていくとしている。目に映ることだけが全てだと考えるようになれば、すごいシンプルな世の中であるが、そういう世の中になっていくということは、自分より力の弱い者を倒すことは倫理に反するどころか、とても理にかなった生き方になると。 また、「どんな物事でも、金銭に置き換えることでしか判断できないような、品のない人たちばかり幅を利かせている世の中」など心にぐさっとくるセリフが多い。 ぜひみなさん一読してほしい。
Posted by 
多くの方がレビューを書かれているのを見て、昔読んで面白かった「神様のカルテ」の作者さんでもあり、買ってみることにした。 高名だが変わり者の民俗学者とその教え子がフィールドワークで日本各地を旅する物語。 二人は旅先で様々な風景に出会い、その美しさが描かれるとともに、あわせて、民俗...
多くの方がレビューを書かれているのを見て、昔読んで面白かった「神様のカルテ」の作者さんでもあり、買ってみることにした。 高名だが変わり者の民俗学者とその教え子がフィールドワークで日本各地を旅する物語。 二人は旅先で様々な風景に出会い、その美しさが描かれるとともに、あわせて、民俗学の意義、学問に対する姿勢、古来からある日本人の神や自然との付き合い方などが語られていく。 偏屈な先生と勝気な女子学生という組合せは、まあ、いいコンビだとは思うが、そのやり取りに新味はなく、そこにはあまり惹かれず。先生が自ら「障碍者」を連呼するのもいかがと思う。 民俗学について書かれた内容やそのあり様については知らないことも多くあり興味深かった。 『人生の岐路に立ったとき、その判断を助ける材料は提供してくれる学問だ』というのにはやや煙に巻かれた感じだが、『未来のために過去を調べる。それが民俗学である』には、主人公と同様になかなか惹かれるところがあり。 エリートだった柳田國男がその後半生を民俗学に費やした理由については、まったく無知だったので、ちょっとした驚きがあった。 古来からの日本における神を感じるという信仰のあり方や神の存在についての考察(『この国の人々にとって、神は心を照らす灯台だった』)、自然との付き合い方についての思いは理解できるし、そうした宗教観や倫理観が薄れてきた結果、権力や金の力が跋扈する今の世相に対する批判にも頷けるところは多かった(いささかお勉強臭かったが…)。 お話の中では第二話の鞍馬での出来事や最終話の桜が満開の風景などがとても印象深い。どちらのエピソードも色や絵柄が目に浮かぶよう。 ただ、それを何度も『理屈の通ることだけが真実ではない』などと言わなくても、普通にファンタジーとして描けば十分に伝わったようには思った。 最後の解説がこれまた難しくて、残念ながら十分に読み下せたとは言い難い。 これについて行けるようであれば、この物語の言わんとするところをもっときっちりと理解できたのであろうかと思わされた。
Posted by 

