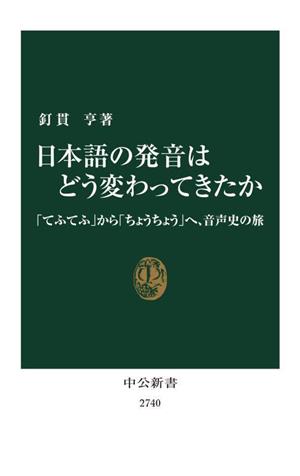
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-33-01
日本語の発音はどう変わってきたか 「てふてふ」から「ちょうちょう」へ、音声史の旅 中公新書2740
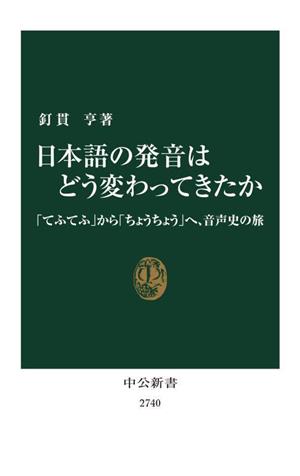
定価 ¥924
440円 定価より484円(52%)おトク
獲得ポイント4P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:2/19(木)~2/24(火)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/19(木)~2/24(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2023/02/20 |
| JAN | 9784121027405 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/19(木)~2/24(火)
- 書籍
- 新書
日本語の発音はどう変わってきたか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本語の発音はどう変わってきたか
¥440
在庫あり
商品レビュー
3.9
20件のお客様レビュー
これもとっくに読んだのだけど。 YouTube番組『ゆる言語学ラジオ』で以前言及されていた本。とても興味深い内容だったが、専門的な知識がないので、少々難しかったな。
Posted by 
高校のころ、古典の授業中にこんな話を聞いた。昔、『母には二たびあひたれども父には一度もあはず』という謎々があった。答えは『くちびる』で、このことから昔は母は『ファファ』のように発音していたことがわかるということ。この話を聞いて、発音も変化するのだと思い、新鮮だった。 書店で帯に『...
高校のころ、古典の授業中にこんな話を聞いた。昔、『母には二たびあひたれども父には一度もあはず』という謎々があった。答えは『くちびる』で、このことから昔は母は『ファファ』のように発音していたことがわかるということ。この話を聞いて、発音も変化するのだと思い、新鮮だった。 書店で帯に『羽柴秀吉はファシバフィデヨシだった!』と書いてあるこの新書を迷わず手にした。 いろいろと新しいことを知ることができたので満足。でも、実際の音は読んで想像するだけでは、どうにもならないなぁ。以下は少し長くなるが、特に興味をもったこと。 万葉仮名の使い方を調べてみると、奈良時代には『い、え、お』の音が二つあり、母音が合わせて八つあったことが分かる。そもそも万葉仮名から、音が推測できることが凄い。その頃の語は1音節か2音節だったものが、情報量の増加に伴い多音節化が進み、微妙な音の使い分けが必要なくなり、平安時代になるころには5母音になっていった。 先ほどのハ行については、奈良時代はp音で、平安時代にf音に近い音になり、18世紀前半頃には現在のh音になった。途中平安時代の後期に、語中や語尾のf音は かは→かわ、かひ→かゐ のようにw音化も起こった。サ行も奈良時代はts音だったが、平安後期までにs音になった。『し』については、室町時代にsh音に変化した。平安時代には、音便による短縮化、い・ゐ、え・ゑ、お・を の合流が起こった。 平安時代にできたひらがなは文芸作品に使われて、書写が繰り返された。連綿体は書写に打ってつけだった。当時の和歌や日記、物語は総ひらがなで書かれていたが、発音通りに文字にすればよかった。しかし定家の時代(鎌倉時代)になると、音声変化のため綴りに乱れが生じて、作品を読むことができなくなっていた。定家はかな綴りの規範を作った(定家仮名遣)。漢字かな混じり文を進め、意味の纏りを意識して文を綴った(我々が普通に読む古典のスタイルを初めた)のも彼だ。 ところが江戸時代に入ると、定家の仮名遣いは平安初期の仮名遣いと一致しないことに契沖が気付いた。契沖は万葉集などに基づく仮名遣いをつくり、次第に受け入れられた。これがいわゆる、歴史的仮名遣いのもとになった。
Posted by 
なぜ接続の「は」は「wa」と発音のか。なぜや行とわ行にはイ段とオ段がないのか。なぜ「じ」と「ぢ」はどちらも「zi」と発音するのか。 日頃、私たちが何気なく使っている日本語。その音の響きには、古代から連綿と続く歴史があります。本書『日本語の発音はどう変わってきたか』(釘貫亨著)...
なぜ接続の「は」は「wa」と発音のか。なぜや行とわ行にはイ段とオ段がないのか。なぜ「じ」と「ぢ」はどちらも「zi」と発音するのか。 日頃、私たちが何気なく使っている日本語。その音の響きには、古代から連綿と続く歴史があります。本書『日本語の発音はどう変わってきたか』(釘貫亨著)は、そんな日本語の音、特に音韻がどのように変化してきたのかを、わかりやすく解説してくれる一冊です。 驚くべきことに、奈良時代には「笹の葉サラサラ」は「ツァツァノパツァラツァラ」と発音されていたそうです。そこから時代を経て、「ササノファサラサラ」「ササノハサラサラ」へと変化したそうです。現代の我々からすると、古代の日本語はまるで外国語のように感じられます。本書は、こうした日本語の音の歴史的変化を、音響学や音韻論の観点から、丁寧に解き明かしてくれます。 日本語の音の歴史は日本と日本人の歴史と密接に関係しています。しかし、日本語を母語とする私たちは、普段意識することなく日本語を使用しているため、その奥深い歴史や仕組みについて意外と知らないことが多いのではないでしょうか。本書は、私たちが当たり前のように使っている日本語のルーツを改めて教えてくれる、知的好奇心を刺激する一冊です。 本書を読み進めれば、冒頭に挙げた音に関する素朴な疑問も氷解するはずです。
Posted by 
