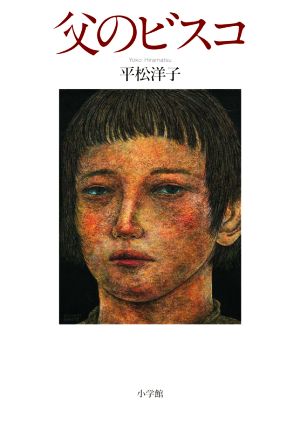
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1220-05-06
父のビスコ
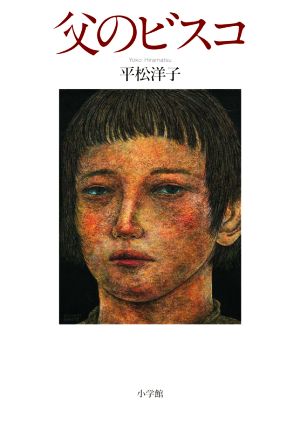
定価 ¥1,870
880円 定価より990円(52%)おトク
獲得ポイント8P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/9(金)~1/14(水)
店舗到着予定:1/9(金)~1/14(水)
店舗受取目安:1/9(金)~1/14(水)
店舗到着予定
1/9(金)~1/14

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/9(金)~1/14(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 小学館 |
| 発売年月日 | 2021/10/26 |
| JAN | 9784093888417 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/9(金)~1/14(水)
- 書籍
- 書籍
父のビスコ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
父のビスコ
¥880
在庫あり
商品レビュー
4.1
12件のお客様レビュー
初読みの平松洋子さんのエッセイ。 落ち着いた文章で、比喩表現が巧みでした。彼女の父親の影響もあるような気がしました。〈父のどんぐり〉の中で、鰻重を食べて「柔らかい宝石を食べている心地がする」という表現にセンスのよさを感じました。なかなか言えない言葉です。この言葉の背景が書かれた〈...
初読みの平松洋子さんのエッセイ。 落ち着いた文章で、比喩表現が巧みでした。彼女の父親の影響もあるような気がしました。〈父のどんぐり〉の中で、鰻重を食べて「柔らかい宝石を食べている心地がする」という表現にセンスのよさを感じました。なかなか言えない言葉です。この言葉の背景が書かれた〈父のビスコ〉が、同じような経験をした私にとっては、とても印象深かったです。 平松さんが郷里の倉敷について、三世代に渡る記憶を紡いだこの本に出会えてよかったです。倉敷のことをなにも知らなかった私が、大いに興味を持ちました。
Posted by 
平松洋子さんはわたしの親世代。 小さい頃の家族の話を読むと、きちんとした家庭で幸せそうだなあと思う。わたしは祖父母に会ったことがない(みんな短命だった)けど、父や母は幼い頃こんな生活をしていたのかなあとちょっとだけ考えたりする。 わたしももう父を亡くしているので、「あんなことも...
平松洋子さんはわたしの親世代。 小さい頃の家族の話を読むと、きちんとした家庭で幸せそうだなあと思う。わたしは祖父母に会ったことがない(みんな短命だった)けど、父や母は幼い頃こんな生活をしていたのかなあとちょっとだけ考えたりする。 わたしももう父を亡くしているので、「あんなことも知らない、こんなことも知らない、もう知れない」という切なさに襲われることがある。母には色々聞いておきたいと思いつつも、いざとなると聞きたいことも浮かばず、あまり帰れてもいないことに気づく。
Posted by 
思い出を食べて生き延びる 著者の幼少期の食の思い出話や生まれ育った場所、家族の思い出を通してのエッセイ。 年代が違う方の食エッセイは「あ、それ聞いたことある」というものから「そういえばスーパーの片隅で見たかも」的なものもあり、面白い。 後半はほぼ故郷への想い、家族への想い、という...
思い出を食べて生き延びる 著者の幼少期の食の思い出話や生まれ育った場所、家族の思い出を通してのエッセイ。 年代が違う方の食エッセイは「あ、それ聞いたことある」というものから「そういえばスーパーの片隅で見たかも」的なものもあり、面白い。 後半はほぼ故郷への想い、家族への想い、というところか。
Posted by 
