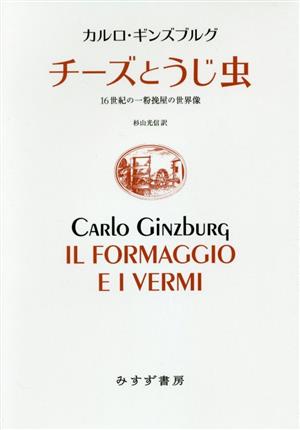
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-04-12
チーズとうじ虫 新装版 16世紀の一粉挽屋の世界像
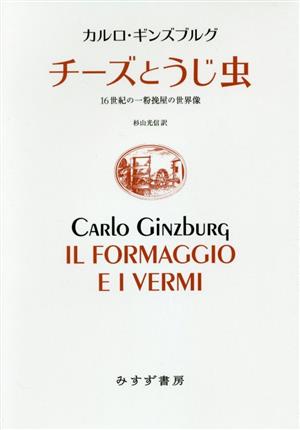
定価 ¥4,400
2,750円 定価より1,650円(37%)おトク
獲得ポイント25P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | みすず書房 |
| 発売年月日 | 2021/05/04 |
| JAN | 9784622090236 |
- 書籍
- 書籍
チーズとうじ虫 新装版
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
チーズとうじ虫 新装版
¥2,750
在庫なし
商品レビュー
4.5
3件のお客様レビュー
『チーズとウジ虫』は、16世紀末のイタリアの片田舎で、一人の粉屋が異端審問にかけられた記録から始まります。その粉屋メノッキオは、教会の目から見れば危険な思想の持ち主でした。でも彼の残した言葉を読んでいくと、そこには当時の知的世界の意外な広がりが見えてきます。 メノッキオは『マン...
『チーズとウジ虫』は、16世紀末のイタリアの片田舎で、一人の粉屋が異端審問にかけられた記録から始まります。その粉屋メノッキオは、教会の目から見れば危険な思想の持ち主でした。でも彼の残した言葉を読んでいくと、そこには当時の知的世界の意外な広がりが見えてきます。 メノッキオは『マンデヴィルの旅行記』『デカメロン』『コーラン要約』など、様々な本を読んでいました。彼はラテン語こそ読めませんでしたが、俗語で書かれた本なら手当たり次第に読み漁っていたようです。そしてその読書から得た知識を、粉屋としての経験や村での暮らしと結びつけて、独自の世界観を紡ぎ出していきました。 たとえば彼は、世界の始まりをチーズ作りになぞらえて説明します。最初に「カオス」があり、そこから物質が凝固して天使が生まれた―これは、チーズが凝固する過程から着想を得た世界創成論でした。また彼は、神を「自然」と同一視し、教会の権威を相対化するような発言もしています。「すべての宗教に救いの可能性がある」という彼の言葉には、当時としては驚くべき寛容さが垣間見えます。 この本の面白さは、そうしたメノッキオの思考の跡をたどることで、私たちが思い描く「16世紀の民衆」のイメージが大きく揺らぐところにあります。彼は確かに正規の教育は受けていません。しかし彼の発言からは、書物から得た知識を自分なりに解釈し、批判的に考える力を持っていたことが分かります。「民衆文化」と「エリート文化」は、実際にはもっと複雑に交わり合っていたのかもしれません。 とりわけ印象的なのは、異端審問官との対話の場面です。メノッキオは、自分の考えを決して曲げようとしません。「私は自分の頭で考えたことしか言っていない」―この言葉には、近代的な意味での「個人」の芽生えのようなものすら感じられます。結局彼は処刑されてしまいますが、その最期まで自分の信念を守り通しました。 ギンズブルグは、こうした一人の人物の記録を丹念に読み解くことで、歴史の「底」に沈んでいた世界を浮かび上がらせます。それは私たちが思い描く「中世」や「民衆」についての固定観念を、静かに、しかし確実に揺るがしているように思えます。
Posted by 
1584年、イタリアの農村に住む粉挽屋の男 メノッキオが異端審問にかけられた。「神とは空気である」「人間はみな神に生まれついている」「チーズからうじ虫が生まれるように、世界から天使や神が生まれでた」と語る彼の反カトリック的な思想を読書履歴から分析し、農村の周縁的存在である粉挽屋と...
1584年、イタリアの農村に住む粉挽屋の男 メノッキオが異端審問にかけられた。「神とは空気である」「人間はみな神に生まれついている」「チーズからうじ虫が生まれるように、世界から天使や神が生まれでた」と語る彼の反カトリック的な思想を読書履歴から分析し、農村の周縁的存在である粉挽屋と異端の関係を解き明かす。ミクロストリア研究の代表作。 カルロ・ギンズブルグってナタリア・ギンズブルグの息子なのかー! 単に同じ姓の人だと思ってた、鈍すぎ。そうと知ると、ミクロストリア(特定の共同体や個人を対象にした歴史学)という考え方自体が『ある家族の肖像』的だ。 解説によれば、発表当時から「農民ラディカリズム」の定義付けが曖昧なこと、メノッキオの〈誤読〉は「農民的なもの」ではなく「周縁的なもの」なのではないかということは指摘されていたようだ。私も、メノッキオには江戸時代のメディア・ネットワークを担っていた人びととの類似を感じた。 このメノッキオというおじさん、同時代の最高知性であるモンテーニュとすらシンクロを見せる先進性がありつつも、議論に付き合おうとしない村人たちを30年相手にしてきたせいで、異端審問官が自説を聞いてくれるという喜びに浸り、めちゃくちゃ喋りすぎてしまう。友人の神父に忠告受けてもまだ喋る。彼のキャラクターのおかげで、小説のように面白く読めたのは嬉しい驚きだった。 メノッキオの思想の組み立て方を、彼が読んだと語る本の読み方から分析していくギンズブルグのスタイルは大胆で面白い。メノッキオは異端審問のなかで、『マンデヴィルの旅行記』や『デカメロン』を援用したらしい。「審問官は自分たちが知っていることを私たちに知られたくないと思っている」と村人に語ったメノッキオの言葉は、自分は特権的な知識に触れたんだ、〈知っている〉んだ、という喜びからくるものでもあったろう。そして知を共有したがったがために、メノッキオは殺されてしまった。 しかし、「教会の律法や戒律は『売り物』」「私がキリスト教徒なのはキリスト教の国に生まれついたからであって、トルコ人に生まれついたら、トルコ人にとどまり続けたいと望むだろう」などと喋りまくっていたメノッキオが何十年も告発されなかったということは、16世紀にもなればこれぐらいのアンチ・カトリック的な考えは田舎でも共有されていたことを表してもいるだろう。現代人はついうっかりメディアが発達する前の田舎の人間なんてみんな盲目的に宗教を信じているものと考えてしまうが、彼らは今と同じく面倒くさくなりそうなことは口にださないだけなのだ。中世からの宗教システムは既に瓦解しはじめていた。一農村の老人に教皇自ら死刑執行を命じるほど、カトリック教会側が追い詰められていたとも言えるのだ。 老いたメノッキオが再審に呼びだされ、教皇直々の命令でジョルダーノ・ブルーノの結審と同月に死刑が執行された、という幕切れは、学術書というより歴史小説のようなエンタメ性にあふれている。ブルーノと並べられることで、この議論好きな老人の死が歴史の転換点のように思えてきてしまう。実際、末端の人びとの意識を変えていったのは、こういう身近な偏屈人間の死だっただろう。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
16世紀後半,一人の粉挽屋メノッキオの異端裁判の記録を読み解くことで見えてくる世界の広がり,農民つまりは民衆と支配する階級との関係性の崩れの様相,この時代の宗教改革などにも表れる考え方の変遷あるいは変わりなさ,など興味深かった. そして何よりこのメノッキオの好奇心,拷問にも覆すことのできない真理,黙っておれない性格など,手強い異端審問官とのやり取りなどからも,あっぱれだと感心した.
Posted by 



